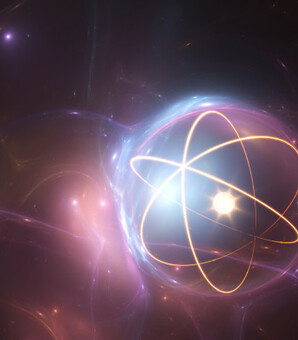そもそも、この世界は何からできているのか…2000年以上に及ぶ大論争の末、ついに人類が気づいた「意外すぎる答え」(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース
そもそも、この世界は何からできているのか…2000年以上に及ぶ大論争の末、ついに人類が気づいた「意外すぎる答え」
配信
138億年前、点にも満たない極小のエネルギーの塊からこの宇宙は誕生した。そこから物質、地球、生命が生まれ、私たちの存在に至る。しかし、ふと冷静になって考えると、誰も見たことがない「宇宙の起源」をどのように解明するというのか、という疑問がわかないだろうか? 本連載では、第一線の研究者たちが基礎から最先端までを徹底的に解説した『宇宙と物質の起源』より、宇宙の大いなる謎解きにご案内しよう。 【写真】いったい、どのようにこの世界はできたのか…「宇宙の起源」に迫る *本記事は、高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所・編『宇宙と物質の起源「見えない世界」を理解する』(ブルーバックス)を抜粋・再編集したものです。
宇宙は何でできているのだろう?
「宇宙は何でできているのだろう?」。この根源的な疑問に、大昔からたくさんの人が思いを巡らせました。 古代ギリシャの哲学者たちは、この宇宙、つまり太陽や地球といったものが、何でできているのかを考えました。この宇宙は、火、水、土、空気でできていると考えた人もいましたし、どんどんと細かくしていくと、これ以上分割できないとても細かい粒に行きつくはずだと考えた人たちもいました。 中でも古代ギリシャの哲学者デモクリトスは、この宇宙にあるものはとても細かい粒でできていると考え、これ以上分割できない粒のことを「アトム」と名付けました。このアトムは、私たちが今、「原子」と呼んでいるものとは違い、彼の頭の中だけで考えられたものです。古代ギリシャ人には、ものをこれ以上分割できなくなるまで細かくしていく技術はなかったので、彼の頭の中だけでそう考え、信じたにすぎませんでした。 宇宙は何でできているのかという問題は、長い間、解決しないままでした。考えることはしてきたのですが、これ以上分割できない粒があったとしても小さすぎて実際に見ることができず、答えを決めることができませんでした。
そこに、画期的な仮説が登場…!
19世紀の初めに、イギリスの科学者ジョン・ドルトン博士が登場します。彼は、気体が小さな粒子でできていると考えれば気体の化学反応をうまく説明できることに気付き、「ものは原子でできている」と主張しました。 ただし、ドルトン博士も実際に原子を見たわけではありません。化学反応を考える単位として原子という考え方を取り入れると、化学反応の前後で重さが変わらない理由や反応の前後の量を説明できるので、原子があることにしようという「原子仮説」でした。 当時もまだ、この宇宙にあるものが、原子のような粒でできているのか、どこまで細かくしても最小の単位はなく連続で一様な存在が続くのかは、科学の世界を二分する大問題でした。ドルトン博士の原子仮説は化学反応を説明できましたが、ものはすごく小さな粒でできている、とみんなを納得させる証拠を示すことはできませんでした。 この世界は粒でできているのか否か。この論争に決着をつけたのは、20世紀を代表する科学者の1人、ドイツ生まれのアルバート・アインシュタイン博士でした。さらさらと連続しているようにしか見えない水が、実は粒の集まりであることを示したのです。1827年にイギリスの植物学者ロバート・ブラウン博士によって発見された「ブラウン運動」の考察がきっかけでした。 ブラウン博士は、水に花粉を浮かべたとき、花粉から出てくる粒が水の中でブルブルと、せわしなく不規則に動くことを発見しました。それがブラウン運動です。ブラウン博士は最初、「何かの生命現象によってブルブルと動くのだろうか」と考えましたが、化石の粉、鉱物の粉、煙の粒などの生きていないものも同じように不規則に動くので、その理由がわからなかったのです。 アインシュタイン博士は1905年に発表した論文の中で、ブラウン運動が起こるのは動き回る粒の側に理由があるのではなく、水がとても小さな粒でできているからだと結論づけました。そう考えれば花粉から出てくる粒の不規則な運動が説明できる、と論文に著しました。 静かに止まっているように見えるコップの中の水も、もし水が小さな粒でできていたら、その粒は動き回っていることでしょう。コップの中の水の粒は、温度が高ければ激しく、低ければゆっくりと、絶えず動いています。水の粒がまるで「おしくらまんじゅう」のようにあちらこちらから押すので、花粉から出てくる粒がブルブルと不規則に動いているように見えるのだ、とアインシュタインは発表しました。 論文には、花粉の動きの観察から水の粒の大きさや数を予測する数式も記されていました。アインシュタイン博士の論文は、「この数式を実験で確かめて欲しい」との呼び掛けで終わっています。 アインシュタイン博士の呼び掛けに応じて、フランスの物理学者ジャン・ペラン博士が花粉から出た粒の運動を細かく記録し、水の粒の大きさや数を計算しました。この実験によって、水の粒が実際に存在していることや、ドルトン博士が示した原子仮説が正しいことが証明されたのです。ペラン博士は、この功績によって1926年にノーベル物理学賞を受賞しました。 ペラン博士の実験によって確認された水の粒の大きさは、1億分の1センチメートルほどでした。18g(大さじ1杯ちょっと)の水の中には6.02×10²³個という、とてつもなくたくさんの粒が存在していることがわかりました。これは、他のどの実験よりも水の粒の数を正確に計算できていました。 こうしてアインシュタイン博士の論文とペラン博士の実験によって、ものをつくっている小さな粒、原子の存在が決定的になってくると、次に興味を引いたのが、その姿です。
原子はどんな形?
原子の姿を考えるに当たり、アインシュタイン博士の論文が発表される少し前の19世紀終わりごろに、物理学史上とても重要な発見がありました。イギリスの物理学者ジョセフ・ジョン・トムソン博士による電子の発見です。ガラス容器に一対の電極を入れ真空にして電圧をかけると光る線がマイナス極から出ることが知られており、陰極線と呼ばれていました。トムソン博士は、電場をかけると陰極線が曲がることを見つけ、陰極線がマイナスの電気をもつ粒子であることを発見し、「電子」と名付けたのです。 私たちの生活に欠かせない電気。この電気の正体は、トムソン博士が発見した電子という粒子です。電化製品のスイッチを入れると電線を電気が流れます。その電線中を流れるのが電子です。電流はプラスからマイナスに流れると、小学校の理科で習いました。これは、まだ電子という電流の正体がわかっていなかったときに決められたことです。実際には、たくさんの電子が電線の中をマイナスからプラスに流れているのですが、私たちはそれを電子の流れと意識しないで使っています。私たちが便利だなと感じている現代の生活は、実は電子という粒子によって支えられていたのです。 アインシュタイン博士の論文とペラン博士の実験によって原子の存在が明らかになると、次にその形が問題になりました。すでにトムソン博士によって電子が発見されていたので、科学者たちは当然、原子の中には電子が入っていると考えました。ペラン博士の実験から計算された水の粒の大きさと、トムソン博士が実験で発見した電子の大きさを比べると、明らかに電子の方が小さいこと、そして電子はマイナスの電気をもっているということも、原子の形を考えるポイントになりました。 私たちの身の回りにあるものは、電気的には中性のものがほとんどです。本、ノート、机、いすなど、手で触れても電気が流れてはきません。それはプラスの電気とマイナスの電気が同数で、電気的に中性だからです。 マイナスの電気をもっている電子が存在しているということは、電子とは反対にプラスの電気をもっている何かがあって、電子とその何かが同数集まって原子をつくっている。だから、ほとんどのものが電気的に中性なのだ。そう考えられました。
「レーズンパン」か「土星」か…巻き起こった大論争
たくさんの科学者が、原子はいったいどのような形をしているのかと考え、2つの候補に行きつきました。 1つはレーズンパン型モデルです。レーズンパンは、パン生地の中に小さなレーズンがたくさん入っています。原子もそれと同じように、プラスの電気をもったものの中に、マイナスの電気をもった小さな電子がたくさん入っているというものです。 もう1つが土星型モデルです。土星は、本体が中心にあり、その周りを環が回っています。土星の環の正体は、大きさが数mから数センチメートルの氷の粒の集まりであるといわれています。それからの類推で、原子には中心部分にプラスの電気をもった土星本体のような「核」があり、その周りを電子が回っていると考えられました。 どちらが正しいのかで大論争が起きました。そして、その論争に決着をつけたのも実験でした。 1911年に、イギリスで活躍したニュージーランド出身の物理学者アーネスト・ラザフォード博士が、金箔に放射線の一種であるアルファ線をぶつける実験に基づいて原子模型を提唱しました。アルファ線はプラスの電気をもつ小さな粒子です。放射性物質から秒速約1万キロメートルという速さで飛び出します。 原子がレーズンパンのような姿だったら、アルファ線はほぼすべて金箔を貫通すると予測されていました。 ところが実験すると、撃ち込んだアルファ線の中に大きく角度を変えて跳ね返ってくる粒子があったのです。ラザフォード博士もとても驚きました。アルファ線が大きく角度を変えたということは、金原子の中の何か小さくてかたいものにぶつかったからと考えられます。この実験により、土星型モデルのように、原子の真ん中にはプラスの電気をもつ小さくてかたい核があり、その周りを電子が回っていることがわかりました。そして、このプラスの電気をもつ核は「原子核」と名付けられました。
古代ギリシャのデモクリトスがその存在を主張したアトムは「これ以上分割することのできない粒子」という意味でしたが、20世紀になり、原子は電子と原子核とに分割できることがわかったのです。
* * * さらに「宇宙と物質の起源」シリーズの連載記事では、最新研究にもとづくスリリングな宇宙論をお届けする。
高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所
【関連記事】