9/4
吉見俊哉氏(東大教授)
が米国と日本の関係について興味ある考察をしていました(本日付朝日朝刊)のでメモしときます。
・米国は戦後大日本帝国の遺産を引き継ぎ、日本がかつて植民地化した多くの地域を自陣営に組み込んだ。日本は米国と最も仲の良い国として自らを再定義することで、戦後もアジアの中心であり続けた。そういう歴史的連続性がある。
・冷戦構造の中、米国は日本に、対共産圏の軍事的防壁である韓国・フィリピンなどを経済的に支える役割を担わせた。
・米国の戦後の占領は1952年の主権回復に終わったのではなく、日本の社会や歴史、構造に内在する形で日本を支配し続けていて、現在も米国から自由ではない。
・日本が原発導入に向かった最大の理由は米国の「原子力の平和利用」の名の下の世界戦略であった
・戦後日本に一貫している強い親米意識は、ひとつは戦前戦中の天皇に代わり、戦後は米国が日本人のアイデンティティを保証した。米国の物差しが評価が日本人に強い影響を及ぼした。ふたつめは、戦中のアジアへの侵略行為を忘れたいという社会心理があったのではないか。冷戦構造の中で、米国が日本の後見役をしていたからこそ、戦前戦中の日本がやったことにフタをし、忘れることができた。日本はアジアを忘れるために、一生懸命米国だけを見てきたのではないか。
・アジアとの問題、米国による支配がある中、日本人が大事にしてきた高度成長という成功物語の裏面で日本は自らが袋小路にはまっている
・日本がアジアの中心だったのは日清戦争以降の100年あまり。中国は大国化して米中の二極構造がはっきりする。日本はもはやワンノブゼムであることを自覚すべき。東アジアを多元性に見て米国覇権の連続性を問い直せ。
私は、
- 戦後史の正体 (「戦後再発見」双書)/創元社
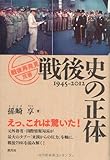
- ¥1,575
- Amazon.co.jp
この本を読んで衝撃を受けました。(後日ブログでメモします。9/2(日)徳島新聞朝刊に書評があります)
わかっていながら、戦後史の検証が学生時代以来出来てなかったなあ、と。
今のアジアとの歴史、戦後の日本の政治や文化史の流れって米国を無視して考えられません。
米国との対峙をどう考えていたか、いるかで政治家や歴史、そして現在の経済の本質が読み取れる気がしてきました。