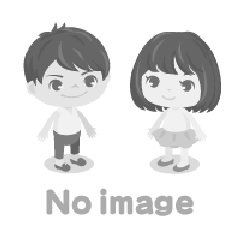今日もアメリカの大学の教授の話をします。
先日、Associate Professorになったら、テニュア(終身雇用)がもらえて、Assistant Professorはそれをもらうために必死に頑張る、というような話をしました。
それでは、テニュアを取得したらどうなるのか?やはり教授も堕落していくのではないか、という不安と不満が大学関係者の中でずっと内在していました。そして、90年代の前半、このテニュアという終身雇用制度を見直すべきだという声が全米各地で見られるようになってきました。これを、Post-tenure-reviewといいます。
Post-tenrue Reviewというのは、各大学によってその内容も随分変わりますが、一般的にはテニュアを持った教授を定期的に評価の対象にかけると言うことです。そしてその評価は給料や、極端な話解雇もありうる、といったところにこのPost-tenrue Reviewが議論を呼んでいる理由があります。
現在、この. Post-tenure-reviewがどれくらい行われているのかというと、1996年にアンケート調査が行われましたが、680の回答した大学のうち、61%(約400)の大学がPost-tenure-reviewを行っていると答えました。また州別では、2000年時点で37の州の州立大学が、何らかの形で Post-tenure-reviewを実施しており、特にアーカンサス、バージニア、カリフォルニア、サウスカロライナ州では、Post-tenure-reviewは義務となっています。また、私立大学で言えば2000年にハーバード大学で行われた研究では、48%の私立大学がPost-tenure-reviewを実施しています。
21世紀に入って以降は、それほどPost-tenure Reviewも話題に上ることは少なくなりましたが、例えば教授が解雇された場合、教授は法的措置に訴えることがしばしばのようです。
詳しくはこちら: http://www.aaup.org/Legal/info%20outlines/legposttenure.htm
先日紹介した教授の全米組織であるAmerican Association of University Professors(AAUP)は、もともと、このPost-tenure Reviewには断固反対、という立場をとっていましたが、時代の波には勝てなかったのか、1999年には、「教授を解雇するのためのPost-tenure Reviewではなく、Faculty DevelopmentのためのPost-tenure Reviewならば賛成」という立場をとるようになりました。
http://www.aaup.org/statements/Redbook/rbpostn.htm
もっとも、先ほども述べたように、各大学のタイプやミッションによってPost-tenure Reviewの内容も随分変わってきます。教授主導で行われる大学もあれば、Staffが主導で行う大学もあります。解雇もありうる大学もあれば、そうじゃない大学もあるわけです。しかし、90年代の議論を通して確立された論理は、先ほどのAAUPの発言にもあるように、罰するためのPost-tenure reviewであってはならないということです。
日本でもPost-tenure Reviewを実施しているところや、実施を考えているところが少なからずあると思います。しかしその第一歩として、まずTenureとは一体どういう意味をもつのか、という議論をする必要があると思います。はっきり言って、日本の大学のシステムは欧米のシステムの借り物なわけで、テニュアもそれに含まれます。アメリカでは様々な人たちの犠牲の上にかちとったのがテニュアなわけで、そこに至るまで長い歴史を経て来ました。だから、Post-tenure Reviewという話が出てきた時に、きれいな言い方をすれば、様々な思いがそこには込められていました。故に、日本の大学でいうテニュアとアメリカの大学で言うテニュア、同じ言葉であったとしても、その持つ意味合いは全く変わってきます。
日本とアメリカの大学は全く異なる環境にあるので、アメリカで行われていることがそのまま日本に当てはまるとは限りません。全体的に見て教授の質の低さは、アメリカとは比べ物にならないです。そういう意味から言えば、ひょっとしたら教授の権利をどうこういう議論の余地すらないかもしれません。
ランキング を見る