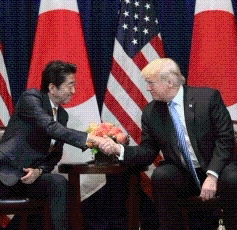1.構造改革のはじまり
「始まっている未来」(宇沢弘文・内橋克人)p26によると、構造改革が日本で主張されるようになったのは、1993年です。当時の細川連立政権下の経済改革研究会が、規制緩和の重要性を強く主張するレポートをまとめました。この研究会は、当時の経団連会長平岩外四氏が座長で、経済学者の中谷巌氏が入っていました。中谷氏は米国帰りの経済学者で、「新自由主義」に基づく経済改革を強く主張していました。(以下は「そして、日本の富は略奪される」(菊池英博)p35~)「新自由主義」という思想は、シカゴ大学のミルトン・フリードマンが唱えた経済思想で、ポイントは次の4つです。第一に、経済活動は企業活動で決まるので、規制緩和と減税で企業活動が活発になれば失業問題は自然に解決する。第二に、低所得者への富の再配分は、怠け者を助長するのでやめるべきで、高所得者への累進税は富を生み出す士気を低下させるのでやめるべきで、富裕層の富を増やせば低所得者や中間層にも富が回る(トリクルダウン)。第三に、金融市場の規制を撤廃し自由化してもバブルは発生しない。第四に、戦後の米国が採用してきた福祉型資本主義(公共投資で需要を作り出し景気を刺激して失業率を下げるケインズ学派の経済政策)は個人の自由な活動を阻害するとし、「大きな政府」は非効率であるから、自由化・民営化・規制改革を行って、「小さな政府」にすべき、です。このような新自由主義の考えは、イギリスのサッチャー政権と米国のレーガン政権の政策に取り入れられました。しかし、いずれの政権も、富裕層はますます富み、トリクルダウンは起こらず、中間層は没落して税収は減り、その結果財政赤字が拡大し、財政危機に瀕することになりました。特に米国は1985年、70年ぶりに債権国から債務国に転落しました。
しかし、この問題の多い「新自由主義」を反映したレポートが、この時期日本政府でまとめられたのです。なぜでしょうか?これについては、1980年代以降の米国から日本への対日要求が背景にあると考えられます。(以下は、「空洞化と属国化」(坂本雅子)2017年p387~p389の要約です)1980年代以降、米国は拡大する対日貿易赤字に苦慮し、日米半導体協定など明らかに日本側に不利な貿易協定を結びます。しかし貿易赤字はふくれる一方で、おさまる気配はありません。そこで米国企業は「自分たちは日本の企業と競争しているのではなく、日本のシステム全体と競争させられている」と考えるようになりました。日本のシステムとは、政府・企業経営者・労働者が一丸となって「ものづくり」に邁進するシステムで、「日本型経営」として、世界的によい意味でも悪い意味でも注目され、日本の驚異の経済成長と輸出競争力の源泉と世界から見なされていました。そこで米国は、「構造改革」の名のもと、日本のシステムに変更を迫る「協議」(具体的に「MOSS協議」(1985~1986年)、「日米構造協議」(1989~1990年)、「日米包括経済協議」(1993~1996年))を開始しました。そして1994年からは、規制改革をせまる「年次改革要望書」を毎年送りつけるようになりました。米国の要求とは、戦後日本の官民一体、労使協調の経済経営システム全般を破壊するとともに、米国資本の参入を容易にし、公共部門も含めて米国企業に開放し、日本の金融資産や日本企業そのものを米国の投機資本の蚕食にさせることでした。そして日本の経済・社会のルールを米国流に改変し、米国企業が米国内と同じように活動できる基盤を日本で整備しようとするものでした。
Wikipediaで「日米構造協議」を見てみると、「米国の対日赤字が膨らむ要因は、日本の市場の閉鎖性(非関税障壁)にあるとして、主に日本の経済構造の改造と市場の開放を迫る内容となっている」と書かれています。Wikipediaで「年次改革要望書」を見てみると、「日本政府と米国政府が、両国の経済発展のために改善が必要と考える相手国の規制や制度の問題点についてまとめた文書で、毎年日米両政府間で交換されていた」と書かれています。しかし、
によると、「年次改革要望書は、日米両国が互いに要望書を出し合う形態をとりますが、日本側の要望はまったく実行されません。その実態は米国側が日本に押しつける一方的な政策命令にほかなりません。しかも米国の要求は通信、医療機器・医薬品、金融、エネルギー、流通など多岐にわたり、法律業務、競争政策をふくめ、国の制度自体を変える内政干渉を含んでいました」と書かれています。この要望書の交換はその後も長く続きましたが、民主党鳩山由紀夫政権で一旦廃止されました。しかし、その後鳩山氏と同じ民主党菅直人政権で名前を変えて復活し、安倍政権にもアーミテージレポートという形で引き継がれました。ただ、初めの頃は米国のきびしい要求に対して日本側も抵抗し、米国の望む改革は容易に進みませんでした。そこで、米国は、日本国内の"改革支持勢力"を大きく抱き込みながら、構造改革を迫るようになったのです。