文章を読むときには「事実」と「意見(判断)」の見極めが大事です。
どの記述が「事実」で、どの記述が「意見(判断)」かを正しく見極められないと、誤った情報に踊らされかねません。
<例文1>
今回の住民投票は、賛成が69万4844票、反対が70万5585票。反対派の圧勝に終わった。
↑この場合、票数は「事実」ですが、「反対派の圧勝」は書き手の「判断」です。
正直、70万票対69万票の結果を受けて、「圧勝」という言葉を使うのはムリがあります。
しかし、読み手の側に「事実」と「意見(判断)」を見極める力がないと「そっか、今回の住民投票は、反対派の圧勝だったんだあ」と受け取ってしまう恐れがあります。
「鵜呑みにする」というやつです。
<例文2>
明日使うセミナールームは、20坪程度なので広くありません。
↑この文章を読んだとき、すべてを「事実」として読んでしまうと「そっか、広くないのねー」と受け取るしかありません。
一方で「広くありません」が書き手の「意見(判断)」だと分かっていれば、「え? 20坪って……参加者20名くらいだから、十分に広くないか?」と考えることができるのです。
書き手のなかには、ミスリード(誤り導く)目的で文章を書く人もいます。
読み手に「事実」と「意見(判断)」を見極める力がないと、書き手の「思うつぼ」となるケースが生まれてしまうのです。
もちろん、自分が文章を書くときには、自分の「意見(判断)」を、あたかも「事実」のように書くのはやめたほうがいいでしょう。
読み手に「この書き手は事実と意見を混同している」、あるいは「この書き手は意見を事実のように書いている」と思われれば、書き手として信用をなくす恐れもあります。
書かずに文章がうまくなるトレーニング/サンマーク出版

¥1,512
Amazon.co.jp
伝わる文章が「速く」「思い通り」に書ける 87の法則 (Asuka business & la.../明日香出版社

¥1,512
Amazon.co.jp
だから、読み手に伝わらない! (もう失敗しない文章コミュニケーションの技術)/実務教育出版
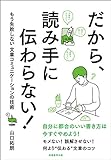
¥1,404
Amazon.co.jp
【山口拓朗の講演・セミナー情報】
講演・セミナーの日程
【人気記事】
なぜ、あなたの文章は分かりにくいのか?
どの記述が「事実」で、どの記述が「意見(判断)」かを正しく見極められないと、誤った情報に踊らされかねません。
<例文1>
今回の住民投票は、賛成が69万4844票、反対が70万5585票。反対派の圧勝に終わった。
↑この場合、票数は「事実」ですが、「反対派の圧勝」は書き手の「判断」です。
正直、70万票対69万票の結果を受けて、「圧勝」という言葉を使うのはムリがあります。
しかし、読み手の側に「事実」と「意見(判断)」を見極める力がないと「そっか、今回の住民投票は、反対派の圧勝だったんだあ」と受け取ってしまう恐れがあります。
「鵜呑みにする」というやつです。
<例文2>
明日使うセミナールームは、20坪程度なので広くありません。
↑この文章を読んだとき、すべてを「事実」として読んでしまうと「そっか、広くないのねー」と受け取るしかありません。
一方で「広くありません」が書き手の「意見(判断)」だと分かっていれば、「え? 20坪って……参加者20名くらいだから、十分に広くないか?」と考えることができるのです。
書き手のなかには、ミスリード(誤り導く)目的で文章を書く人もいます。
読み手に「事実」と「意見(判断)」を見極める力がないと、書き手の「思うつぼ」となるケースが生まれてしまうのです。
もちろん、自分が文章を書くときには、自分の「意見(判断)」を、あたかも「事実」のように書くのはやめたほうがいいでしょう。
読み手に「この書き手は事実と意見を混同している」、あるいは「この書き手は意見を事実のように書いている」と思われれば、書き手として信用をなくす恐れもあります。
書かずに文章がうまくなるトレーニング/サンマーク出版

¥1,512
Amazon.co.jp
伝わる文章が「速く」「思い通り」に書ける 87の法則 (Asuka business & la.../明日香出版社

¥1,512
Amazon.co.jp
だから、読み手に伝わらない! (もう失敗しない文章コミュニケーションの技術)/実務教育出版
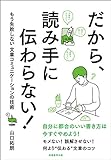
¥1,404
Amazon.co.jp
講演・セミナーの日程
なぜ、あなたの文章は分かりにくいのか?