松平親氏→
松平泰親・三河松平家当主→
松平信光・三河松平家当主→
松平親忠・三河松平家当主→
松平長親・三河松平家当主→
松平信忠・三河松平家当主→
松平清康・三河松平家当主→
松平広忠・三河松平家当主→
徳川家康・征夷大将軍→
徳川頼房・常陸水戸藩初代藩主→
松平頼重・讃岐高松藩初代藩主→
松平頼侯・讃岐高松藩厄介→
松平頼豊・讃岐高松藩三代藩主→
徳川宗堯・常陸水戸藩四代藩主 →
徳川宗翰・常陸水戸藩五代藩主 →
徳川治保・常陸水戸藩六代藩主→
松平義和・美濃高須藩九代藩主→
松平義建・美濃高須藩十代藩主→
徳川茂徳・尾張名古屋藩十五代藩主→
◎徳川達道→
徳川宗敬・(養子・徳川篤敬)→
徳川宗信→
徳川宗親→
徳川宗史
松平義建・美濃高須藩十代藩主→
徳川茂徳・尾張名古屋藩十五代藩主→
◎徳川達道→
徳川宗敬・(養子・徳川篤敬)→
徳川宗信→
徳川宗親→
徳川宗史
ここの部分の親戚を更に深堀りすると・・・
和歌山藩第8代藩主として明和2年(1765年)に就任するも、治世はわずか9年11か月で終わる。20歳で藩主となったが、30歳で隠居し、後を叔父の松平頼淳に譲る。正室を迎えず、晩年は剃髪して太真と号する。文政12年(1829年)に84歳で死去。藩主時代の江戸参府3回、和歌山帰国4回であり、和歌山在国は通算2年7か月と短かった。隠居後の54年4か月間は和歌山と江戸を往来せずに過ごした。
江戸時代中期の大名である徳川治貞は、享保13年(1728年)に誕生。寛保元年(1741年)に伊予西条藩の藩主・松平頼邑の養子となり、宝暦3年(1753年)に藩主に就任。安永4年(1775年)、甥の隠居に伴い和歌山藩主となり、藩政改革を行い財政再建に尽力。倹約政策を重視し、藩の安定を図った。寛政元年(1789年)に62歳で死去し、治政は14年8か月に及んだ。跡を治宝が継いだ。
江戸小石川藩邸で生まれ、若年より聡明で文才に優れたことで知られる。享和3年(1803年)、7歳で将軍徳川家斉の娘・峰姫と婚約、文化11年(1814年)に結婚。文化13年(1816年)に父の死去を受けて家督を継ぎ、藩主となる。水戸藩の財政難に直面しつつも、幕府からの援助を受けて借金返済や助成金を得る。藩政では譜代の重臣に頼りがちで、門閥派の金権政治が続いた。文政6年(1823年)には異国船が頻繁に出没し、文政7年(1824年)には異人上陸事件が発生。これを機に水戸藩で攘夷思想が広がる。斉脩の治世で継嗣問題が表面化し、病気の悪化により文政12年(1829年)に死去。家督は異母弟の敬三郎(斉昭)が継いだ。
江戸時代後期の大名である松平頼恕は、讃岐高松藩の第9代藩主。文化12年(1815年)に高松藩主・松平頼儀の婿養子となり、文政4年(1821年)に家督を相続した。在職中、家老の木村通明と共に藩財政の改革を推進。特に久米通賢を登用し、坂出で大規模な塩田を開発して財政を立て直した。また砂糖作りを奨励し、砂糖為替法を定めた。学問分野では、水戸学の影響を受け『歴朝要紀』を編纂し朝廷に献じた。天保13年(1842年)に45歳で没し、養嗣子の頼胤が跡を継いだ。頼恕の養子入りは高松松平家と水戸徳川家の関係を再び近づけ、高松松平家が初代頼重の血筋に戻る結果となった。
江戸時代後期の大名で、常陸国宍戸藩の7代藩主を務めた。文化4年(1807年)、先代藩主の死去により養嗣子として家督を継承。官位は従五位下・大炊頭、主税頭を授けられた。天保10年(1839年)に死去し、養嗣子である頼位が跡を継いだとされる。法号は又玄院殿道誉上徳先天大居士で、茨城県常陸太田市瑞竜町の瑞龍山に葬られている。
江戸時代後期の公卿であり、二条家25代当主。天明8年(1788年)に京で生まれ、徳川家斉から偏諱を受けた。兄の跡を継ぎ、文化12年(1815年)には右近衛大将兼内大臣に任じられる。その後、左近衛大将や右大臣を歴任し、文政7年(1824年)には左大臣に就任、従一位に叙される。弘化4年(1847年)に薨去。
5年前後で関白職を辞する当時の慣例に反して安政3年(1856年)に辞任するまで、約33年という前例の無い長期にわたって摂政・関白の地位にあり、朝廷で大きな権力を持った。
江戸時代後期の大名である。陸奥国守山藩5代藩主として藩政を担当。天保元年(1830年)に家督を相続したが、藩財政の悪化に直面。豪農・豪商から4500両を借り入れるも、財政はさらに逼迫。結果として農民からの収奪が強まり、減免要求や助郷反対、不正をした村役人の解任要求など、領民による騒動が頻発した。文久2年(1862年)に死去し、後を三男・頼升が継いだ。
江戸時代後期の大名である斉昭は、常陸国水戸藩の第9代藩主として藩政改革を推進した。藩校・弘道館を設立し、人材登用を図り、藩政改革を実施。西洋兵器の国産化や蝦夷地開拓を進めたが、仏教弾圧や幕府との対立により隠居させられた。幕末期には海防参与として幕政に関与し、強硬な攘夷論を唱えたが、開国を主張する勢力と対立し、最終的には蟄居処分を受けた。万延元年(1860年)に水戸で死去した。
江戸時代後期に陸奥国守山藩の第4代藩主として活躍。享和元年(1801年)に家督を継ぐと、菅笠・藍・紅花・養蚕などの殖産興業に力を入れた。菅笠会所を設立し、菅笠・藍玉の前金返済制度を無利息・10年賦とするなど、藩の経済基盤強化を図った。天保元年(1830年)に没し、長男が後を継いだ。著書に『府臣略伝』『守山日記後編』がある。
江戸時代後期の大名として陸奥国二本松藩の9代藩主を務めた。文化10年(1813年)に父の死去に伴い家督を継ぎ、同年に従五位下左京大夫に叙任される。文政元年(1818年)には従四位下へ昇進し、天保元年(1830年)には侍従に、嘉永3年(1850年)には左少将に任官した。安政5年(1858年)には隠居し、六男に家督を譲る。慶応2年(1866年)に死去。

明治時代初期の大名で、美濃国高須藩の最後の藩主。丹波国園部藩主の次男として生まれ、初めは小出英周と名乗った。明治2年(1869年)、高須藩主の養子となり、家督を相続して藩知事に就任するが、翌年には高須藩と尾張藩の合併により免職。明治10年(1877年)には警察職に就き、昇進を重ねたが、明治12年(1879年)に退職。明治14年(1881年)には宮中祗候となるが、同年退職。明治17年(1884年)に子爵に叙され、晩年には駒野城跡を小学校用地として寄付した。大正9年(1920年)に64歳で死去。

幼少期に旧讃岐高松藩主の次男として生まれ、後に尾張徳川家第18代当主となる。明治9年(1876年)、徳川慶勝の婿養子となり、明治13年(1880年)に家督を相続する。華族令制定により侯爵となり、イギリスへ留学しキリスト教に関心を持つ。明治23年(1890年)、貴族院侯爵議員となる。翌年、芸妓との関係が問題となり旧尾張藩士らが騒動を起こすが、徳川一門の介入で収束する。明治41年(1908年)に死去し、家督は義親が継承した。
江戸時代末期の大名で、尾張藩の第16代藩主、最後の藩知事を務めた。幼名は元千代で、幕命によって叔父の徳川茂徳の養子となり、初名を徳成とした。6歳で家督を継いだが、幼少のため実際の執政は父・慶勝が行った。慶応4年(1868年)の戊辰戦争では新政府軍に帰属し、その先鋒として活動した。徳川宗家次期当主候補とされたこともあるが、病弱であったため、18歳で夭折。父・慶勝が再び当主に復帰した。

鳥羽・伏見の戦いの際は江戸幕府の老中であったが、藩主を務める淀藩は藩首脳部の判断で新政府側に付いたことにより老中を辞することになる。
明治維新後は神道に傾倒し、三島神社宮司や大教正などを歴任し、明治初期の神道の発展に寄与した。

毛利元昭は、旧長州藩毛利家の第29代当主であり、1865年に萩で生まれる。明治維新後、東京に移住し、その後家督を継ぎ公爵位を得る。大正5年には貴族院公爵議員となり、麝香間祗候にも任じられる。書に秀で、多くの石碑に揮毫を行った。生涯の大半を防府の多々良御殿で過ごし、その御殿は後に国の名勝に指定される。
明治15年(1882年)9月、オーストリア公使館在勤員外書記生となる。
旧尾張藩主徳川慶勝の十一男として生まれ、1888年(明治21年)に分家して自身の家を持ち、後に男爵となる。学習院中等科を卒業後、陸軍に一年志願兵として入隊し、歩兵少尉に任官。日露戦争に参戦し、軍功により勲六等を授与される。1912年(大正元年)に侍従に転じ、1927年(昭和2年)に退職。生涯にわたって軍人としてのキャリアを築いた。

江戸時代後期の大名であった。天保2年(1831年)に生まれ、高須藩の藩主として嘉永3年(1850年)に就任した。安政5年(1858年)には兄の隠居に伴い尾張藩主となり、徳川茂徳を名乗る。藩内では佐幕派が主に支持を集めた。万延元年(1860年)に養子を迎え、文久3年(1863年)に隠居。慶応元年(1865年)、長州再征の内命を受け、幕政に関与。慶応4年(1868年)の戊辰戦争では徳川家救済に尽力し、明治2年(1869年)には版籍奉還を出願。明治3年(1870年)に一橋藩解体。明治17年(1884年)に没し、法号は顕樹院殿。

明治時代初期の大名で、美濃国高須藩の最後の藩主。丹波国園部藩主の次男として生まれ、初めは小出英周と名乗った。明治2年(1869年)、高須藩主の養子となり、家督を相続して藩知事に就任するが、翌年には高須藩と尾張藩の合併により免職。明治10年(1877年)には警察職に就き、昇進を重ねたが、明治12年(1879年)に退職。明治14年(1881年)には宮中祗候となるが、同年退職。明治17年(1884年)に子爵に叙され、晩年には駒野城跡を小学校用地として寄付した。大正9年(1920年)に64歳で死去。

江戸時代後期の大名で、常陸国府中藩の9代藩主。文化10年(1813年)に世子となり、天保4年(1833年)に父の死去により家督を継ぐ。弘化元年(1844年)には水戸藩主・徳川斉昭の蟄居を命じる役目を果たし、その後も斉昭の跡を継いだ慶篤の補佐を行う。蹴鞠を好み、飛鳥井雅光の門下で紫組の冠懸を許された。明治元年(1868年)に病を理由に隠居し、三男・頼策に家督を譲る。明治17年(1884年)に80歳で死去。
江戸時代中期から後期にかけての武士である。天明7年(1787年)、田安家の屋敷と領地を相続したが、将軍の庶子ではなく御三卿の庶子が相続することに対し、一部反発があった。文化10年(1813年)、将軍家斉の十二男である斉荘を養子に迎えた。天保8年(1837年)、従一位に昇叙される。兄家斉と同様に子女に恵まれ、多くの子女を持ったが、嫡子匡時が病弱を理由に廃嫡され、隠居。養子斉荘が第4代当主となるが、後に実子慶頼が5代当主となり、斉匡が後見となった。嘉永元年(1848年)に70歳で死去。
江戸時代後期の大名である。常陸国水戸藩主・徳川斉昭の十男として生まれ、庶子であった。弘化4年(1847年)、先代藩主の末期養子として越智松平家を相続し、石見国浜田藩の藩主となる。藩政では倹約令を施行し、高津川の治水工事や殖産興業を推進して藩財政を再建。幕末期には佐幕派として第二次長州征討に参加したが、病に倒れ指揮を執れず、浜田城を放棄して逃亡。戊辰戦争では新政府に恭順の意を示すも、病から上京できず、家老の切腹で謝罪を表明した。明治4年(1871年)の廃藩置県後に知藩事を免職され、明治6年(1873年)に隠居。明治15年(1882年)に41歳で死去した。
江戸時代後期における水戸藩10代藩主。父・斉昭が藩政改革で隠居を命じられると、弘化元年(1844年)に家督を継ぐ。幼少期は三連枝の後見を受け、保守派が政務を補佐した。安政の大獄で登城停止となるが、文久2年(1862年)に坂下門外の変を受け、尊皇攘夷派の懐柔に尽力。元治元年(1864年)の天狗党の乱では藩政が混乱。慶応4年(1868年)、勅命を受けて藩政を刷新し、水戸徳川家は朝敵を免れる。4月、水戸城で死去。享年37。墓所は茨城県常陸太田市の瑞竜山墓地。

1880年(明治13年)3月からは外務省の書記官としてイタリア公使館で働いた。1884年(明治17年)の華族令で子爵となる。明治21年(1888年)には式部官となった。 1897年(明治30年)7月10日、貴族院子爵議員に就任し、1899年(明治32年)5月21日の死去まで在任。享年43。家督は定敬の四男である定晴が婿養子となって継いだ。
江戸時代後期の大名である松平容敬は、陸奥国会津藩の8代藩主として知られる。文化3年(1806年)、松平容衆の異母弟として幕府に届けられ、会津藩の後継者として位置づけられた。文政5年(1822年)、容衆の死去に伴い家督を継承し、藩主に就任。文政8年(1825年)には左近衛権少将に任じられた。嘉永5年(1852年)に死去し、享年47。家督は養嗣子の容保が継いだ。

明治時代の知藩事、華族であった。明治2年(1869年)に会津松平家再興を許され、陸奥国で斗南藩主となる。明治3年(1870年)には知藩事に就任し、従五位を受けるが、廃藩置県により知藩事職を失う。幼少から家再興を望まれたが、反抗的な性格で学習院を退学。明治21年(1888年)、同志社英学校に入学。後に東京専門学校を卒業し、日清戦争に参加。明治39年(1906年)、貴族院子爵議員に選出され、在任中に死去した。

会津松平家の12代目当主で、日本海軍において海軍少将に昇進し、日本海海戦に参戦した。貴族院議員としても活動し、会津会や稚松会の総裁を務めた。会津会は会津地方出身者の親睦を図る団体で、松平がその中心人物だった。養女に雍仁親王妃勢津子を迎え、彼女の婚儀を支えた。発病後、東京で急逝し、葬儀は東京と旧領若松市で行われた。

ロンドン在勤、清国在勤を経て、天津総領事、欧米局長、外務次官兼情報部長、駐米大使、駐英大使を歴任。ほかにロンドン海軍軍縮会議首席全権を経験するなど、幣原喜重郎と並ぶ親英米派外交官として知られるようになる。

幕末から明治期にかけての大名であり華族の松平喜徳は、慶応3年(1867年)に陸奥国会津藩の藩主となった。慶応4年(1868年)の戊辰戦争で新政府軍に降伏し、会津を離れ東京へ移る。明治4年(1871年)には斗南藩に預けられ、翌年赦免された。明治9年(1876年)にフランスへ留学し、帰国後、明治17年(1884年)に子爵に叙任される。明治24年(1891年)に37歳で死去し、墓所は谷中墓地にある。養子の頼平が跡を継いだ。

明治9年(1876年)に生まれた上杉憲章は、米沢上杉家の14代当主となる。父・茂憲が沖縄県令を務めた時期に沖縄へ移り、翌年東京へ戻る。学習院で学び、早稲田大学から東京外国語学校へ転学。その後、イギリスのケンブリッジ大学に留学し、帰国後は宮内省御用掛を務めた。家庭では鷹司熙通の長女・房子と結婚し、後に貴子と再婚。大正8年(1919年)には家督を相続する。長男と次男が早世したため、三男の隆憲が後を継いだ。

第13代当主亀井茲明の子として島根県鹿足郡津和野に生まれる。
元政治家の亀井久興は孫にあたる。

1914年家業の左右田銀行取締役及び株式会社左右田貯蓄銀行取締役に就任、翌15年には父が死去したため頭取に就任。神奈川県社会事業協会副会長も務めた。1917年には、父親が創立した横浜商品倉庫で大規模な爆発事故があり、保険金支払いを巡って保険会社と係争となり、重役を務めていた左右田家が損害の一部を負担することになった
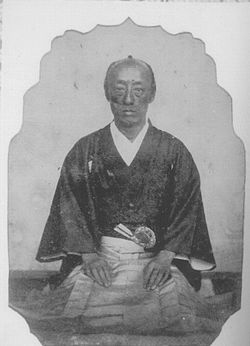
幕末から明治初期にかけて活躍した大名・政治家で、尾張徳川家の当主を務めた。嘉永2年(1849年)、尾張藩の14代藩主に就任し、内政では倹約政策を進めたが、対外では強硬な姿勢を示し、幕府に影響力を持つ。安政5年(1858年)、日米修好通商条約に反対し、井伊直弼に抗議したことで隠居謹慎を命じられる。文久2年(1862年)に復権し、再び政治の舞台に立つ。禁門の変や第一次長州征討など、多くの歴史的事件に関与し、維新後は新政府の議定にも任じられた。明治16年(1883年)、60歳で死去。藩政改革や写真術への興味など、多彩な活動が特徴。
慶応4年(1868年)、二本松藩は奥羽越列藩同盟に加わり、官軍である新政府軍と戦ったが、各地で敗戦。7月29日、二本松城は落城・降伏し、長国は謹慎を命じられた。

鳥羽・伏見の戦いの際は江戸幕府の老中であったが、藩主を務める淀藩は藩首脳部の判断で新政府側に付いたことにより老中を辞することになる。
明治維新後は神道に傾倒し、三島神社宮司や大教正などを歴任し、明治初期の神道の発展に寄与した。

江戸時代後期の大名で、備中国足守藩の第12代(最後)の藩主。従五位下・石見守、備中守として官位を持つ。弘化4年(1847年)に12代将軍・徳川家慶に拝謁し、父の隠居により家督を継いだ。慶応4年(1868年)には上洛し、明治新政府支持を表明。戊辰戦争では備中松山藩の追討に参加した。明治2年(1869年)に版籍奉還で知藩事となり、明治4年(1871年)の廃藩置県で免官。1884年(明治17年)に子爵となり、明治23年(1890年)に59歳で死去した。

藩内が新政府派と旧幕府派で割れていた中、藩主の勝知は旧幕府側に付き、慶応4年(1868年)、旧幕府軍の彰義隊の指揮を任される。一時結城城を奪取するなど奮戦するが、のちに新政府軍の攻撃で落城。明治政府から隠居を命じられた。

美濃大垣新田藩(三河畑村藩)の第8代藩主。のち美濃野村藩主。大垣藩戸田家分家8代。
陸奥国湯長谷藩の第14代藩主。戊辰戦争で先代藩主が新政府軍と敵対し隠居処分となったため、養嗣子として明治2年(1869年)に跡を継ぐ。同年の版籍奉還で知藩事となり、明治4年(1871年)の廃藩置県で免官。明治14年(1881年)に隠居し、長男に家督を譲った。大正8年(1919年)、72歳で死去した。

江戸時代末期の出羽国亀田藩12代藩主である。亀田藩主として、文久元年(1861年)に家督を継ぎ、従五位下・左京大夫に叙位・任官された。慶応4年(1868年)の戊辰戦争では奥羽越列藩同盟に参加するも、後に同盟を脱退して新政府側につくが、庄内藩の説得で再び同盟に復帰し新政府軍と交戦した。最終的に新政府軍に敗れたため、亀田藩は減封され、自身も隠居を命じられた。明治3年(1870年)には亀田藩知藩事の後見人となるが、廃藩置県により免職。その後、家督を再び相続し、子爵となる。明治44年(1911年)に東京で死去した。享年68。
江戸時代後期の大名である。幼少期に藩主となり、数え2歳で高須藩を継ぐ。明治2年(1869年)の版籍奉還により知藩事となるが、同年に病を理由に家督を義生に譲り隠居する。明治24年(1891年)、満31歳で死去した。短命ながらも、時代の転換期に藩主としての役割を果たした。
江戸時代後期の公卿である一条忠香は、関白・一条忠良の四男として生まれた。官位は従一位・左大臣に至り、一条家22代当主を務めた。14代将軍継嗣問題では一橋派を支持し、公武合体派として尊攘派の公家と対立した。余技で絵をたしなみ、鹿背山焼で煎茶器を作らせたほか、煎茶道家元の誕生にも寄与した。文久3年(1863年)に左大臣を辞し、その年に52歳で薨去した。
江戸時代後期の公卿である。文化4年(1807年)に叙爵し、侍従や右近衛権少将などを歴任。文政元年(1818年)に公卿の地位に上る。左近衛権中将や踏歌節会外弁を経験し、文政7年(1824年)に従二位権中納言を務める。天保3年(1832年)からは大歌所別当を兼務するが、天保7年(1836年)に全ての職を辞職し、同年に31歳で亡くなる。

明治期から昭和にかけて活躍した宮中官僚・政治家。田安徳川家第9代当主で、正二位勲一等伯爵を授けられる。兄・徳川家達が徳川宗家を継承した後、田安家の当主となり、父の死後に家督を相続する。明治22年(1889年)にはヨーロッパ視察を行い、貴族院議員や侍従次長、侍従長を歴任。十五銀行の倒産などで経済的に困窮し、邸宅を慶應義塾に売却。野球に熱中し、自宅に運動場を造成し野球クラブを組織するなど、スポーツにも積極的だった。昭和16年(1941年)に75歳で死去。墓所は谷中霊園寛永寺墓地。

明治10年(1877年)に生まれ、徳川慶喜の五男として佐野源次郎方に預けられる。明治13年(1880年)に徳川邸に戻り、学習院に入学。明治23年(1890年)、従兄の侯爵池田輝知の死去に伴い、次女の亨子と結婚し、池田侯爵家を相続。輝博から仲博に改名し、北海道で池田農場を開設。学習院初等科、陸軍士官学校を卒業後、陸軍歩兵少尉に任官。明治42年(1909年)に予備役に編入、貴族院議員を務め、「仁風閣」を建設。昭和22年(1947年)に華族制度の廃止で失爵し、翌昭和23年(1948年)に逝去。墓所は鳥取市の大雲院。

1876年(明治9年)、華頂宮博経親王の死去により華頂宮を継承し、博恭と改名。海軍兵学校予科に入学後、ドイツで海軍教育を受ける。日露戦争では連合艦隊旗艦「三笠」分隊長として黄海海戦に参加し、負傷。以後、海軍内で重要な地位を歴任し、実戦経験豊富な皇族軍人として活躍。1932年(昭和7年)には軍令部総長に就任、1934年(昭和9年)には元帥の称号を受ける。1946年(昭和21年)に死去し、伏見宮家を継承した。

父が隠居した後、公爵を襲爵し貴族院の公爵議員となる。東京帝国大学法科大学を卒業し、政治の道に進む。貴族院議員や第一銀行取締役、華族世襲財産審議会議長を歴任。生涯を通じて日本の政治や経済に貢献した。1922年(大正11年)、東京の本邸で急死。死因は脳溢血とされたが、一部には自殺説も取り沙汰された。没後、正三位勲三等瑞宝章を追贈される。墓は谷中霊園の寛永寺墓地にある。

水戸徳川家第13代当主として生まれ、幼少期に家督を継ぐ。明治20年(1887年)、父がイタリア特命全権公使となり、母と共にローマで過ごす。帰国後、高等師範学校附属学校を経て学習院へ進学し、陸軍士官学校を卒業。明治39年(1906年)、『大日本史』を完成させ明治天皇に献上。陸軍歩兵少尉を務め、後に日本赤十字社社長、第12代貴族院議長を歴任。戦後、公職を辞し公職追放を受けるも、茨城県の山林管理に尽力。昭和42年(1967年)、財団法人水府明徳会を設立し初代会長となる。82歳で死去し、長男が当主を継承。軽井沢に建てた洋館別荘は現在、国の登録有形文化財に登録されている。

勝精は徳川慶喜の十男として生まれ、勝海舟の養子となり伯爵を継いだ。学習院初等学科を卒業後、慶應義塾大学で学び、実業界で活躍した。オリエンタル写真工業や浅野セメントの重役を務める一方、写真やビリヤード、銃猟など多趣味で知られた。特にオートバイに興味を持ち、1923年に国産オートバイ「ヂャイアント号」を製作。これが後に川崎重工業に発展する目黒製作所の設立に寄与した。1932年、愛妾との心中により死去。墓所は東京都台東区の谷中霊園にある。

徳川厚は、江戸幕府最後の将軍・徳川慶喜の四男として生まれ、兄の夭折により事実上の長男として育った。明治15年(1882年)に分家し華族となり、明治17年(1884年)には男爵に叙せられた。学習院を卒業後、旧福井藩主松平春嶽の娘と結婚。貴族院では男爵議員に選出され、1925年まで務めた。実業界では東明火災保険の取締役を歴任。運転免許を取得し自動車を自ら運転するが、飲酒運転で事故を起こし免許返納を命じられた。趣味は幅広く、競馬や絵画などに通じた。

阿波蜂須賀家第17代当主であり、徳川家斉の曾孫である。1871年、徳島南浜邸に生まれる。1886年に渡英し、1890年にケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに入学、1895年に学士号を取得して卒業。帰国後は宮内省の式部官兼主猟官、皇后主事などを歴任する。1885年に徳川慶喜の四女、筆子と結婚。1918年、父の死去により家督を継ぎ、侯爵を襲爵。貴族院侯爵議員となり、1924年には貴族院副議長に就任。1931年に麝香間祗候を仰せ付けられる。脳溢血で62歳で死去し、約100万円の負債が残った。墓所は徳島県徳島市万年山墓所にある。

大蔵書記官、主計局主計課長、専売局主事、大蔵参事官、専売局理事、東京地方専売局長などを歴任した

明治後期から昭和前期にかけて活動した華族であり、陸軍軍人。陸軍騎兵少佐の地位にあり、貴族院議員としても活動した。1898年(明治31年)に家督を継ぎ、侯爵となる。1902年(明治35年)に陸軍士官学校を卒業し、翌年には陸軍騎兵少尉に任官。陸軍騎兵実施学校や陸軍大学校で教官を務める。さらに、宮内省御用掛を兼任し、社会活動としては大日本皇道立教会会頭を務めるなど多岐にわたる役職を歴任した。

幼少期に指物商の元に里子に出されたが、後に戻り学習院に入学。明治41年(1908年)に学習院中等科を卒業し、アメリカのホープ・カレッジへ留学。帰国後、横浜正金銀行に勤務し、海外支店にも赴任。大正2年(1913年)には男爵を授かり、浅野セメントの監査役を務める。昭和21年(1946年)には貴族院男爵議員に選出され、公正会に所属し貴族院廃止まで活動した。墓所は谷中霊園の寛永寺墓地にある。

1865年(元治2年)に田安徳川家の当主となり、1868年(慶応4年)には徳川宗家第16代当主となる。静岡藩主(知藩事)を務め、廃藩置県後は貴族院議員として活躍。1903年(明治36年)から1933年(昭和8年)まで貴族院議長を務め、ワシントン軍縮会議の全権大使や日本赤十字社社長なども歴任。1940年東京オリンピック組織委員会委員長も務めた。

因州池田家第15代当主。父の隠居により明治8年(1875年)に家督を継ぐ。明治法律学校を後援し、明治17年(1884年)に華族令で侯爵を授与される。同年、司法省法学校を卒業。30歳で死去。男子がいなかったため、叔父である徳川慶喜の五男を婿養子として跡を継がせた。墓所は鳥取市の大雲院にある。
因州池田家第17代当主として知られる池田徳真は、1904年(明治37年)に東京市麻布区で生まれる。若い頃からキリスト教に興味を抱き、1921年(大正10年)に初めて聖書に触れる。翌年、キリスト教に関する書籍を贈られたが、両親に新約聖書を没収される。しかし1923年(大正12年)、英語版と日本語版の聖書を再び贈られ、信仰への道を歩み始める。関東大震災で母を失った後、御牧碩太郎との出会いを通じて信仰を深める。徳川慶喜を祖父に持つ家系であり、娘の百合子により家の役目が終焉を迎える。
本籍鹿児島県。陸軍大佐侯爵・西郷従徳の長男として東京府で生れる。母は岩倉具定の二女・豊子。学習院中等科、陸軍中央幼年学校予科、同校本科を経て、1924年(大正13年)7月、陸軍士官学校(36期)を卒業。同年10月、陸軍歩兵少尉に任官し歩兵第1聯隊附となる。1932年(昭和7年)11月、陸軍大学校(44期)を卒業した。

昭和期の政治家で華族。陸軍将校・池田仲博の三男として生まれ、陸軍少将・朽木綱貞の養子となる。1930年(昭和5年)には子爵を襲爵。翌年、東京帝国大学文学部を卒業し、松竹興業社長秘書や東京宝塚劇場嘱託、参謀本部嘱託を歴任。1946年(昭和21年)には貴族院子爵議員に補欠当選し、研究会に属して活動。1947年(昭和22年)の貴族院廃止まで在任した。
