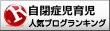こんにちは!
今日は 今まで7つあるとされていた感覚機能にプラスして、8つ目の感覚として注目を浴びつつある機能についてシェアします。
Kelly Mahler というアメリカの作業療法士のインタビューから学んだことのまとめです。
人には自分の周りからの情報を集めて処理する5感と呼ばれる5つの外的感覚(触覚、視覚、聴覚、味覚、嗅覚)、それから体の中の情報を集めて処理する2つの感覚(固有受容覚(手足の状態・筋肉の伸び縮みや関節の動きを感じる感覚)、前庭覚(身体の動きや傾き、スピードを感じる感覚)といった合計7つの感覚があると言われていました。
そこに最近もうひとつ 8つめの感覚がプラスされたことで、注目を集めています。
8つ目の感覚はInteroceptionと呼ばれ、日本語では内受容感覚と呼ばれているようです。
内受容感覚というのは、自分の体の中のさまざまな部分からの情報を集めて処理する感覚のことです。内受容感覚の受容体は体の至るところにあります。 例えば 心臓、肺、膀胱、皮膚、白目、胃、などなど。
こういった体の部分がどう感じているかという情報は、私達がどういった感情を経験しているのかを知る上でとても重要になります。 例えば胃がどういう感じか、空っぽなのか、いっぱいなのか、ガスがたまっているのか、気持ち悪いのか、胃が締め付けられるような感じなのかなどが分からなければ、自分がお腹が空いているのか、お腹がいっぱいなのか、病気なのか、緊張しているのか など、どういった状態なのかを知ることができません。
そして、自分が今どういう感情を経験しているのか ということがはっきりと分からなければ、自分の感情をコントロールして、適切な状態に保つことはできません。
自分が不安感を感じていることに気づくことができれば、そこからパニックにならないように予防したり、対策を考えたりすることができるし、自分がお腹が空いているから力が出ないんだと理解できれば、食事を取って対処することができます。
内受容感覚からの情報で感じることができる「感情」には、私達が普通「感情」というと思いうかぶような不安感、幸福感、悲しみ、喜びなどに加えて、Homeostatic Emotionsと呼ばれる 私達が普段「感情」とは呼ばないような 痛み、病気、空腹、喉の乾き、満腹、体温なども含まれます。
第6感やなんとなく勘が働くなどという時の感覚も内受容感覚です。
研究によると、自閉症スペクトラムの人の多くはこの内受容感覚がうまく機能していないことが分かっています。今までは内受容感覚に対する知識もなかったために 内受容感覚の問題からくる状況が理解されずにいました。
自閉症スペクトラムの人がお腹がいっぱいなはずなのに食べ続けたり、逆に自分からはまったく飲みものを飲もうとしなかったりするのは、この内受容感覚の機能に問題があるために お腹が一杯になったとか 喉が乾いたとかいう体からのシグナルが 食べるのをやめたり水を飲んだりという体を最適な状態に保つための行動に結びつかないことが原因になります。
また、自閉症スペクトラムの人がいきなり癇癪を起こしたりパニックを起こすのは、この内受容感覚の機能に問題があるために、自分が不快に感じる刺激がたくさん入ってきていてもそれに気付いて避けたり対策をとったりするまでに至らず、刺激が限界を超えてはじめて外から見える行動として癇癪やパニックという結果が起こっていることになります。他の人から見ればいきなりなんの理由もなく癇癪やパニックを起こしているように見えますが、実はそうではなく、内受容感覚の問題が原因だったわけですね。
続きます。
読んでいただいてありがとうございます。