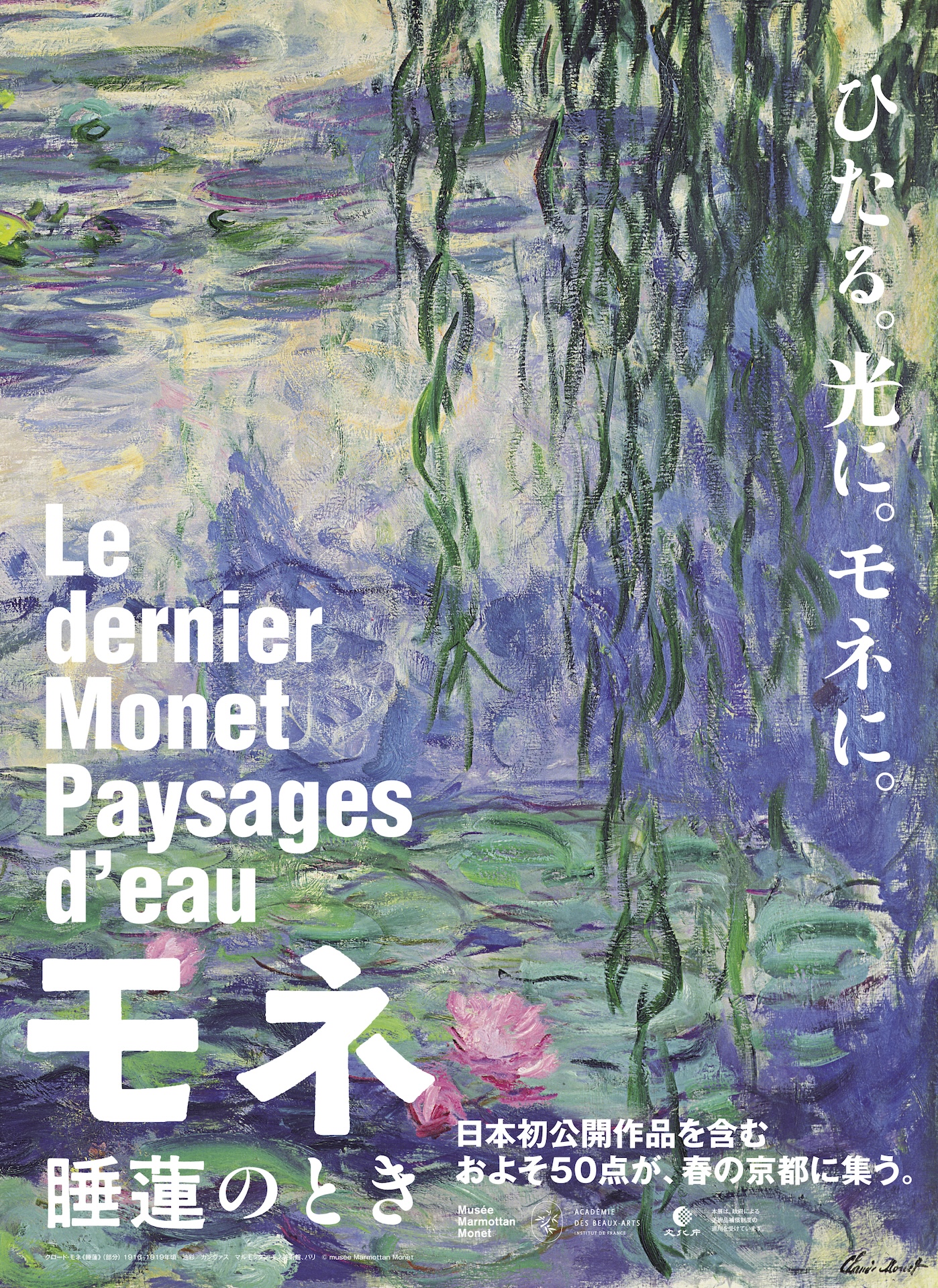京都市美術館のモネ展で
ちょっと興奮してしまったのは、
説明のパネルに「オテル・ビロン」
という文字を見つけたときでした
(フランス語のhôtelには「ホテル」だけでなく、
「(王侯貴族の)館、大邸宅」という意味もあるので、
「ビロン館」と訳します)。
モネは晩年、睡蓮の装飾パネル12点を
国に寄贈しようとします。
そのためにビロン館の敷地に専用の展示館を
建設する計画がもちあがったものの、
結局、財政上の理由から現在の
オランジュリー美術館に変更になった、
という経緯が説明されていました。
パリのオランジュリー美術館といえば、
壁面すべてがモネの睡蓮連作で
埋め尽くされた美術館です。
今回のモネ展でも楕円形の一室が
睡蓮の部屋になっていて、写真撮影もできます。
その庭園で友人と昼食をとったことを覚えています。
そのときはまるで知りませんでしたが、
実はその館にマリー・ダグーが1年間
寄宿生として暮らしていたのでした。
当時その建物はサクレ・クール(聖心会)の
寄宿学校として使われていました。
修道女たちが経営している、
当時もっとも上品だと言われていた学校でした。
マリーは自叙伝「雪下のマグマ」第1部XI章(pp.133-142)で
そこでの生活について語っています。
病気になって医師の処方があるときしか入浴できなかった
(修道女はみだらな肉体からは
できるだけ目を逸らそうとしていたから)とか
「マリアの子どもたち」という一種の
秘密警察組織があったとか、
信じがたい実態が暴かれています。
「マリア様が見てる」(映画・小説)のような
ジャンルに興味のある人には
日本にも聖心女子学院などミッション系の
学校がありますが、その本場というか
源流に位置する学校ということになります。
誰かXI章をベースにした
漫画でも書いてくれないかな、と思います。
ビロン館の敷地に展示館を建設する話が出たのが、
1920年。
聖心会がビロン館を取得したのが1820年、
マリーは1821年4月寄宿学校に入学・入居します。
「オテル・ビロン」の文字だけで
思いは約100年遡ってしまいました。
音声ガイドは雑踏から降り注ぐ騒音から
守ってくれる傘のようです。
ヘッドホンから石田ゆり子さんの
ささやきが聞こえてくると、
甘くひそやかな時間が流れはじめ、
意識は内側に向かいます。
昔日の佳人に思いを致し、
今日の美声を聞き、
睡蓮の池が連なる中をそぞろ歩くひとときでした。