第十八候「ぼたんはなさく」
新暦:4/30-5/4ころ。
「牡丹散りて
うちかさなりぬ二三片」 蕪村
鯉のぼりの時節。
博多では博多どんたく。
「博多どんたく」は、
治承3年(1179年)に始まったと
筑前国続風土記(貝原益軒著)に記されている
「松ばやし」をその起源とする凡そ830年余の伝統行事である。
筑前国続風土記には、
『平安時代、京都御所の正月、
宮中参賀の行事が地方に伝わり、
この博多では源平時代のち冶承3年(1179)、
正月15日、松囃子を取行う…』とある。
以来、祝いあう行事をシャレッ気の多い
博多町人が発展させたものである。
古い文献によれば今から400年前、
筑前の領主となった
小早川秀秋の居城(東区名島城)へ
博多の町人が松囃子を仕立て
年賀のお祝いに行ったと記されている。
その後、黒田藩の城下町となった「福岡」と
博多町人の町「博多」との二つの町が270年間、
博多松囃子を通じて交流している。
明治5年、新政府より下りてこられた県知事によって
松囃子・山笠共中止させられたが、
その後、明治12年に再開され
「博多どんたく」と呼ばれるようになった。
オランダ語のZondag(ゾンターク、休日の意)が
その語源と言われている。
また八十八夜一番茶の時期でもあります。
先の句のように
牡丹の時節でもあります。
魚は、「鮎魚女(あいなめ)」。
野菜は「蕗」。
「クレソン」も時期です。
次節からは夏となります。
- くらしのこよみ 七十二の季節と旬をたのしむ歳時記/平凡社
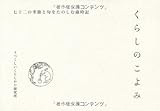
- ¥3,218
- Amazon.co.jp
- くらしのこよみ 七十二候の料理帖/平凡社

- ¥1,512
- Amazon.co.jp
- 日本の七十二候を楽しむ ―旧暦のある暮らし―/東邦出版

- ¥1,728
- Amazon.co.jp
