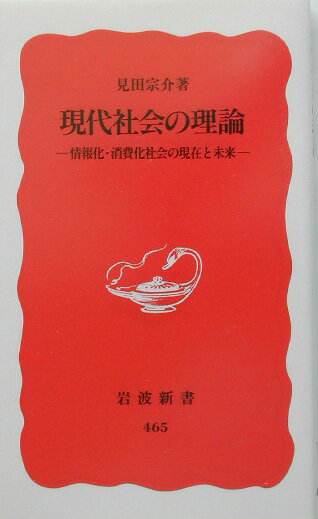ルンペンはなぜ放送禁止用語になったのか?
ルンペンはなぜ放送禁止用語になったのか?その背景には、言葉の意味の変化と、時代ごとの価値観の違いが関係しています。
※この記事では「ルンペン」という言葉の歴史や社会的背景について解説しています。
より深く知りたい方は、以下のような書籍も参考になります。
①「ルンペン」の語源と本来の意味
ルンペンという言葉は、もともとはドイツ語の「Lumpen(ボロ布、ぼろきれ)」が語源です。
この言葉はやがて、カール・マルクスの『ルンペン・プロレタリアート(Lumpenproletariat)』という概念に転用され、「意識を持たない下層労働者層」「無職で反社会的な存在」といった意味合いで用いられるようになりました。
日本ではこの概念が縮められ、浮浪者やホームレスとほぼ同義として使われるようになりました。
しかし、言葉自体が含む侮蔑的なニュアンスは次第に問題視されるようになります。
②昭和には日常的だったが今はタブー
昭和の時代には、ルンペンという言葉はテレビ番組や小説、漫画などでも一般的に使用されていました。
実際、昭和初期の新聞小説などを通じて広まり、世間に広く浸透していた言葉です。
しかし、平成の時代に入るころには、徐々に「差別的な言葉ではないか?」という認識が高まり、使われる頻度は激減していきました。
その背景には、社会の価値観が多様化し、「他人をラベリングする言葉」に対する感受性が強まったことが挙げられます。
③放送業界が避ける理由とは?
放送業界がルンペンという言葉の使用を避ける理由は、視聴者からの反発やクレームを恐れてのことです。
言葉そのものに法的な禁止はないものの、各メディアは自主的なガイドラインを設け、差別的とされる表現の排除に取り組んでいます。
特に公共性の高いNHKなどでは、放送倫理に厳しい規定があり、一度クレームがついた言葉は以後使われなくなることが多いのです。
つまり、放送禁止用語とは「使ってはいけない」と法律で定められているのではなく、「使うと炎上するから使わない」という判断によって生まれているのです。
④朝ドラ『まんぷく』でなぜ使用されたのか
そんな中で話題となったのが、2018年に放送されたNHKの朝ドラ『まんぷく』。
この作品では、登場人物のセリフの中で「ルンペン」という言葉が使用され、大きな注目を集めました。
実はこの使用には、きちんとした意図がありました。
『まんぷく』の時代背景は昭和13年~昭和45年ごろであり、その当時は「ルンペン」という言葉が社会的に一般化していたのです。
⑤NHKが使った背景にある判断とは
NHKは、ドラマの時代考証を忠実に再現するため、「現代では放送禁止用語だが、当時のリアリティを損なわないために必要」として、あえてこの言葉を使ったのです。
視聴者に向けても「作品の歴史的背景を重視した表現である」と丁寧に説明し、批判を最小限に抑える努力をしていました。
つまり、時代背景の中での使用は、例外的に許されるケースがあるということですね。
⑥現代社会における「ルンペン」の認識
現在では「ルンペン」は、使用すれば差別的だと受け取られる可能性が高く、一般的にはほとんど使われません。
若い世代の中には、この言葉の意味をそもそも知らない人も多いのが現実です。
一方で、文学作品やフィクションの中では、あえて使用されることもあります。
表現の自由と差別的表現の間で、微妙なバランスが求められる時代になっているのです。
⑦差別用語とされるまでの歴史的経緯
もともと社会学的な文脈で使われていた言葉が、なぜ差別用語とされるようになったのか。
それは、時代の変化とともに「弱者に対するレッテル貼り」への批判が高まり、特定の層を傷つける可能性がある言葉は「放送に不適切」とされるようになったからです。
ルンペンもその一例であり、「差別の意図がない」としても、使った瞬間に問題視される時代となったのです。
放送禁止用語の決まり方とその基準とは?
放送禁止用語の決まり方とその基準は、法律による規制ではなく、各メディアや放送局が設ける「自主規制」によるものです。
①法律ではなく業界ガイドラインが基準
まず大前提として、放送禁止用語というのは法律で定められているわけではありません。
民間のテレビ局やNHKは、それぞれに放送倫理規定を設け、「この言葉は使用しない」といったリストを自主的に作っています。
この背景には、視聴者からの信頼を守るという姿勢があります。
不快に思われたり、苦情につながる言葉は、あらかじめ排除しておこうという意識があるのです。
②視聴者からのクレームが影響する仕組み
言葉が放送禁止扱いになる大きな要因のひとつが、「視聴者からのクレーム」です。
何気なく使われた言葉でも、差別的だと受け取られた場合、SNSやBPO(放送倫理・番組向上機構)を通じて抗議が殺到することがあります。
結果として、テレビ局はその言葉をNGワードとして社内で扱い、以後の番組で使用しなくなります。
こうして「誰かを傷つけるかもしれない言葉」は、メディアから姿を消していくのです。
③「差別的であるか」の判断基準とは
差別的かどうかの基準は非常にあいまいで、主観的な要素が強く含まれています。
過去には「精神病院」「めくら」「びっこ」などの言葉が使用禁止になった例がありますが、これも時代によって変化しています。
「昔は普通に使っていた」という言葉でも、現在ではNGになるケースが多いのが特徴です。
④時代とともに変わる言葉の価値観
言葉というのは、生きています。
社会の空気や人々の意識の変化によって、その価値観は日々変わっていきます。
そのため、今日許されている言葉が、数年後にはNGになる可能性もあるのです。
逆に、過剰な自主規制が「言論の自由を侵害している」と批判されることもあります。
ルンペンという言葉が持つ社会的背景とは?
最後に、「ルンペン」という言葉が抱える社会的背景を掘り下げてみましょう。
①マルクスが定義したルンペン・プロレタリアート
マルクスは、資本主義の矛盾を示すために「ルンペン・プロレタリアート」という層を設定しました。
これは、労働者でありながら、階級意識が乏しく、革命にも参加しない最下層の人々を指します。
つまり、ただの「貧しい人」ではなく、「体制にも関与しない浮遊層」として捉えられていたのです。
②日本で使われるようになった経緯
日本ではこの思想が昭和初期に流入し、社会問題や文学の中で多く引用されるようになりました。
やがてマルクスの定義から離れ、日常語としての「ルンペン」が独り歩きしていきます。
③浮浪者とホームレスの違い
「ルンペン=浮浪者」と考えられがちですが、ホームレスとの違いは曖昧です。
一般的にホームレスは住居を持たない人、浮浪者は定職がなく街を徘徊している人という認識ですが、社会的には同一視されることも少なくありません。
④生活保護制度との関係
日本には生活保護という制度があり、住居を失った人も支援を受けられるはずです。
しかし、現実には「住所がないと申請できない」「身元を明かせない事情がある」などの理由で、制度を利用できない人も存在します。
そのため、制度の隙間からこぼれ落ちた人々が、「ルンペン状態」に陥ってしまうのです。
【関連商品】ルンペン・社会問題に関連する書籍・映画