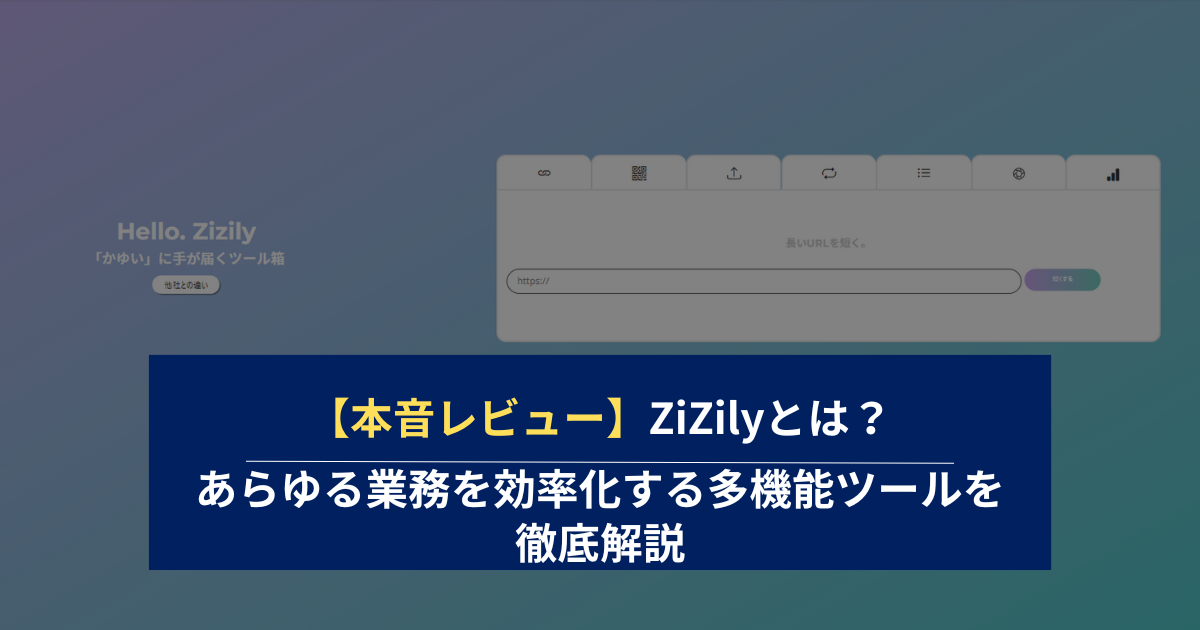バーコードの誕生
今までの話からガラッと変わりますが、ここで少し毛色を変えたブログをやりたいと思います。ネットやテレビの画面、チラシや雑誌に載っていたり、今や目にしない日はないQRコード、このQRコードは、誰がつくりだして、どのように普及していったのでしょうか、今回はQRコードと、
竹花貴騎氏の会社MDSが提供する「zizirly(ジジリー)」というQRコード作成ツールについてのブログです。
QRコードについて述べるにはバーコードについて話をしないといけません。バーコードは商品の値段・名前・などの情報を読み取って素早く正確に計算すること、どの商品がどれだけ売れたのかを記録すること、減った商品をどれだけ追加すればよいか調べること、またどれだけ在庫が残っているかを調べる棚卸や利益を計算を便利にするためのものです。バーコードが開発され普及する前の食料品業界ではスーパーマーケットのなどの食料品店で在庫を正確に確認するのに、店内のすべての商品を手作業で数えるしかありませんでした。もちこんたださえでも忙しいのに膨大な数の商品をすべて数えるなど無理なので、店の責任者たちは恣意的な感情も入れて大雑把な在庫の見積もりで棚卸を月に1回行うぐらいでした。 もちろんレジも手入力しますから、遅くて混雑も当たり前でした。これでは店の正確な利益は計算できまん。また時代が進むにつれて小売店の競争も激しさを増しており、経営者たちはいかにして店の利益を正確に把握して、客に早く欲しい商品を売るかいうことに苦心するようになっていました。
バーコード誕生のきっかけはスーパーマーケットの重役が、アメリカのペンシルベニア州フィラデルフィアにある私立大学でのドレクセル大学の工学部長に、地元のスーパーマーケットの重役が商品の情報を素早く入力できる技術を開発してレジの行列を早くさばけないかといった相談をしているのを、大学院生のバーナード・シルバーさんが人づてに聞いたことだったといいます。工学部長は重役の相談に応じませんでしたが、バーナードさんはこの話に興味を持ち、すでにドレクセル大学の大学院で講師ととなっていた先輩のノーマン・ジョセフ・ウッドランドさんにも話を持ち掛けます。
ウッドランドさんはこの技術にはボーイスカウト時代に学んだ、モールス符号が必要であると考えました。モールス符号とは短点(・)と長点(-)でだけでアルファベットなどの文字を表現するものです。ちなみにこのモールス符号をの短点を「トン」長点を「ツー」という音にして文章などの情報を相手に伝えるのがモールス信号です。ウッドランドさんはマイアミの砂浜で、点と線を指で砂に書いてみたことがきっかけで、モールス符号途に海岸の砂浜で印刷して伸ばし、太い線と細い線で円の符号(コード)作ってみることを思いつき、これがバーコードの原型となりました。
こうして2人はこの円形コード特許を1952年10月7日に取得しました。最初のバーコードは今のような縦じまではなかったのです。しかしこの円形コードを読み取るには500ワットの白熱電球を使用した机ぐらいの大きなオシロスコープが必要で高額な費用がかかり、商用には利用できませんでした。ウッドランドさんは1951年にIBMに入社し、IBMに円形コードの技術を発展させるように説得しますが、やはり商用に開発することは困難でした。シルバーさんとウッドランドさんは家庭電気製品のメーカーであるPhilco:Philadelphia battery company(フィルコ:フィラデルフィア・バッテリー・カンパニー)にこの円形コードの特許をわずか15000ドルで売却してしましました。Philcoさらに放送・通信機器・コンピューターのメーカーであるRCA:Radio Corporation of America(後にGE:General electricに吸収)に特許を売却してしまいます。
1960年代後半、いよいよアメリカの食料品業界は追い込まれてきました。郊外のスーパーマーケットは活況を呈し、年間売上高は1000億ドルを超えていましたが、レジ打ちには相変わらず時間がかかり、混雑はひどくなり、間違いも多発していました。当時150万人といわれた食料品店従業員の多くは、何千もの商品に値札を付けたり、レジの手入力にもますます負担がかかり従業員の多くは手首のしびれや腱鞘炎にも悩まされました。さらに悪いことに、店では在庫やどんな商品が売れているかをほとんど把握できなくなってきました。この極めて深刻な状況に、食料品業界の主要な経営者たちは、小売業者、製造業者、消費者の利益のために、どの店でも利用できる、食料品にコードを付与して、コンピューターで管理する新しいシステムが必要であることを痛感。「統一食料品コードに関する米国スーパーマーケット特別委員会」を結成し、コンピューター企業などに提案を求め、条件に合っていて最も優れたコードを特別委員会が選定して採用することになりました。
RCAはウッドランドさんが考案した円形コードの開発を続けていました。1971年には、円形コードを安全に読める手頃な価格のレーザースキャナーと、その情報を解読できるintelの部品が組み込まれたマイクロコンピューターも開発され、円形コードの商用化が現実的になっていたのです。RCAはアメリカの食品小売業団体であるNAFC:National association of food chainsの関心をを呼び込み、開発を加速させます。RCAが採用していたバーコードはウッドランドさんが考案した円形のバーコードでした。この動きに注目したIBMは、ウッドランドさんをノースカロライナ州の施設に移し、バーコード開発に重要な役割を与えました。またウッドランさんのIBMの同僚であったジョージ・ローラーさんは、ウッドランドさんが考案した円形コードを縦じまの垂直のバーコードにデザインし直します。これで円形コードよりもインクの消費が少なく、安定して読み込めることができたのです。円形コードの発案者であったはずのウッドランさんもローラーさんの考えに賛成しました。
特別委員会ではIBMとRCAを含めた7つの会社からコードが最終候補として残り、その中でIBMとRCAがより優れているとされ、最終的に特別委員会は1973年3月にRCAの円形コードではなく、IBMのバーコード選定され、UPC:Uniform Products Code(統一商品コード)として採用されることになりました。
そして1974年6月、オハイオ州トロイのマーシュ・スーパーマーケットで販売されたリグレーのチューインガムの1袋。これがローラーさんのデザインしたバーコードがレジでスキャンされた最初の商品となりました。UPCは当初、消費者には正確さに疑問を抱かれ、労働組合は失業者が出ることを懸念。食品製造業者は、バーコードラベルの印刷の費用に不満を示し、小売業者はバーコードの利点を自体を疑いました。しかし食料品業界の主要な経営者たちほぼ強制的にUPCを利用させ、IBMもUPCの利用の支援を行います。するとバーコードの利点は徐々に明らかになりました。小売業者は在庫を調べるのが容易になり、IBMの調べではレジの列は40%速く動くようになったといいます。購入履歴の記録により、小売業者は消費者の需要に合わせて適切な量と種類の商品供給が可能になり、利益が正確に把握でき、店員は商品の情報を苦労してレジを手入力する必要がなくなったのです。Kmartなどのアメリカ有数の小売業者もUPCを採用。
1980年代にはUPCはより広範囲に利用されるようになり、工場や図書館でも在庫を調べられるようになりました。こうしてUPCはどんどん普及し、アメリカ・カナダをはじめ、世界の食品や雑貨など身近な店のほとんどの商品に使用されているバーコードとなりました。その後もIBM以外の競合他社などが工業用など様々なバーコードを開発、UPCは8桁から13桁の数字しか情報量がありませんが、アルファベットの大文字、小文字、記号などが使えて、いくつも並べていけば、桁数も自由なバーコードも登場し、現在ではバーコードは100種類ほどのあるといわれています。
ちなみにしま模様のバーコードはこれ以前にも別のところで既に開発されていました。マサチューセッツ工科大学出身のデビッド・ジャレット・コリンズさんが、学生時代にペンシルバニア鉄道で働いていたときに、広大なアメリカの鉄道網では車両がどこにに行ったのかがわからなくなり、車両を探すのに、膨大な時間と手間がかかることがよくあったことや、正確な貨車輸送を実現し、貨車を貸し出す会社に対し正しい請求書を送付するためには車両を追跡する必要性があると考え、卒業後に入社したコンピューター会社で「KarTrak 」という、黒い背面に赤や青のしま模様のバーコードによる鉄道車両識別システムを開発します。
Public domain
1967年にアメリカのすべての貨車にKarTrakのバーコードの付与が義務付けられました。上記の写真のように、大きなスキャナーが線路脇につくられこれでバーコードを読み取るのです。KarTrakは1970年代を通じて使用されていましたが、読み取り精度の低さ、バーコードのメンテナンスに手間がかかること、コンピューターにかかる費用が高額などの利用で1978年には廃止されました。
日本では、1970年代初めにバーコードがダイエーと三越百貨店でテスト導入されたものの、導入費用が高いことから普及しませんでした。しかしセブンイレブンがバーコードの利点に着目し、莫大な投資をあえて行い、1984年、当時約2000店あった店舗すべてで導入し、レジ行列の解消、在庫切れ商品の削減など投資に見合う成果をあげます。こうして他のコンビニエンストアや小売店もバーコードを続々と導入し、日本で一気に普及しました。
QRコードの誕生
そして今度はQRコードですが、これは日本で開発された技術です。物がない昔と比べて物があふれた豊かな時代になると、ただ安くてよい商品だけでは売れなくなり、顧客の要望に合わせた商品をつくり差別化しないといけなくなりました。そのため、製造現場は多品種少量生産へ移行します。1980年代までに、製造業界、物流業界、小売業界などで長年、広く使われてきバーコードでしたが、多品種少量生産とコンピューターの普及による通信技術の進歩や情報システムの高度化を背景に詳細な生産管理と大容量化が求められるようになりました。
1992年、トヨタ自動車グループの自動車部品メーカーのデンソーのバーコードスキャナなどの開発に携わっていた原昌宏さんは製造現場からバーコードの読み取りのさらなる高速化の要望を受けます。当時、生産現場では、バーコードを書類上に複数並べることで容量の限界を補っていました。ただ英数字で限られた桁数しか記録・表示できないバーコードでは、作業者は1日に約1000回もの読み取りが必要で、大変非効率になっており、汚れにも弱くて読み取れないことも問題になっていました。
あとバーコードは最初アメリカで作られたものなので日本語を出すことはできません。製品の小型化も進み、より小さい面積に印字できるコードも求められていました。当時はバブル経済が崩壊した直後でデンソーのバーコード事業も苦境に立たされ、新しい分野での事業を起こさざるを得なくなっていました。原さんは自分を含めたった2人だけのチームで開発を引き受けます。
横方向にしか情報を持たないバーコードは「一次元コード」というのに対し、水平方向と垂直方向に情報を持つQRコードのようなのコードのは「二次元コード」といいます。二次元コード自体はアメリカで1970年代始め頃から開発されており、過去にはマイクロソフトも開発していました。原さんが開発にとりかかかった頃も、アメリカでも新しい二次元コードの開発が始まっていました。
デンソー社内にはアメリカが新しく作った二次元コードを利用すればよいのではないか、という意見がありましたが、アメリカのものは大容量の情報を重視しており、精度としては10回中1回読み取れる程度と聞いた原さんは今から開発しても勝負できると考えました。デンソーは1974 年にトヨタ自動車の生産管理にバーコードを入れることを提案し、そのバーコードを読み取る装置を開発、その事業で培った技術も活用し1年間半かけて苦労して、1994年に新しいコードがようやく完成します。
原さんが開発した二次元コードは工業用の油で汚れやすい工場などの製造現場で使用されることを想定してつくられているため、コードは最大で30%くらいが欠損しても、コード自体がデータを復元する「誤り訂正機能」で破損や汚れがあっても読み取ることができるようになっています。
数字で約7000文字、漢字の表現もできて、バーコードと比べ物にならない大容量。しかも他のコードより10倍以上の1秒間に30回という高速で、どの角度からでも正確に読み取れる、世界でも類を見ない性能を持つものでした。この二次元コードは「Quick Response」という英語のそれぞれの頭文字をとって「QRコード」と名付けられました。「Quick Response」とは「素早く読み取る」という意味です。
デンソーQRコードの特許は保有しているものの、規格化されたQRコードについては権利行使はしないとしました。特許とは発明を公開する代わりに、その発明を保護する制度のことです。特許権を得ると、出願から20年間、権利の対象となる発明の実施(生産・使用・販売など)を独占できて、使用料をとったり、権利侵害者に対して差し止めや損害賠償請求もできます。ただこれら特許権を行使しないというのは開発当初から決めていたことで、より多くの人にQRコードを使ってもらいたい、という原さんたちの気持ちの表れでした。
そして2002年にはQRコードを読み取る機能を持つ携帯電話が発売され、QRコードの普及につながりました。デンソーはQRコードが普及した後で企業に使うときは、QRコードがデンソーの登録商標であることを文章で表示してほしいと頼みました。こうしてQRコードがさらに普及するにつれ、様々な企業のカタログ・パンフレット・ホームページにデンソーの社名が載るようになり、大きな宣伝効果となりました。またQRコードを開発したデンソーの部署は2001年に「デンソーウェーブ」という子会社に再編されました。
ちなみに商標登録とは商品やサービスにつける名前・ロゴ・会社名などを特許庁に登録し、この商標のついた商品はこの会社がつくっています商標登録をすることで、その名前ロゴ・会社名について他人が使用することを防ぐことができる、という利点があります。その結果、自社の商標を守ることができるのです。商標登録は登録料を納付すれば、10年間ずつ期間を更新できるので実質、永久に存続させることができます。あとQRコードはバーコードにとって代わるものでありません。バーコードスキャナーの方が安いですし、QRコードほど情報を必要とせずバーコードでも十分な製造、物流、医療、倉庫などの現場もたくさんあるからです。
読み取るだけでWEBサイトへの接続、買い物の支払い、割引券の取得、名刺交換、乗り物や入場券の発券、Wi-Fi接続などができるQRコードは人々の生活に欠かせないものとなっています。2021年2月のIvantiの調査によると、QRコードを使ったことのある人の割合は日本が6割ほどだったのに対し、最も高いイギリスが9割を超え、中国も9割弱、アメリカ・フランス・ドイツも7割を超えて、世界に広がっており、まさにQRコードは日本初の世界的イノーベーションとなっています。
zizily
最初に述べたようにユアユニの主宰である、竹花貴騎氏の会社MDSがも「zizirly(ジジリー)」というQRコードのデザインをカスタマイズしてつくれるツールを出しています。またzizirlyは「業務効率化ツール」をうたっており、QRコードの作成以外にも、以下の機能があります。
●短縮URLの作成
●容量の大きい書類・画像データの圧縮
●動画などの大容量データアップロードと共有
●リンクツリーの作成
●PCのスクリーンショット・画面録画の共有(PCソフト利用)
●Googleマップの口コミ・インスタのフォロワーを増やす
またタイムスケジューリング機能(やるべき仕事・作業や日程・時間調整を手助けする機能)タスクアラーム機能(重要な仕事・作業などの日程を知らせる機能)などの新しい機能も開発中となっています。以下のサイトではzizilyのちょっとした使い方も載っています。zizilyはできることが多くなる有料版もありその料金は月8.7ドル(2025年4月現在で約1277円)です。
zizirly操作も単純で広告も出ません。ネット上には様々なツールがありますが、メールアドレスと名前とパスワード登録だけで使える無料ツールなのでぜひPC画面などで一度使ってみてください。基本的にはスマホよりもPCで使うツールです。
zizilyの話はここまでです。最後にユアユニにはメール指定された課題をブログに書くと、1件につき2000円の報酬がもらえるプログラムもあります。私は2年前から200本以上のブログを書いて報酬をもらい、その金額は40万円以上にもなります。2025年2月のブログの報酬は7520円でした。少ないようにも思えますが、ユアユニで学べる上にお金を貰えると考えれば、悪いものではないと思いますし、勉強する気が全くなかった私が200本以上のブログを書くぐらい変わることができたので、ユアユニに入ってよかったです。興味のある方は以下のリンクから是非見てみてください。無料体験期間もあります。
Y.H X(旧Twitter)
竹花貴騎の会社が作ったツールだが、操作も単純。複数の機能が一つにまとめられているもがいい。無料で広告もなくこれだけのことはなかなできないと思う。ぜひ一度試してほしい。
— URUで勉強する壮年 (@wJYqoBq2Bv36945) April 3, 2025
業務効率化ツール zizily(ジジリー)でQRコードをカスタマイズ!https://t.co/mrzI5LmBXQ