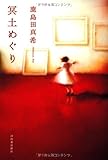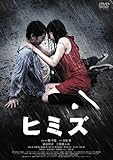- 前ページ
- 次ページ
しかも必然性もなく長い。
ネットのレビューでけっこう高い評価を得ていたが、本当にちゃんと見たのかと唖然とした。
全編を通じて、「どうだお前らは、こういうのが好きなんだろ」いう、監督の得意気な顔が浮かんでくる。
非常に不真面目で軽薄な映画だ。
愛について本当に真摯に向きあっているとは到底思えない。
「愛を乞う人」の方が数百倍良い。(あれは親子の愛を扱った作品だが)
良いとこも一応触れておくと、一つはタイトル。
非常にことばのセンスを感じる。
もう一つは、まだ二つしか見てないが、この監督は主人公の若い女の子を可愛く見せるのに長けていると思う。
黒田の人柄がよくわかる本だった。
勝負の世界には珍しく良い人なんだなと思う。
そんな人物は世界最高峰のヤンキースにまで登りつめるのは凄いことだと思う。
本の中では広島への愛着も語られていたが、戻ってはこないんじゃないかと思った。
ファンとしては早く広島に復帰してほしいところではあるが。
予告編を見て、面白そうだったので観賞。
映画を見た段階ではドラマの存在を知らず、
ドラマは後から見たのだが、
ドラマ版の方が圧倒的に面白く、人間も描けていた。
ドラマをまだ見てない人は、ぜひお勧めしたい。
映画は見ても見なくてもどっちでもいいなという感じだった。
園子温監督という存在は全く知らなかったのだが、
何かでみて面白そうだなと感じ、最近の作品をレンタルしてみた。
今作にかんしては、イマイチだった。
特に、時節柄なのか、無理やり被災地の映像を挟み込んで、
被災地から流れてきた人物を登場させている部分がひどい。
二人の物語とは必然性がなく違和感がある。
最後に、頑張れ頑張れと二人に叫ばせ、
そこに被災地の映像を重ね合わせいるのは、
エールのつもりなのかもしれないが、全くもって浅はかで、
当事者への侮辱でさえあると思う。
ただ、主役の女の子は非常に可愛くてよかった。
「愛のむきだし」「冷たい熱帯魚」あたりが良いらしいので、
それを見てみたいと思う。
本書は水俣と福島をつなぐ書である。
本書を読むと、水俣がいまだ何ら解決していないことがわかる。
そして、二つの土地の共通点が見えてくる。
この国は田舎を、どこか暗いもの、忌むべきものとして描き出してきた。
だからこそ、人々は灯りをもとめ、チッソや原発を自らの土地を明るく照らすものとして受け入れてきた。
いまでも、チッソに恩を感じている人がいるというのは驚きだった。
本書の中では、かつてあった田舎のたわいもない一つ一つの出来事を、
本当に豊かで奥深いものとして振り返っている。
しかし、それは今だから分かることなのかもしれない。
無くなった今だからこそ、余計と尊く思えるのだ。
藤原 やっぱりまだチッソに対してのシンパシーというか、思い入れを持っている人はたくさんいるんですか。
石牟礼 たくさんいらっしゃいます。
藤原 これだけ結果が出ていても、やっぱりそうですか。
石牟礼 はい。
藤原 人間というのは愚かですね・・・・・・。
石牟礼 でも、なんというか、最初の、世の中が開けるはじめの事業に自分たちも参加するという、そんなふうに思い込まれた。それを「チッソに義理を立てる」とおっしゃいますね。義理を立てるというのは、恩恵をこうむったことに対して義理を立てると思いたいですけれど、まったく一方的な心情ですね。「もう義理も切れた」という人もいます。「義理」って、何か関係が生じて、具体的なことが起きたときの絆をいいますよね。「信用貸し」という言葉があったりしますでしょう。人間は信用がいちばん。最初信用してしまったんですよ。チッソを。おそらく、私のおじいちゃん、おばあちゃんの時代ですね、そう思い込んだのは。
(前略)
藤原 そういった自然と一体化した共同体というのが昔はあったわけですね。たぶんそのままでよかったんでしょう、ほんとうは。そのまま時間が止まっていれば貧しいながらも平穏な世界がそこにはあった。
本書を読むと近年の日本の経済的衰退がよくわかる。- 経済力という日本の唯一の強みが失われた中で、
- それでも日本にやってくる外国人がいるとすれば、
- いったい日本の何に魅力を感じてくれているのであろうか?
- 非常に興味深いし、その答えこそが日本再生のカギのような気がする。
第146回芥川賞受賞作。巧い。そして読み易い。
現代に”地”そして”血”というモチーフで書き続けている作家が他にいるだろうか?
そういう意味では、多くの人が指摘する通り非常に古臭い。
(個人的には、”地”そして”血”が今の時代、読むに値するテーマなのか、
若干の疑問がある。)
しかし、モチーフは古臭いものの、
逆に、そこに登場する男は非常に現代的なのである。
父と子を主要テーマに置いたのであれば、
最終的には子が父を乗り越えるという過程が描かれているのが普通であるが、
主人公は、父と同じ暴力性をもった自分の血を恐れているにもかかわらず、
結局、自分からは何もしないのである。
父を否定も肯定もせず、土地から離れようともしない。
主張し行動するのは周りの女ばかりなのである。
そういう意味で現代性のある小説と言えなくもないが、
残念ながら過去の同じようなテーマの名作と比べると、
こじんまりとしており、圧倒的に底暗さが不足している。
今、この国にはノッペラボウの言葉しか存在しない、
辺見庸は、現代社会を、こう言い表している。彼が挙げたのはたとえばこんな表現。
「原子力安全・保安院が、福島第一原子力発電所1~3号機から放出された放射性セシウム137が、
広島に投下された原子力爆弾の168個分にあたるという試算を公表した」
辺見氏は言う。
「具体的、実証的に見える数字を列挙していながら、この記事はあまりにもとりとめがない」と。
「膨大と無の同居」であると。それが「残忍な現代社会の最大の特徴である」と。
逆に、自問自答し、思索を深めてきた言葉として、
原民喜の『夏の花』の次の一節を挙げている。
「スベテアッタコトカ アリエタコトナノカ パット剥ぎトッテシマッタ アトノセカイ」
結局、我々人間には言葉しかないのだと思う。
今みたいな薄っぺらな言葉ではなく、心をかき乱すような本物の言葉。
設定で躓くと物語に入っていけないかもしれない。
しかし、そこは拘らずに見ることができた。
ここに書かれるのは非常に残酷な世界だが、
現実世界もそんなに差がないのかもしれないと思えてしまう。
原作も読んでみようかと思う。