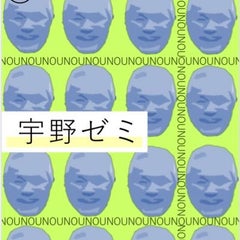担当:そか、ちゆ、はさ
4組織の社会構造
4-1社会構造概念の起源
4-1-1ドイツの経済学者・社会学者マックス・ウェーバーの理念的官僚制
a官僚制の特徴
b組織の理念型を示した
b-2抽象的・観念的な性格が理論化の有益な基礎になる
c信頼できる意思決定、実績に基づく選抜と昇進、非人格的でそれゆえ公平な規則の適用を保証した
←平均的な能力以外何も持たない従業員を、官僚制の顧客と構成員に公平さと能率をもって奉仕する合理的な意思決定者に変えるモデルを生み出した
dモダニストの組織論者はウェーバー理論に基づき、組織の社会構造の3つの中核概念を明らかにした
4-1-2分業
a責任分担をし、作業タスクを割り振る
b組織に求められた成果を能力的かつ有効に生み出す
Ex)自動車生産工場の組み立てライン、銀行や教育、医療サービスを提供するプロセス
c同種ないし密接に関係のある活動を組織の下位単位へまとめることが部門や事業部を作り出し、そこから組織構造の結合が作られる
4-1-3権限の階層
a階層とは組織における権限の配分のこと
b公式の命令・報告関係を定めている
b-1下方と上方という組織の垂直のコミュニケーション・チャネルにあたる
b-2組織全体の権限とタテのコミュニケーションは最も上位に当たる個人のところで結合する(階層の原則)
←組織のどの地位も別の地位に一つだけ従うとき
c効率的に組織全体の情報を集め、仕事の遂行に指示を与え、コントロールすることが可能に
4-1-4公式化された規則と手続き
a公式化
a-1明示的な規則、規制、方針、手続きが組織の活動を統治する程度を含む
←どのように意思決定が遂行されるかを明確にする
a-2イノベーションを阻害しコミュニティを抑制する
⇔非官僚制組織は柔軟性や自発性を示す
b多くの社会が官僚制組織を作り維持する利点がある
←ルーティン技術を安定した環境下で活用するとき
Ex)政府、大学、カトリック教会やマクドナルドなど
4-1-5組織の社会構造を測定する
a広く用いられている組織の社会構造の次元
b測定尺度
b-1集権化:意思決定を行う権限が、組織のトップレベルに集中している程度
b-2公式化:組織が文書の(つまり公式の)職務記述書、規則、手続き、コミュニケーションを用いる程度
c最良の構造の選択は他の変数次第である、つまりコンティンジェントであるとモダニストは信じるようになる
4-1-1ドイツの経済学者・社会学者マックス・ウェーバーの理念的官僚制
a官僚制の特徴
b組織の理念型を示した
b-2抽象的・観念的な性格が理論化の有益な基礎になる
c信頼できる意思決定、実績に基づく選抜と昇進、非人格的でそれゆえ公平な規則の適用を保証した
←平均的な能力以外何も持たない従業員を、官僚制の顧客と構成員に公平さと能率をもって奉仕する合理的な意思決定者に変えるモデルを生み出した
dモダニストの組織論者はウェーバー理論に基づき、組織の社会構造の3つの中核概念を明らかにした
4-1-2分業
a責任分担をし、作業タスクを割り振る
b組織に求められた成果を能力的かつ有効に生み出す
Ex)自動車生産工場の組み立てライン、銀行や教育、医療サービスを提供するプロセス
c同種ないし密接に関係のある活動を組織の下位単位へまとめることが部門や事業部を作り出し、そこから組織構造の結合が作られる
4-1-3権限の階層
a階層とは組織における権限の配分のこと
b公式の命令・報告関係を定めている
b-1下方と上方という組織の垂直のコミュニケーション・チャネルにあたる
b-2組織全体の権限とタテのコミュニケーションは最も上位に当たる個人のところで結合する(階層の原則)
←組織のどの地位も別の地位に一つだけ従うとき
c効率的に組織全体の情報を集め、仕事の遂行に指示を与え、コントロールすることが可能に
4-1-4公式化された規則と手続き
a公式化
a-1明示的な規則、規制、方針、手続きが組織の活動を統治する程度を含む
←どのように意思決定が遂行されるかを明確にする
a-2イノベーションを阻害しコミュニティを抑制する
⇔非官僚制組織は柔軟性や自発性を示す
b多くの社会が官僚制組織を作り維持する利点がある
←ルーティン技術を安定した環境下で活用するとき
Ex)政府、大学、カトリック教会やマクドナルドなど
4-1-5組織の社会構造を測定する
a広く用いられている組織の社会構造の次元
b測定尺度
b-1集権化:意思決定を行う権限が、組織のトップレベルに集中している程度
b-2公式化:組織が文書の(つまり公式の)職務記述書、規則、手続き、コミュニケーションを用いる程度
c最良の構造の選択は他の変数次第である、つまりコンティンジェントであるとモダニストは信じるようになる
4-2組織の社会構造のモダニスト理論
4-2-1構造コンティンジェンシー(条件適合・環境適応)理論
aイギリスの組織論者バーンズとストーカーの理論
b複数の類型と分類を生み出し、実際の構造的次元の型を表せるようになった
c複数の特徴をグループ分けできるようになった
d有効な組織はその構造を組織のコンティンジェンシー要因、つまり環境に適合させる必要がある(オーストラリアの組織論者レックス・ドナルドソンの主張)
e組織が採用した形態がどのように成功の機会を左右するかについての初期の研究の一つでもある
4-2-2機械的組織と有機的組織、集権化、リーダーシップスタイル
a機械的形態
a-1高度の階層的管理、明確に定義された役割とタスク、集権的な意思決定
a-2柔軟性や創造性、イノベーションの阻害
b有機的形態
b-1革新的でタスクを遂行する従業員に自由裁量を与えやすい
b-2公式の規則や手続きに束縛されていない
b-3分権化した意思決定は権限と責任を階層の下位レベルに押し下げる
b-3技術と訓練を使う自由裁量と、問題を提起し解決する柔軟性がある
cほとんどの組織はこれら二つの組織形態を両方持つ
d集権化は下層従業員の参加を最小にとどめる
⇔分権的な組織は、組織の多くのメンバーが意思決定プロセスに参加するが、コントロールが難しい
4-2-3分化と統合
aローレンスとローシュ
a-1組織の業務遂行の有効性は、組織の社会構造と環境の適合によって決まると考えた
a-2組織が垂直・水平に分化し、より複雑になればなるほど、結合とコミュニケーションが必要になる
a-3「結合」を努力の連合体を実現するために必要な共同、(つまりみんなを共通の方向へ引っ張ること)と定義した
b分化と統合は興味深い共依存関係を生み出す
c適切な分化水準と統合の手法は、問題となっている組織や部門、また関連する環境によって異なる
4-2-4組織規模
aアストン大学の研究
a-1組織の社会構造を測定する六つの定量的尺度を開発
←専門化、標準化、公式化、集権化、コンフィギュレーション、柔軟性
a-2階層のどのレベルがその意思決定を行う権限も持っているのかを明らかにした
b規模が社会構造の他の次元と予期せぬ形で相互に影響を与え合っていることも明らかにした
4-2-5コンティンジェンシー理論の現在
aドナルドソンはコンティンジェンシー要因が組織論の本質であると断言した
a-1発見し続けることが、最善の組織化方法とは何か、という問いの障壁にもなっている
a-2すべての組織論には適用可能範囲があり、一部の組織にしか適用できないことを示した
a-3組織化には多数の異なる方法があるということを気づかせた
b明らかにした限定条件
b-1小規模組織では機械的形態の組織化は適切ではない
b-2大規模組織では最も効率的←標準化されたサービスや製品を提供する Ex)マクドナルド
4-2-6類型と分類法
aカナダの組織論者ヘンリー・ミンツバーグの組織構造の5つの類型←単純構造、機械的官僚制、専門職官僚制、分権的形態、アドホクラシ―
a-1組織構造の規範的理論の発展を促した
a-2組織デザイン学派←組織内外の要求に基づいて異なる組織形態を推奨する=組織をデザインする
b組織形態の多様性を記述した分類学的アプローチ←モダニストの組織論者ウイリアム・マッケルビー
4-2-7構造変化のモデル
a構造変化に着目するモダニストのモデル
a-1大きく分けて2つの理論
a-2進化モデル←静的な状態や段階を経てどのように発展していくかを示す
a-3構造変化モデル←日常生活文脈における変化のダイナミクスに注目する
a-4進化モデルはモダニストの枠組みにある
a-5ダイナミクスモデルはシンボリック・パースペクティブに視座がある
b組織構造の発展段階について異なる考え方
b-1ラリー・グレイナーのライフサイクル理論←組織の成長を進化期間の連続とみる
b-2ダニエル・カッツとロバート・カーンのオープンシステムモデル←技術と社会の圧力から社会構造ができる
b-3アンソニー・ギデンズは組織構造を構成する要素のダイナミックな役割について述べる←構造化理論と構造と行為主体性の二重性概念から
4-2-8組織のライフサイクル
a組織は企業家、集合、権限委譲、公式化、協働の段階を経る
a-1段階特有の問題と危機が存在する
b企業家段階
b-1小規模な状況で生じる←直接のフィードバックと密接な監督を受けられる
b-2企業家的組織は専門経営者を必要としていることに気づく←組織外部からor内部で育つ専門経営者
b-3専門経営者が必要だと納得させることが危機をもたらす←企業家が今まで通りやればうまくいくと思っているため
b-4リーダーシップの危機←初期の分化と経験不足の経営者によって
c集合段階
c-1過度の集権化の結果から危機が生じる←意思決定プロセスへの過重負荷
c-2経営者は階層下部が求める意思決定についていけなくなる←機能し続けるには解決しなければならない
c-3自律性の危機←経営者が集権的意思決定を他の人に任せるのは難しいと思ってしまっている
d権利委譲段階
d-1意思決定の分権化が始まるとさらなる統合の必要性
d-2コントロールの危機←必要性が大きくなるにつれて
d-3官僚制にする←公式化段階
e公式化段階
e-1形式主義の危機←経営者が官僚制に頼りすぎる
e-2公式の規則と手続きを普遍的に、没人格的なやり方で運営←従業員に嫌われる環境
f協働段階
f-1過度に分化してしまったタスクをまとめ直す
f-2共同責任を割り当て直し、仕事を理解し直させる
f-3統合スキルとリーダーシップスタイルに質的転換が必要になる
f-4刷新の危機←経営者のモティベーションの再生がうまくいかない、無気力状態
f-5新しい形態を生み出すか、組織の縮小と終局の死をもたらすか
4-2-9組織構造発展のオープンシステムモデル
a構造の発展
a-1最初は技術的必要件
a-2のちに環境からの要求に結びついた内部の総合圧力
a-3原始的組織から何段階にも分けて発展する
b購買、販売といった活動がコアの生産活動から構造的に分化する
b-1この段階の分化は組織に緩衝的余力をもたらす
b-2従業員が原材料を製品へと変換することに集中する
b-3他の人は、変換プロセスに供給する仕事と生産物をその環境へと移す仕事に特化する←原材料が滞りなく行われるようにする
b-4支援活動と名付けられる
c分化が進行
c-1干渉しあわない購買、生産、販売の3つの機能を持つ
c-2ゼネラルマネージャーによる統合が必要になる
Ex)購買の注文と生産のスケジュール監督
d維持活動
d-1成果を生み続けられる安定した状態に保つことを助ける
d-2生産コアから独立←統合が必要になる
d-3新しい管理者の階層が出現する
d-4さらに分化が加速する
e環境変化に遭遇する←製品需要に影響するような
e-1組織に問題をもたらす
Ex)販売予測、購買計画、生産計画
e-2適応活動を導入する
e-3環境変化に注意を払う、変化の意味を読み取る
Ex)経営者による意思決定、戦略計画、経済予測、市場調査、R&D、納税計画、法務活動、ロビー活動
4-2-10構造化理論
a構造化という用語は、モダン・パースペクティブとシンボリック・パースペクティブの中間に位置する
a-1この理論は、概念である構造と構造化する行為主体性を結ぶ
b構造と主体性が相互作用する
b-1どちらかの概念が特別重要なわけではない
b-2ギデンズは構造と行為主体性の二重性と呼ぶ
b-3主体は資源、ルーティン、期待から成る構造によって可能になり、または制約を受ける
b-4そこで形成される活動が次の段階の構造化を促す
b-5構造的文脈は、シンボルの持つ意味、権力が行使される関係、規範を規定する解釈枠組みとなる
Ex)会話様態、階層、文化による同調圧力の行使など
cフランスの社会論者ピエール・ブルデューは構造の側を強調する2つの概念を提示
c-1場とハビトゥス
c-2場は構造である←階級的な関係を確立する内部論理を持つ
c-3資本は権力や影響力の有無を表すもの
c-4場は行為者の行為によって変化する
c-5ハビトゥスはあらゆる場に浸透し、個人はゲームのセンスを得る←階級上の地位を考慮し振舞えるようになる
c-6外部者からは不可侵、内部者からは暗黙知
dアメリカの社会学者ムスタファ・エミルベイヤーとアン・ミッシェは第3の構造化理論を発表←行為主体性を強調
d-1主体が構造を生み出すキープロセスは3つ
←反復、実践による評価、投射
d-2反復は、再生産するルーティンのために過去の行動パターンを再利用する
d-3実践による評価によって、変化する状況に即した判断が可能になる
d-4投射を通じて、将来の可能性が創造的選択肢を生み、既存構造の再構成が可能になる
4-2-1構造コンティンジェンシー(条件適合・環境適応)理論
aイギリスの組織論者バーンズとストーカーの理論
b複数の類型と分類を生み出し、実際の構造的次元の型を表せるようになった
c複数の特徴をグループ分けできるようになった
d有効な組織はその構造を組織のコンティンジェンシー要因、つまり環境に適合させる必要がある(オーストラリアの組織論者レックス・ドナルドソンの主張)
e組織が採用した形態がどのように成功の機会を左右するかについての初期の研究の一つでもある
4-2-2機械的組織と有機的組織、集権化、リーダーシップスタイル
a機械的形態
a-1高度の階層的管理、明確に定義された役割とタスク、集権的な意思決定
a-2柔軟性や創造性、イノベーションの阻害
b有機的形態
b-1革新的でタスクを遂行する従業員に自由裁量を与えやすい
b-2公式の規則や手続きに束縛されていない
b-3分権化した意思決定は権限と責任を階層の下位レベルに押し下げる
b-3技術と訓練を使う自由裁量と、問題を提起し解決する柔軟性がある
cほとんどの組織はこれら二つの組織形態を両方持つ
d集権化は下層従業員の参加を最小にとどめる
⇔分権的な組織は、組織の多くのメンバーが意思決定プロセスに参加するが、コントロールが難しい
4-2-3分化と統合
aローレンスとローシュ
a-1組織の業務遂行の有効性は、組織の社会構造と環境の適合によって決まると考えた
a-2組織が垂直・水平に分化し、より複雑になればなるほど、結合とコミュニケーションが必要になる
a-3「結合」を努力の連合体を実現するために必要な共同、(つまりみんなを共通の方向へ引っ張ること)と定義した
b分化と統合は興味深い共依存関係を生み出す
c適切な分化水準と統合の手法は、問題となっている組織や部門、また関連する環境によって異なる
4-2-4組織規模
aアストン大学の研究
a-1組織の社会構造を測定する六つの定量的尺度を開発
←専門化、標準化、公式化、集権化、コンフィギュレーション、柔軟性
a-2階層のどのレベルがその意思決定を行う権限も持っているのかを明らかにした
b規模が社会構造の他の次元と予期せぬ形で相互に影響を与え合っていることも明らかにした
4-2-5コンティンジェンシー理論の現在
aドナルドソンはコンティンジェンシー要因が組織論の本質であると断言した
a-1発見し続けることが、最善の組織化方法とは何か、という問いの障壁にもなっている
a-2すべての組織論には適用可能範囲があり、一部の組織にしか適用できないことを示した
a-3組織化には多数の異なる方法があるということを気づかせた
b明らかにした限定条件
b-1小規模組織では機械的形態の組織化は適切ではない
b-2大規模組織では最も効率的←標準化されたサービスや製品を提供する Ex)マクドナルド
4-2-6類型と分類法
aカナダの組織論者ヘンリー・ミンツバーグの組織構造の5つの類型←単純構造、機械的官僚制、専門職官僚制、分権的形態、アドホクラシ―
a-1組織構造の規範的理論の発展を促した
a-2組織デザイン学派←組織内外の要求に基づいて異なる組織形態を推奨する=組織をデザインする
b組織形態の多様性を記述した分類学的アプローチ←モダニストの組織論者ウイリアム・マッケルビー
4-2-7構造変化のモデル
a構造変化に着目するモダニストのモデル
a-1大きく分けて2つの理論
a-2進化モデル←静的な状態や段階を経てどのように発展していくかを示す
a-3構造変化モデル←日常生活文脈における変化のダイナミクスに注目する
a-4進化モデルはモダニストの枠組みにある
a-5ダイナミクスモデルはシンボリック・パースペクティブに視座がある
b組織構造の発展段階について異なる考え方
b-1ラリー・グレイナーのライフサイクル理論←組織の成長を進化期間の連続とみる
b-2ダニエル・カッツとロバート・カーンのオープンシステムモデル←技術と社会の圧力から社会構造ができる
b-3アンソニー・ギデンズは組織構造を構成する要素のダイナミックな役割について述べる←構造化理論と構造と行為主体性の二重性概念から
4-2-8組織のライフサイクル
a組織は企業家、集合、権限委譲、公式化、協働の段階を経る
a-1段階特有の問題と危機が存在する
b企業家段階
b-1小規模な状況で生じる←直接のフィードバックと密接な監督を受けられる
b-2企業家的組織は専門経営者を必要としていることに気づく←組織外部からor内部で育つ専門経営者
b-3専門経営者が必要だと納得させることが危機をもたらす←企業家が今まで通りやればうまくいくと思っているため
b-4リーダーシップの危機←初期の分化と経験不足の経営者によって
c集合段階
c-1過度の集権化の結果から危機が生じる←意思決定プロセスへの過重負荷
c-2経営者は階層下部が求める意思決定についていけなくなる←機能し続けるには解決しなければならない
c-3自律性の危機←経営者が集権的意思決定を他の人に任せるのは難しいと思ってしまっている
d権利委譲段階
d-1意思決定の分権化が始まるとさらなる統合の必要性
d-2コントロールの危機←必要性が大きくなるにつれて
d-3官僚制にする←公式化段階
e公式化段階
e-1形式主義の危機←経営者が官僚制に頼りすぎる
e-2公式の規則と手続きを普遍的に、没人格的なやり方で運営←従業員に嫌われる環境
f協働段階
f-1過度に分化してしまったタスクをまとめ直す
f-2共同責任を割り当て直し、仕事を理解し直させる
f-3統合スキルとリーダーシップスタイルに質的転換が必要になる
f-4刷新の危機←経営者のモティベーションの再生がうまくいかない、無気力状態
f-5新しい形態を生み出すか、組織の縮小と終局の死をもたらすか
4-2-9組織構造発展のオープンシステムモデル
a構造の発展
a-1最初は技術的必要件
a-2のちに環境からの要求に結びついた内部の総合圧力
a-3原始的組織から何段階にも分けて発展する
b購買、販売といった活動がコアの生産活動から構造的に分化する
b-1この段階の分化は組織に緩衝的余力をもたらす
b-2従業員が原材料を製品へと変換することに集中する
b-3他の人は、変換プロセスに供給する仕事と生産物をその環境へと移す仕事に特化する←原材料が滞りなく行われるようにする
b-4支援活動と名付けられる
c分化が進行
c-1干渉しあわない購買、生産、販売の3つの機能を持つ
c-2ゼネラルマネージャーによる統合が必要になる
Ex)購買の注文と生産のスケジュール監督
d維持活動
d-1成果を生み続けられる安定した状態に保つことを助ける
d-2生産コアから独立←統合が必要になる
d-3新しい管理者の階層が出現する
d-4さらに分化が加速する
e環境変化に遭遇する←製品需要に影響するような
e-1組織に問題をもたらす
Ex)販売予測、購買計画、生産計画
e-2適応活動を導入する
e-3環境変化に注意を払う、変化の意味を読み取る
Ex)経営者による意思決定、戦略計画、経済予測、市場調査、R&D、納税計画、法務活動、ロビー活動
4-2-10構造化理論
a構造化という用語は、モダン・パースペクティブとシンボリック・パースペクティブの中間に位置する
a-1この理論は、概念である構造と構造化する行為主体性を結ぶ
b構造と主体性が相互作用する
b-1どちらかの概念が特別重要なわけではない
b-2ギデンズは構造と行為主体性の二重性と呼ぶ
b-3主体は資源、ルーティン、期待から成る構造によって可能になり、または制約を受ける
b-4そこで形成される活動が次の段階の構造化を促す
b-5構造的文脈は、シンボルの持つ意味、権力が行使される関係、規範を規定する解釈枠組みとなる
Ex)会話様態、階層、文化による同調圧力の行使など
cフランスの社会論者ピエール・ブルデューは構造の側を強調する2つの概念を提示
c-1場とハビトゥス
c-2場は構造である←階級的な関係を確立する内部論理を持つ
c-3資本は権力や影響力の有無を表すもの
c-4場は行為者の行為によって変化する
c-5ハビトゥスはあらゆる場に浸透し、個人はゲームのセンスを得る←階級上の地位を考慮し振舞えるようになる
c-6外部者からは不可侵、内部者からは暗黙知
dアメリカの社会学者ムスタファ・エミルベイヤーとアン・ミッシェは第3の構造化理論を発表←行為主体性を強調
d-1主体が構造を生み出すキープロセスは3つ
←反復、実践による評価、投射
d-2反復は、再生産するルーティンのために過去の行動パターンを再利用する
d-3実践による評価によって、変化する状況に即した判断が可能になる
d-4投射を通じて、将来の可能性が創造的選択肢を生み、既存構造の再構成が可能になる
4-3シンボリック・アプローチ:社会実践、制度的理論、コミュニティ
aシンボリック・パースペクティブからの組織構造(=組織の社会構造、以下は組織構造と記す)の研究について
bモダニストの組織論者は、「構造=事物、実体、客体、要素」と捉える←組織の存在は組織図、方針、規則などの事柄から分析することで確認できる
b-1シンボリックの組織論者は、「構造=人の意識や物的資源など社会的相互作用によって生まれる=人間の創造物」とみなす←組織は存在しない、あるのは組織化のみである(ワイクの主張)
cシンボリック組織論者の関心は、組織メンバーの日常的実践がどのように組織化のパターンを構築するのか
4-3-1社会的実践:ルーティンと即興
a組織構造を構築、維持する実践にはどのようなものがあるか←ルーティン、即興
bルーティン
b-1モダニストの組織論者は「ルーティン≒組織の習慣、プログラム、遺伝子」にたとえてきた←組織構造の安定に役立つもの
b-2アメリカ組織論者のマーサ・フェルドマン
b-2-1「ルーティン=アイディア、行為、結果が連続する流れ」と定義←ルーティンそのものも無限に再生産される
b-2-2組織内でも組織間でもルーティンは影響を受けてさまざまにむすびつき変化する
b-2-3用いられなければ廃れることも
Ex)警察官やソーシャル・ワーカーのDV事件への対応
c即興
c-1アメリカ組織論者のカール・ワイク
c-1-1組織構造は固定的でないプロセス←相互作用するルーティンと即興が出現し続けるために
c-1-2ルーティンに即興をはさむことで組織構造を再生産、安定をもたらす
c-1-3役に立ったらすぐに消滅するかもしれない、反復され広く受け入れられ制度化されてルーティンの一部に組み込まれるかもしれない
Ex)ジャズの演奏における即興、料理のレシピにおける隠し味
c-2このような実践により、既存のルーティンや実践を維持しながら、継続的に組織構造を刷新していくことが可能に←組織に新しい選択肢をもたらすため
4-3-2制度的論理としての社会構造
aモダン的な考えにシンボリックな考えを取り入れた組織構造についての考え方
b組織論者ロバート・ドラジン、メアリー・アン・グリン、ロバート・カザンジアン
b-1構造は社会的に共有された意味を備えるようになり、それゆえその「客観的」機能に加えて、組織についての情報を組織内外の人びとに伝えるようになる
b-2あくまで組織構造は、意味を備えた「対象」であると仮定←モダン的な考え方
b-3組織の意味は、制度的文脈によって形成される←シンボリックな考え方
4-3-3コミュニティとしての社会構造
a実践共同体
a-1教育学者エティエンヌ・ウェンガーとジーン・レイヴ
Ex)サブゼミ
a-2学習と知識発達に関する共通利害によって、例えばルーティンなどのレパートリーを共有する人の集団のこと
a-3非公式的な結びつき←学校や"ゼミ"のような階層関係でもなく公式関係でもないむすびむき←経営者の役割や、組織学習とイノベーションが可能
b言語共同体
b-1共通の言葉が構造の安定をもたらしている集団のこと
Ex)業界用語、テレビ業界、モダニスト集団
b-2組織ならではの表現を発達させることで、メンバーは組織の経験について語る方法を共有するようになる
b-3自分たちなりの語り方が組織構造の特徴を創造・維持する
c不安定と幻想という特徴をもつ←言葉は変化するものであるため←言葉の共有によってつくりあげられた共同体という意味で幻想的
aシンボリック・パースペクティブからの組織構造(=組織の社会構造、以下は組織構造と記す)の研究について
bモダニストの組織論者は、「構造=事物、実体、客体、要素」と捉える←組織の存在は組織図、方針、規則などの事柄から分析することで確認できる
b-1シンボリックの組織論者は、「構造=人の意識や物的資源など社会的相互作用によって生まれる=人間の創造物」とみなす←組織は存在しない、あるのは組織化のみである(ワイクの主張)
cシンボリック組織論者の関心は、組織メンバーの日常的実践がどのように組織化のパターンを構築するのか
4-3-1社会的実践:ルーティンと即興
a組織構造を構築、維持する実践にはどのようなものがあるか←ルーティン、即興
bルーティン
b-1モダニストの組織論者は「ルーティン≒組織の習慣、プログラム、遺伝子」にたとえてきた←組織構造の安定に役立つもの
b-2アメリカ組織論者のマーサ・フェルドマン
b-2-1「ルーティン=アイディア、行為、結果が連続する流れ」と定義←ルーティンそのものも無限に再生産される
b-2-2組織内でも組織間でもルーティンは影響を受けてさまざまにむすびつき変化する
b-2-3用いられなければ廃れることも
Ex)警察官やソーシャル・ワーカーのDV事件への対応
c即興
c-1アメリカ組織論者のカール・ワイク
c-1-1組織構造は固定的でないプロセス←相互作用するルーティンと即興が出現し続けるために
c-1-2ルーティンに即興をはさむことで組織構造を再生産、安定をもたらす
c-1-3役に立ったらすぐに消滅するかもしれない、反復され広く受け入れられ制度化されてルーティンの一部に組み込まれるかもしれない
Ex)ジャズの演奏における即興、料理のレシピにおける隠し味
c-2このような実践により、既存のルーティンや実践を維持しながら、継続的に組織構造を刷新していくことが可能に←組織に新しい選択肢をもたらすため
4-3-2制度的論理としての社会構造
aモダン的な考えにシンボリックな考えを取り入れた組織構造についての考え方
b組織論者ロバート・ドラジン、メアリー・アン・グリン、ロバート・カザンジアン
b-1構造は社会的に共有された意味を備えるようになり、それゆえその「客観的」機能に加えて、組織についての情報を組織内外の人びとに伝えるようになる
b-2あくまで組織構造は、意味を備えた「対象」であると仮定←モダン的な考え方
b-3組織の意味は、制度的文脈によって形成される←シンボリックな考え方
4-3-3コミュニティとしての社会構造
a実践共同体
a-1教育学者エティエンヌ・ウェンガーとジーン・レイヴ
Ex)サブゼミ
a-2学習と知識発達に関する共通利害によって、例えばルーティンなどのレパートリーを共有する人の集団のこと
a-3非公式的な結びつき←学校や"ゼミ"のような階層関係でもなく公式関係でもないむすびむき←経営者の役割や、組織学習とイノベーションが可能
b言語共同体
b-1共通の言葉が構造の安定をもたらしている集団のこと
Ex)業界用語、テレビ業界、モダニスト集団
b-2組織ならではの表現を発達させることで、メンバーは組織の経験について語る方法を共有するようになる
b-3自分たちなりの語り方が組織構造の特徴を創造・維持する
c不安定と幻想という特徴をもつ←言葉は変化するものであるため←言葉の共有によってつくりあげられた共同体という意味で幻想的
4-4ポストモダンの社会構造:脱・分化、フェミニスト組織、反・統治
aモダンは、「階層、集権化、統制、統合、構造のような隠れた秩序が実在を説明」
a-1ポストモダンは、「どんな構造も実在を説明しなあ、言葉のみが表面的に概念を正当化できる」
a-2モダニズムの構造や統制などの言葉が権力者たちの一方的な支配を助け正当化 Ex)植民地化
a-3関心は、概念、構造、経営実践を脱構築することで、これらがどのように秩序、合理性、統制を前提としているのかを明らかにすること
4-4-1脱・分化
a組織が分化すれば統合が必要になる、それがまたさらなる分化をうみ、の繰り返し←2-2-3分化と統合、ローレンス&ローシュによるモダニズム理論
a-1組織は絶え間ない発展軌道から抜け出せないという問題←グレイナーやナッツ&カーンのモダニズム理論
bイギリス社会学者のスコット・ラッシュ
b-1「脱・分化」の概念を提案
b-2これが、モダニストが推進してきた理論を逆転させるだろう
cオーストラリア組織論者のスチュワート・クレッグ
c-1モダニストの分化と統合の理論を批判し「脱・分化」による統合を主張←統合は階層と関係なく成し遂げられる
c-2メンバーに自身の活動の自己管理と調整を認めることで組織の活動を統合させる←上からの指示やマニュアルによってメンバーの活動を統合するのではなく
4-4-2フェミニスト組織
aジェンダーや人種にもとづく組織構造について
bモダニズム的な官僚制を脱構築して分析
b-1官僚制=男性性的、基本的に白人男性支配型、権力(パワー)と地位によって階層に特権を認めて正当化
b-2その結果、女性や有色人種やマイノリティを支配する傾向
cフェミニスト組織=より平等で柔軟な構造、参加的意思決定、協力的行為、共同社会の理想が実現できる場
Ex)女性の健康管理センター、DVシェルター
dカレン・リー・アッシュクラフト
d-1フェミニスト官僚制=官僚制とフェミニスト組織のハイブリッド
d-2タスクは、公式かつ非公式、専門化するが全般的、階層と集権化は存在するが平等主義と分権的な実践によるもの
4-4-3反・統治理論
aアメリカ哲学者・経済学者のデイビッド・ファーマー
a-1「官僚制的統治」の理論に、「反・統治」をぶつけることで、これを中和できると考えた←酸性とアルカリ性を混ぜると中和するように
a-2官僚制は階層や権力によって実現される合理性と効率が正義である、という考え方
a-3これに、「道徳的正義」を取り入れたら
a-4統治者は「合理性に基づく正義の強制」の代わりに「合理性に基づく不正義」を取り除くことに力を入れるよう、考え方をかえるかもしれない
aモダンは、「階層、集権化、統制、統合、構造のような隠れた秩序が実在を説明」
a-1ポストモダンは、「どんな構造も実在を説明しなあ、言葉のみが表面的に概念を正当化できる」
a-2モダニズムの構造や統制などの言葉が権力者たちの一方的な支配を助け正当化 Ex)植民地化
a-3関心は、概念、構造、経営実践を脱構築することで、これらがどのように秩序、合理性、統制を前提としているのかを明らかにすること
4-4-1脱・分化
a組織が分化すれば統合が必要になる、それがまたさらなる分化をうみ、の繰り返し←2-2-3分化と統合、ローレンス&ローシュによるモダニズム理論
a-1組織は絶え間ない発展軌道から抜け出せないという問題←グレイナーやナッツ&カーンのモダニズム理論
bイギリス社会学者のスコット・ラッシュ
b-1「脱・分化」の概念を提案
b-2これが、モダニストが推進してきた理論を逆転させるだろう
cオーストラリア組織論者のスチュワート・クレッグ
c-1モダニストの分化と統合の理論を批判し「脱・分化」による統合を主張←統合は階層と関係なく成し遂げられる
c-2メンバーに自身の活動の自己管理と調整を認めることで組織の活動を統合させる←上からの指示やマニュアルによってメンバーの活動を統合するのではなく
4-4-2フェミニスト組織
aジェンダーや人種にもとづく組織構造について
bモダニズム的な官僚制を脱構築して分析
b-1官僚制=男性性的、基本的に白人男性支配型、権力(パワー)と地位によって階層に特権を認めて正当化
b-2その結果、女性や有色人種やマイノリティを支配する傾向
cフェミニスト組織=より平等で柔軟な構造、参加的意思決定、協力的行為、共同社会の理想が実現できる場
Ex)女性の健康管理センター、DVシェルター
dカレン・リー・アッシュクラフト
d-1フェミニスト官僚制=官僚制とフェミニスト組織のハイブリッド
d-2タスクは、公式かつ非公式、専門化するが全般的、階層と集権化は存在するが平等主義と分権的な実践によるもの
4-4-3反・統治理論
aアメリカ哲学者・経済学者のデイビッド・ファーマー
a-1「官僚制的統治」の理論に、「反・統治」をぶつけることで、これを中和できると考えた←酸性とアルカリ性を混ぜると中和するように
a-2官僚制は階層や権力によって実現される合理性と効率が正義である、という考え方
a-3これに、「道徳的正義」を取り入れたら
a-4統治者は「合理性に基づく正義の強制」の代わりに「合理性に基づく不正義」を取り除くことに力を入れるよう、考え方をかえるかもしれない