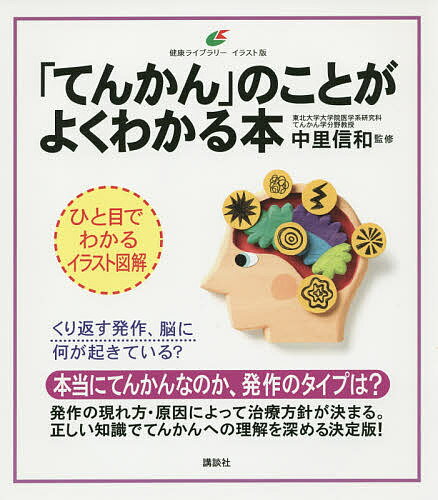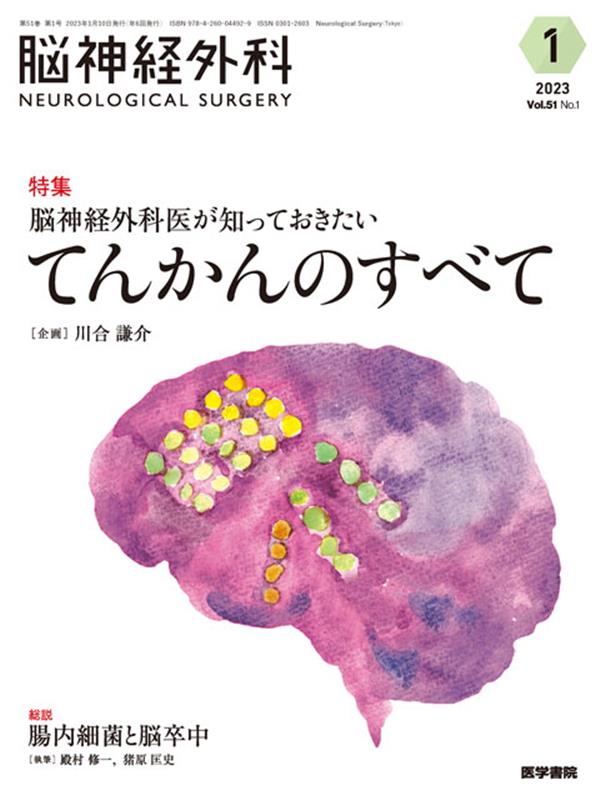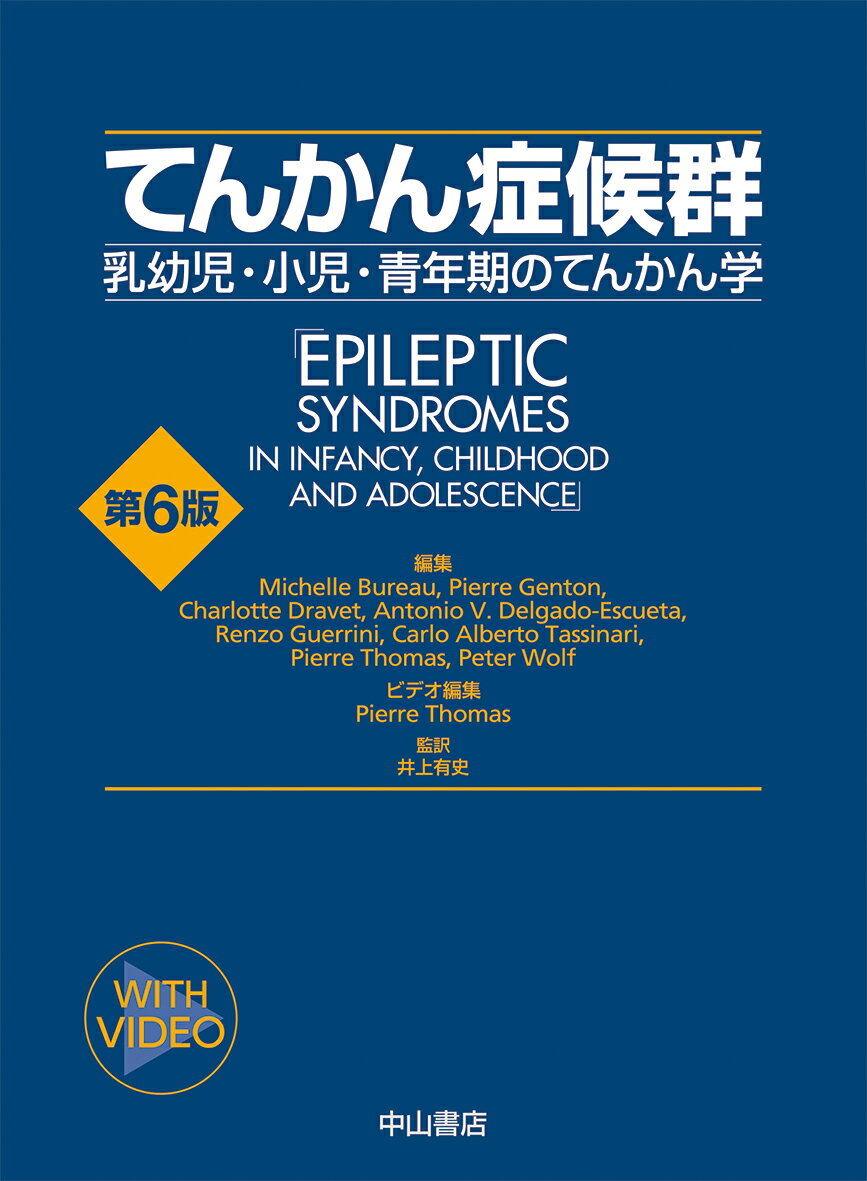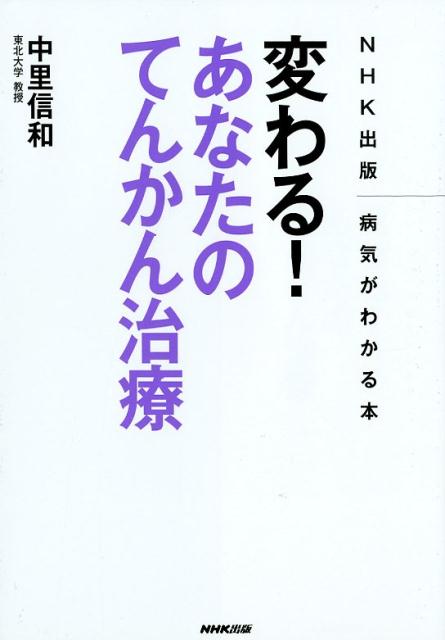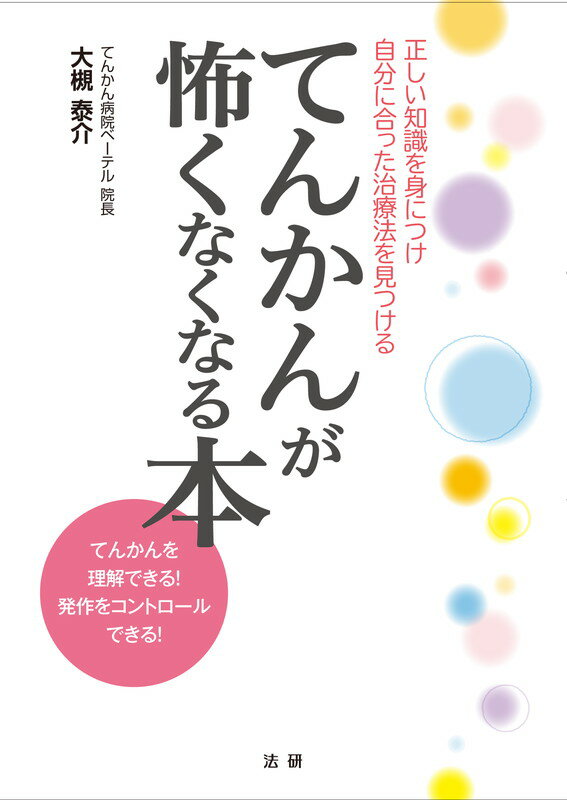🌟 はじめに:てんかんって、正直よくわからないですよね?
「てんかん(癲癇)」って聞くと、「急に倒れて全身がガクガク震える」という、ちょっと怖いイメージがありませんか?
でも、子育て中のママ友や職場の同僚など、私たちの周りにも、実はてんかんと上手に付き合いながら暮らしている人は少なくありません。
私も医療職(透析専門の看護師ですが!)として働く中で、てんかん患者さんを受け持つ機会があるのに、「脳の誤作動ってことはわかるけど、いざとなったらどうすればいいの?」と正直不安です。
今日は、**「脳の電気的な嵐」**とも言えるこの病気について、私と一緒にわかりやすく学んでみましょう!
🧠 第1部:てんかん=「脳の一時的なショート」が原因!
専門的に言うと、てんかん発作は**「脳の神経細胞(ニューロン)が、一時的に過剰な電気を発生させてしまう状態」**です。
これは例えるなら、家電製品が急に壊れて誤作動を起こす「ショート」のようなもの。この「ショート」が脳のどこで起こるか、どれだけ広がるかによって、症状は驚くほど多様になるんです。
| 発作が起こった場所 | 症状の例 | イメージ |
| 運動を司る部分 | 体の一部(手足など)がぴくつく | 短いけいれん |
| 意識を司る部分 | 数秒〜数十秒ボーッとする | 「魂が抜けた」ような状態 |
| 記憶や感情を司る部分 | 突然不安になったり、口をモグモグさせる | 無意味な動作の繰り返し |
だから、「倒れてけいれんしないからてんかんじゃない」とは限らないのが、この病気のわかりにくいところなんですね。
🤔 第2部:原因は?遺伝?それとも頭を打ったから?
てんかんの原因は一つではありません。
もし、お子さんや身近な人が発症しても、「誰のせい?」と責める必要は全くありませんよ。
-
構造的な原因(約3割): 脳梗塞や脳炎、頭部外傷などで脳に傷がついた場合。これは明確な「誤作動の焦点」ができてしまうケースです。
-
遺伝的な体質(約7割): 専門用語では「特発性」や「原因不明」と言われますが、これは生まれつき発作を起こしやすい体質(遺伝子)を持っているためです。決して親から子へ必ず遺伝するわけではなく、**「たまたまそういう性質を持って生まれた」**と捉えるのが適切です。
私も透析の現場で勉強しましたが、透析患者さんだと、体液や電解質の急激な変化で発作が誘発されることもあるんです。
基礎疾患や生活環境によって、引き金は本当に多様なんですね。
💡 第3部:もし発作を目撃したら?パニックは禁物!
一番不安なのは、「目の前で発作が起きたらどうしよう」ということだと思います。
でも、大丈夫!ほとんどの発作は数分で自然に治まります。
【発作中の対応ステップ】
-
安全確保!: 危険なもの(家具の角など)から頭を離し、頭の下に柔らかいもの(衣服など)を敷く。
-
無理に抑えない!: けいれんを無理に止めようとしないこと。口の中に物を入れたり、舌を掴んだりするのも厳禁です。
-
時間を計る!: 何分続いたかを冷静に確認。5分以上続く場合は、迷わず**救急車(119番)**を呼んでください。
-
記録を取る!: どんな動き(左右差は?全身か?)、顔色は?など、スマホで動画を撮るのが、お医者さんが診断する上での何よりの財産になります。
🌈 第4部:予後は大丈夫?てんかんは治る病気です!
「てんかん=一生治らない」というイメージは過去のものです。
実際には、てんかん患者さんの約7割は、抗てんかん薬で発作を完全にコントロールできます。
特に小児期のてんかんの中には、成長と共に薬なしで治ってしまうものも多いんです。
もちろん、コントロールが難しい「難治性てんかん」もありますが、現在では手術や特殊な治療法も進化しており、発作の頻度や重症度を下げる努力が続けられています。
発作を抑え、普段通りの生活を送れるようにするのが治療の目標です。**てんかんは、「不治の病」ではなく、「治療と管理ができる病気」**なんですよ。
💖 さいごに:理解とサポートが一番の薬
私たちにできることは、知識を持って、必要以上に怖がらず、もし身近な人がてんかんを持っていたら**「発作の誘発因子(睡眠不足など)を避けるようサポートする」**ことです。
過度に心配せず、正しい知識を持つことが、患者さんの不安を和らげ、より良い日常生活につながります。お互いに理解を深めて、温かい社会を作っていきましょう!