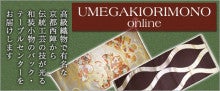いつも “ ときどき日記 ” をご覧くださりありがとうございます。
今回紹介させて頂きます帯は、『 重要文化財 束のし文様振袖 』 より取材した柄です。
割付文様を原本に近づける為に、筆の線を一定の太さにせず、太い線や細い線を
作る事で、自然な描写と織物の力強さを強調する事ができました。
『 佐賀錦 』 の技法で織り上げています。

≪ 慶長熨斗文 ≫ けいちょうのしもん
実際の変わり結びをご覧頂けないのが残念です


【 佐賀錦 】は、約180年前に佐賀鹿島藩、鍋島家の深窓で着想され、当家の女性達の
手芸として、盛行発展したものです。
金銀漆を貼った特製の和紙を細く裁断した箔を経糸 ( たて糸 )とし、絹の撚糸を染色
したものを緯糸( よこ糸 )として製織されたものです。非常に根気のいる手仕事で精密な
技術をようするために、1日2 ~ 3センチしか織れない物もあり、主に小物等に使用され
ました。
この【 佐賀錦 】を、西陣において帯地に応用するようになり、戦後本格的に「 佐賀錦帯 」 が
登場しました。
一般的に西陣における佐賀錦帯は、あくまでも本佐賀錦の応用である為に、経糸 ( たて糸 )に
箔を使用すれば図柄表現の手法は問わず、たとえば唐織のような、浮き糸による表現技法を
用いることもありました。

「 たまり 」 → 七宝の赤い濃い部分 ( 説明は下記にあります )
弊社では、「 本佐賀錦 」の持つ本来の “ 上品さ・繊細さ ” を表現することを目指し、図柄
表現に浮糸の技法を使用せず、経糸 ( たて糸 ) ですべておさえる 「 綴技法 」に似た表現を
用いました。
結果的に、「 たまり 」と呼ばれる緯糸 ( よこ糸 ) の 「 ゆるみ 」 ( 上のアップの写真に
ある七宝の赤い濃い部分で、写真で見ると、柄の左から右へと織り返す時に端が二重に
なる箇所 )が生じる事で “ 上品さ・繊細さ ” の中に “ 力強い表現 ” をする事が出来ました。
「 たまり 」は、じっくりと丁寧に織らなければできない技術です。
又、緯糸 ( よこ糸 ) の染色には 「 岩絵具 」といわれる含金染料を用い、非常に “ 重み
のある色料 ” を出しています。
【 佐賀錦 】本来の “ 繊細さ ” と、「 綴技法 」 による “ 力強さや色の重み ” を十分に
用いた本佐賀に劣らぬ、上品な【 佐賀錦 】になっていると思います。



【 参考本 】





【 留袖 】にも、合せて頂けます

いつも難しい説明になってしまい、すみません。“ 帯の写真 ” だけでも、お楽しみ
頂けたら嬉しいです。
最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。
2箇所のランキングに参加しています
にほんブログ村
にほんブログ村 ファッションブログ
2箇所共クリックして頂ければ嬉しいです
過去の日記は【 和装小物・バック umegakiorimono オンラインショップ 】をご覧頂けると嬉しいです
http://umegakiorimono-online.jp/hpgen/HPB/categories/7431.html