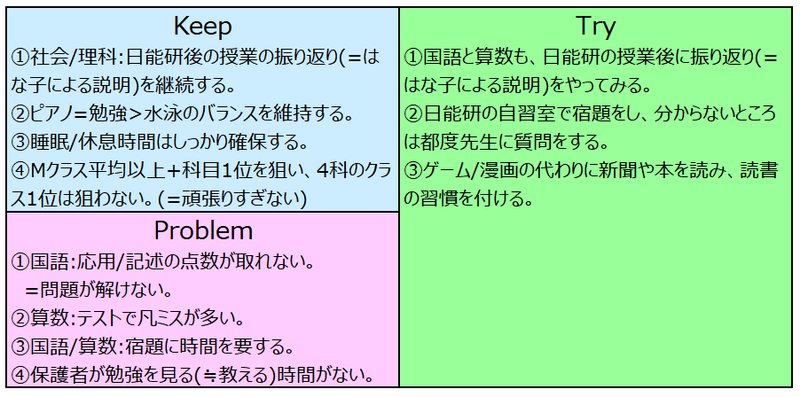母/父親塾は、永遠には続けられません。
このブログをご覧の皆様は、いつ辞められましたか? または辞められますか?
私は娘が中学受験の勉強を始めた僅か三カ月後に、親塾を辞めました。
辞めた一番の理由は、私自身の仕事が忙しく、勉強を教えられる時間がほぼゼロになったためです。
もし、「辞めようかな、どうしようかな・・・」と悩んでいらっしゃる方がいましたら、
「私はこういう理由で辞めた/辞められた」
ということをお伝えし、続けるか/辞めるかを決める際の参考として欲しいです。
もし、「まだまだ親塾は健在だよ!」という方がいらっしゃいましたら、数年後にまた見て頂けると嬉しいです。私も可能であれば、受験の前日まで親塾をする意気込みでしたので、私は親塾を全力で応援します!
私は親塾を辞めたことにより、子供が「分かった!」という瞬間の喜びを一緒に味わうことは出来なくなりました。しかしながら、不要な親子喧嘩は減りました。
今日は何故、私がこういう決断をすることに至ったのか、その理由を述べます。
母/父親塾を辞めた理由
辞めた一番の理由は、前述したとおり、時間が確保できなかったことです。それを含め、以下3つの理由で辞めました。
- 母/父親が勉強を見る/教える時間がない。
- 子供の理解度が分からない。
- 自分の理解度が足りない。
1.時間がない
理由としては、最低最悪です。
社会人として、上司に「時間がないのでできません」なんて言ったら、昭和の時代だったら殴られて、「徹夜だ、徹夜! 死ぬまで働け!」と言われ、栄養ドリンク漬けになって夜明けまで仕事です。
令和の今となっては、「ブラック企業」や「働き方改革」という言葉が浸透したおかげでそういうのは減ってきましたが、時間が無いのはいかんともできません。
ですが、
「どうしてできないんだっけ?」
「ちゃんと計画立てたの?」
「どこで出来ないってわかった?」
「報告/連絡/相談って知ってる?」
くらいは言われても仕方ありません。
私のFirst Missionは、家族の生活を守ることであり、子供のテスト成績維持/クラス維持ではありません。そのため、私自身の健康と家族の生活を第一に考え、辞めることが出来ました。
2.子供の理解度が分からない
3番の私自身の理解度が足りない、とリンクする面がありますが、誰かに物事を教える際に必要となるのは、教える相手の理解度/知識レベルです。
例えば1歳から2歳の子にはじめてひらがなを教えるのであれば、一文字一文字丁寧に教える必要がありますが、小学校4年生の子に算数を教える際、1+1から教える必要はまずありませんよね?
例えば正方向の面積の計算を教えるとして、仮にかけ算の理解度が乏しいとすると、面積の公式より先にかけ算をしっかりマスターしてもらわないと、面積の計算方法が分かったとしても、掛け算ができない時点で、正しい答えが出せるとは思えません。
そうすると、面積ではなく、掛け算まで戻る必要があります。
これと同じことが、4年生の算数で頻発しました。
具体的に言いますと、例えば算数の練習問題を解くとして、正解率が約50%しかありません。こうなると、何か重大なポイントを理解していないか、誤って理解しているかのどちらかです。
ここらが、大変なんです。
何が分からないのか?
どこまで分かっているのか?
これを探すために、塾で習った内容をほぼゼロから教えることになり、家で塾の勉強をもう一度最初から繰り返す羽目になるんです。
これって塾に行く必要あります?
私だったら、「塾代返せ」と言いたくなります。
子供も子供で、
「どうせ分からなくっても、家で聞けば教えてくれるし」
という甘えが出てきて、塾の授業に集中しているかどうかも怪しくなりました。
3.自分の理解度が足りない
1、2番目の理由とも強くリンクしますが、人に何かを教えようとする際、自分はそれの10倍くらい深く知っている必要がある、と私は思っています。
例えば、自動車の教習所で運転技能講習を受ける際、助手席に座って指導してくれる方は、免許取り立ての方じゃありませんよね?
車運転して何十年のベテランの方だと思います。
中学受験の問題は、年々難しくなってきており、中学受験問題の解き方、傾向について熟知してないと、子供目線で教えるのはとても難しいと思ったからです。
言い換えると、私が中学受験問題を解けないというのではなく(もちろん解けない問題もありますよ!?)、私が解けたとして、子供に納得して教えられるくらい、私がその分野の中身を深く理解していないという意味です。
もっと簡単に言うと、問題集やテストの解答/解説の棒読みは出来ても、それを補足する説明ができない、ということです。
以上3つの理由で、我が家では親塾を辞めました。
辞めたことによる変化
親塾を辞めたことによって、色々変わりました。
そちらについても、少し補足します。
辞めたタイミング
辞めたのは、今でもよく覚えていて、以下の記事を記載したタイミングです。
上の記事を書いた以降、子供と同じ宿題やテスト問題を解いて、点数の比較をすることはあれど、私から教えることは一度もありません。
逆に、「こんなのも分からないの?」と言われ、教えられることはしばしばあります。
辞めて良かったこと
一番は、親子喧嘩が減りました。
「おまえ、こんなのも分からないの?」
「塾でなに習ってきたの?」
「もうやめちゃえば?」
といった感じの発言が一切無くなりました。
逆に
「これ、よけ解けたな!」
「これはむり、わたしも解けない」
というような、解けたことを純粋に褒めたり、解けなくても、問題の難易度的に困難な場合は、解こうという努力を褒めたり、そういうポジティブ発言が増えました。
続ければ良かったと思うこと
「わかった!」
「できた!」
「そういうことか!」
と、子供が理解した瞬間の笑顔、喜びの場に、一緒にいられないことです。
できれば子供と一緒にそういうのを一つずつ喜んでいけると良かったのですが、子供が理解できていないところの説明については、専門家(塾の先生)にお任せすることにしました。
さいごに
今、親塾を辞めたことが、正解だったか不正解だったかは、中学受験の結果や高校/大学への進学、さらにその先に進んだときになるまで、分からないと思います。
ですが、私の願いはただ一つ。
三人の子供の幸せでもあり、受験生みなさまの幸せです。
まだまだ長い長い道のりですが、頑張っていきましょう!
おしまい![]()