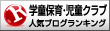こんばんは。
放課後児童支援員の「しんごうき」です。
このブログにお越しいただき
ありがとうございます。
このブログは、
小学生の放課後の安心・安全を担う
「放課後児童支援員」がその処遇の悪さから
「支援員を諦めるより他ない状況」から
抜け出す方法や考え方を伝えるものです。
そこでこのブログでは
『放課後児童支援員のスタイル革命』と
称してすぐに取り組める「仕事術」
「お金の守り方」「お金の増やし方」を
発信していきます。
■男はつらいよ ~男性児童支援員の苦悩(下)対処法~
前回は男性の児童支援員(以下男性支援員)
が女児とのスキンシップなどで第三者に
意図せぬ誤解をされて、仕事しにくい状況に
陥らないための考え方を中心にしました。
今回は私が現場で実践してきた具体的対処法
についてお伝えします。
児童との身体接触やスキンシップの加減に
悩む男性支援員の参考になれば幸いです。
◆男性支援員が意識したい3つの目
これからお伝えしていく対処法は、
あくまでも参考であり絶対的なものでは
ありません。
児童対応には正解というものはありませんか
ら当然といえば当然なのですが、それでも
自分の対応が誤解や不快感を覚えられて
いないかを確認する方法はあります。
それは次の3つの目(視点)で
自分の対応を客観視することです。
①保護者(母親)の目
②行政・学校の目
③(同僚の)女性支援員の目
保護者については、他児童の保護者の目も
含めています。なぜなら男性支援員と身体
接触している児童が自分の子どもでなくとも
それを自分の子どもに置き換えてみている
からです。
また父親でも身体接触について厳しい目を
持っている方もいますが、たいていは母親
よりも見方が甘くなる傾向にあるので、
あえて含めませんでした。
この3つの目を厳しさ順に並べると、
①保護者(母親)の目>②行政・学校の目
>③女性支援員の目となります。
そして男性支援員は自分の対応について
客観視した場合に、同僚の女性支援員の目
からみて児童とのスキンシップが過度や
不快に映るだろうなと思ったら即刻対応を
改める必要があります。
ある程度、男性支援員の人柄や児童との
関係性を理解している同僚でさえ不快に
映るならば、それより見る目が厳しい
行政や学校、保護者には絶対に受け
入れられません
もしも①~③の客観視が難しければ、
思い切って同僚の女性支援員に
自分の対応をみてもらったり、相談して
率直な意見を教えてもらうとよいでしょう。
◆対処法とポイント~「Yes,but」法~
ここからは「痴漢に間違われないために
満員電車では両手を上にあげておく」の
ように保育や育成支援の際のリスク回避の
方法をご紹介します。
これはあくまでも
不要な身体接触を回避するためのもので
リスクを過度に恐れて身体接触やスキン
シップを求めてくる児童との関係性を
壊さないようにしてください。
そのために心がけたいポイントは
「Yes,but」法です。
児童からの要求に対し、たとえ結論が
「No」だとしても最初から否定せずに
まずは「Yes」つまり「いいよ」と
受け止めてください。
その後で「but」つまりダメな理由を
伝えます。こうすることで児童は男性
支援員に否定された感覚が薄まり、
関係性を保てます。
【対処法 その①】『状況をつくらない(自然に回避する)』
<状況> 背中にのられる。飛びつかれる。
<対応> ・極力、しゃがまない。
・児童に乗られない位置でしゃがむ
これが対処法の基本中のキホンです。
しかし児童と目線を合わせようとすれば
自然にしゃがみますし、床に座って
児童の遊びのサポートをする機会も多いので
徹底するのは難しいかもしれませんが
心がけていきましょう。
この対処法に【対処法 その②】を
組み合わせると効果が高まります。
【対処法 その②】『ダメな理由を伝える』
<状況>足に抱き着く
<対応>
『(先生の手が当たる可能性があり)怪我を
するから離れてください』
『誰かが怪我したときに、
助けに行けなくなるから
離れてください』
理由を伝え方にもパターンがあります。
「(身体接触してきた)児童がケガをする」
「男性支援員がケガや痛い思いをする」
「緊急事態に助けにいけなくなる」
の3つです。
全ての理由を伝えても構いませんが、
身体接触をするほどその男性支援員に
好意や信頼感を抱いている児童であれば、
2つめの「男性支援員が痛い思いをする」
ことを伝えるのが有効でしょう。
また
「腰に持病がある」
「ケガをして痛めている」
「妊娠している」などの理由は
児童と接触する前に児童支援員から
伝えることも大切です。
先に理由を伝えることでそのことを
知らずに大好きな児童支援員に
突撃して悪化させてしまい、
児童がキズついてしまうのを
防ぐことができます。
【対処法 その③】『ユーモアや頓智(とんち)でかえす』
<状況> おんぶ・だっこ
<対応>
『先生のことを先におんぶして
くれたらいいよ。でも先生の体重は
50kg以上あるから○○さんが
つぶれちゃうからダメだね。』
私はここに児童支援員の腕の見せ所が
あると考えています。ダメや禁止を作るのは
簡単です。
しかし安易にそれに頼らずユーモアや頓智を
駆使して、それとなくキズつけずに児童を
誘導しましょう。
そのためには日頃から発想力、表現力、
語彙力を磨いていきましょう。
ちなみに上記の<対応>を言うと
「いいよ、先生おぶってあげるよ」という
児童がいますので、そのときは
『50kgはランドセル※が50個ぐらいだよ。
それを持ち上げられるの?』と身近なもので
重さを例えて諦めされるとよいでしょう。
※一般的なランドセルの本体の重さ=1~1.5kg.
あるランドセル会社の調査では荷物が入ったランドセル重さは
1年生で平均約3,7kg。
【対処法 その④】『他のことに気をそらす』
<状況> 身体接触、スキンシップでも可能
<対応>
・○○はだめだけど、▲▲しようか。
(○○は身体接触、スキンシップ)
≪対応例≫
○○ね。じゃあまずジャンケンを
しようか。ジャンケンで先生に
勝ったら、○○をしてあげるよ。
・先生が勝ち
→「先生が勝ったので○○はナシね」
・児童が勝ち
→先生「おめでとう」
児童「えー勝ったら○○してくれるっていったじゃん」
先生「じゃあ、あと3回勝ったらね」
児童がジャンケンに勝った場合には、
すこし強引にジャンケンを続ける流れに
することがポイントです。
ジャンケンをしているうちに、○○をして
もらうよりジャンケンに夢中になります。
そのうち楽しそうなやりとに他児童が
寄ってきて大人数になります。
そうなったら「こんな大勢に○○をしらた、
先生は死んじゃうよ」といって断ります。
すこしズルい終わらせ方ですが、
結果的には児童が楽しめるので
よいと思っています。
■■■まとめ■■■
・男性支援員は「保護者(母親)」
「行政・学校」「女性支援員」の
3つの目を意識して対応しよう
・対処時のポイントは最初に児童を
「いいよ」と受け止めてから理由を
伝える「Yes,but」法。
・ダメな理由を伝える対処法では
「先生(男性支援員)がケガや痛い
思いをする」が有効
2回に分けてお伝えしてきた、
児童との身体接触やスキンシップへの
考え方や対処法ですが、男性のみならず
女性支援員にも、ぜひご一読頂きたい。
その理由は2つ。
1つは同僚の男性児童支援員への
アドバイスの参考にしていただきたい。
もう1つは、これらの対処法を行っても
うまく身体接触やスキンシップをコント
ロールできない男性指導員に助け船を
出してほしいからです。
男性支援員から児童に直接「No」と
伝えるよりも第三者の口から
「○○先生にべったりしすぎだよ」と
いってもらえたほうが関係性が崩れず、
児童も冷静になれて効果が高いからです。
もしかしたら
児童にすこし嫌われてしまうかも
しれませんが、この業界で貴重な
男性支援員を誤解から守ると思って
声掛けをお願いします。
最後までお読みいただき
ありがとうございました。
今日もワクワクする1日を!