zakzak(産経デジタル)の記事を紹介します。
---引用ここから---
緊縮財政の誤り 実行した英国は景気低迷 消費増税の大義名分あるのか
2013.04.24
経済理論をめぐるアカデミックな世界での論争が大きな話題になっている。米マサチューセッツ大の研究者が、ハーバード大のカーメン・ラインハート教授とケネス・ロゴフ教授が2010年に発表した公的債務に関する研究について、誤りがあると批判したことだ。
問題の「ラインハート・ロゴフ論文」は、公的債務残高が対GDP(国内総生産)比で90%を超えている国家の平均実質成長率はマイナス0・1%に減速すると主張している。この「90%」という数字は一人歩きして、ここ数年、緊縮策をめぐる議論で影響力を発揮してきた。そのため、アカデミックな論争が一般紙でも報じられているのだ。
ラインハート・ロゴフ論文が出された当時、IMF(国際通貨基金)をはじめとする国際機関などでは、財政再建の必要性のバイブルのように扱われていた。欧州委員会のレーン委員(経済・通貨問題担当)も今年2月、公的債務残高対GDP比が90%を超えれば成長減速になると述べており、今月19日にワシントンで開かれた20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議でも、各国の公的債務を長期的に国内総生産(GDP)の90%を下回る水準に削減するとの案が準備されていた。
もっとも、経済学者の間では当初から議論があった。例えば、プリンストン大のクルーグマン教授は「公的債務対GDP比が増えると経済成長が低下するのでなく、経済成長が低下したから公的債務対GDP比が増えた」「G7の中で、イタリアと日本を除くと公的債務残高対GDP比と成長率には関係がない」と異論を唱えていた。
論点となっているのは、公的債務残高対GDP比が90%を超えると、成長率がマイナス0・1%になるのかということと、公的債務残高対GDP比が高くなると成長率が低くなる「因果関係」があるのかだ。
前者は、マサチューセッツ大論文によるとプラス2・2%であり、ラインハート・ロゴフ論文の数字に間違いがあるようだ。しかも、間違いの原因として意図的に一部のデータを除いた疑いがあるという。特にニュージーランド(1946~49年)のデータを除外したのが大きいとしている。ここまでくると、単純な間違いではすまなくなる。
後者の公的債務残高対GDP比と成長率の因果関係も怪しい。日本では経済成長率と「1年後」のプライマリー(基礎的財政)収支に「相関」がある。ということは、経済成長率からプライマリー収支への「因果関係」とみていいだろう。
プライマリー収支と公的債務残高対GDP比は一定の条件の下で数学的な対応関係があるので、日本だけでいえば、公的債務残高対GDP比が高くなると成長率が下がるのではなく、成長率が下がった結果、債務残高対GDP比が上がったことになる。
英国ではラインハート・ロゴフ論文の主張に沿って財政再建のために消費税を増税したが、かえって景気低迷している。日本も今秋には消費税率引き上げの議論になるが、財務省はどのような理由で増税を主張してくるのだろうか。 (元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一)
^^^引用ここまで---
消費増税、緊縮財政の根拠が嘘っぱちだったということです。
今まで、緊縮財政を訴えてきた人の多くは、悪意があったわけではなく、このような学術論文が正しいという前提で、緊縮財政が必要と主張してきたものと思われます。
ラインハート・ロゴフ論文が間違いだとなると、これは消費増税反対の有力な武器として使えます。
消費増税の無期延期、および緊縮財政の破棄ができれば、TPPをはじめ余計な成長戦略など全くせずに日本経済の復活が達成できる可能性が高いでしょう。
なぜなら、日本の低成長の原因はデフレであり、デフレの原因は金融引締めと緊縮財政なのですから。
p.s.
高橋洋一氏に対して一部には新自由主義者というレッテル貼りで批判する人もいますが、このように財政支出についても肯定的な見解を出していることも確認しておいてください。高橋洋一氏などのリフレ派は保守派の敵ではないのです。分裂工作に惑わされないでください。敵はデフレなのに金融引締めと緊縮財政の両方を主張する民主党や社民党、共産党、生活の党、みどりの風、および財務省の一部のような偽リベラル(売国奴)です。
売国奴をあぶり出すリトマス試験紙↓
岩田規久男日銀副総裁任命に関する参議院本会議投票結果
消費税増税は問題だと思われる方は↓クリックお願いします
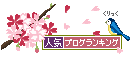
人気ブログランキングへ