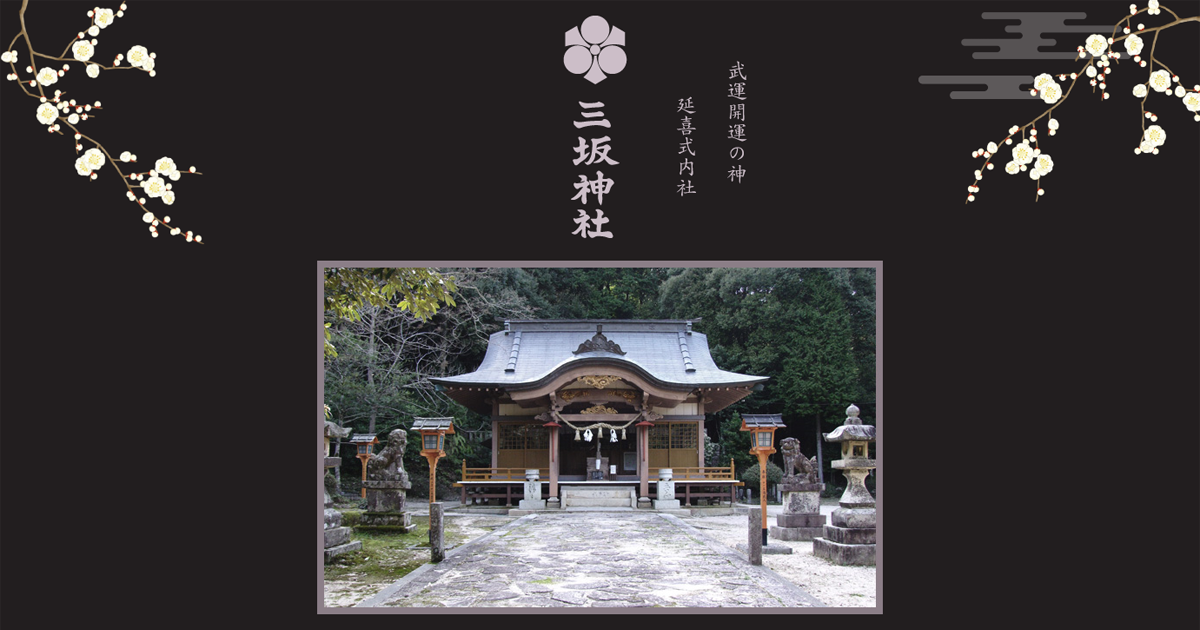山口県山口徳地岸見に鎮座します
三坂神社
市町村合併で、今は山口市になっていますが、防府市の方が近いです。
周防国 佐波郡 御坂神社の式内社とされています。
この日は、
周南市の「辰尾神社」⇒「山崎八幡宮」⇒「神上神社」⇒
山口市の「船路八幡宮」⇒御坂神社と、巡ってきました。![]()
![]()
実は、この日の最後の神社だったんですけど、車で境内に行くのに一番苦労しました。![]()
ナビが、狭い道を案内するもんで、垣根で、車の側面をこすって、ちょっと筋が入ってしまった~![]()
車に傷をつけながら、どうにか駐車場に着きました。![]()
参道の途中から一の鳥居の方を振り返ります。![]()
参道が、そこそこ長いです。
最近、参道の石畳が整備されたようです。![]()
拝殿が見えてきました。![]()
拝殿、新しいです。![]()
![]()
参拝時に、急に突風がびゅ~って吹いてきました。![]()
![]()
御祭神は、
大国主命さま
事代主命さま
配祀が
速玉之男命(はやたまおのみこと)さま
道反大神(ちがえしおおかみ)さま
合祀が
スサノオ様
大歳神さま
埴山姫命(はにやまひめのみこと)さま(=埴安姫)
由緒によると
足利尊氏公さんや、豊臣秀吉公さんも来られたことがあるそうです。![]()
「毛利元昭(もうりもとあきら)」という名前が見える扁額です。![]()
この方は公爵で、大正時代に来られたようです。
長州藩最後の藩主の御長男だそうです。 …Wikipedia参照
社紋は、剣三つ星のようです。![]()
この紋は、めずらしいのでは![]()
一の鳥居の方をもう一度振り返りました。![]()
この景色が気に入りました![]()
参拝を終えると、
もう4時ぐらいで薄暗くなってきて、風は吹いてくるし、誰もいなかったので、さすがの私でも、ちょっと怖かったです。。。![]()
それに、なんか、山の方から、「ど~ん」という音が聞こえたりしてきて。。。
神域ではありますけど、夜のとばりが近づいてきてたから。。。![]()
空き地![]() のようなとこに駐車したんです。
のようなとこに駐車したんです。
帰ろうとすると、地元のおじさんが、なんか作業するために二人来られたんです。
「こんにちは、神社の駐車場はここでいいんですか?」なんて、ちょっと話しました。
これまた、感じの良いおじさんたちでした。![]()
そして、帰りの広い道を教えてもらいました。
とは言え、帰りも狭かったです。![]()
でも、来たときよりも広い(笑)
ここは、参道がいい~って感じでした。![]()
それにしても、1000年以上前に、今でも田舎(失礼)のこの地に神社があるなんて、、、すごいです。
この神社は1300年以上の歴史があるようです(ホームページ参照)
当時は、この辺りに、どのくらいの人が住んでいいたんでしょう。。。
御坂神社の式内社だろうという、二つの神社
1つ前のブログの「船路八幡宮」と「御坂神社」
御祭神は、どちらも
道返大神なんです。
道返大神は、黄泉の国と現世の境にある石のことなんです。
もしかしたら、かつての御坂神社は、そういう意味で祀られた神社だったのかもしれませんね。
島根県に、黄泉の国と現世の境界の場所で有名な「黄泉比良坂(よもつひらさか)」があります。
式内社の「御坂神社」も、「坂」という文字が入っています。
そして、「船路八幡宮」も一時は「御坂大明神」と呼ばれていたんです。。。
船路八幡宮の三坂神社も、背後の山は、黄泉の国の入り口だと思われていたとかね。(個人的な仮説)
年月が過ぎる過程で、
船路八幡宮は、八幡神をご祭神に迎え、
三坂神社は、大国主様他をご祭神に迎えているようです。
でも、はじめは、どちらも道返大神様のようです。
ならば、どちらのお社も式内社論社のままでよい気がします。
どちらかが式内社であると決定しなくてもいいような気がします。
山口県周南市の二俣神社についても、論社と考えられている神社のご祭神が同じでした。
それも、まれな組み合わせの御祭神でした。![]()
始まりは、一つの式内社であると思われます。
その神社から、分霊や勧請された神社がいくつか存在するのではないかと。
何が言いたいのかというのは、どのお社が式内社を後継しているのかということが、神社を守っている人たちに、どれほどの意味があるのかということです。
論社争いがあって、競争に負けたみたいなことになっていたりしますが、、、
もしかしたら、元々の式内社は、消滅している可能性だってあります。
史実を知ることは、学問的には大事でしょう。
でも、今は、過疎化の問題などにより、地域の神社が消えていくことを防ぐということが大事だと、私は思います。
そこに神様がいるなら、そこには人間もいることが必然ですよね。
だって、神と人間は、共存関係なんですもの。![]()
![]()
最後に、この神社は
「弾除け神社」として有名だそうです.
三坂神社のホームページに、とても詳しい説明があります。
どうぞ、ご参照くださいませ<m(__)m>
黄泉の国と現世の境界の場所、黄泉比良坂のブログです![]()