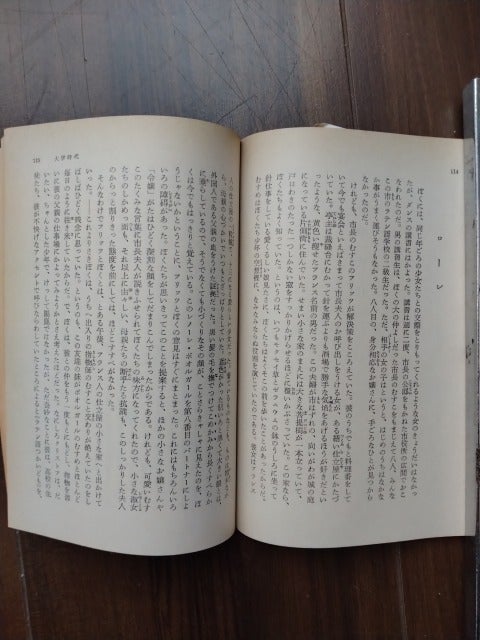今回はドイツ文学のその他の作家について語ろう。ドイツ文学はおおむね岩波文庫で読んだのだが、その中で特に印象に残った作品の著書についてふれてみる。
まずゴットフリート・ケラー(1819~90)である。彼はスイス人だが、ドイツ語で小説を書いた。
彼の代表作は『緑のハインリヒ』(以下、ハインリヒと略す)である。
岩波文庫では『村のロメオとユリア』という作品も訳されているが、私は読んでない。
この本はドイツ教養小説の中でも有名な作品である。ドイツ文学を系統だって読んでいた私は、ドイツ文学の特長として、主人公の自己形成を描いた教養小説があることを知った。その最初の作品はゲーテの『ヴィルヘルム・マイスター修業時代及び遍歴時代』(以下、ヴィルヘルム・マイスター)である。『ハインリヒ』以降の作品にはヘッセの『ピーター・カーメンチント(郷愁)』、トーマス・マンの『魔の山』が挙げられる。
教養小説の特長は、主人公が純粋で、誠実で、理想を求め、意外と禁欲的である。異性関係においてふしだらではない。ここにドイツ文学の特長がある。異性関係が派手、破滅的、堕落的な主人公が多いフランス文学やロシア文学と違うのである。
若者はいつの時代でも様々な体験を行い、試行錯誤し、暗中模索をする。それを通して自己形成を図る。この過程を描くのが教養小説である。
私も上京すると、刺激ある東京に幻惑され、様々な分野に挑戦した。どん底に落ちそうになったこともあるが、最終的に浮上した。そういう人間だったから、このジャンルの小説にひかれたのだろう。
『ハインリッヒ』を読んだのは大学2か3年の頃。すなわち73,74年だったと思う。この作がゲーテの『ヴィルヘルム・マイスター修業時代』の影響を受けて書かれ、やがてヘッセの『郷愁』に影響を及ぼしたことはすぐ分かった。
4冊にまたがる長編だが、一気に読んだことを覚えている。その内容はほとんど忘れたが、観念的ではなく写実的なため読みやすかったことを覚えている。抒情的な描写もあった。
主人公の前向きで、道徳的で健全な性格は気持ちがいい。市民精神にあふれている点に共和制スイスの影響があろう。
ヘッセの『郷愁』はこの作品の延長にあると思われた。それだけ本作の影響力がすごかったのだろう。
私にもそれは当てはまる。やはり人生は、投げやりになってはダメだ、ハインリヒのように前向きに進もうと思った。本作から勇気をもらった。
若者向けの作品は古今東西数多あるが、私は本作を薦める。
続いてテオドール・シュトルム(1817~88)である。
彼の作品は3冊読んだ。『みずうみ』『大学時代・広場のほとり』『美しき誘い』である。72年の頃だろうか。
これらはすべて短編である。抒情的でセンチメンタリズムにあふれ、失恋、片恋、慕情、あこがれ、別れなどを描いている。それも追憶と言う形が多かった。よく下宿で寝転んで読んだ。
高校時代、私はヘッセのリリシズムが満ちた短編や中編(『ラテン語学生』、『青春は美し』など)が好きであった。その影響で、ヘッセの先輩のようなシュトルムに引かれたのだろう。
(ヘルマン・ヘッセ)
ただ、読書体験を重ね、東京で様々なバイトをしたり、色々な人間と交わううち、この手の小説に飽き足りないものを感じた。鼻に付くことさえあった。だからある時期から読まなくなった。
代わりに長編や思想的に深い作品、破天荒で乱脈な生活を描いた作品を片端から読んだのだ。だが、社会に出て働くようになると読めなくなった。退職し、枯淡の境地に達した現在はもっと読めなくなった。疲れてしまうのだ。
そこで、シュトルムの作品のような感傷的な短編なら面白さを感じるだろうと、この記事を書くにあたり、『みずうみ』や『大学時代・広場のほとり』をもう一度読んでみた。しかし、心は揺さぶられなかった。老人になるのは厄介なことだ。
『大学時代』には考えさせられた。昔の女性たちとりわけ下層階級の女性たちが幸せになるのは大変だったことを改めて感じた。いつの時代でも社会のひずみは弱者に押し寄せる。現代の女性たちがこの作品を読むとどう思うだろう。
最後はフランツ・カフカである。
カフカは富裕なユダヤ人商人の息子としてチェコのプラハに生まれた。父は彼の将来が困らないように、ドイツ語を教える小学校に入学させた。当時ドイツ語は支配階級の言葉だったらしい。したがって彼は作品をチェコ語ではなく、ドイツ語で書いた。そのためドイツ文学に位置付けられたのだろう。
当時ユダヤ人は差別されていた。だからといってカフカはユダヤ教を熱心に信仰する人ではなかった。キリスト教に対しても距離を置いていた。
このような背景が彼の文学に反映している。
私は、彼の作品は、長編の『城』(未完)、『審判』(未完)、短編の『変身』しか読んでない。
高校時代、取っていた河出書房の世界文学全集の中に『城』と『変身』があった。『城』に挑戦したが、堂々巡りをしている内容が退屈で途中で放り投げた。この不思議な作品を味わう力が私にはなかった。
高校卒業後、一浪を経て大学に入学した。その頃、私はカフカが20世紀の世界文学に彼が大きな位置を占めていることを知った。サルトルやカミュに代表される実存主義作家たちに大きな影響を与えていることも分かった。新しい潮流に深い関心を抱いていた私は彼に興味を持ち、『城』を再読した。71年の時である。
主人公は城に採用されたのに、いつまでたっても城に入ることが出来ない。麓の村で待機し、そこで様々な出来事に巻き込まれる。結局城に入ることのできぬまま未完となる。主人公が翻弄されるように、読者も迷路に迷い込み、宙ぶらりんになったような読後感を抱く。いわば、劇的な展開がない、筋のない小説の見本のような作品である。
作者は何が言いたいのか。城と村との官僚制か。自分の意志ではどうにもならない不条理を描こうとしているのか。こう考えることはあまり意味がないのかもしれない。とにかく謎めいた、不気味な作品である。
続いて『変身』や『審判』をひもといた。『変身』は主人公がある朝目覚めたら毒虫になっている作品である。当然世間と軋轢を生む。これも不条理を描いた作品だということなのだろう。ただ、私にはSF小説のように感じられた。SFが苦手な私はこの作品には引かれなかった。
むしろ『審判』の方に衝撃を受けた。主人公がある日、自分でも分からない罪でつかまり、裁判を受けさせられ、死刑の判決を受けるという作品である。捕まる場面や死刑執行の場面は強烈だが、途中の展開は退屈だった。
この本は初め新潮社版カフカ全集で読もうとした。古本屋で買ったが、読みづらかったので改めて岩波文庫を購入した。全集の方は古本屋に売ってしまった。
この不条理対する絶望が伝わって来た。
実際これに近いことは現実に行われていた。スターリンやヒットラーの独裁国家においてである。ユダヤ人、政治犯、一般市民が犠牲になった。
そういう点でいろいろなことを考えさせられる小説である。
その後、私は安部公房を読んだ。『壁ーS・カルマ氏の犯罪』、『砂の女』、『他人の顔』、『燃え尽きた地図』などである。明らかにカフカの影響を受けていると思った。
(60年から70年代にかけ、純文学が売れている頃、新潮社からこのようなシリーズが函に入れられて刊行されていた)
カフカという名前には思い出がある。
71年の夏、大学1年の私は、渋谷駅の前の大井ビル1階にあった大井フルーツ店でバイトをした。
(道路の向こう側にある駅前広場にハチ公の銅像があった)
その店には20代後半のAさんという男性店員がバイトをしていた。彼は川越商業高校時代に演劇に目覚めたが、卒業後都市銀行に勤めた。しかし演劇が忘れらず、都市銀を辞め、小さな劇団の研究生になった。ところが、夢見た世界と違ったことと、自分の表現力のなさに自信をなくし、劇団を辞め、この店で働いていた。仕事が出来、誠実な人柄のため先輩の信頼があつかった。彼はここで働いて金を貯め、アメリカを放浪し、自分を見つめ、人生の仕切り直しをしたいという話をした。当時、小田実の『何でもみてやろう』や五木寛之の『青年は荒野をめざす』の影響もあり、海外を放浪する若者がけっこういた。Aさんもその一人だったのだろう。
私はそんなAさんに憧れ、いつしか自分も海外放浪をやってみたいと思った。
Aさんから「君は文学青年らしいが、外国文学ではどの作家が好きなんだい?」と聞かれた。
「カフカです」
私は本当は『城』しか読んでないのに背伸びして答えた。
「カフカ? それは小説家ではなく心理学者じゃないの」
Aさんは大学には行ってないが、かつて心理学に興味を持ち、その種の本を読んだという。
心理学者にカフカという人がいるかどうか私には分からなかった。そこで大型書店に行き、心理学のコーナーで調べた。すると心理学者に「クルト・コフカ」というドイツ人がいた。Aさんは、コフカとカフカを間違えたのだと思った。
(クルト・コフカ)
Aさんにコフカの名を告げると、Aさんは一瞬考え込み、「そうだ、コフカだ。カフカじゃなかった」と間違いを認めた。Aさんは、世間に時々見られる、我を張る大人ではなかった。たとえ年少の人間の前でも、自分の間違いを素直に認めた。
そんなAさんに助けられた思い出もある。
あの頃の渋谷にはやくざがいた。この店の界隈を仕切っていたのはB組だった。ある夜、サングラスをかけた一目見てやくざと思われる格好の中年男性が買いに来た。ただ、親分クラスではなく下っ端のような感じがした。店には私とAさんしかいなかった。その男が私を見て、「お前はさっきから俺の顔を見ている。なんか俺に文句があるのか」と因縁をつけて来た。普通とは思われる格好をしてない人間が入って来たので、顔を見たのは事実であるが、すぐ目を伏せたつもりである。
私は、この手の人にからまれたのは初めてなので、震えあがり、「すいません」と謝った。そしたらAさんがすぐ割って入り、「この若者は田舎から出て来た新米なんです。どうか許してください」と頭を下げた。そしたら彼は、「これから人の顔をじろじろみんじゃねえぞ。気をつけろ」と言って立ち去った。
B組の連中は時々店の前をうろついていたのでAさんはその対応に慣れていた。私は、助けてくれたAさんに本当に感謝した。もし私一人だったらどうなっていただろうと思った。
私を助けてくれたAさんはその後どういう人生を送ったのだろう。
これから4年後、私はAさんと似たようなMK君に出会った。彼は大学の1年先輩だった。歳も1つ上。彼も卒業後演劇目指し、小さな劇団に入ったが、数年経って挫折し、自分探しをするために渡米した。1年間にわたって各地を放浪し、帰国後福岡に帰郷した。そこで就職し、結婚した。
私は文学だったが、夢破れて都落ちした点は同じである。MK君のことは「思い出の演劇・1971-77・青春回顧33」で述べたのでここでは繰り返さない。
一つ言えることは、文学・映画・演劇・音楽・美術など芸術の分野でひとかどの人間になるのは大変だという事である。飯が食えるようになる人はその分野でのエリートだ。人生を棒に振る場合があるので、自分の才能に疑問を抱いた場合、見切りをつけることも大切である。
その他の作品では、以下が挙げられるが、面白かった印象はない。
まず、初期ロマン主義の作家のノヴァーリス(1772~1801)の『青い花』(未完・長編)。
幻想風な作品。こちらの作品より、同名の吉行淳之介の短編の方が心に残っている。ノヴァーリスから影響を受けたのだろうか。
次に、同じロマン主義のホフマン(1776~1822)の『黄金の壺』(中編)。
人間と精霊が恋するという幻想的怪奇的な世界を描いている。ロマン主義は現実から遊離するのでどうしてもこのタイプの作風が多い。
非現実的な作品を私は好まない。
続いてシュティフター(1805~1861)の『水晶』。
これは薄い短編集でリアリズムの世界。ただ、内容は忘れたが、まあまあ面白かった。
最後に『ヘッベル短編集』である。
ヘッベル(1813~1862)のこの作品も記憶からすっぽり落ちている。シュトルムに比べると見劣りすると思われた。。
私は、短編が好きということもあり、岩波に入っている短編集の多くを買ったが、私の嗜好に合うものもあれば、合わないものもあった。
なお、『青い花』と『水晶』は手元にない。
――― 終 り―――
※次回からフランス文学に入ります。まずジャン・ジャック・ルソーを語る予定です。