「ライ麦畑でつかまえて」の謎 2
《反転》と《一体化》の物語?
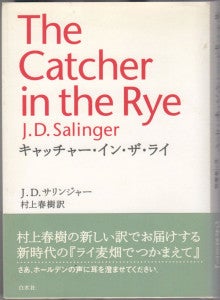
――で、反転・一体化の話のつづきですが、まずそれが第1です。
第2に、それと同時に、救うものと救われるものとの反転を呼び寄せているらしいということです。fuck youの落書を消す作業が「The Catcher in the Rye」のこの世での仕事だとすれば、世のなかにはfuck youはあまりにも多すぎて、消しきれません。そう気づいたホールデンは、ライ麦畑のキャッチャーをあきらめることになります。
ホールデンの空想の世界では、ライ麦畑のキャッチャーの仕事は、崖から落ちそうになる子どもをつかまえる作業でした。もちろん、そこではホールデンは救う側であり、転落を防いでもらう子どもたちは救ってもらう側のはずでした。
けれども、世の中には落書がかぎりなくあり、消しきれないこと、すなわち、ライ麦畑のキャッチャーになれないこと、崖から落ちる子どもたちをつかまえることができないこと、を悟ったホールデンは、ここで一気に救う側から救われる側へと反転していくわけです。
fuck youを書かれてしまう側へ、崖の比喩でいえば、崖から落ちていく側へと、反転していくのです。
ですから、この後すぐトイレに行ったホールデンが、なぜかトイレの床へ気を失って倒れてこんでしまいます。「倒れてしまう」とは、原文では「fall」と表現されていて、当然、ライ麦畑の崖からの「転落」を意味します。
この「fall」に注目するのは、すごくありきたりですが、大事なことは、ホールデンがライ麦畑のキャッチャーになるのをあきらめたことではなく、つかまえる役から、つかまえられる役にひっくり返ってしまった点です。
その上さらに大事な点は、大回転があることです。それは生から死への大回転です。
まえに引用しました、たんにfuck youという落書を消しきれないことをホールデンは嘆いているように見えたけれど、そうではなくて、博物館のファラオの墓に書いてあったfuck youに刺激されてホールデンが自分自身の墓を、――つまりいい換えれば、自分自身の死を、想像しているということです。
ここで、fuck youが死ぬことと決定的に結びついていることを見逃してはならないでしょう。落書が書かれている場所に注目すれば、そこがなんであるかがわかります。
博物館では、ファラオのミイラにfuck youが書かれ、ギャッツビー亡き後の家にfuck youが書かれ、そしてここではホールデンの想像上の墓の上にも書かれているということ。いうまでもなく、ミイラも死者ならば、ギャッツビーも死者です。ですからここではホールデンも死者へと反転していくというわけです。
じっさい、彼はこの後すぐに、「フィービー(妹)に会うのがこれが最後になるかもしれない。いや、親戚の誰かってことだけどね」といっています。これは死んだらもう、だれにも会えないことを暗示しているのだとおもえます。
「グレイト・ギャッツビー」のなかでfuck youの落書を消していたニックを反復するように、ホールデンはおなじ落書を消していきます。つぎに、fuck youを家に書かれてしまったギャッツビーと同化するかのように、想像上のホールデンの墓にもおなじ落書が書かれます。その結果、ギャッツビーの後を追っかけるホールデンには死の影が漂うことになってしまいます。
しかし、このことはあらかじめわかっていたと見えて、ホールデンが「グレイト・ギャッツビー」を好きだといっていた引用を、もう少し注意深く読んでいけば、すでにそこが、死の雰囲気でいっぱいだったことがわかります。
なぜなら、さっきホールデンは「グレイト・ギャッツビー」が好きなだけでなく、同時にリング・ラードナーも好きだといっています。
ラードナーの短編小説のなかでホールデンが好きなのは、この、女の人が交通事故で死んでしまうという小説だったし、作家のラードナー自身、1933年にはもう死んでいて、ホールデンがしゃべっている時点(1949年)ですでに死んでいたわけです。むろん、フィッツジェラルドもすでに死んでいるし(1940年)、その物語の主人公ギャッツビーも、最終的には銃で撃たれて死んでいたわけです。
死んだ人間のオンパレード。――その上、ホールデンは「もうやられた」といっており、そう訳される表現は、原文では「killed me」と書かれていて、直訳すると、「ぼくを殺した」という意味にもなります。
一般的には「……やられちゃった」という意味で使われます。
雨が、キーワード? ――「The Catcher in the Rye」の最後で、セントラル・パークの回転木馬にホールデンの妹フィービーが乗っているシーンが出てきます。
くるくる回転している彼女をホールデンが眺めている。するととつぜん、雨が降ってきます。どしゃ降りになる。周りにいた大人たちは、だれもが当然そうするように、みな雨宿りへと走りだす。
けれども、ホールデンだけは雨のなかにとどまりつづけます。ふしぎなのは、ひとりだけびしょぬれになっているだけでなく、このときホールデンはとても幸せな気分になっていると書かれています。なぜなのだろう。
雨自体のなかに象徴的な意味を見出そうとするべきなのだろうか? 雨は再生を意味するとか、逆に死を意味するとか、いや、雨は雨だ。それ自体に意味などあるはずがない、などなど。
――いろいろな考えがあります。
じっさい、ここでの雨はひとつの目印にすぎないと、ぼくはおもっています。
雨は「The Catcher in the Rye」を「グレイト・ギャッツビー」と結びつける印なわけです。ぼくにはそう見えます。さっきのfuck youのように、この雨は2つの作品を結びつけるヒントみたいなものがあるからです。そしてfuck youがホールデンを死に近づけたように、この雨をホールデンをほとんど殺すことになります。なぜなら、死んだギャッツビーにも雨が降り注いでいたわけですから。
もうひとつは、ヘミングウェイの「武器よさらば」の最後に、キャサリンが出産に失敗して亡くなります。相手のヘンリー中尉は、涙も見せず、大きく落胆して、どしゃ降りの雨のなかをホテルへと帰っていきます。
ギャッツビーは、最後に銃で撃たれて殺されますが、ギャッツビーの葬式は、けっきょく、わずか数名の参列者しかいない、ひじょうにさびしいものに描かれています。
そしてそのとき、天気はどしゃ降りの雨でした。
その部分の文章を引用してみましょう。
五時ごろ、ぼくたち三台の車の葬列が墓地に到着し、こい驟雨(しゅうう)のなか、門のそばに停車した――先頭は雨にぬれた、不気味に黒い霊柩車、つぎがギャッツビー氏と牧師とぼくが乗ったリムジン、それから少しおくれて、四、五人の従僕とウェスト・エッグの郵便配達が、ギャッツビーのステーションワゴンに乗り込み、みんなずぶぬれになっている。
雨のなか、いよいよギャッツビーの埋葬というときになって、ある男が雨と死者との関係をこんなふうにぼそっとつぶやきます。「幸いなるかな、死して雨に降られたる者……」
死んで雨に降られるのは、幸せ者だというのです。ギャッツビーも死んで雨に降られて幸せ者だ、と。そのいっぽうで、回転木馬のまえのホールデンも雨のなかにひとりたたずみ、「幸せで叫びだしそう」になっています。
その部分を確認しますと。
もう、雨が狂ったように降りだしてきた。どしゃぶりさ、それはもう誓うね。親たち全部だ、母親たちも誰もかれも、回転木馬の屋根の下に駆けこんだんだ。びしょぬれになったりなんかしないようにさ。でもぼくはベンチのとこにしばらく残ってた。……でも気にしちゃいないよ、フィービーがくるくる回りつづけるようすとかでさ。とつぜん、ぼくはすっごく幸せな気分になったんだ。
雨のなか、ホールデンは「雨にぬれた者」になっていることです。
つまり、彼は生きているけれど、「幸いなるかな、死して雨に降られたる者」になってしまっているわけです。その上、「すっごく幸せな気分」になっている。――すごく不自然ですね。
けれども、この場面の謎を解くカギは、ぼくらには明らかなので、ホールデンがぬれて幸せでなければならない必然性は、ギャッツビーのなかにひそんでいたわけです。雨にぬれて幸せになっているという、一見気が狂ったような自虐的な状態は、じつは「グレイト・ギャッツビー」のなかの「幸いなるかな、死して雨に降られたる者」を経由することで、よりよく理解されるべきなのだということを。
つまり、ホールデンはギャッツビーの真似をしていたわけです。
ぼくはさっきいったように、すでにギャッツビーが死んでいるという点です。「雨」と「幸せ」はいいとしても、「死者」においても、2人は重なるべきものとして描かれているように見えます。それにしても、ホールデンはほんとうに生きているのだろうか、という疑問が湧いてきます。
では2人の「死に方」を比較してみます。
ギャッツビーはいちおう銃で撃たれて死んだということになっています。けれども、実際に撃たれた場面を作者フィッツジェラルドは細かく描写していません。ただ、ギャッツビーの運転手が銃声を聞いた、と書かれているだけです。
その運転手も、べつにそれでギャッツビーが死んだとも気づいていない。あとになって、運転手がそう証言するだけの話です。
じっさいに描かれているのは、ギャッツビーがどのようにして発見されたかだけです。奇妙なことに、彼の死体が発見されたようすは、以下のようにプールの水ばかりが強調され、一見、死とはまるで関係ないプールの状態を描写しています。
一方の端から流れ込む新しい水が、他の端の排水口に向かって流れていくにつれて、かすかな、ほとんど目にもとまらぬくらいの動きが水に感じられる。彼の影ともいえぬ小さなさざなみを立てながら、人を乗せたマットレスが、プールの下手に向かって不規則に動いていた。水面に小じわさえ立てぬくらいのかすかな風が吹いていただけでも、思い設けぬものをのせて、思い定めぬ方向にただよっていくそのマットレスの進路を乱すにはたりた。一片の木の葉が触れると、それは転鏡儀の脚のように、水面に細い円を描きながら、ゆっくりと旋回した。
「グレイト・ギャッツビー」もまた、奇妙な作品です。――これには理由がちゃんとあるのですが、ここでは触れません。
ギャッツビーの血が水のなかへと溶けこんでいきます。プール、波、さざなみ、水面などなど、水についてこれほど細かく描写しておきながら、いっぽうでギャッツビーの死体については直接的には、一言も触れられていないのです。まるで銃で撃たれたことよりも、水の上で、水に溶けこむようにしてギャッツビーは死んでいったのだとフィッツジェラルドはいいたげではないですか。
それが作品「グレイト・ギャッツビー」の、じつはテーマだったわけです。ギャッツビーの死と水との関係をいちおう頭に入れて、こんどは、ホールデンの妙なクセを見てみたいとおもいます。
たびたびホールデンは銃で撃たれる真似をしています。
銃で撃たれたギャッツビーの真似をしているように見えます。けれども、そこでぼくの目を引くのは、ホールデンが撃たれた真似をしながら、息ができない、溺れて死にそうだ、と感じている点です。――これはちょっと、奇妙だとおもいませんか? それはちょうど、雨のなかの葬儀とかプールのなかでの死とか、ギャッツビーの死の様式をそっくりなぞっているように見えるからです。
そこで、水のなかで溺れて死んでしまう感覚が、どのようなものか、銃で撃たれる空想を呼び寄せるプロセスを振り返ってみましょう。
だけど今度ばかしは死ぬと思った。ほとんど死にそうだった。溺れたりとかすると思った。困ったのは、息がほとんどできなかったことなんだ。なんとか立ち上がって、バスルームに歩いていったんだけど、からだを折り曲げて、腹を押さえたりしてたんだ。
だけどぼく、狂ってんだな。ほんとに狂ってる、バスルームに行く途中で、腹に銃をうち込まれた真似みたいなの、やってたんだ。
溺れて死ぬことと、銃で撃たれて死ぬこととは、ふつうまったく別の死に方だとおもうのですが、「腹を銃でうち込まれた真似」といっています。ふつう、溺れそうになったとき、腹を銃で撃たれた気分になるものでしょうか。ぜったいにならないとぼくはおもいます。そこを変だ、と読者に感じてほしいと作者がいっているように見えるのです。
銃で撃たれる苦痛と、息ができないほど溺れていく感覚とが、なぜかホールデンのなかでは同時に発生してしまっているのです。
「息がほとんどでき」ず、「溺れたり」しそうに感じること、すなわち、水中での死の感覚が、すかさず銃で撃たれる真似を、奇妙なことに誘発させているわけです。銃と水が密接に結びついた死の雰囲気をたたえながらも、ここでホールデンは適切にも「バスルーム」という水場へと向かっていること、それを見逃すわけにはいかないでしょう。もちろん、水場=プールへと向かってから銃で撃たれたギャッツビーとは順序が逆になっていますが。
銃で撃たれることと、バスルームとのつながりは、さらにべつの箇所でホールデンが銃で撃たれる真似を繰り返すときにも、ふたたび浮上してきます。読者に銃による死と、水中に潜りこむことのつながりを、執拗におもい出させようとしているかのようです。
ぼくはほんとに酔っ払っていたんで、腹を撃たれたバカみたいな真似をまたはじめたんだ。バーのなかで、ぼくだけが腹を撃たれてたんだ。ジャケットの下で、腹を手で押さえたりしてさ、血がそこらじゅうに滴り落ちたりしないようにしてたんだ。
この後、ホールデンは「血が滴り落ちたりしないように、ジャケットの下に手を入れっぱなしに」しながら、女友だちサリーに電話をします。そして「気絶しないように電話にしがみつきながら」もなんとか電話ボックスから出てくると、トイレ(すなわちバスルーム)へと向かいます。アメリカ英語では、一般的にそこをトイレット・ルームといっています。
銃で撃たれて水場へと向かうパターンが、ここでも繰り返されています。銃で撃たれるという、この空想自体そもそも「気違い」沙汰ですから、妙に目をひく特異な行動だけれど、それ以上に、ここでホールデンが洗面所で水をためて頭をどっぷり浸すという、じつにふしぎな仕種をすることで、ぼくらの注意をさかんにひきつけようとします。
季節はクリスマス直前で真冬。
この世のどこに、真冬の夜中に頭を水に浸し、乾かしもせずに凍えて笑っている人間がいるでしょうか。
まず、変なことばかりが目につきます。この異常な水没行為のせいで、先ほど見たこれまた特異な溺死の感覚を連想しない人は少ないとおもいます。
「だけど今度ばかしは死ぬと思った。ほんとに死にそうだった。溺れたりするかと思った。困ったのは、息がほとんどできなかったことだった。」
というホールデンの描くイメージが、ここでは形を変えて、じっさいに頭を水のなかにどっぷりとつけるという形で書かれていることです。ただここでは、ぬれた頭を乾かしもせず、ぬれるがままに放っておくことで、より直接的にホールデンのからだと水が結びつくように描かれています。「グレイト・ギャッツビー」では、泥酔した婦人がプールに頭をつけられ、溺れそうになったという何気ない挿話が出てきます。
銃で撃たれ、水に浸ること。――それは撃たれたギャッツビーがさざなみの立つプールの水面にぷかぷか浮かぶイメージと、まるでおなじ死に方じゃありませんか。
「The Catcher in the Rye」のなかで水と死との関係は、のちにギャッツビーとはべつの観点から何度も振り返ることになるのだけれど、ひとまずここでは、銃で撃たれることと水とを接点にして、まるでギャッツビーの死をホールデンの行動パターンが反復しているように描かれている点に注意しておきたいとおもいます。