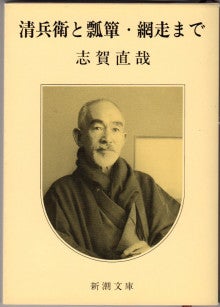「網走まで」。―志賀直哉。

昨夜、寝ながら志賀直哉の初期の短編「網走まで」を読んだ。この小説は、もう5、6回は読んでいるだろう。ぼくは寝室で、手を伸ばせば届くところに、いろいろな本を並べている。その日の気分しだいで、睡魔に襲われるまで好きな本を読む。あるときは画集だったり、あるときは世界地図だったりして、読む本はこれといってまとまりのないものばかりだ。植物の図鑑もながめる。
そばで眠っているヨーコが目を覚まし、ガバッと起きて、ぼくの顔をのぞき込む。メガネをかけたまま眠っていることがあるからだ。
「お父さん、まだ読んでるの?」
「うん」
ヨーコは、志賀直哉という作家の名前を見て、
「あした、わたし旅行だから、眠りますけど、お父さん、明日お願いね?」という。ヨーコの書いた書を明日の朝、郵送してほしいといっている。
「わかってるよ」
「それから、もうひとつお願いがあるのよ」という。
「お風呂の水、捨てていないので、気が向いたらお洗濯、お願いしていいかしら?」という。いま、夢のなかで思い出したというふうにいうのである。
「せんたく? ………うーん」
「明日はちょっと、出かけるから」
「あら、どこへ?」
「大学時代の、友だちだよ」
「先日の人?」
「ちがうよ。先日の人の友人。息子と同級生の子のいる、……ヨーコの知らない人だよ」
「ふーん。何時に?」
「まだ決めていないけど」
「どこで会うの?」
「――網走まで」
ヨーコは、ガバッと起きて、「北海道の網走? ははははっ。お父さん、ボケたんじゃないの? それは小説でしょ?」
「網走っていったかい?」
「そうよ。びっくりしたわよ。目が覚めました」といって、ヨーコは立ち上がった。
「起きるの?」
「おしっこよ」
それから、ヨーコはしばらくリビングルームで何かしていた。たぶん、明日のぼく宛ての用事をメモ書きしているのだろうと思った。
やがてヨーコが寝室に戻ると、
「お父さん、一時を過ぎていますよ。もう寝なさい」といった。ぼくはちょうど、志賀直哉の「或る朝」という小説を読んでいた。その小説の冒頭は、こんなふうに書かれている。
《「明日坊さんのおいでなさるのは八時半ですぞ」と云った。
暫くした。すると眠っていると思った祖母が又同じ事を云った。彼は今度は返事をしなかった。
「それ迄にすっかり支度をして置くのだから、今晩はもうねたらいいでしょう」
「わかっています」
間もなく祖母は眠って了(しま)った。/どれだけか経った。信太郎も眠くなった。時計を見た。一時を過ぎて居た。彼はランプを消して、寝返りをして、そして夜着の襟に顔を埋めた。/翌朝(明治四十一年正月十三日)信太郎は祖母の声で眼を覚した。》(志賀直哉「清兵衛と瓢箪・網走まで」、新潮文庫、平成15年版)
ここに出てくる「明治四十一年正月十三日」という日付は、明治39年1月13日に亡くなった志賀直哉の祖父直道の三回忌にあたっていて、これはほんとうの話を書いたものと思われる。彼はおばあさん子として幼いころから大いに可愛がられた。しかし、父親とはうまくいかず、父親に反感を抱きながら成人した。ようやく和解にこぎつけたのは36歳のときだった。「和解」という小説は、ながいあいだ父親と確執していた事実をめぐる小説で、どのようにして和解にこぎつけたかが書かれている。
それから、ぼくはふたたび志賀直哉の本を読んだ。「網走まで」という小説である。この小説はいつ読んでもいいなあと思う。
上野駅から乗り込んだ男が、網走まで行こうとしている子連れのおかみさんの話として書かれている。ふたりの子供は母親にいろいろ甘えて、やれ、何がほしいだの、おっぱいがほしいだの、やれおしっこだのと、大宮までのわずかな時間ながら、細密な描写で書かれている。
男は大宮駅を下車するのだが、おかみさんも子供のおしっこのために下車し、電車のなかで書いたというハガキ2枚を差し出して、これを投函してほしいという。あれじゃあ、一週間たっても、果たして無事に網走に到着するかどうかわかったものじゃない、と心のなかで思う。女からあずかったハガキ2枚をポストに投げ入れるとき、宛先をちらっと見る。ひとりは女宛てで、もうひとりは男宛てのハガキだった。文面を読もうかと思ったが、読まなかった。
女には亭主がいるふうじゃなかった。何か問題を抱えたまま、遠い北海道の網走くんだりまで行くのだ。その人の過酷な運命を垣間見て、いかにも気の毒だと思うくだりがある。
明治41年に書かれたこの短編で、志賀直哉は決定的な進路を確立した。同年彼は26歳で、東京帝国大学英文科の学生だった。
「或る朝」、「速夫の妹」、「荒絹」など矢継ぎ早に書き、生き生きとした生活描写をものして、文壇へのデビューを果たした。志賀直哉は父親との確執が有名だが、そのために、終生「父と子」の問題に収斂される一連の小説を書きつづけた。長編には「暗夜行路」があるが、ぼくが読むかぎり、成功しているとは思えなかったが、彼の短編は、いずれも優れていて、「網走まで」という小説は、26歳で書いたとは思えないほど成熟した描写が光る。
文庫本の「剃刀」まで読んで、ぼくはようやく眠りについた。