MUSICAL FANTASY
ジュール・ヴェルヌの海洋SF小説『海底二万里』に登場するネモ船長──潜水艦ノーチラス号で植民地支配を目論む国々に敢然と戦いを挑む孤高の英雄を新たな視点で描くミュージカル・ファンタジー。
19世紀後半、イギリスの捕鯨船が南大西洋サウスサンドウィッチ諸島付近で謎の遭難事故を繰り返し、船乗りたちからは魔の海域と恐れられていた。イギリス政府は学者たちを招聘し調査隊を編成、南大西洋へと艦隊を派遣した。だが魔の海域に近付いたとき艦隊は次々に船底から爆発、沈没。救命ボートで九死に一生を得たわずかな学者たちは、地図にない島に辿り着いた。その島は植物も育たない寒帯地方にもかかわらず、海底火山帯の地熱で温暖な上、地熱を利用した発電装置まで備え、世界中の何処よりも発達していた。島の住民は、東欧・アジア・アフリカなど帝国の植民地支配から逃れてきた人々だった。そして、その島の主は、潜水艦「ノーチラス号」の船長ネモ、有能な物理学者でもある彼は、寡黙で謎に包まれてはいるが、島民からは絶大な信頼を得ていた。ところが、島の秘密は調査隊の知るところとなり、本国にも知られてしまった。島民たちを護るためネモ船長は「ノーチラス号」で敵艦隊に敢然と立ち向かって行く……。
争いを憎み、類い希な英知をもって地上の楽園を創り上げようとしたキャプテン・ネモの孤高の美学を、彼に思いを寄せる女性調査隊員とのロマンスを交えて描きます
以上公式サイトより
雪組日本青年館ホール公演『CAPTAIN NEMO』を2回観劇。9月2日11時開演と15時開演。
本拠地宝塚の小劇場であるバウホールで行われる、トップ以外の組子が主演した作品は、以前まで日本青年館で行われてきたのだが、最近それがなくて、なぜか赤坂ACTシアターでやったりしていた。なんでだろうとずっとおもっていたが(調べてはこなかったので、それほど問題視していなかったのかもしれない)どうやら改装していたらしい。といっても場所はちがう。前回の星組特別公演をこけら落としとして、新・日本青年館がオープンしたのである。主演は雪組2番手の彩風咲奈だが、お目当てはむろん専科から派遣された華形ひかるである。あと僕的には永久輝せあも・・・。
新日本青年館だが、あれは、評判どうなのだろう。ホールにかんしていうと、椅子はかなり座り心地がよかった。列ごとに段差になっているから真ん中にいるひとの姿がまるまる前のひとのあたまで隠れてしまうなんてことはなさそうだし、今回両方とも通路側だったのでうまく把握できなかったが、男性もほとんどうしろを気にしなくていいかも(ほとんど、です)。2メートル近いとかだったら別だけど。舞台は特に可もなく不可もなくという感じなので、ということはよかったのだろう。なにかに特化しているという感じもなく、ごく標準的な高さと奥行きだとおもう。
ところがロビーの様子ときたら、それはもう、たいへんなものだった。どこにいってもぐちゃぐちゃに混雑し、前に進めず、遠回りをして、ひとにぶつかるのである。これについてはまず、開場したばかりであるという、ある程度考慮しなければならない事情は、たしかにある。たとえばこれが東京宝塚劇場だと、来場しているひとたちはもう、数え切れないくらいそこに訪れているひとたちなので、眼をつぶっていてもトイレや出口にたどりつけるわけである。ところが、新日本青年館はそうではない。みんなはじめてなので、どこになにがあるか、どのくらいの歩行速度、間隔で歩けばいいのか、よくわからない。そういう意味では判断保留の余地はある。わたしたちにはまだその構造のよしあしを語る段階にないのかもしれないのだ。オープンしてからまだほんの少ししかたっていないので、会場スタッフだって、どういうところでお客が迷うのか、進行をためらったり、行き先まちがえたりするのか、まだ把握できていなかったとしても不思議はない。しかし、それでも、これは果たして、ほんとうに、動線を考えて設計されたものなのだろうかとなってしまうようなぶぶんが多々あった。たとえば喫煙所だ。喫煙所なんてなくてもいい、というポリシーであるなら、それはそれでかまわない。しかし、館内にはちゃんと喫煙所が用意されている。しかしこれがぜんぜん見つからない。というのも、狭い通路がくの字に曲がった先にあるわけなのだが、その向かいに女性トイレがある。したがって、休憩中はその通路が女性で埋まることになる。傍目には、どう見てもその通路は女性トイレに向かう通路なのである。そして、その先に喫煙所があるということを理解したとしても、とても通れたものではない。僕はあんまり気にしないけど、気の弱いひとりの男性客だったら、まずあれは通れないだろう。女性トイレの列に並んでいるひとは、当然のことながら喫煙所のことなんてあたまにないので、この通路は女性トイレに向かうものと認識しているはずである。そこに男性が突っ込んできたら、ぎょっとなるにちがいないのである。というか、少なくとも男性は、「女性はぎょっとなるにちがいない」と考えるにちがいないのである。原因のひとつとして、この劇場が宝塚の専用劇場ではないということがむろんある。宝塚の青年館公演の割合を調べたわけではないが、あれほどに女性がトイレに向けて列をつくる現象は、いちおう例外的なことであると、専用でない以上原理的にはいえなくもないわけである。なにが問題なのか判断できなかったが、トイレから伸びる列も非常に長く廊下に横たわっているので、ただ廊下を横切るという行為が非常に困難なものとなる。聞くところによれば女性トイレの個室の数も少ないとか。たしかに、いわれてみると、第一部も第二部も、またその幕間も、開演間際になっても席についていないひとが非常にたくさんいたが、あれはそういうことなのだろう。なにやら2階席も問題含みだとか・・・。
とはいえ、作り直すわけにもいかないし、これから小劇場公演にかんしてはここが基点になるのだろうから、我々は慣れていかなければならないのかもしれない。くりかえすように厳密には、わたしたちはまだ冷静な判断ができない状態である可能性が高い。慣れてみたらどうってこともない問題なのかもしれないし、いろいろ改善の方法も探られていくことだろう。
さて、谷正純演出の本作だが、なかなかかわった作品だった。谷先生ってなに書かれてたかたかな・・・と調べてみたら、僕が小学生か中学生のころに見てたようなやつをけっこう担当されている。最近(といってもけっこう前だが)観劇したものではサンテグジュペリがそうみたい。なんか、なるほどとおもってしまった。
原作というか底本はヴェルヌの名作『海底二万里』である。僕も谷先生同様、創元SF文庫でヴェルヌにはまっていた時期があったが、はるかむかし、25年くらい前のことで、また好きだったのは『地底旅行』や『八十日間世界一周』とかで、じつは海底二万里のことはあまり記憶にない。なので本作の舞台であるマトカが作中にあらわれるのかどうかというのはわからないのだが、しかしまあ、プログラムにもあるように、原作のことはほとんど気にしなくてよさそうである。谷先生の思い描くかっこいいネモ船長を、宝塚の文脈で肉付けした、という感じがほんとうのところのようだ。
ネモ船長は本作ではポーランド出身となっているが、劇中演奏される別れの曲の作者ショパンもポーランドからパリへ移民した人物である。別れの曲じたいはエチュードで、このタイトルは日本独自のものだったと記憶していたので、劇中でそのタイトルを呼んだときはちょっと戸惑ったが、あらためて別れの曲について調べてみると、どうやらロシアなどに征服されつつあったポーランドからパリに逃れたそのときに、かの有名な「革命」などとともにショパンはこれを作曲したようで、本作での使われ方は歴史的にも誤りではないようである。まさか番号や音階で呼ぶわけにもいかないし、あんまりリアリティにこだわると逆にリアリティというのは損なわれるもので、劇的効果という点でも、まあこれはしかたないかなというふうにも感じる。手元に譜面がないし音源もないのだが、別れの曲はあの非常に有名な美しい旋律のあいだに、かなり激しい、狂気すら感じさせる破調の展開をはさんでいて、もちろんそのあたりは演奏されない。ネモ船長はおだやかにパイプオルガンに座って、あのぶぶんを、シンプルなアレンジで演奏するのみである。おもえばこのあたりもネモ船長のほとんど異様な人格を裏取っているかもしれない。ある意味では、あのありかたはすべてフィクションであり、みんなの望む姿なのである。
物語のはじまりはじゃっかんややこしい。時代は19世紀で、イギリス海軍のラヴロック少佐(朝美絢)は、南極のあたりで捕鯨船の沈没事故が相次いでいる件について調べている。理由がわからないので、海洋気象学者で本作のヒロインであるレティシア(彩ちひろ)、海洋生物学者のジョイス(華形ひかる)、なんとかという学者と間違えて連れてこられた新聞記者のシリル(永久輝せあ)をつかってこの謎を解こうとする。しかし、その船も、南極近辺で沈没することになり(ネモたちのしわざ?)、彼らがたどりついた(救助された?)のが、ネモ船長が管理・維持するユートピア、マトカなのであった。マトカには強国の支配から逃れてきた難民たちが暮らしていて、科学のちからで少佐や学者たちが目をまるくするような環境が実現している。マトカには、おそらくいちぶのものしか知らない立ち入り禁止区域があり、そこにはじつはノーチラス号というロシア製の潜水艦がある。ネモやそのとりまきの美しい軍服はみんなロシアに拉致された科学者たちで、これを完成させ、逃げてきたのである。メンバーには行方不明だったレティシアの父・モリエ博士もいた。マトカは帝国支配の対立概念ではあるが、争いは避けている。不審船が訪れても、人命を奪うことはなるべく回避し、救助できたひとびとは敵であっても歓迎しようと努めている。そんななか、ふとしたことから、ロシアの全艦隊が押し寄せる事態を招いてしまう。と、こんなおはなしである。特筆すべきはネモ船長の教祖っぷりである。彩風咲奈は器用なタイプの舞台人ではないが、じっさいこの役はそうとう難しいものであると想像できる。なにしろほとんど動かない。ほとんど感情をあらわさない。激昂してもどこか一方的で波打ったものがない、そういう、なにか超人的な人柄なのである。深みのある声をよくつくりあげてきていて、よく洞察しているとおもうが、なにしろ上演時間が短い。映画だったらラストエンペラーみたいな大作になるであろう内容であって、やってるほうは非常にしんどいのではないかとおもう。このややこしい物語の前提にかんしては、永久輝せあがおしゃべりという設定になることによって、なんとかカバーしている。非常に聴き取りやすい発声で、二回見たうち、あれだけしゃべって一度もかまなかったのは見事というほかないが、正直に書くと、ほとんどが物語の背景の説明に終始する第一幕は、僕は眠くて眠くて、たいへんだった。たんに寝不足なだけなんだけど・・・。1幕にかんしてはひとつの場面がけっこう長くて、変化がないパターンが多いということもあり、なかなか、こう、たいへんだった、けど、これはだいぶぶん僕の問題だろう。でもじっさい、永久輝せあの声がなんかにゃーにゃー鳴いてる猫みたいで眠気を誘うぶぶんが・・・。1幕ラストでリトアニアの女の子が出てくるあたりから、物語はようやく動き出していく感じだ。
このあと梅田での公演もひかえており、本作は一種の驚きを最終部分に含む物語でもあるので、ネタバレはしない。その範疇でいくつか考えていきたいことがあるのだが、まずはネモ船長の人物像である。というか、これを考えていくと、結果としてだいたいの謎について触れていくことになるはずである。
マトカは帝国支配の対立概念だ。量にものいわせて相手を屈服させ、弱いものを従わせ、必要であれば排除していく、それが帝国支配であり、それに反対するものとして、マトカはひとびとをなかに入れていく。ネモ船長のセリフに、ひとの価値は弱さにある、という印象深いものがある。弱いから、強くなろうとし、また助け合って生きていく。列強の価値観は、強いから成立するものであり、外部的には強いことに価値を見出すという宣言にほかならない。たとえば、「ひとの価値は弱さにある」ということを量で、ちからで相手に納得させることは原理的にできないわけである。そうであるから、マトカのありようは、列強と対立しながら、自然消極的なものになる。ネモ船長たちがノーチラス号を隠していた理由は、いくつか考えられるが、ひとつにはたんじゅんに彼らは逃亡者なので、なんらかの手段で潜入したスパイに見られてしまってはまずいということがあるのだが、もうひとつは、この必然的な消極性をノーチラス号の外観は破綻させてしまうかもしれないということもあったろう。強いこと、たくさんのものをもっていることが価値観として「強い」のは、あとに残るからである。強国の価値観をもってすれば、ほかのどのような価値観も駆逐することは可能だし、仮に論理的に破綻していても、それに文句をいうものは出現できない。これがおそらく、ほとんど狂気の様相でリトアニアの女の子に生への執着のようなものを語るあの場面に転じている。とにかく生きる、生き延びること、それだけが、弱さを基準にしたマトカの価値観が強さに勝利する唯一の道なのである。
こうした閉ざされた島の価値観はどのように成立するかというと、そこにあのほとんど宗教的な島民のありかたが関係しているだろう。現実には、武力をもっていないから、強力な国が攻めてきたらマトカにはなすすべはない。島民には、これで正しいのだと確信できる根拠が必要である。そのために、ネモ船長は島民の前であの人柄を保持している。これは彼自身の資質でもあったとはおもわれるのだが、さきほどちょっとだけ書いたように、故国への別れと、家族をおいてきたノーチラス号クルーの贖罪の気持ちを代弁した「別れの曲」が、彼らのBGMとなってそこには響いている。非常におだやかで美しい、あの旋律。あれが、島民の目にするネモ船長である。ところが、この曲はその半ばで突如として激しい展開を見せる。しかしそれは隠されている。ここのぶぶん、ネモ船長の使命感とは別にある彼の激しい感情は、どこに昇華されているかというと、それがあのダンスではないかと考えられるのである。なにか、奇妙に長い時間をとったネモ船長のダンスが、奇妙なタイミングで、何度か挿入されるのである。振り付けがすべて一緒だったのかどうか、どういう音楽だったか、記憶にはないが、あれはそのように、ひとびとのヒーローとして、「これでいいのだ」と確信できる証明として立たなければならないネモの激情だったのではないかと考えられるのである。
その意味で、島民の目にする「キャプテン・ネモ」は、虚構である。そうかもしれないとおもえたのは、少佐の件があった。船長は、あることがあってから、じぶんの後任を少佐に任せたいともちかけるのだが、これがじつに奇妙なのである。少佐は島にきてからずっとイギリス海軍の軍服を身につけている。しかしイギリスはイギリスで最強国のひとつであり、まさしく量、強さでなにもかも決してきたところだった。島民にはインドのお姫さまもおり、イギリスの軍服に強いトラウマがある。彼女も努力はするが、どうしても軍服を克服できない。少佐が悪いひとではなさそうだということは、おそらくみんなわかっているのだが、問題はそういうことではないのである。ところが、彼は軍服を脱がない。そんな彼をネモは後任として突如指名する。もちろん少佐はなぜかと問う。なんといっていたか、じぶんは嫌われ者じゃないか、なぜじぶんなのかと。これに対してネモは、奇妙な応答をする。軍人であることをやめて、ひとりの人間になってくれと、このようなちぐはぐなこたえをするのである。いちおう注意深く見ていたが、なぜ少佐が軍服を脱がないのか、そしてなぜネモが彼を後任に選んだのか、はっきりした理由はひとことも得られなかった。島民からの信頼、またその知性という点で、華形さん演じるジョイス博士のほうがしっくりくるぶぶんはある。だがそうはならない。これはいったいなんなのか。逆にいえば、この空白の二箇所がつながっているのだと考えれば、ことはすっきりする。すなわち、ネモ船長は、少佐が軍服を脱がなかったから、彼を後任に選んだのである。
それはどういうことか。まず、少佐が軍服を脱がないということは、どういうことを導くだろうか。少佐は明らかに善人である。インドのお姫様・ラニが、少佐じしんではなく軍服を恐れているのだという論理を聴いて、少佐は黙ってしまう。いや、その作戦じぶん参加してないし、的なことをいいはするものの、知らん振りしているというふうではない。たしかに彼は、その恐怖の過程にかんして納得してしまっているし、責任を感じてしまっている。強国の負の側面をマトカにきてからつきつけられている状況ではよけいそうだろう。彼は、誠実であるからこそ、これまでそういう発想をしてこれなかったという可能性がある。しかし、なぜか少佐は、直接脱いでくれと頼まれても、これを断る。ここには引責の感覚を見て取りたい。彼は、イギリスのインドへの侵攻を、もはや世の合理性や強国としての必然としては見ていない。全部分においてとはいわないが、それでも、悪いことだった、直接参加はしてなくてもお姫様には悪いことをしてしまった、とてもかわいそうだ、という感想を抱えているにちがいないのである。しかしそれでいて、彼はイギリス海軍の将校であることをやめはしない。むしろ、それでい続けようとする。彼にとってはイギリスは交換不可能な故郷である。男であるとか、長男であるとかいうことと等しく、気に入らないからといってあとで変えるわけにはいかない本質的事項であり、さらにいえばそれを誇ってもきた。そして、誇るべき故国が、こうして恥ずべき行為を行ってきて、しかもじぶんはそれに気づかなかった。彼はそのことを引き受ける。無言の非難も、沈黙も、じぶんがイギリス人として浴びなければならない責任としてとらえるのだ。イギリス海軍であることが嫌われる原因であるなら、じぶんはたしかにそこに足場を築いているぶん、嫌われる状況を容れなければならないと、そういう思考回路が感じ取れるのである。
そしておそらく、ネモはそれを感知している。ネモの後任として必要なことは、虚構の存在としてひとびとの支えになれることだ。たんじゅんに少佐が軍人なので、ひととしての、意志としての強さが学者より優れているとか、そういうことももちろんあったろう。そしてそこに付け加わるのが、この引責感である。あるいは少佐じしんには、その自覚はないのかもしれない。しかしネモは、彼がそういう葛藤を抱え、イギリス人であることをみずから選び取っているということを見抜いている。別れの曲はノスタルジーだけではなく、捨ててきたもの、おいてきたものに対する贖罪の感情も含んでいる。みずからの構成要素のなかに負の面を見出しても、それを捨てるのではなく、たしかにそれとして抱えながら、そのままに保存し、責任をとっていこうとするそのありかた、そこに、ネモはおそらくノーチラス号のクルーとおなじ意志の強さを見て取ったのである。彼らも、マトカをつくるにあたって、家族を捨て、故郷を捨ててきた。別れの曲は、そこへのなつかしさと、そのことをつぐなう気持ちがこめられている。たんに清浄なだけではネモ船長にはなれない。島民のリーダーにはなれない。清浄であることを選び取るためには、不浄であることを捨てるのではなく、まるで供養するように、どこかにしまっておく手続き、そしてときどき思い出す手続きを必要とするのである。これが少佐では軍服に集約される。嫌われているからといってあっさり軍服を脱ぎはしなかったその点に、彼の不浄ははずされはするものの保存され、供養される可能性がすでに含まれているのである。
いちばんの謎といえばモールス信号である。突如一定の音で歌いながらあらわれる娘役が練習しているのは、モールス信号である。これは、どうやら島民はみんな練習しているらしかった。やってきたばかりのリトアニアの女の子もどうやらそのうちやらされるというはなしで、最終局面では和解にも用いられる。これがけっきょくなんだったのかよくわからないのである。僕は最初、さまざまな言語の国のひとたちが集まるのだから、初歩的な共通言語として用いられているのかとおもったのだが、でもモールス信号って文字を表現する手段ですよね。英語だったらアルファベットだし、日本だと五十音。つまり、もとの英語だとか日本語だとかの言葉がわからないと、言語の代用にはならない。そう考えると、やはり実用性は低いと考えられる。もっと直感的な感覚にたよってみれば、やはりあの場面は、ちょっとこわい。いきなりちっさい娘役が出てきて鳴き声みたいにそれを練習している姿はまあなんというか和むのだけど、しかしそれを笑顔で島民がぜんいん練習していると考えると、なにかぞっとする。で、ちょっと考えたのは、モールス信号というのは信号の長短とその数で文字をあらわすわけだが、これは節のない四分音符と八分音符と休符ととらえることができる。ネモがその虚構の姿で体現する別れの曲の「有名なぶぶん」は、美しい旋律を抱えているが、島民のうたう歌には旋律がないわけである。象徴的には、ここに抑揚をほどこすのがネモの教祖性なのであり、ここが合致するときに、マトカのうたは完成する。ネモは指導者と島民の関係性を両者補完的なものとするために、じしんのカリスマ性の対極として、島民に抑揚を欠いた音楽を仕込んでいるのではないか・・・などといってみても納得はできないけど。
華形さんの存在感はさすがで、脚本的にもキャスト的にもあまり必然性は感じられないものの、最後のほうなどではすばらしい包容力を見せている。出てくるだけでなんか安心しちゃう、そういう男役だ。なんかきれいな女のひとがいるな、とおもってみると舞咲りんだった、ということは雪組は多いのだが、このひとと華形さんは同期で、劇中ではどうやらこのふたりがなんとなくいい雰囲気になってるっぽいのもある。直接いちゃつく描写はないが、マトカに備わる狂気の空気感に、一種の基準、「大人」として常識人的スパイスを加えるいいカップルになっているとおもう。ネモにとってのモリエ博士のような、少佐のブレイン、よきアドバイザーになっていくことだろう。
少佐役の朝美絢はやっぱりいい男役である。少佐も、いま考えてきたとおり、ネモ船長に匹敵するほどによくわからない役で、通してかたい動作、表情で芝居を続けなければならず、要するになにを考えているのかぜんぜんわからないので、非常に難しい役どころだとおもう。
主演の彩風咲奈にかんしては、とりあえずこのひとはなにをやってもかわいくなっちゃうのがずっとネックだったが、少しずつ、そこから脱しはじめているとはおもう。今回は声がよくできていた。ネモは、はっきりいってほとんど動かない、文字通りの偶像のような存在である。それでいてはじめてマトカにきたひとが引くようなことをいい、ときには大きな声も出さなければならない。そういうわけで、おそらく声の作りこみからはじまっていったのだとおもう。しかしあの髪の毛は・・・、あれは正解なのだろうか。じゃあどんな色や髪型がいいのかといわれても、僕にはわからないので、なんともいいがたいぶぶんはあるが・・・。海の男ではあっても海賊ではないわけだからワイルドである必要はないし、彼には神秘性も要求される。そういう吟味の結果なのだとはおもうのだが、なにかずっと「これで合ってるのかな?」という感じがつきまとっていた。そういう分野はくわしくないのでうまくいえないが。
東京のほうはちょうど今日が千秋楽か。梅田での公演も成功を祈っています。
 |
海底二万里 (創元SF文庫)
Amazon |
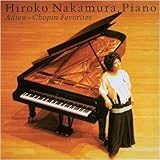 |
別れの曲/中村紘子が選ぶショパン名曲集
2,935円
Amazon |