第130話/斬った・・・
携帯槍をおとりにして蹴りをくらわせ、続くメリケンを握った一撃により武蔵をダウンさせた本部。正座のような体勢のまま動かない武蔵に、本部はとどめをさそうとする。しかし、脳震盪などの症状がそのまま動けるかどうかの結果につながるわけではないのがこの武蔵である。武蔵には、身体を乗り物と解釈しているようなところがある。仮に片腕を落とされても、普通は痛みと出血で気を失うか、少なくともたたかうどころではないところ、おそらく武蔵なら、たんに機能として片腕が欠損したということ以上の反応はないのではないかとさえ思えるのである。そうして、脳震盪が回復したわけでもないまま、武蔵は近寄る本部の腹を、かざした小刀ごと斬ったのである。
観戦しているバキをはじめとしたすべてのものが、この「斬る」という現実に驚愕している。烈なんかもっと盛大に斬られているし、ピクルだって全身ずたずたになっちゃったわけだが、一同はなにについてそんなに驚いているのだろう。これはおそらく、本部の戦略が成功していたことを示すのではないか。現実には武蔵の刀はちょっとずつ露出していき、前回も槍の先を切り落としたわけだが、基本的に本部は、出ようとする相手の肩をポンと押すような、相手の呼吸と心理を読んだ奇策に終始していた。奪った刀を返してまた奪おうとする、などということも、解釈としてはいろいろ可能だが、現実的には「なにをするかわからない」という不気味さを武蔵に与えるためだった可能性が高い。そうして、武蔵も観客も気づかぬまま、刀で攻撃するという動作がまるで非現実であるかのような気持ちになっていたのではないか。じょうぶな刀を持ち出してチャンバラしたって宮本武蔵に勝てるわけはない。だから、それ以前の地点で武蔵を圧倒しようとしたのが、本部の戦略だったのである。そして、それをしばらく見ていた観客も、そのやりとりじたいが本戦であるかのような気分になっていたのだ。しかし、このたたかいの本質はその先にある。おそらく武蔵がついに本部を斬ることになったのは、本部じしんが刀を出して武蔵を斬ろうとしたからだろう。本部は、刀が抜かれる前から、抜かれてもそれが肉体には接触しない前戯のような地点で、武蔵を倒そうとしたが、みずから、本番に足を踏み入れてしまったのである。
武蔵の頬はひどい状態だ、瓶で切り裂かれ、鎖分銅で痛打を受け、さらにトゲつきのメリケンで思い切り殴られたのだ。だが、むしろそれは「気付け」になったという。バキが花山戦で、口の中にガラスを仕込んでいたようなものだろうか。素手の殴打だったらまだ昏倒したままだったかもとまで武蔵はいう。つまり、決定的なのはあの蹴りだったのだ。あれで、武蔵は脳震盪を起こし、意識をとばした。しかし続くトゲつきの鉄拳が、神経にさわる痛みをもたらしたことで、むしろ武蔵は覚醒してしまったのである。
武蔵はその斬りごたえになにかを感じ取ったようだ。本部は鎖帷子を着ているらしいのである。くさりかたびらというと僕はドラクエではじめて知った防具だけど、実物はけっこう薄いんだね・・・。ほんとにこう、本部が武器としてつかってたやつか、なんならもっと太いようなのが巻きついてる感じなのかとおもってた。これならそれほど重くはないのかも。軽くもないだろうが。
忠臣蔵で有名な四十七士も、全員がこれを身につけており、満身創痍ながら全員生還しているという。ケガをしているということは、それなりに攻撃も受けているということであり、そのなかにはおそらく胴体に加わった、くさりかたびらがなければ致命傷となっていたようなものもあっただろう。それだけ防具としては優秀なのだ。
しかし、それなのに、本部は出血している。ふつうに考えて、武蔵は巻きついてるだけの鎖をきれちゃうわけだから、そんなものは斬れそうだが、くさりかたびらじたいは無事のようなのである。バキとガイアはどういうことかと困惑するが、佐部だけはじたいを理解しているようだ。くさりかたびらがどうなってるかはともかくとしても、斬撃によるダメージはあると、こういうはなしなのである。
でもまだ解説は必要だ。防弾チョッキは弾丸を通さない。しかしマグナムのよう大きく強力な銃だと、弾を通さずとも、それを着ている人間はダメージを受けてしまう。貫通しなくても、その衝撃は身体に伝わるのだ。うずくまる本部に武蔵は語りかける。ジャックは、じぶんが本部にかみついたときのことを思い出している。あのときは特殊な繊維で編まれた上着で、ぜんぶの歯をもっていかれてしまったのだった。同じ意味でいえば、ジャックの噛みつきも、貫通は防げても、それなりにダメージはあったはずである。ジャックは「俺のときも・・・」というふうに回想しているが、じゃっかんタイミングがおかしい。いまはもう、その本部が着込んでいる防具が通用していないというはなしをしているのだから。となると、ジャックはひょっとして、そんな防具を無視するような噛みつきのできなかったじぶんのふがいなさを悔いているのだろうか。
峰打ちや木刀で相手を絶命させることも武蔵ならたやすい。そんなじぶんの真剣の打ち込みが、鎖の布一枚で防げるわけないだろと、こういうのである。このはなしの流れでいくと、やはり鎖帷子そのものは無事のようである。もし鎖帷子ごとからだが斬られているなら、防弾チョッキや木刀などのはなしを持ち出す意味はない。これは要するに、刃のぶぶんをつかって相手を斬らなくても命を奪うことはたやすい、ということなのだ。でも血は出てる。武蔵だって峰打ちで腹を叩いて出血させたりはできないよな・・・?
武蔵には本部の服のしたの様子が手に取るようにわかる。鎖帷子だけでなく、腕や足にも丈夫そうな具足を施しているのだ。その左手を、武蔵の刀が斬る。武士としての本部に敬意を払いつつも、武蔵は決着を宣言するのだった。
つづく。
鎖帷子が実際には切断されていて、それで本部の腹が切れているという可能性が完全になくなったわけではないが、描写からして、ふつうに読むと鎖帷子は無事であり、にもかかわらず、マグナムをくらった人間が防弾チョッキを着ていても無事ではいられないように、衝撃を受けてしまったということだとおもわれる。しかし銃のはなしにしても、腹に弾がめりこむことはないが、同じくらいの威力のパンチを食らうくらいの衝撃はあるというはなしであって、弾丸と同じ効果があるわけではない。木刀で相手を殺すことはできても、首をとばせるわけではないのと同じである。ではなぜ本部の腹は切れているのか?
考えられることとしては、本部がじっさいに受けているダメージと出血はあまりかんけいがないというものである。鎖帷子が破損していない以上、刃は皮膚に接していない。接しているのは鎖帷子そのものである。顔を殴ってくちから出血するのは、ほとんどばあい、歯が口内に強く当たってこれを裂くからだ。同様にして、このときの鎖帷子はむしろ刃の衝撃を伝える媒体となってしまっており、これが強く当たり、またすべったことによって、皮膚が裂けたのである。しかしそれだけではあれほど重傷にはならないだろう。つまり、この攻撃で受けたダメージそのものは、防弾チョッキ越しの銃弾のようなものだったのである。それほどの打ち込みは、鎖では防げない。腹に武蔵の斬撃レベルに強烈なパンチをもらった、くらいのダメージを、本部は受けたのである。出血はあくまで副次的なものなのだ。
なんでもすぱすぱ切っちゃう武蔵だけど、鎖帷子が切れていないのだとしたら、強度が問題なのではないのかもしれない。つまり、同程度のかたさのたとえば鉄の棒とかは切れても、刀で斬られることを想定して設計された鎖帷子はさすがに強いのである。だとすれば、最後に武蔵が斬った本部の腕も、ちょうど具足が装着されているところだから、無事かもしれない。でも、真っ二つにしようと打ち下ろすのと、表面をすべらせるように斬るのではぜんぜんちがうだろうしなあ。武蔵の言い方だと、本部が鎖帷子をつけていることがわかったのはたったいまっぽい。そしてそれと同時に、あったかもしれない違和感の正体が、手足につけているにちがいない防具だと、武蔵はあたりをつけたのだ。もし打ち下ろしても鎖帷子は切れないのだとしたら、ちょっと前に宣言した大袈裟とかそういう斬りかたはかなり難しくなるだろう。それで本部を倒す、あるいは殺すことはできるかもしれないが、たぶん真っ二つにはできない。
なんにせよ、本部が大ピンチであるにはちがいないだろう。失敗だったのは予想外の武蔵の小指の強さと、みずからすすんで刀の領域に下りてしまったことである。武蔵に刀を握らせ、はい斬ってください、という状態から試合を開始したのでは、まず誰も勝てない。勝ち目があるとすれば武蔵が刀を抜く前であり、抜いた場合であっても、これを無力化させることに徹すれば勝機はある。たとえば槍の攻撃は、刀でこれを斬らせることによって振り切らせ、一時的に刀が存在しない状態を作り上げたものである。素手の打撃にかんしては武蔵も認めるところで、刀をとにかく制御し、そのうえで本部の土俵に持ち込めが勝ち目はあったわけで、げんにそれまでは本部が試合をリードしていたわけである。しかし蹴りで昏倒した武蔵を見て、本部は、とどめをさそうと、刀を抜いてしまった。そうすることでみずから、刀でのやりとりが行われる本身の領域におりてしまったのである。
通常の試合であれば、昏倒した武蔵はカウントをとられ、立ち上がらなければ負けている。本部の基準でいえば、生殺与奪の権を握ったとき、本部の勝利は確定する。ここで本部がとどめをさしにいったということは、まだその権利が握られていないと本部が判断したことを意味する。つまり、ある程度までは、武蔵のタフネスを理解して、これではまだ勝ちではないと判断したということになるのである。ただ、そのタフネスへの理解がまだ浅かったということなのだ。たぶん本部の理解では、こんな程度ではすぐに武蔵は立って反撃してくる、いまのうちに致命傷を与えておかなければ、というようなところだったろう。しかし武蔵には「いまのうち」などない。生きているか死んでいるか、動いているか停止しているかのふたつの状態しかないのである。このときでも、本部がまだ素手か、あるいは遠距離の武器に徹していれば、ほんとうに勝ちはやってきたかもしれない。が、本部は「いまがとどめをさすとき」と判断してしまった。くりかえすように、武蔵の状態には、そのようなときは存在しない。脳震盪になろうと、大出血しようと、動ける以上、まだそれはふつうの戦闘状態なのである。これにはおそらく、何度か書いた、武蔵の身体のとらえかたにかかわっている。もともと彼は人工的な肉体に魂が宿るというしかたで復活したものであり、そのぶん余計にその思考法は強化されているのだろう。それはつまり、身体を乗り物としてとらえる、どちらかといえば西洋的な、合理的な発想なのである。武蔵からすれば、その肉体は車みたいなものである。整備次第で調子が悪いということはあっても、闘争という面でいえば、その車はけっきょく動くのかぴくりとも動かないのか、ふたつの状態でしかありえない。脳震盪を起こせば、長時間立っていることはできないし、吐き気もあるだろうし、精密な動きもできないだろう。しかし動く。である以上、脳震盪である状態とそうでない状態には、そうたいしたちがいはないのである。
 | 刃牙道(14)(オリジナルアニメDVD付限定版)(マルチメディア扱い) 4,190円 Amazon |
 | 刃牙道 13 (少年チャンピオン・コミックス) 463円 Amazon |
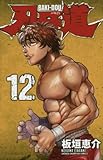 | 刃牙道 12 (少年チャンピオン・コミックス) 463円 Amazon |