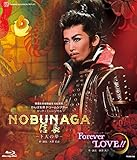 | 月組宝塚大劇場公演 ロック・ミュージカル『NOBUNAGA<信長>―下天の夢―』/シャイニング... 10,800円 Amazon |
簡易生命保険誕生100周年 かんぽ生命 ドリームシアター
ロック・ミュージカル 『NOBUNAGA<信長> -下天の夢-』
作・演出/大野 拓史
簡易生命保険誕生100周年 かんぽ生命 ドリームシアター
シャイニング・ショー 『Forever LOVE!!』
作・演出/藤井 大介
月組東京公演『NOBUNAGA<信長>―下天の夢―/Forever LOVE!!』観劇。9月2日13時半開演。
月組トップスター、龍真咲の退団公演である。
おもえば龍真咲は現トップのなかでもっともちゃんと追ってきたひとだった。といっても、下級生のころから見ていたというわけではない。僕は小さいころから宝塚を観てきてはいたが、ところどころ空白期間があって、いまのように相方といっしょになってしっかり見るようになったのは2011年の花組ファントムからである。当時月組のトップは霧矢さんで、このひとのことはむかしから知っていたし、僕は月組育ちなので、そのときの「アルジェの男」以来、月組の本公演はひとつも欠かさず、少なくとも1回は見るようにしてきたのだった(宝塚では複数回見るのがごく当たり前なので、こんなのは見ているうちに入らない可能性もあるが)。
穴だらけではあったが、それ以前も瀬奈じゅん時代の月組もぽつぽつ見ていて、まああんな見た目なので、明日海りおのことは認識していた。青樹泉とか星条海斗のことも知っていたとおもう。しかし龍真咲のことは知らなかった。瀬奈トートの月組エリザベートも見ているのだが、このときルキーニをやっていたのが龍真咲だった。しかしこれも記憶にない。要は、僕のなかで龍真咲は、「アルジェの男」で「よ~ぅ、ジュリアン」という非常に特徴的な台詞回しとともに、“いきなり”2番手として認識されたひとだったのである。
当時の印象だが、正直にいうとあまりよいものではなかった。僕には嫌いなものというのがないので、それが嫌だということではなかったのだが、トップになると決まっても大丈夫なのかという心配ばかりだったし、じっさいトップになってからも、そして明日海りおが異動し、次々と有力な組子が退団していくにつれて、ほんとうに月組はこの先大丈夫なのだろうかと、よけいな心配をしていた。「アルジェの男」の時点では、いまおもうとまだ未完成で、その後の2番手最後の作品「エドワード8世」でようやく指先まで行き届いた男役に変化し始めた、という印象であった。その意味では、(僕的には)不安なぶぶんを残しながらトップになり、みずからのすべきことが極まって、完成するのを見届けることのできた、これまでの人生であまり経験したことのなかったトップだったのである。蘭寿とむのファントムはお披露目公演だったし、あとはたとえば壮さんとかも追ってはいたけど、このひとたちはもうトップになる前にほぼ完成していたというところがあって、そういう感じではなかったのだ。
龍真咲は独特なセリフ表現のひとで、ここが特に好みの分かれるところだったとおもう。芝居なんだから当たり前といえばそうだが、非常に芝居がかったセリフまわしで、いちいちおおげさで、うたも、歌唱力はあるのだけど、メロディの導入部分に、なんというのか、ピアノでいう装飾音みたいなものがたくさん施されていて、まあなにをやらせてもふつうじゃない。立ち居振る舞いもナルシスティックで唯我独尊というもので、古風ないいかたをすればまさしく「わが道を行く」というタイプのひとであった。ここ1年くらいかな、じぶんでもそういうことを自覚しているというメッセージなのか、たとえばこう、娘役が作品についてインタビューするみたいな企画で、大物アーティストが気取ってはなしをはじめる、みたいな設定であえておおげさに、ナルシスティックにふるまう、ということをやっていて、ああ、このひとは、場合によっては否定的になりうるこうした要素を、肯定的に、じぶんの味として取り入れているのだなと、深く納得したものである。あの「芝居がかった芝居」にかんして、僕はセリフがうたの延長なのだ、という仮説を立てた。ミュージカルというのは慣れないと意味のわからない形態で、ふつうにしゃべっていた登場人物たちが、感極まっていきなりうたいだしたりするわけだが、龍真咲においてはおそらく、それまでふつうにしゃべっていたものの感情がたかぶり、そこに節がついて、音楽が鳴り出してうたになる、というものではなく、ある意味では、その「ふつうのしゃべり」の時点で、すでにうたなのである。ただ、はっきりとした抑揚やリズム、バックのオーケストラがないというだけで、あれはうたっているのだと。
今回の芝居は織田信長役ということで、これら龍真咲を特徴づけているすべての要素が極まり、このひとの目指していたことがついに完成したのではないかと、僕には感じられた。織田信長というのはまあ、非常に有名な人物なわけだが、ひとによってどういう像を思い浮かべるかというと、たぶんばらばらだろう。しかしおそらく、そのどれにも通奏しているものはあるはずだ。僕が織田信長というときは、ゲームの戦国無双の信長である(ポスターにもなっている、最後に信長がきている魔王チックな衣装は、無双のものとよく似ているのだが、これは史実として信長が着ていたものをモデルにしているのだろうか)。魔王らしくみずからのわがままを最後まで押し通し、かんたんに人を殺し、常人には理解できないタイミングで爆笑し、「是非もなし」とか「で、あるか」とか、ひどいときには「ぞ」とか、短く、意味の読み取れないことばで配下に語りかけ、いつの間にかいなくなっている、そういう、かかわりたくないタイプの不思議ちゃんである。宝塚では、武田信玄とのたたかいにいまから向かおうというあのタイミングでの急展開があるせいか、かなりはなしのわかる人物に修正されているが、基本的には、なにを考えているかわからず、秀吉や家康のような武将さえもしたがえてしまうカリスマで、ときどき発せられることばもほとんど暗号であると、そのような人物だと僕は認識してきた。そしてこの宝塚というメディアを信長というイメージが通過して出てきたものが、もういまとなっては、龍真咲が達成しようとしてきたことそのものに見えてしまうのである。芝居がかった言葉、ときどきうた本体と区別がつかなくなるほど抑揚のきいたメッセージ、唯我独尊、ナルシシズム、しかしその本音を語ることはなく、ただそのことによって生じる結果のみを存在の足跡として認めていく・・・。織田信長を宝塚でやるなら龍真咲しかいない、のではなく、龍真咲の方向性が極まった先には織田信長しかないと、そこまでおもわせるほどぴったりなのだ。
朝美絢演じる妻木という女を信長が殺してしまったとき、理由を問う兄の光秀らに対して、信長はなにも語らない。珠城りょうの魔術に操られていた彼女を信長は殺したわけだが、その説明をしない。説明をすればもしかしたら誤解も解けて、あの謀反もなかったかもしれないところ、信長は、説明して納得させられるようなものではない、「殺めた命に言い訳は出来ない」と応える。これが、本作における信長のすべてである。妻の濃姫・帰蝶に薙刀を向けられ、これでおしまいにしようといわれて、信長は応える。
「こればかりは頷く訳には参らぬ。
これまでにわしが討ち、滅ぼしてきた者共を、他の者に背負わせる訳には参らぬ」
これは、トップスターが抱えている責任とほぼ同等と見ていい覚悟である。いまトップの立っている位置のしたには、幾人もの「それをあきらめていったひとたち」が埋もれている。学校というシステムで、ファンに温かく見守られながら、その実、トップになるということはあらゆる意味で競争を勝ち抜くということであり、誰かがトップになるということは、誰かがなれなかったということなのだ。そして、トップであるということは、トップになれなかったものたちの“かわり”に、そのポジションを死守するということにほかならない。僕にこれを教えてくれたのは、ほかならぬ観劇体験であった。お芝居というのは生ものであり、録りなおしもやりなおしもない。その日の気候、役者の体調、観客の質、日程のタイミング、昨日の酒、プライベートでの揉め事、そうした無数の要素がからまって完成する一回性の芸術である。その日に上演されたものと同じものは、もう二度と再現されることはない。聞くところによると劇団四季などは、その再現にこそこだわり、日によって提供するものが異なることがないよう、社をあげて注意しているようだが、宝塚はその真逆で、初日は初日の緊張感を、また千秋楽は千秋楽の手遊び感を、それぞれに味わうこともできるようになっている。宝塚ではむしろ日によって異なることが推奨されているのである。加えて、座席である。その距離、その角度は、ほかのどの座席とも交換のできない、一回的なものである。前方4列以内であれば視線が飛んでくるし、うしろはうしろで、緊張感なく舞台全体を見渡すことができる。座席の価値はひとつひとつ異なっている。そして、とりわけ人気公演のときなどに強く感じることだが、その席は、僕ではなく、ほかの誰かが座っていたかもしれない席なのである。この、見逃すことのできない一回的な芝居を、交換不可能なこの一回的な位置で見ていたのは、僕ではなかったのかもしれない。つまり、僕はその「誰か」のかわりに、そのとりかえることのできない体験をしている。そんな貴重なものを、てきとうに過ごすことなどできない。だから、全身を目に、耳にして、わたしたちは舞台のすべてを見ようと努めるのである。
そして、なにかおこがましいはなしだが、この感覚はスターさんのポジションにかんしてもあてはまるのではないかと考えたのである。特に宝塚では、新組でも設置されない限り、基本的にトップは先代トップから組を継ぐかたちになる。文字通り、退団した先代の“かわり”として、次期トップは就任する。そうしたなかで、トップがオリジナルティを発見するのは、それが「じぶんでなければならなかった理由」を見出したときである。先代トップと、そこに立てなかったものたちの“かわり”に、トップスターは彼女たちの魂を背負ってセンターに立つ。それが肯定されるのは、そのひとたちの魂を背負うのはほかならぬじぶんでなければならないと確信できたときなのである。
本作では光秀を凪七瑠海が、秀吉を美弥るりかが担当している。信長の生涯を描くとなるとやはり山場は本能寺の変で、光秀をどのように描くかがかなり重要になってくる。僕は当初、なぜ光秀を珠城りょうにやらせて、ふたりの関係性で描いていかなかったのかなと考えたのだが、たぶん、複雑な事情があるのだろうと思いなおした。まず、そういうはなしにすると、おそらく観客は光秀に感情移入してしまう。光秀が主人公になってしまうのだ。そうすると、自然に光秀の出番は抑えられることになるが、信長のカリスマを際立たせるひとつの要素として、その配下のそうそうたる面々である。秀吉や家康のようなビッグネームですらが、表面上は信長に屈服していたわけである。そして歴史的にはそのことじたいが、信長の強大さを際立たせる。本作では秀吉が後半そのようなことを述べるが、たぶん秀吉は、あのような衝動的なものではなく、もっとずっとずるく、長期的な目線で、野心を抱えていたはずである。そのあたりも、おそらくあえて描かれていない。それというのは宝塚の人事的な事情で、いまのところ3番手以下がくっきりしてはいないので、ああいうことになったのではないかと考えられる。
信長でもそうだったが、ショーの「Foever LOVE!!」は、より龍真咲が演じることが前提となった再演不可能なものになっている。よくもわるくも、最近は特に退団公演はこういうのが流行ってるよね。冒頭のうたでは、地声と男役の声を使い分け、ほとんど、タカラジェンヌ・龍真咲じしんの感想であるかのように、ステージに立つということへの喜びがうたわれている。藤井先生はいつものことだが非常に凝った演出で、サビのぶぶんのシンプルな歌詞も心地よく耳に残る。むかしなにかのショーで、銀橋に元気よく登場した緒月遠麻が、うたうのかとおもいきや、そのまま元気よく銀橋を駆け抜け、奇声をあげながら去っていく、という衝撃的な場面があったが、ああいう感じで、龍真咲は、元気いっぱいに、退団するということをあまり感じさせず、すごいスピードで向こうにいってしまうのではないかと考えていたが、じっさいそのぶぶんはあった。龍真咲じしん、そういう退団のしかたをしようとしているのではないかとも感じた。しかしそのことじたいがまた、さびしい。退団の気配を少しも感じさせず、いつも通りの芝居がかった芝居で、ショーでふざけていることが、よりいっそうさびしさを増すのである。霧矢さんが退団したときも、蘭寿さんが退団したときも、それは悲しかったけど、この種類の喪失感は僕にははじめての経験だった。なんだろう、お金のない子供時代、仲のいい友達が、遠くの土地に引っ越してしまうような・・・。泣くというより、ただたださびしいのだ。
4日が千秋楽ですか。最後までケガのないよう、無事に退団を迎えることができますように。
時に「うつけ者」と、時に「魔王」と呼ばれながらも、己を貫き通し、幻の如く儚い「下天(人の世)」にあって、確かな生き様を示した織田信長の生涯を、信長に夢を抱き、愛し、戦った同時代の群像と共に描く、ロック・ミュージカル。
龍真咲演じる織田信長が、戦国乱世の下天を華々しく駆け抜け、そして、飛翔する。