今年はモーリス・ブランショの『明かしえぬ共同体』からはじまり内田樹の『レヴィナスと愛の現象学』まで、ぜんぶで40冊の本を読んだ。
内訳は、すっぴんマスターの分類規則にしたがえば(あまり厳密なものではない)、日本文学6冊、海外文学4冊、文芸批評7冊、哲学・思想系6冊、言語系1冊、ふだん雑多に投げ込んでいる「文化」というジャンルが、珍しく少なく1冊、講演1冊、随筆・紀行文4冊、説話関連1冊、教育1冊、理工系2冊、英文1冊、児童書1冊、音楽4冊。情けなくなる数字だが、まあ、幅広さでいえばここ数年なかった程度かもしれない。カテゴリも新しく増設した。去年が24冊ということで、今年は秋ごろに集中して論文を書いていたことも考えれば、とりあえず昨年対比としてはこれでじゅうぶんかもしれない。重要なのは量じゃない!と言い聞かせる。この質を維持、あるいは超えつつ、ブログも筋トレも同程度に継続し、たまに別の文章も書いたりして、なおかつ年100冊もいくくらいなら満足できるだろうか・・・。まあ、しっかり読んでいる自負はあるので、じっさい量なんてどうでもいいんだけど、でもやっぱり60冊はいきたい・・・。
2011年のはじめにたてた目標、というか読書計画としては、僕ではバタイユが圧倒的な壁としてあって、関連してモーリス・ブランショもそこに加わってきていた。そこで、これを乗り越えるためにとりあえずニーチェの名だたるところを読み、ブランショを読み、バタイユに戻ってこようと考えたのだけど、現実的にはニーチェを1冊読んだきりで、そこから一歩もすすむことはできなかった・・・。けっきょくそれを言い訳にしてしまうのはなんだかくやしいが、このことに関しては夏から秋にかけてまとまった文章を書いていたことが大きかった。バタイユもからませることができたらよかったのだけど、ちょっと、それはできなかったのだった。じっさい、8、9、10月はほとんど書評を書いていない。
リストを眺めつつ、印象に残っているもの、オススメ本はなにかなと考えると、小説では岡本かの子『老妓抄』、高橋源一郎『恋する原発』、ホフマン『黄金の壺』、チェーホフ『馬のような名字』、講談社文芸文庫『第三の新人名作選』、そのほかではやはりニーチェ『道徳の系譜学』、それに小田嶋隆『地雷を踏む勇気』、浦雅春『チェーホフ』、内田樹『レヴィナスと愛の現象学』あたりかとおもう。「この1冊」を選ぶことは難しいが、個人的には、いろいろなことのきっかけとなった『馬のような名字』になるだろうか。浦雅春の翻訳もすばらしい。導入的に、これからチェーホフを読もうというひとにもよいかもしれない。
- 馬のような名字 チェーホフ傑作選 (河出文庫)/アントン・チェーホフ
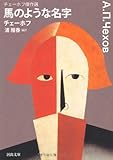
- ¥798
- Amazon.co.jp
- 恋する原発/高橋 源一郎
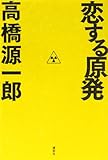
- ¥1,680
- Amazon.co.jp
- 地雷を踏む勇気 ~人生のとるにたらない警句 (生きる技術!叢書)/小田嶋 隆

- ¥1,554
- Amazon.co.jp
- 道徳の系譜学 (光文社古典新訳文庫)/フリードリヒ ニーチェ

- ¥780
- Amazon.co.jp
とりあえずの来年の読書目標としては、積んである本がいくらなんでも積みすぎというほどの量になっているので(たぶん50冊くらいある)、それを消化しつつ、引き続きニーチェ‐バタイユ‐ブランショのラインを見つめていきたい。もちろん、ニーチェやバタイユに加え、バルトやレヴィ=ストロース、中沢新一や加藤典洋など、集中してまともに読んでも時間がかかる系のものが大半なので、要するにまずすべきことは、衝動買いをもう少しおさえようかなというおはなしである・・・。目的を定めない衝動買いは知性を賦活するけれど、これでは現実的なぶぶんがもたない・・・。
- 老妓抄 (新潮文庫)/岡本 かの子
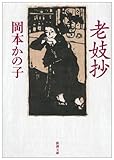
- ¥460
- Amazon.co.jp