From:ななころ
プライベートオフィスより
◆『人を動かす』を7回を読むプロジェクト
日本を代表する商売人が、
「この本は良い!」
「私の本を読むぐらいならこの本を読め!」
「7回は読みなさい!」
というほどの名著。
「人を動かす」(デール・カーネギー)
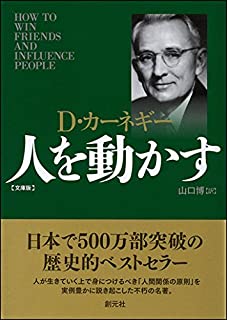
しかし、簡単なようでいて難しい。
なかなか7回も読むことができない。
さらに言うと、1回すらちゃんと読むことができない。。。
ということで、1話づつクイズ形式にしてブログでシェアすれば、ななころが本の内容を理解しながら読み進められるのではないか!?
ついでに、ブログの読者のために役立つのではないか!?
と思い立って始めたプロジェクト。
「『人を動かす』を7回を読むプロジェクト」
「不動産投資のブログなんだから、不動産投資に関して発信してよ」と文句が出そうな企画(笑)。
自己啓発系に興味の無い方や毛嫌いしている人は、どうか読み飛ばしてしまってください。
(毎週1回だけの配信の予定です。)
とはいえ、人生をより良く描くには人間関係を良好に保つことが不可欠。
「人の動かす」の原文タイトルは、
「How to win friensd and infulence people」
(友を得て人々に影響を与える方法)
ブログ読者様と一緒に「人を動かす」を読み進めながら、良好な人間関係を築いていきたいと考えている次第です。
【第一話】日本一の商売人が「7回読め!」と言った本とは?
【第二話】アメリカの最も偉大な大統領リンカーンが、良好な人間関係を保つために大切にしていた言葉は?
【第三話】人を動かすためのたった1つの秘訣とは ?
【第四話】「人の立場に身を置く」とはどういうことなのか?
【第五話】数年間ずっと断られ続けてきた営業マンが、相手の方から「買うよ」と言われるようになった秘訣とは?
【第六話】人生を強力に変える「◯◯」の効果とは?
【第七話】少年時代の成功体験にもととなる、鉄鋼王アンドリュー・カーネギーの成功の秘訣は何か?
【第八話】歴史的なアメリカ女性誌を作り上げた人物が、少年時代にアメリカ中の成功者とつながった秘訣とは?
【第九話】史上最年少42歳でアメリカ大統領になったルーズベルトが考えていた「人の心をとらえる近道」とは?
【第十話】人間関係の重要な法則「相手に重要感を持たせる」その具体的な方法は?
【第十一話】相手と議論になった時、この世にただ1つ最善の解決策とは?
【第十二話】相手が明らかに間違っている時でも、意固地にさせず、誤りを認めさせて、納得してもらうには?
【第十三話】自分の非がある時、相手がすんなり許してくれるためには?
【第十四話】ことわざ「1ガロンの○○よりも、一滴の△△△△の方が、多くの□□が取れる」
【第十五話】建設的な議論をしたい場合、絶対にやってはいけないこと、やるべきこと
【第十六話】話しをまるで聞かない反抗期の娘の心を開いた母親の態度とは?
【第十七話】人が自ら進んで動くようになるには?
【第十八話】相手と意見・主張が異なる時、非難することではなく、まずは◯◯する
【第十九話】相手の敵意を好意に変えるためには?
【第二十話】成功している人ほどお金では動かない理由
【第二十一話】人を動かすには事実を伝えるだけでは足りない。◯◯が必要!
【第二十二話】鉄鋼王カーネギーが重宝した人物の優れた業績アップの方法
【第二十三話】相手を納得させるのは、過失を責めるのではなく、まず相手を○○る。
【第二十四話】対立を生まずに、相手を注意するには?
【第二十五話】相手を不愉快にさせずに注意するには?
【第二十六話】反感を生まずに人を動かすには「命令せず、○○を求める」
【第二十七話】相手の○を立てるだけで、伝わり方がまるで変わる!
【第二十八話】人を動かすどころか、人生を大きく動かすほどの威力のある「○める力」
【第二十九話】最近能率の落ちてきた従業員にかける言葉は?
◆カーネギーからのクイズ #029
幼い頃、自動車事故で頭に大怪我を負った青年がいた。
額にはひどい傷跡が残っている。
友達には”フランケンシュタイン”と馬鹿にされ、知恵遅れと冷やかされた。
特別学級に入れられ、同じ年齢の子供よりも遅れて勉強をさせられた。
掛け算の九九も覚えておらず、足し算には指を使い、字もろくに読めなかった。
本人も自信を無くし、生きる希望も見いだせなくなっていった。
そんな彼が、ある時からその後の人生が大きく変わる。
突如として、物事を覚えることも、やり遂げることもできる自信が生じたのである。
その結果、高校生までずっと優秀な成績を納め続けた。
高校ではアメリカの全国優等生協会のメンバーにも選出された。
それは、どんなことがきっかけだったのだろうか?
あなたが彼の親だったら、どうやって彼が人生を切り開くきっかけを見つけるサポートをしてあげるだろうか?
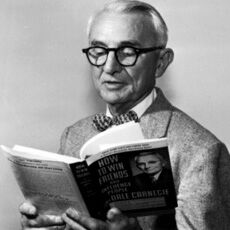
◆答え
彼は自動車事故をきっかけに、人生のすべてを失った。
自信を失くし、未来への希望も失くしていた。。。
ただ、彼には1つ、長所があった。
ラジオやテレビをいじるのが大好きで、テレビ技師になりたがっていた。
そんな彼の様子を見て、父親は彼を励ました。
ただただ励ました。
テレビ技師になるには数学が必要だと話し、数学の勉強をサポートした。
簡単なところからとにかく激励。
夫婦でひたすら鼓舞して、勉強の面白さを伝えていった。
すると、彼の数学の成績が飛躍的に伸びた。
本人がびっくりするほど成績が上がった。
それ以外にもいろいろな変化が次々と彼に起こった。
読み方も急速に進歩し、絵の才能も発揮しはじめた。
その結果、高校生までずっと優秀な成績を納め続けた。
高校ではアメリカの全国優等生協会のメンバーにも選出されたのだ。
親の惜しみない激励によって、自信が芽生え、能力が開花したのだ。
人を変える原則⑧「激励して、能力に自信を持たせる」

◆ななころの体験談と実践
前回にも触れたかなと思うのですが、ななころは褒められると伸びるタイプです。
たぶんほとんどの人がそうなんじゃないかと思うのです。
怒られて、けなされて、心が折れずに頑張れる人はわずかなんじゃないかと。
しかし、これまでの昭和の教育といったらいいでしょうか。
ほとんどが叱る、怒るの教育だったと思います。
ななころも少なからず挫折を繰り返してきました。
だからこそ、自分の子供や受講生には、絶対に褒めて伸ばすということを心に誓っています。
本人のために指摘してあげることはあっても、人間性を否定するようなことは絶対に言わないと、心に決めています。
そのお陰か、次男はのびのびと育ち、小学一年生にしていかんなく能力を開花させています。
ところが、ななころも親として若かったからでしょうか。
長男には、幼いころに少し厳しく接してしまったところがありました。
ななころ自身が経験したことを、長男にもしてしまったのです。
そのため、今でも引っ込み思案なところがあり、自信が無いところもあります。
この「人を動かす」の本に書かれている内容を活かしながら、未だに試行錯誤している次第です。
◆編集後記
ななころは小学生のコーチをやっています。
そこで心がけているのが、この章の言葉です。
「激励して、能力に自信を持たせる」
しかし、今でもとても悔いに残っていることがあります。。。
シュート練習をしていた時のことです。
コーチの私がパスをして、ゴールにシュートするという、練習はとてもシンプルなものでした。
ほとんどの子どもたちが、次々にゴールしていきます。
ところが、一人の男の子だけ、どうしてもゴールできません。
小学校三年生の男の子です。
まわりの子たちが茶化します。
最初は楽しみながらやっていたのですが、だんだんと表情が暗くなっていきます。
そのうち自信を失くして泣き出してしまったのです。
ななころは必死に鼓舞して、自信をもたせるようにしていたのですが、逆効果。
途中で練習を止めて、家に帰ってしまったのです。。。
その後、二度と練習には顔を出さなくなってしまいました。
この時はどうしたら良かったのだろうか・・・
どんな風に彼を応援してあげれば良かったのだろう・・・
なんと声をかけてあげればよかったのだろう・・・
今でも心残りです。
(この番組に出ている大人のように、ちゃんと伝えられる大人になりたいです。※英語が分からなくもて、日本語字幕で結構理解できます。)