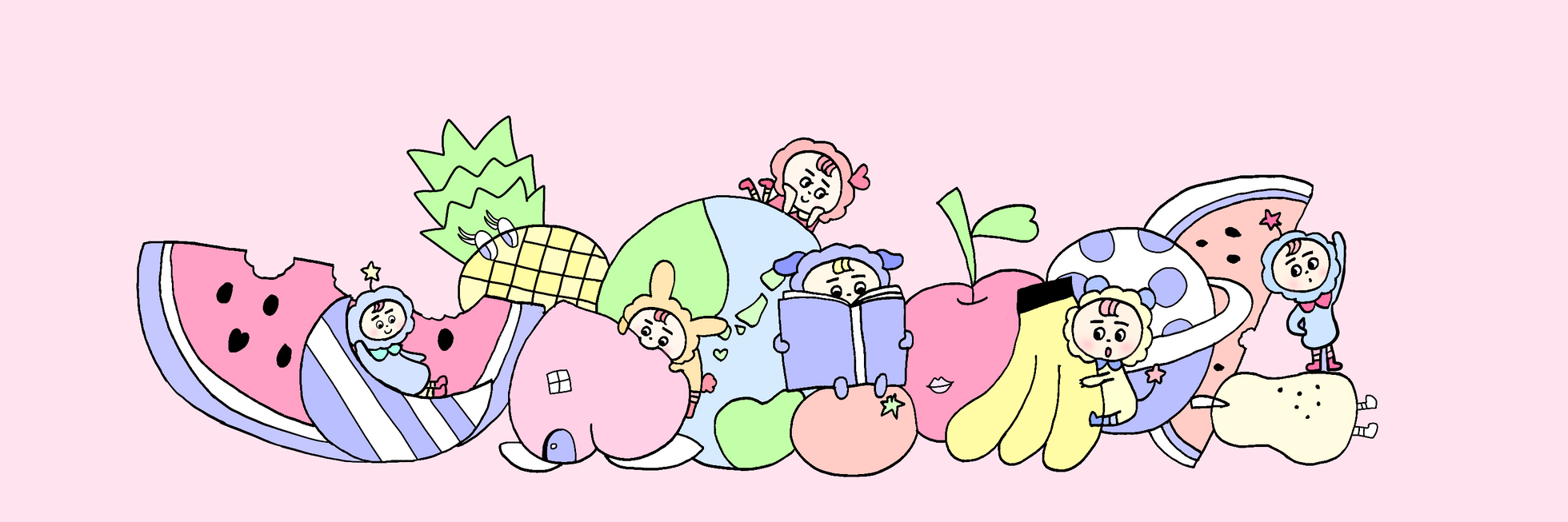内田栄一について
なんかの対談で時代とエッチしまくってきたと話していたことがある。
うまいこと言うなぁと感心してしもた。
内田栄一は何かに囲い込まれることを極端に嫌い、時代の空気を鋭く読んで生きていくという生き方がダサかっこいい。
わけがわからない時代に、わけが分らないことを徹底して行っている人が何よりも好きだと語っていたが、本人自体がその究極系だと思う。
大好きです、こういうおっさん。
この人物紹介が素晴らしい。
日本のアンダーグラウンド・シーンに絶大な影響力を持ち、そのアナーキーな活動でさまざまなトラブルと新しいジャンルを開拓し、1994年に肺がんで亡くなるまで、東京を縦横無尽に駆け抜けた男、内田栄一。
彼は1930年、岡山市の古書店の息子として生まれた。太平洋戦争の終結後、上京して文学を志し、前衛文学に傾倒。安部公房の進めもあって文筆家として立ち上がる。また編集者として埴谷雄高らと交流を持つ。
1960年代に入り、テレビの時代になると、いち早くテレビ脚本の仕事をこなし、和田勉監督作『悪い奴』では国会議事堂を爆破しようとするテロリストの姿を描き物議をかもし出す。その後も『七人の刑事』など、社会からドロップアウトした人間を描き続ける。
同時期、盛り上がったアンダーグラウンド演劇シーンにも身を投じ、瓜生良介らと「発見の会」で『ゴキブリの作りかた』などの過激な芝居の台本を発表。その後も戸羽山文明や金子正次といった若い才能と次々と組み、東京アンダーグラウンド・シーンの中心人物となる。
また70年代より映画界でもシナリオ・ライターとして活躍。『妹』はじめとする日活フォーク路線で、当時のフーテン青春風俗を生々しく描き出し、圧倒的な支持を得る。その後も角川映画『スローなブギにしてくれ』では、凡庸な青春小説だった原作を、脇役の中年男の視点から再構成し、「原作キラー」の称号を得る。
映画と関わることから、80年代初頭に盛り上がりを見せた8ミリ・インディーズ映画にも視線を向け、山本政志、石井聰互、松井良彦といった新鋭作家たちとマブダチ関係を結ぶ。ベテランであることを偉ぶらず、常にニューウェーブと併走する内田は、90年代に入り、還暦を迎えると自ら8ミリ・カメラを手に取り、初監督作『きらい・じゃないよ』を発表。翌年には続編を製作、まだまだ現役で突っ走るつもりだったが、94年、病に倒れ、この世とオサラバした。享年64歳。好きなタバコの銘柄はハイライト、映画・演劇人には珍しく酒は飲まずにコカ・コーラを愛飲し、タケオ・キクチとリーバイス501を愛着。乗り物なら自転車、特技はナンパ。
アングラ戯曲「ゴキブリの作り方」で有名な人だが、上記のように、そもそもは岡山市の古書店の息子だそうだ。
雑誌「綜合文化」を通じて知り合った安倍公房と連絡を密にして、彼の勧めで上京。
鎌倉アカデミアに入学。先輩に鈴木清順、前田武彦、山口瞳がいたという。

鎌倉アカデミアは、第二次世界大戦終結直後に、鎌倉在住の画家や演劇家らが設立した「鎌倉文化会」が、「自分の頭で考える人間づくりが必要」の趣旨で母体となり、地元町会長らの協力を得て、材木座・光明寺を仮の校舎として開講し、のちに横浜市栄区小菅ヶ谷の旧第1海軍燃料廠第3試験所跡へ移転した、高等教育のための私立学校、すなわち専門学校だ。
大船駅が最寄り駅であり、通称「大船」校舎。
当初は大学設立を目指し「鎌倉大学校」と称したものの、資産や運営資金の不足から「鎌倉アカデミア」という専門学校としてのみ申請受理されたという。
財政難のため1950年(昭和25年)9月、わずか4年半で廃校。
しかしながら映画・演劇界などに多くの人材を輩出した伝説の専門学校でもある。
そう、鎌倉アカデミアは何と内田入学の年1950年に閉校、彼はやむなく東洋大学に入学しようとする。
しかし学生部長は海軍兵ノリの坊主頭で、庭には「八紘一宇」なんていう碑が立っていたりして「これはあかん」と入学を取りやめたそうだ。
その後は横須賀米軍基地で警備員アルバイト等をして、なんとかやりくりしていたという。
で、『記録芸術の会』にも関係し、新日本文学会に入会している。
安倍公房を通じて色々な文化人との交流を持ツことに成功。
一番大きかったのは、当時安倍公房はテレビの台本を手掛けていたことであろうか。
内田が下書き、安部が仕上げという形でテレビ台本を次々に手掛け、こうやって内田はテレビ業界へとまんまと進出。
そして和田勉と知り合うに至る。
この後ノリに乗った内田は次々と問題台本を手掛ける。
タブーに挑みかかるようにだ。
もともとの反体制過激的気質がうなりを上げ始めたのだろうか。
1960年に、テロリストが国会議事堂に侵入して屋根裏に爆弾を仕掛けるという問題ドラマ「悪い奴」を発表。
これが放送中止の憂き目を受け、以降テレビの仕事がじり貧に。
時は安保の時代、ご法度だったのだ。
この後は安倍公房、花田清輝に無理やり新進劇作家としてデビューさせられ「表具師幸吉」を発表。
時代劇台本も手掛けるという何ともなマルチぶり。
そもそもが器用な人で、安部らは内田のその才覚を敏感にかぎ取っていたのであろう。
代表作「ゴキブリの作り方」は、フォンタナの「赤い画布に三つ裂け目が入った作品」を見たときにひらめいたという。いわゆるルーチョ・フォンタナの「切り裂かれたキャンバス」、すなわち「空間概念・期待:Concetto spaziale・Attesa&Attese」のことであろう。
フォンタナは
「時代と共に人々の生活が変わっても、依然として絵画や彫刻といった芸術の手法や枠組みは変わらない・・・印象派や野獣派、キュービズムに抽象画など、モチーフやマチエールが変わっただけで現代空間の様式の中で画家が描いた「美しい」は成りたっているのだろうか?・・・」
そのことに強い疑問を抱き、1947年にミラノで空間主義(Spazialismo)を宣言した美術家・画家・彫刻家。
「空間概念・期待:Concetto spaziale・Attesa&Attese」は、一色で塗り込めたキャンバスを切り裂き、穴をあけ、従来の平面的な風景や人物の絵画や抽象絵画という枠組みを越え、凹凸のある「キャンバスレリーフ」と云える様な、従来の絵画常識を飛び越えた「キャンバス一体型造形作品?」だが、これはまさしく内田の思想的感性と著しく共鳴してはいまいか。
「ゴキブリの作り方」の話に戻ると、ゴキブリを作る研究者ゴキブリ博士が人間型ロボットを作るが失敗、その失敗作「美女」を研究室に放置するところから物語が展開してゆく。
博士は将来は人間に変わりゴキブリが天下を制すると信じてやまない。
米兵の鉄カブトにゴキブリの卵とゴマ粒を入れてそこにコカ・コーラをぶっかけて仕込むという方法を開発。
こうやって生まれたゴキブリが、古いポンコツ人間をスペックで上回った時点で古い人間どもを次々に廃止するようにしなさいと総理大臣に提言、記者会見するにいたるという。
しかしやがて「美女」が徐々に学習して自立してゆきゴキブリを次々に食い殺す。
ゴキブリは「内田にとっては相当に意味のあるシンボルであると見受けられよう。
「現状を全否定した、新しい生き方の提唱」「権力を破壊する庶民の力」の象徴として扱われているのだ。
内田にとってのゴキブリは、時代を表す、己の分身ともいえる最重要なアイコンと言えよう。
この頃、内田は「パンチジャーナル」というニッポン放送をキーとするラジオ番組も手掛けていた。
構成作家として参加する傍ら、時折ゲストとして討論にも参加していたそうだ。
そのあたりのことは「ティーチイン騒乱の青春」という本に詳しい。
1960年代後半、ニッポン放送にて毎週放送されたレギュラー番組『ザ・パンチ・ジャーナル』の、いわゆる討論会である「ティーチ・イン」の模様を活字化した貴重な1冊。
丸山明宏、ミッキー安川、青島幸男、野末陳平ら有名人がゲストに招かれ、当時の若ものたちに取材、討論を促します。パリの五月革命、新宿のアングラ劇場にたむろする若者たち、当時の恋愛観。カウンターカルチャーを当時の若もの目線から検証することのできる貴重な1冊編・著:内田栄一 / 出版社:三一書房 / 新書判 / 242P / ソフトカバー / 1969年発行 /
本当に器用な方である。
器用貧乏の権化だ。
そして70年代に入ると、プレイボーイ誌上で「日本共産党50年伝」という劇画の原作を担当。
これは反体制、反天皇制の立場に立ちつつ、日本共産党の歴史を反共産党的立場からまとめるというもので、日本共産党からの圧力がかかり、連載休止に追い込まれたという。
あさま山荘事件の約一年後のことで、この劇画で「党内粛清」の様子が生々しく紹介されていたりしたそうだ。
日本共産党の天皇に登り詰めたと内田が主張する宮本顕治を痛烈に批判もしている。
宮本顕示大嫌いだったのだろう。
全体的には新左翼的イメージ色が濃厚。
この後雑誌「プレイボーイ」はまっとうな政治的雑誌から様変わりしてエロ雑誌へと舵を切る。
最初はお堅くて武骨な雑誌だったことに驚きを隠せない。
このころは演出家、小説家としての顔もあったが、特筆すべき活動は、外波山文明、西田敬一らとクスボリ共同体を結成したことか。
演劇を通して共産党や体制、権力を否定、抵抗するという活動を展開。
クスボリとは「玄関で火鉢を起こしながら親分を待つ」という意味のいわゆるヤクザ言葉だ。
ちょうどこのころに、ある演劇集団に脚本を書いている。
題して「天皇のつくり方」。
これがまた、なんともパンチが利きすぎていて身もだえする。
四場構成のこのハレンチ劇は「人民に伝承すべき新しい民話としてこの話を借定するという、なんとも危なくて壮大な物語である。
内容は詳しくは書けませぬが、完結部では民衆が「天皇になろう国」を作り、千代田区一番地に大挙して押し寄せて、皇居を占領、「天皇象徴罪」を制定して縛り首にするという、なんともハナもミもある代わりにとんでもいくタブーに満ち満ち驚愕をはるかに超えまくっている、そんな新民話となっているという。
「藤田敏八との共同作業に見る内田栄一の演劇的実践」内で、日活ポルノ裁判傍聴記である「日活ポルノ裁判」、「権力はワイセツを嫉妬する―日活ポルノ裁判を裁く」の著者・日本の映画・演劇評論家である斎藤正治は
「粗暴のようで豊穣なる言語は、速射砲のように敵を撃ちながら、なお、素朴な感性と狂暴な生理がきらめいている」
と評していたりする。
ちなみによく似た名前の「齋藤 正治(さいとう しょうじ)」さんは山形県酒田市出身の画家である。
この後の内田栄一の活躍を端的に記すと、「痴漢と女子高生」でポルノ男優としてデビュー、「妹よ」「海燕ジョーの奇跡」、「スローなブギにしてくれ」などの映画脚本にも進出。
さらには還暦を迎えた90年代に入ると「きらい・じゃないよ」シリーズの映画監督も手がける。
金子正次とノンポリ劇団を主宰していたこともあるという。
佐木隆三の「復讐するは我にあり」の映画化に関するトラブルに内田が巻き込まれた件で、金子とともに「青年行動隊」を結成して、佐木に謝罪を求めたり、佐木の夫人の実家の石垣島迄追い込みをかけたりということもやっている。
ヤクザの親分と子分的な、金子正次との関係。
極めつけは、自身の主宰する劇団東京ザットマンで、「佐木隆三を個人攻撃する会」という芝居を1976年4月16、17日に天井桟敷地下劇場で開催する徹底ぶり。
容赦はしない内田氏。
ちなみに佐木と内田は新日本文学会の会員同士だった。
まあこのようになんとも多彩過ぎてわけがわからないおっさんのまんま天に召された天才、奇人、怪人?でしたが、何と言っても「探偵物語」での「欲望の迷路」「裏切りの遊戯」の脚本家としての仕事が一番好きかも。
「欲望の迷路」には「妹よ」が垣間見えるし、「裏切りの遊戯」には「海燕ジョーの奇跡」が透けていたりする。
もう会えない。
1994年、病死。
小田彩加さんの作品、なんか好き
マテウス・アサト、そう来るか!!
終了 ペルセウス座流星群 流星ライブカメラ@沖縄県南大東島