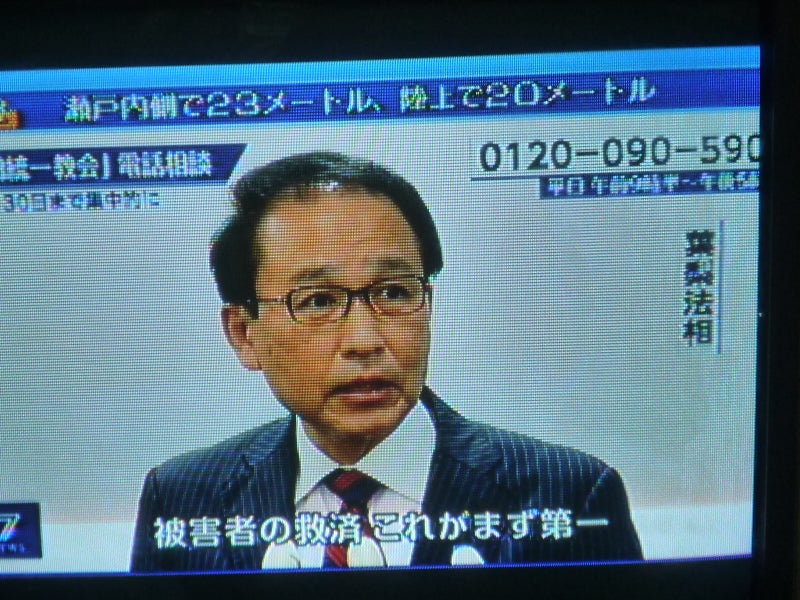日本女子大の「理系強化」 看板学部の再編は「筆舌に尽くしがたく大変だった」
AERA DIGITAL配信より
日本女子大の「理系強化」 看板学部の再編は「筆舌に尽くしがたく大変だった」(AERA DIGITAL) - Yahoo!ニュース
配信より
日本女子大学が2025年に新設した食科学部。家政学部から独立した。21年に全学部が都心の目白キャンパスに集まり、人気上昇中。23年には国際文化学部も新設(撮影/岡田晃奈)
募集停止や共学化が続く“女子大受難の時代”に、日本女子大はなぜ志願者数を伸ばしたのか。
飛躍の秘密は、学内のさまざまな思いを乗り越えて実現した、看板学部の再編だった。
* * *
女子大学の志願者数は軒並み減少しており、京都ノートルダム女子大学が募集停止を決め、
武庫川女子大学も共学化に踏み切る。
そのなかで、日本女子大学の総志願者数は、前年度から10%も増えて1万643人になった。
志願者数(一般選抜)は、全国の女子大で1位を誇る
(朝日新聞出版『大学ランキング2026』)。
女子大の淘汰が進む最大の要因は、18歳人口の減少だ。文部科学省によると、
1992年に205万人だった18歳人口は、2035年頃には100万人を切る見通しだ。
大学間の競争は激しさを増している。
「日本女子大学は歴史とブランドだけで学生が集まる時代がありました」
日本女子大学の篠原聡子学長は過去を振り返る。
高度経済成長による人口ボーナス期だった約30年前までは、
「名門女子大」のブランドが学生を引き寄せており、学部再編の動きは低調だった。
だが、いまは「選ばれる理由」が問われている。
■株分け戦略で改革が加速
そんななか、日本女子大学は大胆な一手に出た。看板学部であった家政学部の再編だ。
「筆舌に尽くしがたい大変さがありました。家政学部は伝統学部でしたから、再編には学内でもさまざまな思いがあったのです。しかし、家政学といえば『家庭の中の学問』という誤解を解かなければなりませんでした」(篠原学長)
家政学は本来、生活を科学的に捉える「実学」だ。多分野と結びついており、派生形として新学部を作りやすい。
「自分たちの強みは何か、社会から求められているものは何かを整理して、『強み』を押し出すことにしました。既存の学部から『株分け』して、カリキュラムや人事を補強して専門性を高めています」(同)
株分け戦略により、改革がここ5年で加速。
1992年に「家政学部家政理学科」が独立して「理学部」が生まれ、
情報科学やバイオテクノロジーが専門の教員を増やすなど、時代に合わせて強化。
実態に合わせて2022年に名称変更をした。
24年に「家政学部住居学科」が「建築デザイン学部」に独立。
27年には「家政経済学科」が「経済学部(仮称)」になる構想だ。
「理系シフト」に見えるかもしれないが、新分野を増やしたわけではない。全て既存の学部を磨いて誕生した。
今春、「家政学部食物学科」が独立して「食科学部」が開設。農学部という名称にすれば、幅広い受験者層を呼び込むことができると思いきや、アピールするのはそこではない。
6月、食科学部食科学科の実験の授業を訪ねた。白衣姿の学生たちが、試験管の中で起こる化学変化に目を凝らしていた。
この日のテーマは、体内で食品はどう分解されるのか。胃の消化酵素ペプシンが卵白をどう分解するのかなどを確かめるため、液体の色が変わるかどうかを観察していた。
食科学科1年生の鈴木汐織さんは「私にドンピシャの学科でした」と話す。
夜遅くに帰宅して疲れていても、簡単に食べられて栄養価のある食物って何だろう。
そう考えて、食品開発の道を志し、学部を探していた。
「実験、調理実習の機会がダントツで多い」と考えて入学を決めた。
「周りの学生も、やりたいことが明確な人が多いです。だからこそ、授業や実習にも積極的で、大学生活が楽しくなるんだと思います。私も『自分は自分』という気持ちで、のびのび学べています」(鈴木さん)
■学生のモチベーションが高い
ここで学びたい、という意志を持って入学してきた学生は、モチベーションが高い。そのために、特色を明確化していると篠原学長は言う。
「一般に食関係の学部といっても、農学系統からマーケティングまで幅広いですが、私たちの食科学部は『生活者』の視点から、『食』を科学的に深く読み解く学びが特徴ですが、家政学部の傘の中にあることで、文系の学びと誤解され、本来の学びの特徴が正確に伝わっていない側面がありました。今後ますます高度化した『科学的な観点』が求められていく中、生活者視点での『食』を科学的に広く深く読み解く学びにより一層の重点を置き、グローバルな『食』の課題に立ち向かい、未来の社会に貢献していく力を育てていきます」
「責任をもって学生を育てるためにも、どんな学びなのか、見える化することが重要。学部ごとの専門性を高めることで、幅広い教養と高度な専門性を身につけた人材を養成していきたいと思っています」(篠原学長)
教育ジャーナリストの石原賢一さんは言う。
「いまの女子大の姿は、10年後の共学大の姿です。共学大でも募集停止のニュースが出てくるようになるでしょう」
文科省によると、10年後の2035年から、18歳人口は急激に減少して、今年生まれた子どもが入学する頃には、現在から3割も少なくなる見通しだ。
「知名度があり安泰とされる大学も一部ありますが、これからは女子大も共学大も、工夫をしなければ淘汰される時代になります。その淘汰は、偏差値の順に起こるわけではないと思います」(石原さん)
有名大学でも、学びが時代遅れなら選ばれなくなる。
「就職市場がますます売り手市場になるなかで、就職率、満足度以外の特色を打ち出す必要があります。社会で通用する『実利』のある学び、学生の興味を引く『面白さ』がより重要になっていきます。ゲームやアニメ関連といった専門学校の発想を参考に、いままでの大学にない学問を作る発想も必要でしょう」(同)
何を学べるかを示せなければ選ばれない時代は、既に始まっている。
(AERA編集部 井上有紀子)
井上有紀子
3/3ページ
【関連記事】



令和4年6月10日、国際交流における 各国における、コロナウイルス感染症対策事業対策 対応があり、東京都 一般財団法人 製粉振興会 職員と私は、対談する。
令和4年6月9日、ドイツ総領事館 文化部 飛鳥井様のもとへ、私は、プラザ合意 、坂本龍馬 飛鳥井雅道 平凡社選書42、 1975年10月9日、初版発行 以来の 国際金融、プラザ合意、学習院、京都 飛鳥井家、土佐 山之内家、薩摩 島津家、長州 毛利家、肥前 鍋島家、等における その一連における対応が 私の元にあり、対談する。
令和4年6月9日、プラザ合意 、並び、 坂本龍馬 飛鳥井雅道 平凡社選書 42、 1975年10月9日、初版発行より、ドイツ総領事館 文化部 飛鳥井様のもとゑ、連絡を入れる。
◎坂本龍馬 (1975年) 飛鳥井 雅道/平凡社
◎坂本龍馬 (講談社学術文庫) 飛鳥井雅道/講談社
◎坂本龍馬―幕末の自由精神 (福武文庫) 飛鳥井 雅道/福武書店
◎1985年の無条件降伏~プラザ合意とバブル~ (光文社新書) 岡本 勉/光文社
◎プラザ合意の研究 近藤 健彦/東洋経済新報社
◎ドイツ金融資本と世界市場 (慶応義塾大学商学会 商学研究叢書) 赤川 元章/慶応通信
◎経済学とファイナンス 和美, 浅子,和人, 池尾,敬一, 大村,美矢子, 須田,俊作, 西川/東洋経済新報社
◎計量経済学のすすめ (1970年) (エコノミスト・シリーズ) 西川 俊作/毎日新聞社
◎「日本の麦政策 -その経緯と展開方向-」 折原直 著 農林統計協会(2000)
◎「小麦粉製品のフードシステム:川中からの接近」 斎藤修、木島実編 農林統計協会(2003)
◎数量経済史の原点―近代移行期の長州経済 (慶應義塾大学産業研究所選書) 西川 俊作/慶應義塾大学出版会
◎労働市場 (1980年) (日経文庫 経済学入門シリーズ) 西川 俊作/日本経済新聞社
同じ記事を見つけてみよう
#コロナウイルス感染症対策支援事業
#農業水利権の帰属について
#カナダ産小麦
#経済安全保障
#福沢諭吉の横顔
#慶應義塾大学統計学
#数量経済史の原点
#日本の麦政策
#プラザ合意
#小麦粉製品のフードシステム
令和7年7月5日、今まで、私は、歴代 山口市長 と面談し、日本女子大学 による 日本女子大学 学祖 成瀬仁蔵先生 輩出した 山口県 山口市に 学術対応をされてきている 東京都内だけにおける、山口市長に対する、その応接内容、応接対応に関しても、拝聴ができているため、日本女子大学 学長、教職員、事務員 との 島根県、津和野町、吉賀町、大学、学校、研究機関、図書館・文書館、資料館・美術館 との連携に関しても、それを願っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
成瀬仁蔵
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』配信より
なるせ じんぞう
成瀬 仁蔵
生誕 1858年8月24日
(安政5年6月23日)
周防国吉敷郡(現・山口県山口市)
死没 1919年3月4日(60歳没)
墓地 雑司が谷霊園
国籍 日本
出身校 アンドーバー神学校、クラーク大学
職業 教育者
著名な実績 日本女子大学校(現:日本女子大学)創設
宗教 キリスト教→帰一思想
テンプレートを表示
成瀬 仁蔵(なるせ じんぞう、安政5年6月23日〈1858年8月2日〉[1] - 大正8年〈1919年〉3月4日)は、日本の牧師・教育者。日本における女子高等教育の開拓者の1人である。族籍は山口県士族[1]。
生涯
出生から就職まで
周防国吉敷郡吉敷村(現在の山口県山口市吉敷赤田大形)に生まれる。成瀬小右衛門の長男[1]。成瀬家はもとは河崎姓で、仁蔵の父の代に成瀬姓を名乗る。父は長州藩毛利家の一門・吉敷毛利家に仕える下級武士。仁蔵の母・歌子は隣村の大歳村出身で、藩士である秦家の娘。
仁蔵は幼少時は郷校の憲章館に学び、維新後の1874年(明治7年)には調剤師として医家に住み込む。この年には父が死去し、山口の教員養成所(山口師範学校)の2期生となる。1876年(明治9年)に卒業し、小学校教員となる。
大阪時代
成瀬仁蔵と妻の満寿枝
1877年からアメリカに留学し、帰国後牧師になった同郷の沢山保羅の感化を受けて山口を離れ、1878年(明治11年)に大阪の浪花教会で入信する。組合教会の運動で同年に設立された梅花女学校で主任教師を務め、翌1879年(明治12年)には浪花教会に属し、旧福井藩士の娘で女学校生徒であった服部満寿枝と結婚。私財を投じて学校経営の維持を図るなど教職には熱心であったが、伝道活動への意思が強く、1882年(明治15年)に卒業生を送ると教職を辞し、牧師としての活動をはじめる。沢山保羅の浪花教会を拠点に、翌1883年(明治16年)には奈良県生駒郡郡山町(現大和郡山市)の出張伝道所へ移る。1884年(明治17年)には郡山教会の独立を許されてその初代牧師となり、布教活動をおこなう一方で女子教育を研究する。
現在の日本女子大学
新潟時代
このころ、キリスト教受容の壁が厚かった新潟ではT・P・パーム、押川方義らが教会を形成した。1883年にパームが帰国すると、O・ギューリック夫妻とR・H・デイヴィス夫妻らアメリカン・ボードのメンバーが伝道を引き継いだが、伝道活動が困難をきわめており、成瀬は組合から新潟での伝道を依頼される。成瀬はこれを拒むが、病床の沢山から赴任を懇願されると新潟へ移り、1886年(明治19年)には新潟第一基督教会(現・日本基督教団新潟教会)を設立。女子の就学状況が不振であった新潟で女学校の設立案が出されると成瀬はこれに参加し、翌1887年(明治20年)に私立新潟英学校を基礎に設立された新潟女学校の校長となる。同じく英学塾を基礎に設立された男子中等教育機関である北越学館にも関わり、教師として招かれた内村鑑三が生徒の支持を得て分離する動きを見せると、成瀬らは内村に反論し、解任を求めた。内村が去った後には旧知の松村介石や麻生正蔵らが招かれた。
→詳細は「北越学館事件」を参照
米国留学
1891年(明治24年)にはアメリカへ渡る。アンドーバー神学校で、キリスト教の社会的役割に強い関心を持っていた神学者ウイリアム・J・タッカー教授に師事して「新神学」の影響を受け、さらに1892年9月にはクラーク大学で心理学者スタンレー・ホールに師事して女子教育について学んだ。その後、各種社会施設も視察して1894年(明治27年)に帰国。
日本女子大学校設立へ
第5代梅花女学校校長を務め[2]、女子高等教育機関の設立に着手。成瀬はこの梅花女学校校長時代に日本初となる「球籠遊戯」(日本式バスケットボールの原型)をカリキュラムに採用、後に自らが創立した日本女子大学校でも「球籠遊戯」をカリキュラムに採用していることから、成瀬はバスケットボール紹介者のひとりと言われている[2][3]。
大阪市東区清水谷東之町(現天王寺区清水谷町[4])に校地を確保したが、その後、広岡浅子の働きかけで三井財閥から東京・目白の地(現在地)を寄贈され、1901年(明治34年)、日本女子大学校を創設した(設立発起人、創立委員に西園寺公望)。
1912年(明治45年)6月、渋沢栄一、森村市左衛門、姉崎正治らと共に帰一協会を設立する。これは、諸宗教・道徳などが、同一の目的に向かって相互理解と協力を推進することを期した会である。会員には、江原素六、島田三郎、新渡戸稲造、石橋智信、今岡信一良、高木八尺やM・C・ハリス、D・C・グリーン、C・マコウリー、W・アキスリングなどの宣教師たちも参加した[5]。
1919年3月4日、肝臓癌のため死去[6]。墓所は雑司ヶ谷霊園(1-17-6-1)
死後
生家跡は1934年(昭和9年)に山口在住の卒業生有志によって、成瀬公園として整備された。公園内に設置された記念碑は毛利本家第29代当主の毛利元昭(貴族院議員)の揮毫によるものである[7]。
栄典
1915年(大正4年)11月10日 - 勲五等瑞宝章[8]
1919年(大正8年)3月4日 - 従五位[9]
成瀬仁蔵のことば
「聴くことを多くし、語ることを少なくし、行うことに力を注ぐべし」
「信念徹底」
「自発創生」
「共同奉仕」
出版物
著作
『婦女子の職務』成瀬仁蔵、1881年12月。NDLJP:848226。
『婦女子の職務』(増補)成瀬仁蔵、1887年8月。NDLJP:758235。
A Modern Paul in Japan. Congregational Sunday-School and Publishing Society. (1893)
『女子教育』青木恒三郎、1896年2月。NDLJP:808868。
『講演集 第一』桜楓会出版部、1907年12月。NDLJP:809098。
『進歩と教育』実業之日本社、1911年11月。NDLJP:808926。
『新時代の教育』博文館、1914年2月。NDLJP:980189。
『新時代の教育』(再版)桜楓会出版部、1931年10月。
『教育と信念涵養』帰一協会事務所、1915年1月。
『新婦人訓』婦人文庫刊行会〈家庭文庫〉、1916年8月。NDLJP:953347。
『新婦人訓』(再版)桜楓会出版部、1925年4月。
上笙一郎、山崎朋子 編『新婦人訓』クレス出版〈家庭文庫〉、2006年7月。ISBN 9784877333263。
『世界統御の力』成瀬仁蔵、1917年10月。NDLJP:957731。
『女子教育改善意見』成瀬仁蔵、1918年9月。NDLJP:941389。
『女子教育改善意見』(再版)桜楓会出版部、1930年12月。
『軽井沢山上の生活 大正六年日本女子大学校夏期寮に於ける成瀬校長の山上十回講演』家庭週報編輯部、1923年7月。
『軽井沢山上の生活 大正六年日本女子大学校夏期寮に於ける成瀬校長の山上十回講演』日本女子大学教育文化振興桜楓会成瀬先生研究会、2002年3月。
『軽井沢山上の生活』日本女子大学通信教育部、1965年8月。
『成瀬仁蔵の社会的活動』日本女子大学女子教育研究所、1969年6月。
『女子教育 女子教育改善意見』日本図書センター〈近代日本女子教育文献集 第5巻〉、1983年11月。
『女子教育 女子教育改善意見』(新装版)日本図書センター〈近代日本女子教育文献集 第5巻〉、2002年6月。
『成瀬仁蔵研究文献目録』日本女子大学女子教育研究所成瀬記念館、1984年10月。
新井明 訳『沢山保羅 現代日本のポウロ』日本女子大学、2001年12月。
作品集
『成瀬先生講演集』
『成瀬先生講演集』 第1、桜楓会出版部〈桜楓文庫 5〉、1940年8月。NDLJP:1449922 NDLJP:1458196。
『成瀬先生講演集』 第2、桜楓会出版部〈桜楓文庫 6〉、1939年3月。NDLJP:1457905。
『成瀬先生講演集』 第2(再版)、桜楓会出版部〈桜楓文庫 6〉、1940年8月。NDLJP:1449927。
『成瀬先生講演集』 第3、桜楓会出版部〈桜楓文庫 7〉、1939年6月。
『成瀬先生講演集』 第3(再版)、桜楓会出版部〈桜楓文庫 7〉、1940年8月。NDLJP:1449936。
『成瀬先生講演集』 第4、桜楓会出版部〈桜楓文庫 8〉、1939年5月。NDLJP:1458166。
『成瀬先生講演集』 第4(再版)、桜楓会出版部〈桜楓文庫 8〉、1940年8月。NDLJP:1449944。
『成瀬先生講演集』 第5、桜楓会出版部〈桜楓文庫 9〉、1939年6月。NDLJP:1457904。
『成瀬先生講演集』 第5(再版)、桜楓会出版部〈桜楓文庫 9〉、1940年8月。NDLJP:1449948。
『成瀬先生講演集』 第6、桜楓会出版部〈桜楓文庫 10〉、1939年10月。NDLJP:1457962。
『成瀬先生講演集』 第6、桜楓会出版部〈桜楓文庫 10〉、1939年7月。NDLJP:1449952。
『成瀬先生講演集』 第7、桜楓会出版部〈桜楓文庫 11〉、1939年12月。NDLJP:1449958 NDLJP:1458161。
『成瀬先生講演集』 第8、桜楓会出版部〈桜楓文庫 12〉、1940年1月。NDLJP:1449962 NDLJP:1458165。
『成瀬先生講演集』 第9、桜楓会出版部〈桜楓文庫 13〉、1940年3月。NDLJP:1438688 NDLJP:1449968。
『成瀬先生講演集』 第10、桜楓会出版部〈桜楓文庫 14〉、1940年5月。NDLJP:1449971 NDLJP:1458154。
『女子大学論選集』
成瀬先生研究会 編『今後の女子教育 成瀬仁蔵・女子大学論選集』日本女子大学、1961年6月。
日本女子大学女子教育研究所 編『今後の女子教育 成瀬仁蔵・女子大学論選集』(新版)日本女子大学、1984年10月。
『成瀬仁蔵著作集』
成瀬仁蔵著作集委員会 編『成瀬仁蔵著作集』 第1巻、日本女子大学、1974年6月。
成瀬仁蔵著作集委員会 編『成瀬仁蔵著作集』 第2巻、日本女子大学、1976年4月。
成瀬仁蔵著作集委員会 編『成瀬仁蔵著作集』 第3巻、日本女子大学、1981年3月。
以下内容は、それを省略しています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
参議院選挙公示 山口選挙区に現職と新人の計5人が立候補
07月03日 20時18分、NHK NEWS WEB 配信より
https:/
参議院選挙が3日公示され、定員1人の山口選挙区には現職と新人のあわせて5人が立候補し、今月20日の投票日に向けて選挙戦に入りました。
山口選挙区に立候補したのは、届け出順に、
自民党の現職の北村経夫氏(70)、
参政党の新人の山崎珠江氏(47)、
NHK党の新人の奥野信治氏(47)、
無所属の新人の戸倉多香子氏(66)、
国民民主党の新人の関谷拓馬氏(35)
のあわせて5人です。
今回の選挙では、立憲民主党県連は自主投票としています。
公明党は対応を決めていません。
共産党県委員会と社民党県連合は無所属の戸倉氏を自主的に支援しています。
候補者は、街頭などで支持を訴えました。
北村候補は「希望を持つことができる未来に向けて政策を示すのが政治だ。強い経済の実現と暮らしの安定、国益を守る外交・安全保障、未来を担うことができる人材育成、この三本柱を軸に断固としてこの国、山口を守っていく」と訴えました。
山崎候補は「税金はどんどん上がり、お金を搾り取ろうとしている。日本の学生は学生ローンで学費を卒業後もずっと払い続ける状況だが、日本政府は留学生を優遇している。日本人ファーストで行っていく政治に取り戻していく」と訴えました。
奥野候補は「SNSは無法地帯になっている。情報開示が大事で、SNSの規制ではなく法律の改正が現実的だ」と訴えました。
戸倉候補は「上関原発の問題と、中間貯蔵施設の建設計画の問題を抱えている。私が手をあげなければ、誰もこの問題を取りあげる方がいないのではないか。安保法制の問題などもあり、何より暮らしのための政治を実現する」と訴えました。
関谷候補は「教育は未来の投資だと思っている。未来に投資をしなければこの国は豊かにならない。まず今を支えること、手取りを増やす夏にする。それは働く世代を支えることだ。皆さんと一緒に山を動かしていきたい」と訴えました。
選挙戦では、物価高対策をはじめ、少子化対策や年金といった社会保障などをめぐって論戦が交わされる見通しです。
また、衆議院で少数となった与党が参議院では非改選を含めて過半数の議席を維持するのか、それとも野党側が過半数割れに追い込むのかが、政権運営への影響を含め、今後の政治状況を左右するだけに大きな焦点となります。
投票は一部の地域を除いて今月20日に行われ、即日開票されます。