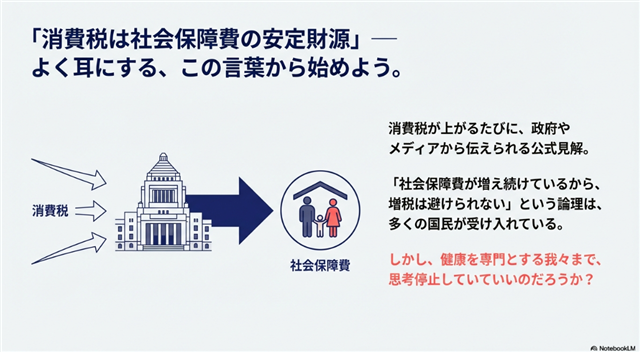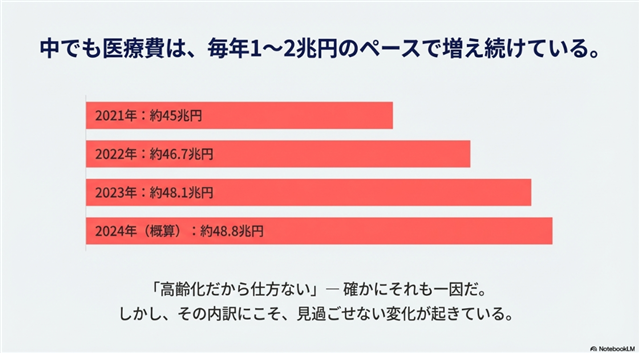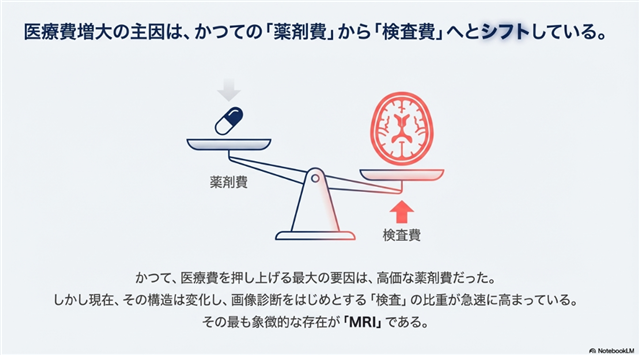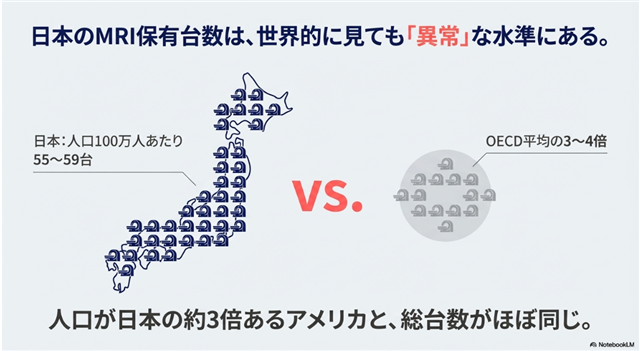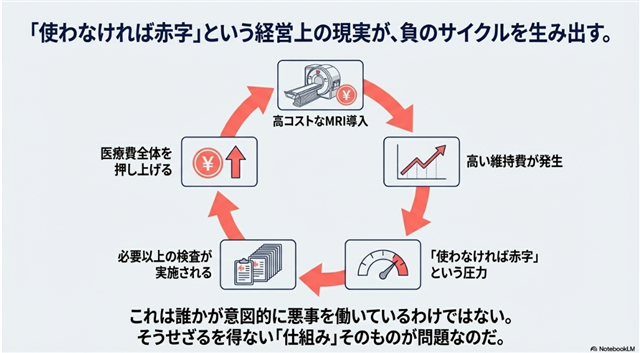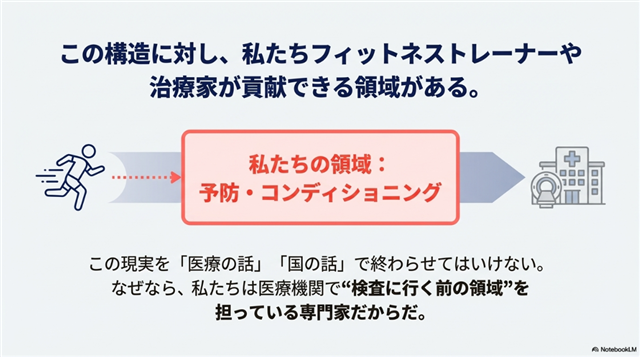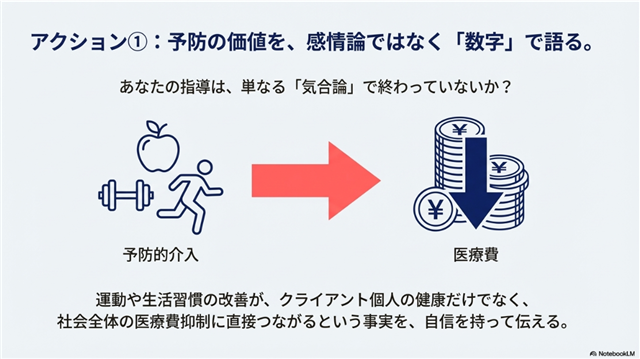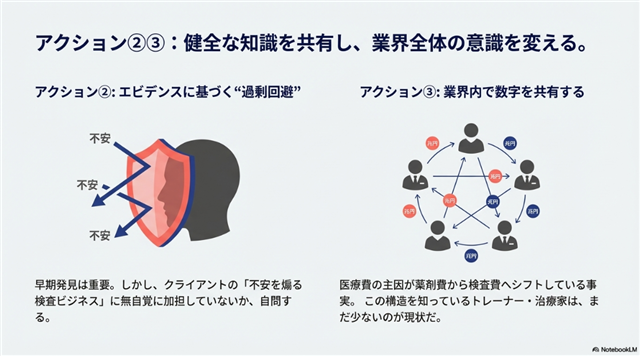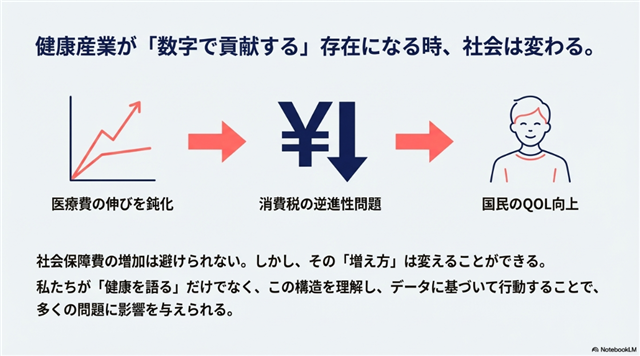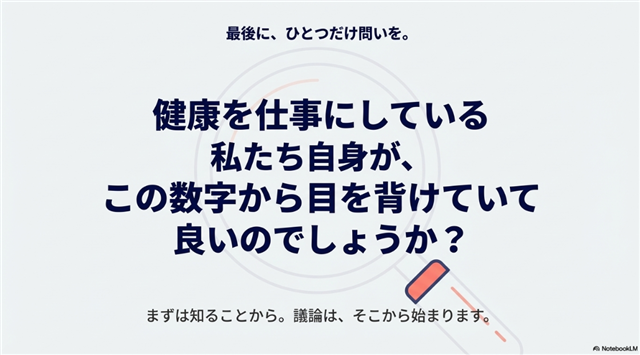私の徒手療法の先生は、よくこんなことを言っていました。
「施術家は、限界を感じると神仏にすがる」
これは、かなり本質を突いた言葉だと思っています。
そして最近は、
神仏だけでなく疑似科学にすがる人も増えました。
---
■ 仏教用語は「便利な飾り」になっていないか
徒手療法の世界では、
般若心経や阿頼耶識といった仏教用語を持ち出す人は少なくありません。
ただ、ここは一度、冷静に整理しておきたいところです。
実は
般若心経や阿頼耶識は、釈迦本人が説いた教えではありません。
これらは大乗仏教で後世に体系化された思想であり、
仏教学の世界では常識とされています。
参考
般若心経(Prajnaparamita)の成立
https://en.wikipedia.org/wiki/Prajnaparamita
阿頼耶識(唯識思想)
https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%80laya-vij%C3%B1%C4%81na
仏教アカデミアの人間で
「般若心経や阿頼耶識を釈迦の直説だ」と考える人は、まずいません。
---
■ 「色即是空」の解釈にもズレがある
有名な
「色即是空 空即是色」
このフレーズも、
釈迦の時代の文脈そのままではありません。
釈迦の時代、パーリ語での「色」は
**物質(フォーム)**を指します。
その文脈で直訳すると
「物質は空であり、空は物質である」
となり、かなり無理が出ます。
後世の大乗仏教は、
これを「現象一般」と拡大解釈しました。
哲学としては面白いですが、
それをそのまま身体論や施術理論に持ち込むには注意が必要です。
参考
五蘊(色・受・想・行・識)
https://en.wikipedia.org/wiki/Skandha
---
■ 今度は量子力学が持ち出されるようになった
最近では、
量子力学を徒手療法に結びつける人も増えました。
素粒子の
「重ね合わせ」
「観測で状態が変わる」
といった話を、
・エネルギー療法
・遠隔操作
・意識が身体を変える根拠
として語るケースも見られます。
ですが、ここにも大きな飛躍があります。
---
■ 重ね合わせは現実世界ではすぐ壊れる
量子の重ね合わせ状態は、極めて不安定です。
熱、振動、電磁ノイズなどがあると、
量子的な状態はすぐに崩壊します。
これを
デコヒーレンス(量子干渉の消失)
と呼びます。
参考
量子デコヒーレンス
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_decoherence
だからこそ、
量子コンピューターは
・ほぼ絶対零度まで冷却
・外部環境を徹底的に遮断
という、非日常的な環境を作って
ようやく量子状態を扱っています。
---
■ それを「人間の意識」で操れるなら
もし本当に、
人間の意識やエネルギーで
量子の重ね合わせを意図的にコントロールできるなら──
それは徒手療法に使うより先に、
物理学者と一緒に研究した方がいい。
ノーベル賞どころではない、
科学史を書き換える大発見だからです。
---
■ 阿頼耶識と量子力学をくっつける危うさ
興味深いのは、
阿頼耶識と量子力学を無理に結びつけて語る施術家が
少なくないことです。
自分では検証できない
理解も十分ではない分野を、
専門家でもない人が語り、
それを信じてしまう人がいる。
---
■ 人は「超越した力」を欲してしまう
理由は色々あるでしょう。
ただ、人は誰しも
「自分は特別かもしれない」
「何か超えた力に触れているかもしれない」
そう思いたくなる弱さを持っています。
---
■ 私たちは一般の人の模範でもある
でも、私たちは
一般の人たちの健康づくりの
模範になる立場でもあります。
正しい・正しくないの前に、
「それが社会に広まったら、どうなるのか?」
一度、立ち止まって考えてみてもいいのではないでしょうか。
私は、そう思っています。