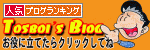「人は他人の話は聞きたくないが、自分の話は聞いて欲しい生き物だ。」
というお話をしました。人前で話をする以上、最低限必要分かっておかねばならない
前提の考え方だと思っています。
置き換えると、ビジネスや人生の全てに言えることだとも思っています。
「人は他人が差し出すものはできるだけ安く買いたいが、自分が出すものはできるだけ
高く売りたい生き物だ。」
とも言えるし、
「人は他人の主張は聞きたくないけど、自分の主張は聞いて欲しい生き物だ。」
「人は他人の書いたブログなんて読みたくないけど、自分の書いたブログは多くの人に
読んで欲しい生き物だ。」
「人は他人に時間を使いたくないけど、自分の都合には合わせて欲しい生き物だ。」
「人は他人には言いたい言葉はあるけど、自分にはその言葉は言って欲しくない。」
「人は他人の人生や事情など知りたくもないけど、自分の人生や事情は分かって欲しい
生き物だ。」
「人は他人に教えられたくないけど、自分は教える側でいたい生き物だ。」
等、色んな側面で置き換えられます。
この言葉を聞いて、その為には自分は人社会において何をせねばならないか?、
ということが見えてくる人か、まるで見えない人かで、圧倒的な違いが生まれてきます。
それによって、周りにどんなタイプの人が集まるのか、から始まって、いつも話を
聞いてくれる獲物を探さねばならないのか、勝手に人が集まってくる人なのか、
ビジネスが成功するかどうか、等、生き方や、人生に至るまで、全てに埋めようのない
圧倒的な差がついてしまうのだと思っています。
この言葉をどう受け止めるかは、個人の価値観にもよりますし、あぁ、こういうことだ、
と完全に達観するのはほとんど無理だとは思っていますが、でも、人社会で生きて
いる以上、考え続けてチャレンジすることは必要であるし、そうすることそのものに
意味があると思っています。
その言葉そのものは、誰でも理解できるでしょうが、本当に分かっているかどうかは、
私は私なりに見ている基準があって、それは、実は人が発信している時ではなくて、
受信している時、すなわち、人の話や発信を聞いている時の姿勢で一発で分かります。
正解かどうかは分かりませんが、私の経験則で言えば、一定期間、関わってきた人達を
見てきて、魅力的な話ができる人かどうかは、人の話を聞いている姿の魅力と比例します。
人の話を聞いてもいないけれど、自分の話をする時は俄然エネルギーがあがりまくって
とにかく喋り続ける人の話の多くは、メリットも感じなければ、興味もありません。
それでもお構いなしに、人の話を遮るほどの大声で延々と楽しそうに一方的にする人も
いますし、その伝え方も抑揚もクソもなく、全く面白くもなんともありません。
聞いている方は人生の無駄ですが、そんなことお構いなしで喋り続けます(苦笑)。
そういう人からは、他人はできるだけ離れていこうといますから、他人が離れれば
離れる程、また誰かを捕まえては、誰かの話を聞かないで、自分の話を聞いて欲しがって、
また、人が離れていくという最悪のスパイラルに入り込んで、もう抜けられません(苦笑)。
そのタイプの人は、私から見ていると、人の話を最後までちゃんと聞くことができない
人です。
任意の誰かと、会話やコミュニケーションを円滑に魅力的に成立させることができるか
どうかと言うのは、恐らく、それは「スキル」の問題ではなくて、「センス」の問題
だと思っています。
「スキル」と「センス」は全く違います。
ここでいう「スキル」というのは、体験・経験を通して培う「技術」のことです。
例えば、美容師さんなら、より長い時間を使って経験を積んだ方が、技術は以前より
上がります。
比較的、定量化がしやすい、共通の認識で高い・低いというのが分かりやすい項目です。
対して「センス」といのは、煎じ詰めれば「好き・嫌い」ということになります。
価値観とか、人間性とか、感情とかに左右されるものであって、それは人によって
評価は違ってくるし、共通の定量評価ができません。
例えば、他人のファッションを見て、ある人はセンスがいいと言うし、ある人はセンスが
悪い、といったように意見が分かれます。
生き方のセンスがいい・悪い、というのも人によって基準は全く違います。
要するに最後は「好き・嫌い」の世界なのだと思うのです。
これを前提とすると、「スキル」は時間をかけて努力したり、訓練すれば確実にアップ
していきますが、「センス」というのは努力や訓練では何ともなりません。
金持ちだろうが、人真似をしてみようが、「センス」が悪い奴はとことん悪いし、逆に
いい奴は何をやっても光ります。
だから、私から言わせると、「センス」が悪い奴をどうすればいいか?というのは、
もうどうしようもない、別の道を歩ませる、というくらいしか解決法が見つかりません。
しかし、です。
私が思っている「センスが良い・悪い」というのは、私の基準であり、価値観であり、
好みであって、それが正しいというわけではありません。
私の一方的な見解であり、そこに整合性や客観性や科学性などはまるでないわけです。
逆に、私の日常生活やファッションスタイル、生き方を見て、あるいはブログを読んでは
「こいつはなんてセンスがないんだ。救いようがない。関わり合いたくもない。」
と思っている人は、周りには、きっとたくさんいることくらいは分かっています。
(でも、100万人とかいたら凹むな(笑)。思いたくないけど、でも恐らく
たくさんいるだろう現実は受け止めるよう努力しています(笑))。
実際に、私から見て「センスがねーなぁ、こいつは。」と思う奴でも、その人はその人で
ちゃんと立派に生息しているコミュニティーがあったりして、そこはそこで、ちゃんと
「センス」を共有しているわけです。
私としては、ここに、どんな「センス」の奴でも、ビジネスも成果を出して、ちゃんと
生息していく、といくのは可能なんじゃないか?と可能性を見ています。
「センスが良い・悪い」という評価は誰でも常に付きまとうものの、その評価に対して
過敏になって意に反して自分を変えたり、我慢して、ストレスを抱えるかどうかに
関しては、今の時代は、もうどぉでもいいんじゃないか?と思ってもいます。
「今の時代は」ということに限っての可能性です。
昔は・・・・・、
例えば、村社会だとして、村人口が100人しかいなかったとします。
生活していく上で、100人と関わり合っていくのが生活の基本だとすると、生きて
いく上で重要なのは、100人と歩調を合わせることであり、調和していくことです。
だから、「個人のセンス=好き・嫌い」よりも優先せねばならないのは、100人と
調和するかしないかであり、言ってみれば100人という限られた範囲の中では、
個人が目立たないことでしょう。
100人の多数決で決まる価値観が、1人の人生の全てだということになる。
と、まぁ、そうします。
しかし、今は、SNSの普遍化に始まり、情報量の膨大さとスピードアップ、さらには
価値観の多様化とされている時代背景にともなって、生息できる範囲がまるで違って
きています。
仮に、生きていくのに100人と関係を維持していくのが必要だとすると、一つの村
では1人しか「センス」が同じ人がいなくて、生活できなかったとしても、
100人単位の村が100個あって、同じ確率で1人づつ「センス」が同じ人がいれば、
必要な100人との関係は構築できるという理屈上の計算になります。
昔は「自分のセンス」では生きてはいけなかったのに対して、今は十分生きていける、
となるわけです。
これは、私の、当時の大手アパレル・パリコレブランド営業時代~名古屋中心の
傘問屋時代~東海三県中心のリサイクルショップ時代~、そして、今の全国を行ったり
来たりの無職時代(笑)の経緯と、時代の変遷の中で、なんとなく得ている感覚に
よるのかも知れません。
これは、SNSの台頭と普遍化が、それまでの社会やビジネスの在り方とは圧倒的に
変えてきているのだと思っています。
私は名古屋に住んでいるのに対して、実際の仕事の現場は、名古屋以外の場所がほとんど
なわけです。
何が正解かどうかは分かりませんが、ただ、経験してきて感じるのは、所属する
集団・組織に関わる人によってつくられる文化・風土と、時代の変化の関係によって、
自分をどこまで出すか、殺すか、というバランスは変わってくるというのはあり得る
んじゃないか?と実感しています。
私はまだ日本という枠内でしか発想ができていませんが、考え方としては、世界全部に
顧客がいる可能性だってあるといえますね。
こうなってくると、あとはもう、本人がどうありたいか、だけになってくる気がして
います。
「私は地元の全ての人達を相手に幸せになりたい。」のであれば、地元の人達との調和を
最優先すれば良いのだろうし、
「私は自分がワクワクして楽しいと思えることを、共感してもらえる人達と一緒に
進めていきたい。」というのであれば、最大キャパとして世界として、その中の必要人数
だけいればいいとなります。
より大きな会社・企業にしたいのであれば、自分のセンスやコダワリなど二の次で、
多くの人が好みそうなことを、より安く安く渡せることだけをひたすら考えればいい
だろうし、
自分のセンスやコダワリを全面に出して生きたのであれば、利益の分岐点を越える
だけの限られた人数と深く長く関わっていくことを考えればいいのでしょう。
まぁ、それすらも、センスと言ってしまえば、センスで一括りになってしまいますが(笑)。
自分のセンスを全部出し切って生きていく、ということの分かりやすいリスクは、
それで実際に資本主義社会の中でやっていけるかどうか、要するに食っていけるかどうか、
になると思います。
でも、そう考えると、そもそも自分はどういう軸や核を持って生きていきたいかを
一旦明確にした上で、チャレンジはしやすい環境になっていることは確かでしょう。
昔はとんでもなくリスキーだったけれども、でも今はチャレンジしやすい、あるいは、
実験はしやすい、という時代であるというのは、個人が世界へ向けて発信ができる
SNSの機能というのは、本当に大きいと思っています。
そういう意味で、SNSは、世の中を大きく変える、という主張は私は正しいと思って
いるのです。
もし、自分が、自分の主張や、自分の話を人に聞いて欲しいなら、近くの誰かを獲物の
ように探しては面倒くさがられるよりも、SNSで発信することの方をオススメします。
その方が、よっぽど早く分かりたいことが分かると思うのです。
と、いうようなことを、一緒にいた人に、「ここでこんな風に撮って。」と何枚も
撮ってもらった手前、その画像をブログに出すにはどうしたらいいんだろう?と考え
ながら、無理矢理思いつきました(苦笑)。
自分の話を聞いて欲しいなら、人を捕まえずに、勝手にSNSで発信しとけよ(苦笑)。
応援クリックお願いします~。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓