鹽竈神社
読めますか?
フォントサイズ最大の「XXL」にしてみると
鹽 竈
「しおがま」と読みます。
アメブロ繋がりの地元民・usagisanだったら読めるし書けるのでしょうか!?
鹽竈神社の最寄り駅は、
JR仙石線
本塩釜駅
住所は、
塩竈市
1941年(昭和16年)の市制施行より表記を「塩竈」に統一、それ以前は「鹽竈」、「塩竈」、「鹽釜」、「塩釜」など、混在して用いられていたのだそう。
正式な市名は「塩竈」ですが、駅や行政機関のほとんどは「塩釜」が使われているようです。
公文書などでも「塩竈」「塩釜」どちらを使っても良いのだそうです。
それにしても「竈」って漢字難しいですよね。
21画もあるんですよ(;^_^A
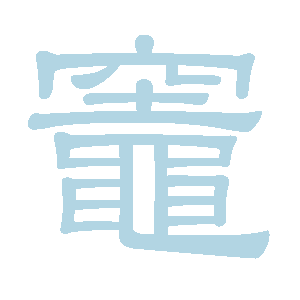
※ 画像は、塩竈市Web siteより引用。
竈 = 竃
前者が標準字体、後者は許容字体で略字。全然略字になっていないのだが(;^_^A
「繩」→「縄」と同様の変化ですが、「縄」は常用漢字の新字体であり、それに対して「繩」が旧字体となります。なんだか矛盾していると思うのは私だけ!?
私の生活行動範囲だと、
京都市下京区塩竈町
甕竈冠地蔵堂(かめかまかぶりじぞうどう/三重県津市)
があるので、読むことはできますが、書くことはできません。。。
鹽竈神社
塩竈市一森山1-1 <Googleマップ>
TEL: 022-367-1611
授与所時間: 5:00~18:00
創建時期は不明、奈良時代と伝わる。陸奥国一之宮。
「塩竈市」の市名由来になっている。
主祭神:鹽土老翁神(シオツチノオジノカミ)、左宮に武甕槌神(タケミカヅチノカミ)、右宮に経津主神(フツヌシノカミ)。
国道45号、塩釜港に沿って桝形に湾曲するあたり道路標示に従い進んで行きました。
第1駐車場に停め、裏参道と呼ばれているコンクリ舗装路の参拝道を上っていきます。
この日は1ヶ月前の4月21日(日)
境内に植えられた様々な桜は満開で、地元奈良ではもう完全に散ってしまっていた時期だったので、春に二度桜の開花に立ち会えました。
鬱金桜(うこんざくら)
名前の由来は、花色が鬱金染めに似ることから名付けられたのだそう。
「鬱金」という漢字、一発変換できず「うつ」「きん」と入力しました(;^_^A
八重紅枝垂(やえべにしだれ)
明治初期、京都御所より贈与された桜だそう。
同時期に内祝いとしてこの地の枝垂れ桜「細雪」を京都にお返し、平安神宮に奉納されています。
その他にも、かなり色々な種類の桜が咲き乱れ、案内書きを読んでいるだけで時間がいくらあっても足りなくなりそうなので、先に進むことにします。
石段を上り切り平坦になった左手、甑炉型鋳銭釜(こしきろがたいぜにがま)
1728年(享保13年)から明治維新頃まで石巻鋳銭場で使われていた。
左手に、鹽竈神社の大鳥居
鹽竈神社には、人道参道が3つ、車道参道が1つあります。
西から、表参道(通称:男坂)、七曲坂(最古参道)、東参道(通称:裏坂・女坂)、そして北東の車道参道。

※ 画像は、鹽竈神社公式HPより引用。
右手には、志波彦神社の鳥居があるのですが、順路がわからないので鹽竈神社の鳥居より参拝することにしました。
鹽竈神社の参道石段を上ります。
中間あたりに大絵馬、今年の干支・甲辰が描かれています。
最後の石段の上には、1941年(昭和16年)竣工の東神門
東神門を潜ると、平坦な参道になりました。
草木に灯籠となかなかいい雰囲気の神社ですね。
舞殿
名称から感じられるのは、神事をする建屋?
天然記念物の鹽竈桜。
鹽竈神社の神紋になっているのが、鹽竈桜なのです。
穏やかな顔立ちの撫で牛
案内書きによると「商いは牛の涎」。
牛の涎が細く長く尾を引くように、商売は気長に辛抱せねばならない。
どこを撫でてよいか迷った末、右脳能力を高めたいので右頭あたりを撫でさせていただきました。
手水舎
どこを見てもよく整備されています。
一番奥には、出四社の末社。
神明社、八幡社、住吉社、稲荷社の四社を祀っています。
隋身門
表参道(通称:男坂)からの参拝者は、この立派な楼門を潜ります。
樹齢600年、高さ約31mの大杉は、老杉(ろうさん)
唐門を潜ると境内中央となります。
唐門正面に左右宮拝殿
左宮に武甕槌神(タケミカヅチノカミ)、右宮に経津主神(フツヌシノカミ)を祀っています。
右手に、別宮拝殿。
主祭神・鹽土老翁神(シオツチノオジノカミ)を祀っています。
なぜか主祭神は、右側西向きに鎮座されているのです。

1809年(文化6年)伊達9代藩主伊達周宗によって奉納された文化燈籠(銅鐵合製燈籠)
芸術性がかなり高いと感じもう少し細部まで見学したかったのですが、写真を撮る人が順番待ちされていてフレアゴーストの写真となってしまいました(;^_^A
1187年(文治3年)藤原忠衡(和泉三郎忠衡)が奉納した文治燈籠。
「文治三年和泉三郎寄進」と刻まれています。
平安後期鎌倉初期の貴重な燈籠を雨ざらしにしていても良いのでしょうか?
授与所にて御朱印@500円を授かりました。
A5サイズ右頁には、志波彦神社の御朱印も押してあります。
それでは、鹽竈神社の東隣に鎮座する志波彦神社に向かいます。
同一敷地内にある神社なのですが、公式HPでも「志波彦神社・鹽竈神社」という順に記載されていて格式があるのでしょうか?
志波彦神社(しわひこじんじゃ)
塩竈市一森山1-1 <Googleマップ>
TEL: 022-367-1611
授与所時間: 5:00~17:00
※ 鹽竈神社より1時間早いので注意。
かつて宮城郡岩切村(現仙台市宮城野区岩切)の冠川(現七北田川)左岸に位置していた。創建時期不詳、1871年(明治4年)現在地に奉遷。
Googleマップ航空写真を見てみると、
左の鹽竈神社の左右宮は南南西(別宮は西向き)、そして右の志波彦神社は南南東。
それぞれの神様が相対するように鎮座されているのは訳あってのことなのでしょうか?
調べてみましたが不明でした。
志波彦神社神門
参拝は17:00までとなっており、すでにタイムオーバー。
神門前で二礼二拍手一礼。
隙間より志波彦神社拝殿を撮影させていただきました。
高台にある神社なので塩釜港が見下ろせ、奥の遠景には小島が多くあることが確認できます。
西側の表参道、東側の東参道との間にある未舗装の「七曲坂」。
ここより次の目的地に向かおうと思います。
確かに七回曲がったような気がすと思ったら、「七曲坂」の入口付近に到着。
砂利が多く滑りやすい参道ですがなかなかスリリングでハイキング気分になり面白かったですよ。
県道3号塩釜吉岡線に出て左(東向)に進むと、東参道(別称裏坂・女坂)の入口があります。漆喰の常夜燈、奥に鳥居。女坂といわれるからか?たまたまか?女性参拝者さんしか見当たりませんでした。
東参道の鳥居を潜ると、右手に1921年(大正10年)建立の五重塔。
石段の先に鹽竈神社の鳥居へと繋がります。
末社
御釜神社
に続く。


































