東京練馬区に仕事で行った帰路、都道245号杉並田無線(通称:新青梅街道)を走行していてふとナビに目をやると、
東伏見稲荷神社
西東京市東伏見1-5-38
私は、京都伏見稲荷大社に毎月一日参りをするほどの稲荷信仰信者なので、これは気になる!
ちょっと寄り道して行こう(*^▽^*)
最寄り駅は、西武新宿線・東伏見駅か西武柳沢駅 いずれも徒歩7分のようです。
※ 画像は、東伏見稲荷神社公式HPより引用。
朱色の大鳥居と「東伏見稲荷神社」と刻まれた石柱。
1929年(昭和4年)創建で新しいということもありますが、非常に美しい神社だという印象をもちました。
ローズマリー?も丸く剪定されて、定期的に庭師の方が整備されているのでしょう。
鳥居の両サイドには2基の常夜燈
鳥居右側は自動車参道のスロープとなっています。
私もこの先の駐車場に駐車させていただきました。
大鳥居で一礼、石段を上って行くと、右手、玉を咥えたキツネ様。
左手、鍵を咥えたキツネ様。
大きくはないですが、神門(楼門)を潜り境内に入ります。
大扉の中央に金の神紋
総本社京都伏見稲荷大社の神紋と比較してみると酷似していますが、微妙に違うのがわかります。
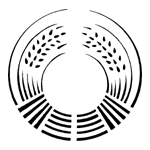
※ 画像は、伏見稲荷大社公式HPより引用。
神門入り右手には手水舍があります。
手と心を清めさせていただきます。
境内の全容はこんな感じ。
広くはないけれど、先ほども述べましたが美しい境内です。
正面の拝殿で二礼二拍一礼。
奥に本殿が鎮座されているようです。
立派な神額
東伏見稲荷神社は、関東の稲荷信仰信者の熱望により、京都伏見稲荷大社から分霊を勧請して1929年(昭和4年)に創建されたのだそうです。
総本社の伏見稲荷大社では、拝殿の撮影は禁じられているのですが、こちら分霊の東伏見稲荷神社にはそのような注意喚起がなかったので撮影させていただきました。
明治以前の住所は、武蔵国新座郡神保谷村、1967年(昭和42年)保谷市発足と同時に東伏見の地名を設置、2001年(平成13年)田無市・保谷市が合併し、西東京市発足。
東伏見稲荷神社が鎮座していたことが地名設置の要因だったのです。
●主祭神
宇迦御魂大神(うがのみたまのおおかみ)
佐田彦大神(さだひこのおおかみ)
大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ)
拝殿左脇に進んで行くと、「お塚参拝道入口」という看板があるので入らせていただきます。
こちらの「お塚」と呼ばれるところは、京都伏見稲荷の稲荷山を模様した高台になっていて、18ヶ所の末社が祀られているのです。
そして、この「お塚」を参拝するにはルールがあるようで、
① 18社すべてお詣りする。
② 同じ社を参ってはいけない。
③ 願い事は一字一句同じ内容で伝える。
となっています。
千本鳥居と呼んでもいいのかわかりませんが、朱色の鳥居が立ち並んでいます。
歌舞、芸術の守護神の開照大神(さきてるおおかみ)
天鈿女命(あまのうずめのみこと)を祀っています。
同じく芸能の神、綾太郎稲荷社
盲目の浪曲師浪花亭綾太郎(1889年-1960年 71歳没)を祀っています。
八幡大神
左:愛徳稲荷大神、右:愛法稲荷大神
前述したように全18ヶ所の末社が祀られていますが、ご紹介はこの辺で。
拝殿まで戻り、授与所にて春季限定の御朱印@500円を授かりました。
ほんのりピンクがかった奉書紙に手作業でちぎり絵が貼られてかなり凝ったデザインになっていて即決で決めました。御朱印ガールの気持ちがわかります。
時間に限りがあったので、40分程度で参拝をさせていただきましたが、「お塚」も含んでもそれほど広い境内でもないので、所要1時間あれば充分なのではないかと思います。
毎月一日参りに訪れる総本社・伏見稲荷大社と対比しながらでしたが、分霊されているだけあって酷似しているのがよくわかります。
「伏見」の地名を関東圏でお目にかかれるのも嬉しいものですね。




















