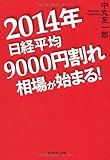イエレンFEDの2014年2月以降5年間の金融政策はどのようなものになるだろうか。それを的確に予測する上で、最近話題になっている二つの論文を見逃すわけにはいかない。
イングリッシュ氏とウィルコックス氏という現在FOMCにスタッフとして参画している最も重要なエコノミストの二人が、IMFセミナーでそれぞれ論文を発表して注目されている。むろん、バーナンキ議長とイエレン副議長による大まかな同意が存在したことは明らかだろう。
前者の論文は、基本的に、イエレン女史が2012年に発表したオプティマル・コントロール(最適制御)に関するスピーチを拡張したものだ。標準的な金融政策のルールよりも、政策金利をより低くそしてより長期に維持することを事前にコミットすることを主張している。
これに対し、後者の論文は、「内性的な供給」というものだが、要するに、アメリカの一時的な総供給への打撃が恒久的なものにならないように、米連銀が積極的に行動すべきだとするものだ。
これらの総合的なメッセージは、量的緩和はほぼスケジュール通りに終了させる代わりに、政策金利の将来の経路に関して超緩和的なスタンスを採用することで、相殺するというものだ。
つまり、量的緩和に関して、彼らは、米連銀の資産規模は所与として扱っており、量的緩和の継続は前提にされていない。むしろ、今後の課題は、政策金利の最初の引き上げをどれだけ遅らせるかにあり、それをどのように事前にコミットするかにある。
次に、両者ともに、イエレン流のオプティマル・コントロールを使ったモデルを採用している。今後数年間の失業率とインフレ率の動きを最適化する今後の政策金利の経路を求めているのだが、結論的には、最適な政策金利の引き上げ時期が、これまでの想定よりも一年ほど遅れた、2017年まで先送りされる。
これを市場に納得してもらうために、たとえ米経済が回復しインフレ率が目標を上回っても、政策金利の引き上げを失業率が5.5%を下回るまで実施しない(現在は6.5%を下回るまで政策金利を引き上げないとコミット中)と変更することが望ましい。
要するに、FOMCの結論を事務方で支える重要なエコノミスト、イングリッシュ氏とウィルコックス氏は、量的緩和はかなり早い時期に実施されることを前提にしている。同時に、それを相殺するために、同時に、いわゆる政策金利のフォワードガイダンスに関して、ゼロ金利政策をたとえば2017年まで維持すべきだと主張しているのだ。
ただし、金融市場はかれらの見解を正しく理解しているようにはみえない。2013年には米長期金利が大幅に、しかも急上昇した。金融市場は量的緩和の縮小と政策金利のフォワード・ガイダンスとは、今後、別物になると理解する必要がある。だが、両者の溝が簡単に埋められるかは簡単ではないだろう。
もし、金融市場が、5月に発生したように、量的緩和縮小が長期的な短期金利の上昇をも意味し、したがって長期金利が同時に上昇(長期国債が売られる)するようになれば、株式市場はパニックを引き起こし起こしかねない。
- 2014年日経平均9000円割れ相場が始まる!/中丸 友一郎
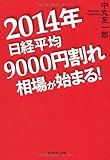
- ¥1,575
- Amazon.co.jp