ブログに訪問してくださいまして
ありがとうございます。
今朝、起きると雪が積もっていました。
シベリアからの寒波の影響で、これから寒い日が
何日か続くとの予報です。
幸い、雪は午後になる前にはすっかり溶けて
しまいました。
朝の近くの公園の景色です。
スノードロップ。雪と同化していて分かりにくい
かもしれませんね。
以下が映画大好き!1、2、3です。
2 で書きましたように、先日、主人と
昨年亡くなったロビン・ウィリアムズ主演の
映画「いまを生きる」を観ました。
観たかった理由は私が好きな映画だと
いうこと。
そして昨年、テレビで放映されて
観た「ヒストリーボーイズ」という
イギリス映画と比較したかったから。
「ヒストリーボーイズ」は主人と二人で観て、
二人の間で随分長い期間、この映画について
話が尽きませんでした。
- ヒストリーボーイズ [DVD]/ジェームズ・コーデン,リチャード・グリフィス,ドミニク・クーパー
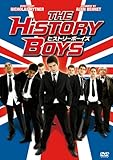
- ¥1,533
- Amazon.co.jp
- 現在、イギリスを代表する人気劇作家、脚本家である
- Alan Bennett(アラン・ベネット)による舞台を映画化
- したもの。
舞台は、2004年に初演され、爆発的な人気を呼び、
ローレンス・オリヴィエ賞、そしてトニー賞も
受賞した作品。
粗筋を簡単に説明しますと
1983年のイギリス北部のグラマ-スクールで
オックスフォード、ケンブリッジの受験を目指している
8人の男の子達を中心としたストーリー。
彼らを教えるのは人間のより深い部分に触れることを
奨励し、それを文学を通して、独特な方法で教える、
初老の英語教師のHector(ヘクター)。
そしてヘクターと教育について同じスタンスを取る
歯に衣着せぬ物言いが光る、唯一の女性教師、
歴史を教える、Miss Lintott (ミス リントット)。
結果を出すことだけにこだわる校長に批判的。
ミス リントットは知られている歴史の事実を知り、
キチンと学ぶ土台、フレームワークを作ることを教え、
ところが、校長が取った手段はヘクターの授業の時間を
減らし、オックスフォード出の若手の教員 Irwin (アーウィン)を
雇い入れる。
全く違うアプローチとゴールを持つ3人の教師の下、
受験のための徹底指導が始る。
アーウィンの教え方はシニカルで冷たく、計算の入った
アプローチ。
豊かな知識を持つことを奨励するのは、
試験のため。
有名な詩や本、歴史的事実、芸術、建築等の引用を
することを例に、豊富な知識は試験官により強い印象を
残すのに有効なツール、スパイスとなると。
二本の映画は国も時代もセッティングも細かく言えば、
違いますし、意図したところも違うとは思いますが、
共通なテーマが幾つか浮き上がっています。
「いまを生きる」の内容は今更。。。と思われる方も
いらっしゃると思いますが、簡単に説明します。
厳格な名門校で学ぶ生徒達は、学校の規律と伝統、
親の絶対的な期待のプレッシャーを感じつつも
それぞれがそんなものだと受け止めている。
それが元OBである英語教師のキーティングが赴任
してきたことから重い空気が少しづつ変わっていく。
キーティングはいきなり型にはまった詩のウンチクが
書かれた教科書のページを破り捨てさせ、
ひとりひとりが違う視点を持つことと説き始める。
自分の心の声を聞くことの大切さも教える。
- 初めは戸惑っていた生徒達も徐々にキーティングの
言葉、ユニークな授業に触発されて、自由を感じ、
一人一人の個性も現れて、生き生きとしてくる。
ただし、現実はそんなに甘いものではなく。。。
どちらの映画も英語の教師が大きな役割を
担っています。
本来教育が持つ価値と意味を問いかけている。
一方で、受験という現実的なことに対しての
葛藤も。
結果を出すための勉強を最優先してしまうと
本当に学ぶことを楽しむことはどうなるのか?
自分の心がどう感じるのか?それなくしては
文学、詩、歌、舞台といったものを楽しむことは
出来ない。
それらは生きた人間の言葉だから、など等。
どちらの映画にも惹かれる私は
恐らく、ヨーロッパという国が伝統的に
持っている文学との深い関わりへの
憧れもあるもしれません。
比較。
主人と私が好みが合致した映画とそうではない映画の
そういう意味でも主人との間で交わした映画を
巡る話は今回時間をかけることで、更に面白い
展開を見せています。
長くなりましたので、続きは次へ。
最後までお読みくださいまして、
どうもありがとうございました。

