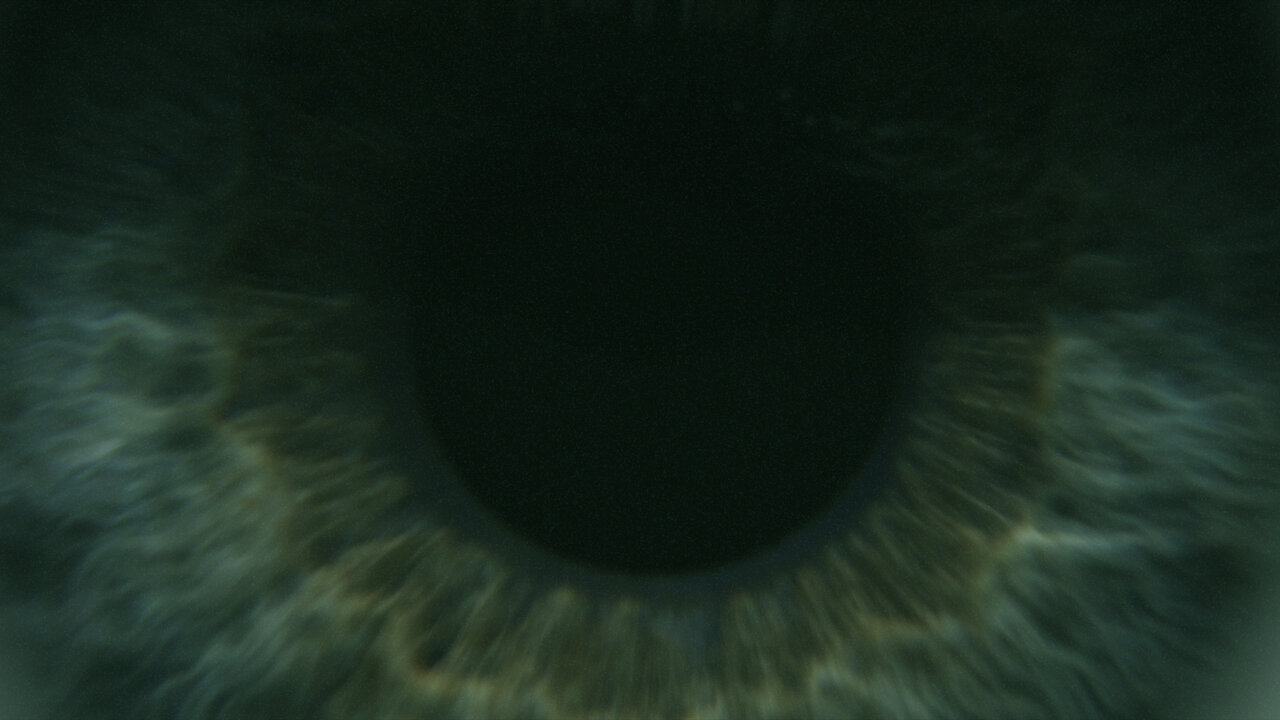映画を観るということ
それは船におけるアンカーのような、基準点となる作品だ。
同じ感動(と、シンプルに表現していいものかすらわからない感情)を得ようと、映画を観る回数が増えていく。
比較対象(サンプル)が増えていき、新しい魅力に気づいたり、なにも見つからずに落胆したりしながら、アンカーの存在を忘れる。
いつしか大量のアーカイブのなかでマイリストを作業的に消化している、腕を組んでどんどん理屈っぽく映画を見ている自分に気がつく。
実人生が上手くいかなくて、その怒りを映画のレビューにぶつけたこともある。
やがて自分の観ているものが良い映画か悪い映画かわからなくなる瞬間がやってくる。
そもそも良い映画とはなんなのか、と。
鑑賞済の半券を手に路頭に迷ったとき、ふと最初に海に出たとき海に沈んでいったイカリを思い出す。むかしの自分がさいしょに感情を動かされた映画をあらためて観直すのだ。
いったいこの作品のなにに、若い自分は魅了されたのだろう……。
真夜中、部屋を真っ暗にしてその作品と向き合う。
あくる日、わたしの足は劇場に向かう。シネマコンプレックス。ポップコーンとバターの匂い、長い廊下、壁にある額縁入りのポスター、大作公開をPRする巨大パネルまえを進み、まずはブルー/レッドの人型マークを探す(あれ? さいきんそんな映画あったな?)。
首の関節を鳴らしながら、シアターに入り、慎重にチケットの座席を探し、やがてスマホをポケットにしまって、スクリーンの前に腰を下ろす。
視界いっぱいに広がる未知の世界。
何度もそれをくり返す。
ほんとうに良い映画というものがわからないからだし、どうして自分が映画にここまで惹かれるのかわからないからだ。
Netflixで映画に関する映像エッセイを観たとき、ふと気が付いた。
トライし続けている。
探し続けている、まさにこの状態こそ良い状態で、良い映画なのではないか。
自分はすでに、映画という文化の一部になっている。
人生は映画ではないんだ、と「ニュー・シネマ・パラダイス」の台詞で出てくる。
そうなのか、たしかにそうだ……と思いつつ、
わたしはまた、映画を観る。