体ごと声(息)になる。
イメージ・感情・内動を一つにして。
そうすると、声は魔法になる!
昔、「日本昔話」というテレビアニメがありました。
市原悦子さんと男性の方が朗読していましたが、
大好きでよく見ていたものです。
中でも、ご飯を食べるおじいさんやおばあさんの
食事音の声が、いかにもおいしそうで、
大根飯や、みそ汁がご馳走に見えました。
いまでも、大根ご飯のレシピを見ると、
その音と情景が思い出されます。
あの声は、まさに魔法の声でした。
朗読技術や声の特質を越え、
食べ物のイメージと、「おいしい」という感情が、
まさに体の内を変え、再現されていたのでしょう!
言葉が内容を伝えるのではなく、
息がイメージや感情、
すなわち物語の中身を伝えていたのです!
増田先生の書いた『白雪姫』の脚本では、
お妃が、白雪姫にリンゴを食べさせた後、
小人の攻撃を受け、それをやっつけるために、
魔法で操るシーンがあります。
杖の動きと「ハッ」「シュッ」「ギュ~」などの声で、
小人を操るのですが、この「声の演技」が重要です![]()
小人役のこどもたちの体の内から
変えていけるような、イメージのある声を出すと、
子どもたちは喜んでその動きをしてくれます。
たとえば・・・
学校などでもよくつかわれる「ピシッ」
本当に相手がピシッとしたくなる、
緊張のある息でピシッとするよう、
イメージした声にします。
「トロトロトロ・・・」では、
アイスクリームが溶けるような、
とろける声です。
すると、こどもの体が溶けて、
経っている姿勢から、
柔らかく寝てしまいます![]()
舞台でもいかせる、声の魔法。
普段から、こどもの心を切り替えるのにも効果的です。
「ピシッとしよう」
「シーッ、静かに」
「おーい、集合だよ~」
どれもこれも、全身で声になると、魔法は掛かり、
子どもの動きが促されます。
そうそう、関西人の擬音語の多さも
まさにこの心理ですね![]()
![]() 朗読は楽しい
朗読は楽しい![]()
- 朗読のススメ (新潮文庫)/永井 一郎
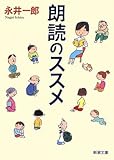
- ¥420
- Amazon.co.jp
- ミムラの絵本日和/ミムラ

- ¥1,470
- Amazon.co.jp
- ミムラの絵本散歩/ミムラ

- ¥1,575
- Amazon.co.jp
