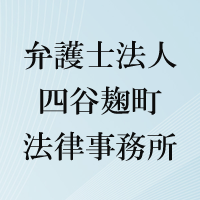労働審判のすすめ-11
第3回目
・労働者側の気持ちの持ち方
...ダメで元々、大きな期待をしないこと
行動を起こすこと、やってみることに
意義がある。実際、もしかしたらこの
労働審判の席に参加してこない可能性
もある。労働審判はその参加を強制す
るものではない。しかし、もし相手方
が参加してこないとしてもこれは殆ど
裁判と同じなので、「判決」は下る。
もちろん、異議申し立てをすれば、
労働審判そのものは無効となる。
しかし、その後に正式に裁判に移行す
れは、労働者側が圧倒的な有利な状況
で裁判が可能となる。従って、覚悟を
もって挑めば、負けることはないので
たとえ欠席されたとしても、悲観する
必要はない。むしろ、有利になったと
おもうべきでしょう。
***
労働審判委員会も申立書の内容はすべて正しい
とは思わないのですが、会社側に答弁書を作成
してもらって出席してもらわなければ、 申立書
の記載どおりの事実があったとして会社側欠席
のまま労働者に有利な労働審判を出します 。
労働審判が出たとしても審判書が会社に届いて
から2週間以内に異議を出せばその労働審判の
効力を失わせることはできます
(労働審判法21条1項・3項)。
審尋期日
審尋期日には、申立人も必ず出席します。
会社側は上司や人事担当者が来ることになり
ます。
審尋期日には、事前に出された書類に補足
することを弁護士の方で簡単に述べた後、
審尋に入ります。審尋期日の持ち方は裁判
官によって異なり、
東京地裁では、弁護士に先にしゃべらせずに、
いきなり裁判官からの質問が始まるケースが
多くなっています。審尋では裁判官や労働審
判員から、出席した関係者に直接質問がされ
ます。法廷での証人尋問のようにある人につ
いて一方が主尋問をして相手方が反対尋問を
して、それから次の人というような段取りで
はなく、適宜質問が飛び交います。現実には、
争点ごとに申立人に聞いて相手方に聞いて、
次の争点でまた申立人に聞いて相手方に聞い
てというような展開で、まず裁判官が聞き,
そこに労働審判員が聞いたり、代理人の弁護
士が聞いたりというような形で話に入ってい
くような感じになります。
そういうことをしながら、それぞれの争点に
ついて、事実はどちらの言い分が正しいのか
の心証を取っていきます。その上で、関係者
が一旦退席して、裁判官と労働審判員が合
議し、早ければ第1回の審尋で、おおかたの
心証が示され、調停案の方向とかさらには調
停案そのものまで示されたりします。
審尋が第2回期日にも継続されることもあ
りますが、事実上第1回で事実関係について
は決着が付いてしまう場合もあります
(というか、それが大部分です)ので書類で
出すなら、第1回前、要するに申立書と答弁
書に賭けなければならないわけです。
調停が始まると、申立人側、相手方側の片
方ずつ順番に呼ばれて、和解についての意向
を聞かれ、裁判所側から調停案が示されます。
東京地裁では多くの場合、第1回審尋でそこ
まで行ってしまいますし、遅くとも第2回審
尋では調停案が示されます。
=======================
労働審判のすすめ-10
第2回目
<労働審判での注意事項>
・黙秘、沈黙時間はできるだけ少なく、
かと言って焦って発言しないこと。
通常、理解不能な言葉や、質問の
意図が不明、必要以上に警戒する
心が、沈黙につながるようです。
特に、今までの人生経験で全くなか
たこと(法廷の雰囲気の場にいるの
は生涯で初めての人も多いので)
とても緊張しますが、沈黙は×です。
・そこで専門用語で理解不能なことには
知ったかぶりせずに完全に分かるまで
何回でもしつこくてもいいから聞くこ
とです。その質問の意図が理解できる
ように、違う言葉や事例(例え話等)
を聞くことです。そうすることで、
当方の時間稼ぎをしながら、沈黙を
回避することが可能です。即ち、分か
らないことを聞くことで、沈黙を回避
するということです。分かっていても
敢えて質問しても構いません。
<審判の現場で予想される質問について>
1)裁判官から申立人への質問
...本当の事を申立しているかどうか
...本人の意思で申立しているどうか
...労働審判の意味を理解しているか
2)申立人(従業員側)からの回答
...自分のことに関する根拠ある事実
...同僚助言に基づく本人の固い意思
...労基申告➡あっせんを経ての理解
3)代理人(弁護士)からの質問
...不当解雇の意味を理解しているか
...申告金額の計算根拠の理解度合は
...提出証拠の信ぴょう性の度合いは
4)相手方(雇用者)からの質問
...申立人証拠の否定を誘導する質問
...申立人意思の否定を誘導する質問
...申立人環境の否定を誘導する質問
5)審判員(裁判所)からの質問
...双方の発言の真偽を確認する質問
...双方の発言妥当性を確認する質問
...双方の争点の重点を確認する質問
ょうか?民事訴訟の場合、原告が求める貸金
請求権や損害賠償請求権といった権利の存否
具体的には以下のステップで判断を行います:
- 法令の解釈(法令解釈):裁判官は適用する法令を解釈し、 権利がどのような場合に発生するかを把握します。
- 事実の認定(事実認定):裁判官は証拠を評価し、法律が 要件とした事実がこの事件において認められるかどうかを判断します。
- 権利の判断:法令と事実を組み合わせて、権利の有無を判断します。
例えば、損害賠償請求権については、民法により「故意又は過失に よって他人の権利又は法律上保護された利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定されています。 損害賠償請求権が発生するためには、相手が故意または過失があったこと、 相手の行為によって自分に損害が発生したこととた要件を満たす必要があ
ります。裁判官はこのような要件を考慮しながら判断を下します。
裁判官の仕事は、公平で正義に叶う解決を求めて、具体的な紛争事件を
考慮しながら判断するものであり、法令と事実を組み合わせて最適な結論
=============================
労働審判のすすめ-09
<労働審判シナリオ>05.30原案
https://kigyobengo.com/media/useful/737.html
第1回目
・労働審判制度の解説……..裁判官より
・事情聴取:
…申立人への質問
・論点:不当解雇=解雇無効かどうか
………主な根拠
① 自己都合でないこと
② 解雇通知書がなこと
➡突然で一方的な口頭通知
③ 解雇理由が明示されないこと。
④ 解雇手当も支給されないこと。
⑤ 累計の未払い賃金の支給もないこと。
⑥ 就業規則も、雇用契約書もないこと。
⑦ 非常識な言動
⑧ 過去にも他の従業員に対する実績
・予想される想定問答:
1)なぜ、解雇無効と言えるのですか?
その理由を述べてください。
回答:・突然の口頭での解雇の通告あり。
本来、30日以上前に予告すべきだが、
即日解雇であったこと。
・その時に明確な理由も明示されていないこと。
一方従業員側に特段の非(不正行為や業務上
の過失など)がないと言えること。
即ち、会社都合であること。自己都合でない
こと。
・就業規則もないこと。
理由1:
正当な解雇理由がなければ不当解雇として多額
の金銭支払いを命じられる。
下記の<普通解雇>の定義に照らした場合、
これに相当しないことは明らかであること。
後述する2つの解雇以外のすべてが、こちらの
普通解雇に該当します。普通解雇は、労働者と
の労働契約の継続が困難な事情と客観的に認め
られるに場合に限られており、例としては次の
ようなことが挙げられます。
①勤務成績が著しく悪く、指導を行っても改善
の見込みがないとき
⓶健康上の理由で長期にわたり職場復帰が見込
まれないとき
③著しく協調性に欠けるため業務に支障を生じ
させ、改善の見込みがないとき
会社側(企業側)は「解雇権」を有しています
が、労使の力の格差から労働者を保護するため、
解雇権は制限されています。
すなわち、「解雇権濫用法理」によって、
客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当
でない限り、解雇は「権利濫用」として無効と
なります。
労働契約法第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念
上相当であると認められない場合はその権利を
濫用したものとして、無効とする。
この条文により解雇に「客観的に合理的な理由」
がないとして、解雇が無効とされるケースのこ
とを「不当解雇」と言います。
・未払い賃金も要求しているのに未払いであ
ること。
・会社都合の解雇と解釈しているが解雇予告
手当も支給されなかったこと。
① 一旦、労基に申告したが労基の調査に誠実
に対応していなかった。
② 労基の忠告に基づき内容証明郵便で請求書
を送付したが無視されたこと。
③ 労基の忠告に基づき、の手続きを行
ったが、やはり無視されたこと。
理由2:
就業規則に該当する解雇事由があるか確認して
おく必要がある。
就業規則には解雇事由を必ず記載することが義
務付けられています。
そして、解雇は基本的に就業規則に記載されて
いる解雇事由のどれかに該当する場合に限り認
められます。つまり、解雇にあたって懲戒解雇
を選択する場合は、懲戒解雇は就業規則に定め
た解雇事由に該当する場合以外はできません。
理由3:
解雇理由について従業員から証明を求められれ
ば応じる必要がある。
解雇理由が重要になる理由の3つ目は、解雇理
由について従業員から証明を求められたときは、
会社は証明書を発行する義務があるとされてい
るためです。
上記理由1.~3.の理由に基づかない解雇につき、
不当解雇を主張する。
即ち、正当な解雇事由もなく、根拠となる就業
規則もなく、解雇事由を明示する機会が
3回(労基調査面談時、内容証明到着時、あっ
せん召喚時の3回)あったにも関わらず、
解雇事由を明示されていないこと。従って、
これは不当解雇である。
=================================