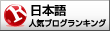”一体どうして、調整のやり直しをすることなるのか、こうなったのは設計担当のそちらがより注意深く見るべきであったと思います、一体何を見ていたのですか?・・・”
メールの![]() 文面がやたらときつい人、貴方の周りに居ませんか?
文面がやたらときつい人、貴方の周りに居ませんか?
・・・なんでこんなキツイこと書いてくるんだよ、責任全部おっかぶせてきやがって![]() !ふざけるな!文句言ってやる!
!ふざけるな!文句言ってやる!
そう思って、電話![]() をすると・・・
をすると・・・
「あ、いや、そんなつもりで書いたのではなくて・・・」
相手が驚き、こちらが呆れつつもその後の話をするようなこともちらほら有ったり。時にはその勢いのまま喧嘩別れになったり。![]()
メールやチャット、つぶやきや掲示板の書込みなど対面で話をしなくても連絡や報告ができるようになった現代。コミュニケーション手段は、昔の様に直接相手と予定を合わせて対面するよりも、だいぶお手軽になっています。しかし、一方では冒頭の様な行き違いがいろんな場面で増えています。
本来、人は相手の情報を言葉以外の様々な部分から得ています。声色、表情、視線、話す時の挙動、雰囲気。。これらの直接話す時の情報に留まらず、それ以前の相手の言動や、嗜好、大体の性格をも加味したうえで、相手にどんな風に話したらよいのかを全身で感じ取ってコミュニケーションを取っています。
これが手軽なコミュニケーション手段になればなる程、相手から情報を得る手段は限られていきます。対面より電話(音声とそれに付随する声色、雰囲気のみ)、電話よりメール(相手の文章のまとめ方)、メールよりチャット(相手の返信)、チャットよりつぶやき(相手の反応の有無)。
コミュニケーションがより手軽になるということは、同時にコミュニケーションの相手を、”目の前の人間”ではなく、より”反応する存在”もっと突き詰めると”記号情報”として認識することになります。
人間を認識しないコミュニケーション、その行きつく先は一方的な主張、要求、指示と、それに肯定的な反応や指示の実行のみを求めるものとなります。
私が学んでいる武道の先生が、こんなことを仰っていました。「平和な時代であればある程、技は残酷なものになる」
人の命のやり取りが日常的であった時代。刀![]() による斬りあいで眼の前の相手の命が尽きるのを間近で見届ける状況、自分も次は相手の様に斬られて最期を迎えるかもしれない、そうした光景を間近で見るならば、残酷な技などとてもできるものではないのでしょう。しかし、平和になりそうした光景が無くなっていくと、想像することもできなくなっていくものなのかもしれません。
による斬りあいで眼の前の相手の命が尽きるのを間近で見届ける状況、自分も次は相手の様に斬られて最期を迎えるかもしれない、そうした光景を間近で見るならば、残酷な技などとてもできるものではないのでしょう。しかし、平和になりそうした光景が無くなっていくと、想像することもできなくなっていくものなのかもしれません。
コミュニケーションも同様です。目の前の相手が見えなくなれば、相手がどう反応するかを想像する力も機会も薄れるのでしょう。言葉の刃が残酷なものになっても、気付かなくなるのかもしれません。その結果、言葉の鋭さを見誤り冒頭のやりとりの様ないさかいの種となります。
歴史上、「互いのコミュニケーションを直接会って行うこと」の重要性に気付き、国家規模で実行した国が有ります。それが江戸時代の日本でした。全国の諸大名が定期的に江戸に集まり直接顔を合わせた”参勤交代”は、ひょっとしたら200年の太平を築き上げた稀代の政策、だったのかもしれません。
どんなに通信手段が発展しても、コミュニケーションの基本は直接対面すること。それは、時代を超えて普遍的なものなのでしょう。