今回は旧土浦中学校本館の記事で少し触れましたが、土浦第一高等学校(以降は土浦一高)の沿革(現在までの成り行き)について書いてみようと思います。
土浦一高というか、明治以降の近代日本において、土浦市内の最初の学校というのが、明治11年(1878年)10月に土浦城の敷地内にあった土浦藩校の郁文館跡地に、師範学校土浦分校が出来たのが始まりだと思うんですね。
(師範学校土浦分校は翌年4月に廃止され、その郁文館及び師範学校土浦分校の跡地に、現在の土浦第一中学校が建っている)
その後、紆余曲折を経て明治30年(1897年)4月に、土浦一高の前進となる茨城県尋常中学校土浦分校が始まるんですね。
上記を見てお気付きだと思いますが、明治30年当時は明治19年に始まった県内に中学校は一つという中学校令により、同じ茨城県内にあった水戸の尋常中学校が本校で、土浦にあった土浦中学は分校という形を取らざるを得なかった為に、『茨城県尋常中学校土浦分校』という名称を用いていたんです。
土浦分校は現在の土浦一高がある場所と違い、 新治郡役所楼上にあったみたいです。
土浦分校が設置された明治30年4月14日に193人が受験を受けて、その僅か4日後に入学式が行われ、受験合格者の80人が入学式に参列した模様です。
その入学式が終わった4日後に授業が開始されました。
現在の高校受験から入学式や授業開始までの成り行きを考えると、当時の受験から授業開始までの成り行きが、やたらと慌ただしく凄まじいスピードで進んでいます。
因みに当時は三年制ではなく、四年制でした。
明治32年12月には立田町の現在の土浦警察や消防署から程近い場所に新校舎が完成、土浦分校はその立田新校舎に移転する事になり、翌年の明治33年4月には遂に土浦分校は独立を果たし、名称を茨城県土浦中学校と改称します。
明治38年には、現在地の真鍋町(現・土浦市真鍋4丁目)に建てられた西洋式の新校舎(旧土浦中学校本館)へ移転が決定し、旧土浦中学校として使われていた立田町の校舎の跡地には、後の土浦第二高等学校が作られ、現在の土浦二高は共学制の学校として運営されています。
(一高・二高が出来た当初は、一高が男子高で二高は女子高だった)
土浦中学校は、昭和23年(1948年)4月に茨城県立土浦第一高等学校として発足し、今では土浦一高は土浦二高と共に、茨城県の県南地域では有数の進学校としてその名を轟かしています。
それでは最後に、現在の土浦一高の写真と、旧土浦中学校本館の写真を見比べて頂きながら、今回の記事を締め括ろうと思います。
現在の土浦第一高校。
(Wikipediaより写真を転載させて頂きました)

明治38当時の土浦一高(土浦中学校本館・国指定重要文化財)
校舎自体は前年の37年には完成していたそうです。

(旧土浦中学校本館の写真は自分で撮影)
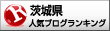
茨城県ランキングへ
土浦一高というか、明治以降の近代日本において、土浦市内の最初の学校というのが、明治11年(1878年)10月に土浦城の敷地内にあった土浦藩校の郁文館跡地に、師範学校土浦分校が出来たのが始まりだと思うんですね。
(師範学校土浦分校は翌年4月に廃止され、その郁文館及び師範学校土浦分校の跡地に、現在の土浦第一中学校が建っている)
その後、紆余曲折を経て明治30年(1897年)4月に、土浦一高の前進となる茨城県尋常中学校土浦分校が始まるんですね。
上記を見てお気付きだと思いますが、明治30年当時は明治19年に始まった県内に中学校は一つという中学校令により、同じ茨城県内にあった水戸の尋常中学校が本校で、土浦にあった土浦中学は分校という形を取らざるを得なかった為に、『茨城県尋常中学校土浦分校』という名称を用いていたんです。
土浦分校は現在の土浦一高がある場所と違い、 新治郡役所楼上にあったみたいです。
土浦分校が設置された明治30年4月14日に193人が受験を受けて、その僅か4日後に入学式が行われ、受験合格者の80人が入学式に参列した模様です。
その入学式が終わった4日後に授業が開始されました。
現在の高校受験から入学式や授業開始までの成り行きを考えると、当時の受験から授業開始までの成り行きが、やたらと慌ただしく凄まじいスピードで進んでいます。
因みに当時は三年制ではなく、四年制でした。
明治32年12月には立田町の現在の土浦警察や消防署から程近い場所に新校舎が完成、土浦分校はその立田新校舎に移転する事になり、翌年の明治33年4月には遂に土浦分校は独立を果たし、名称を茨城県土浦中学校と改称します。
明治38年には、現在地の真鍋町(現・土浦市真鍋4丁目)に建てられた西洋式の新校舎(旧土浦中学校本館)へ移転が決定し、旧土浦中学校として使われていた立田町の校舎の跡地には、後の土浦第二高等学校が作られ、現在の土浦二高は共学制の学校として運営されています。
(一高・二高が出来た当初は、一高が男子高で二高は女子高だった)
土浦中学校は、昭和23年(1948年)4月に茨城県立土浦第一高等学校として発足し、今では土浦一高は土浦二高と共に、茨城県の県南地域では有数の進学校としてその名を轟かしています。
それでは最後に、現在の土浦一高の写真と、旧土浦中学校本館の写真を見比べて頂きながら、今回の記事を締め括ろうと思います。
現在の土浦第一高校。
(Wikipediaより写真を転載させて頂きました)

明治38当時の土浦一高(土浦中学校本館・国指定重要文化財)
校舎自体は前年の37年には完成していたそうです。

(旧土浦中学校本館の写真は自分で撮影)
茨城県ランキングへ