私の書いた合格体験記が、一発合格道場様にアップされました。
↓体験記はこちら↓
http://rmc-oden.com/blog/archives/61286
字数制限の関係で記述できなかったことも多くありますので、
体験記をお読みになって、疑問点などある方がいらっしゃいましたら、
本ブログにコメントなど頂けますと幸いです。
回答させていただきます。
本日、2013年12月25日は口述試験の合格発表日でした。
無事に合格していました。
よかったです。
それはそうと今日立ち読みしてた本に書いていましたが、単行本を出せる人って1万人に1人らしいです。
目指すかいがある目標です。
20代のうちに単行本出したい。
あと、仕事は今日で今関わっているプロジェクトのヤマを超えて落ち着きました。
明日、明後日は会社で粛々と雑務をこなして仕事納めです。
本日は、診断士試験を経験して得たもの、失ったものを書きます。
○得たもの
・勉強そのものの内容面
‐以下の浅い知識
‐浅いとは、お客さんが話しているのを聞いて単語が分かる、理屈が少しわかる程度のレベル
‐1:経営理論(経営戦略、競争戦略、組織論、人事労務管理、マーケティング(STP、応用マーケティング))など
‐2:財務会計(簿記論、ファイナンス(企業価値算出、事業価値算出、証券ポートフォリオ))など
‐3:オペレーション(SLP、工程分析、在庫管理手法、店舗運営(4P)、インストアプロモーション、FRP分析)など
‐4:経営法務(会社法、知財法、民法、不正競争防止法)など
‐5:情報システム(ハードウェア、ソフトウェア、システム開発体制など、システム経営(組織の成熟度モデルとか)
‐6:経済学(マクロ経済(IS‐LM分析、AS‐AD分析)、ミクロ経済(MC曲線?))など
‐7:中小企業の動向など(補助施策(地域団体商標制度、マル経融資など)業種別、規模別、地域別、進出先別×開廃業率、成長率)
→仕事への効果:1人ヒアリングの際などのアドリブが増えた(持っている知識で多角的に質問し、なんとか対応)
→仕事への効果:世間一般の常識的なものが少しわかったので、何が常識でないか(ポイントか)が少し判断がつくようになった
‐短く、多くの意味を含んで、人に伝わり、伝わるだけでなく納得される文章の記述グセ
‐切り口(多様かつMECEな観点)、具体例(キーワード)、要は何?、改善の一手、その効果(意味)は?
→仕事への効果:打合せ資料の作成がうまくなった(相手に何を、なぜ、いま言いたいのかが伝わるようになった)
○失ったもの
・700時間という時間
‐期間が10ヶ月なので、1日平均2時間以上を投資
‐平日の行き帰りの電車の時間、昼の時間はかなり勉強、休日も結構勉強
・視野の広さ(反省点)
‐試験に時間を投資することで、世間の動向をチェックする時間が消滅
‐例えば、日経新聞、東洋経済など
‐理屈は勉強しても事例がないから周囲の人と話ができない(勉強不足と思われてしまう)
‐次回への学び:定点観測の時間は、固定された時間として確保すべきだった
・仕事の機会
‐人事のことだけ勉強しまくってプロジェクトに没頭して、いちはやく専門家になるという道
‐どこかでセーブをかけていたような気がする
‐新人の何でも教えてもらっても許される時期に自分で勉強していたことは実は大きな機会損失だった?
・自身の興味好奇心の在処
‐他の、自分のやりたいことや興味があったものは排除したので自分の興味が有るものが何かよくわからなくなった
・自分で考える習慣
‐資格試験とは、書いてあることを書いてあるとおりにできるか確かめること
‐しかも書いてあることはかなり単純化された状況
‐実務とは、書いてあることも無い中で、自分なりのベストを探すこと
‐自分で考える行動がないと仕事はできない
‐勉強をしていると、たまに自分で考えなくなっている自分がいてゾッとする
‐疑問が湧いてこない、素直に受け取ってしまう
無事に合格していました。
よかったです。
それはそうと今日立ち読みしてた本に書いていましたが、単行本を出せる人って1万人に1人らしいです。
目指すかいがある目標です。
20代のうちに単行本出したい。
あと、仕事は今日で今関わっているプロジェクトのヤマを超えて落ち着きました。
明日、明後日は会社で粛々と雑務をこなして仕事納めです。
本日は、診断士試験を経験して得たもの、失ったものを書きます。
○得たもの
・勉強そのものの内容面
‐以下の浅い知識
‐浅いとは、お客さんが話しているのを聞いて単語が分かる、理屈が少しわかる程度のレベル
‐1:経営理論(経営戦略、競争戦略、組織論、人事労務管理、マーケティング(STP、応用マーケティング))など
‐2:財務会計(簿記論、ファイナンス(企業価値算出、事業価値算出、証券ポートフォリオ))など
‐3:オペレーション(SLP、工程分析、在庫管理手法、店舗運営(4P)、インストアプロモーション、FRP分析)など
‐4:経営法務(会社法、知財法、民法、不正競争防止法)など
‐5:情報システム(ハードウェア、ソフトウェア、システム開発体制など、システム経営(組織の成熟度モデルとか)
‐6:経済学(マクロ経済(IS‐LM分析、AS‐AD分析)、ミクロ経済(MC曲線?))など
‐7:中小企業の動向など(補助施策(地域団体商標制度、マル経融資など)業種別、規模別、地域別、進出先別×開廃業率、成長率)
→仕事への効果:1人ヒアリングの際などのアドリブが増えた(持っている知識で多角的に質問し、なんとか対応)
→仕事への効果:世間一般の常識的なものが少しわかったので、何が常識でないか(ポイントか)が少し判断がつくようになった
‐短く、多くの意味を含んで、人に伝わり、伝わるだけでなく納得される文章の記述グセ
‐切り口(多様かつMECEな観点)、具体例(キーワード)、要は何?、改善の一手、その効果(意味)は?
→仕事への効果:打合せ資料の作成がうまくなった(相手に何を、なぜ、いま言いたいのかが伝わるようになった)
○失ったもの
・700時間という時間
‐期間が10ヶ月なので、1日平均2時間以上を投資
‐平日の行き帰りの電車の時間、昼の時間はかなり勉強、休日も結構勉強
・視野の広さ(反省点)
‐試験に時間を投資することで、世間の動向をチェックする時間が消滅
‐例えば、日経新聞、東洋経済など
‐理屈は勉強しても事例がないから周囲の人と話ができない(勉強不足と思われてしまう)
‐次回への学び:定点観測の時間は、固定された時間として確保すべきだった
・仕事の機会
‐人事のことだけ勉強しまくってプロジェクトに没頭して、いちはやく専門家になるという道
‐どこかでセーブをかけていたような気がする
‐新人の何でも教えてもらっても許される時期に自分で勉強していたことは実は大きな機会損失だった?
・自身の興味好奇心の在処
‐他の、自分のやりたいことや興味があったものは排除したので自分の興味が有るものが何かよくわからなくなった
・自分で考える習慣
‐資格試験とは、書いてあることを書いてあるとおりにできるか確かめること
‐しかも書いてあることはかなり単純化された状況
‐実務とは、書いてあることも無い中で、自分なりのベストを探すこと
‐自分で考える行動がないと仕事はできない
‐勉強をしていると、たまに自分で考えなくなっている自分がいてゾッとする
‐疑問が湧いてこない、素直に受け取ってしまう
ご無沙汰しています。
3連休は診断士合格後の動き方について学ぶために情報収集をしていました。
といっても、合格後の診断士に関する本を集めてざっと読んでいただけですが。
世にある診断士試験合格後に読みたい本について、良し悪しを述べている情報は少ないと感じていたので以下でコメントします。
以下はざくっとした個人的所見なので、書籍が気になる方はレビューを見る、購入するなどして自分の目で確かめてみてください。
==1冊目==
フレッシュ中小企業診断士の合格・開業体験記-資格取得と、その活用はこのように進める/同友館

¥1,995
Amazon.co.jp
合格後に一番最初に読む本としてオススメです。
実務補習の話、独立の話、企業内診断士の話などがバランスよく詰まっています。
==2冊目==
中小企業診断士の資格を取ったら読む本―ミーコッシュ革命で年収3,000万円は達成できる/同友館

¥2,310
Amazon.co.jp
ミーコッシュなどという耳慣れない言葉が印象的ですが、中身は特に特別な手法論に偏っているわけではなく、独立の手続きから売上の向上策まで生々しい実話と実践的な内容が述べられています。
ただ、独立の際に必要な視点を広く浅く、述べているので深さはないです。深さについては、実際に活躍されている独立診断士の方から聞く必要があるでしょう。
内容は独立する診断士の方向けですが、企業内診断士として活動する方にもおすすめです。
今から数年後の独立を視野にいれておけば、そのときに役に立つ行動を今から起こすことができるからです。
特に営業先の確保に苦労する診断士の方々が多い中で、今から地道に人脈を確保することは企業内診断士としても必要ではないでしょうか。
数年後に独立なんて考えていないよ、という方もいらっしゃるかもしれませんが、いい意味でも悪い意味でも何が起きるかわからない今の御時世を、幸せに生きるためには複数の選択肢を持っておくことが必要だと個人的には思っています。
==3冊目==
企業内診断士の可能性 NECグループ中小企業診断士103人の挑戦/同友館

¥1,575
Amazon.co.jp
この本は、企業内での診断士資格の活かし方について多くの事例が掲載されています。
(すべてNEおよびNECグループの事例です。)
だいぶ具体的な話がほとんどなので、診断士資格合格後の右も左も分からない方にはおすすめしません。
(特に大企業で)企業内診断士として資格を活かしたい方には参考になると思います。
診断士資格を取得して、社内でどう活かしたか、具体的な話が掲載されておりますので。
==4冊目==
職業、企業内診断士―アサヒビールグループ診断士の会の挑戦/同友館
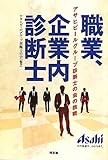
¥1,575
Amazon.co.jp
3冊目はNECの事例でしたが、本書はアサヒビールの事例です。
NECの本に比べて、酒類販売店でのコンサル事例などビールメーカーならではのコンサル事例(企業内診断士として資格を活かした事例)が豊富なので、そちらに興味のある方はぜひ
====
本の紹介は以上です。
本をざっと読んでわかったことは、
・診断士として独立して稼ぐことと、ダブルライセンスなど複数資格取得との相関はない
→金を稼ぐために資格をいかに活用するかは、知識などの資格とは別の能力
・実務補習に向けて、コンサルの手法を磨いておく必要があるということ
(※補習と言ってもあなどってはいけない。お客様は真剣勝負なのだから)
・診断士の研究会などは定員制の場合もあるので、参加したい研究会へは早めにアプローチしておくこと
・会社にいるうちに自分の強みといえる分野の形成、執筆、講演、異業種交流会などの診断士活動を通じた将来の営業先の確保を意識しておくことが重要
(※個人的には、強みというのは自分で意識して気づく前に、必死に仕事していたら気づいていたら強みができていたというほうが正しいのではないかと思う面もある)
書籍を読んでいて、残念に感じた点
・とにかく試験を俺はこうやって頑張ったんだ!どうだ!という、読者のニーズを外した(?)記述が随所に見られたこと
→読者もそれぞれなので、一概には言えないが、私は一歩引いてしまった。
→だから何?頑張ったから何?それを書いてなにの価値がある?と読者に言わせてはいけない、とう教訓を得た
3連休は診断士合格後の動き方について学ぶために情報収集をしていました。
といっても、合格後の診断士に関する本を集めてざっと読んでいただけですが。
世にある診断士試験合格後に読みたい本について、良し悪しを述べている情報は少ないと感じていたので以下でコメントします。
以下はざくっとした個人的所見なので、書籍が気になる方はレビューを見る、購入するなどして自分の目で確かめてみてください。
==1冊目==
フレッシュ中小企業診断士の合格・開業体験記-資格取得と、その活用はこのように進める/同友館

¥1,995
Amazon.co.jp
合格後に一番最初に読む本としてオススメです。
実務補習の話、独立の話、企業内診断士の話などがバランスよく詰まっています。
==2冊目==
中小企業診断士の資格を取ったら読む本―ミーコッシュ革命で年収3,000万円は達成できる/同友館

¥2,310
Amazon.co.jp
ミーコッシュなどという耳慣れない言葉が印象的ですが、中身は特に特別な手法論に偏っているわけではなく、独立の手続きから売上の向上策まで生々しい実話と実践的な内容が述べられています。
ただ、独立の際に必要な視点を広く浅く、述べているので深さはないです。深さについては、実際に活躍されている独立診断士の方から聞く必要があるでしょう。
内容は独立する診断士の方向けですが、企業内診断士として活動する方にもおすすめです。
今から数年後の独立を視野にいれておけば、そのときに役に立つ行動を今から起こすことができるからです。
特に営業先の確保に苦労する診断士の方々が多い中で、今から地道に人脈を確保することは企業内診断士としても必要ではないでしょうか。
数年後に独立なんて考えていないよ、という方もいらっしゃるかもしれませんが、いい意味でも悪い意味でも何が起きるかわからない今の御時世を、幸せに生きるためには複数の選択肢を持っておくことが必要だと個人的には思っています。
==3冊目==
企業内診断士の可能性 NECグループ中小企業診断士103人の挑戦/同友館

¥1,575
Amazon.co.jp
この本は、企業内での診断士資格の活かし方について多くの事例が掲載されています。
(すべてNEおよびNECグループの事例です。)
だいぶ具体的な話がほとんどなので、診断士資格合格後の右も左も分からない方にはおすすめしません。
(特に大企業で)企業内診断士として資格を活かしたい方には参考になると思います。
診断士資格を取得して、社内でどう活かしたか、具体的な話が掲載されておりますので。
==4冊目==
職業、企業内診断士―アサヒビールグループ診断士の会の挑戦/同友館
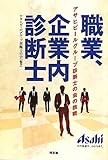
¥1,575
Amazon.co.jp
3冊目はNECの事例でしたが、本書はアサヒビールの事例です。
NECの本に比べて、酒類販売店でのコンサル事例などビールメーカーならではのコンサル事例(企業内診断士として資格を活かした事例)が豊富なので、そちらに興味のある方はぜひ
====
本の紹介は以上です。
本をざっと読んでわかったことは、
・診断士として独立して稼ぐことと、ダブルライセンスなど複数資格取得との相関はない
→金を稼ぐために資格をいかに活用するかは、知識などの資格とは別の能力
・実務補習に向けて、コンサルの手法を磨いておく必要があるということ
(※補習と言ってもあなどってはいけない。お客様は真剣勝負なのだから)
・診断士の研究会などは定員制の場合もあるので、参加したい研究会へは早めにアプローチしておくこと
・会社にいるうちに自分の強みといえる分野の形成、執筆、講演、異業種交流会などの診断士活動を通じた将来の営業先の確保を意識しておくことが重要
(※個人的には、強みというのは自分で意識して気づく前に、必死に仕事していたら気づいていたら強みができていたというほうが正しいのではないかと思う面もある)
書籍を読んでいて、残念に感じた点
・とにかく試験を俺はこうやって頑張ったんだ!どうだ!という、読者のニーズを外した(?)記述が随所に見られたこと
→読者もそれぞれなので、一概には言えないが、私は一歩引いてしまった。
→だから何?頑張ったから何?それを書いてなにの価値がある?と読者に言わせてはいけない、とう教訓を得た
口述試験を受けてきました@明治大学リバティタワー
面接官は1人は圧迫系とニコニコ系のペアだと想定しておりましたが、 2人ともニコニコ系でした。
そのおかげでリラックスできました。
考えたこともなかった視点の財務の質問をされて全然わかんなくて、 10秒位うーんちょっと時間頂いていいですか?えーとぉーあのぅーとか言って、その後に分かんないなりに適当なことをさも自信ありげにベラベラ言いました。
面接官の方、終始笑顔でしたが「適当なこといってんじゃねえぞ」って怒ってたかな。
まあでも予定通り、4問答えて終了。
あとは24日を待つのみです。
面接官は1人は圧迫系とニコニコ系のペアだと想定しておりましたが、 2人ともニコニコ系でした。
そのおかげでリラックスできました。
考えたこともなかった視点の財務の質問をされて全然わかんなくて、 10秒位うーんちょっと時間頂いていいですか?えーとぉーあのぅーとか言って、その後に分かんないなりに適当なことをさも自信ありげにベラベラ言いました。
面接官の方、終始笑顔でしたが「適当なこといってんじゃねえぞ」って怒ってたかな。
まあでも予定通り、4問答えて終了。
あとは24日を待つのみです。
2次試験合格しました。
独学一発合格できて良かったです。
昨年の12月1日から650時間勉強しました。
かなりコスパは良かったのではないでしょうか。
記述試験のノウ・ハウが学べて良かったです。
シンプル・イズ・ベストですね。
独学一発合格できて良かったです。
昨年の12月1日から650時間勉強しました。
かなりコスパは良かったのではないでしょうか。
記述試験のノウ・ハウが学べて良かったです。
シンプル・イズ・ベストですね。