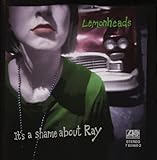ジャンルの違いこそあれ、「星を継ぐもの」の読後感は、「十二人の怒れる男」というサスペンス映画を観た時の衝撃に近かった。
錯綜する謎を解明すべき様々な人物の討論だけで、ほぼストーリーが成立してしまう様は圧巻である。
「星を継ぐもの」は、スケールの大きな王道SFだが、基本は百家争鳴による謎の解明だ。
つまり、徹底した演繹と帰納による論理と話し合いで、ストーリーが展開していく小説なのである。
この作品は、映画には不向きだと思われる。
学者の数々の憶測によって想像を膨らまし、傍証を固めて推理していくこの作品の醍醐味が、映像化する事によって半減する気がしてしまうからだ。
ある意味、小説の良い面が最大限活かされている作品と言えるだろう。
主役であるヴィクター・ハントのステータスは巧く機能している。
原子物理学者のハントは、国連宇宙軍本部長グレッグ・コールドウェルによって、グループLの総指揮官に任命される。
要は、専門領域の各部局の学者の調査した情報を統合して、パズルを完成させる仕事である。
情報のやり取りが無駄なくシステマチックに行われ、謎が徐々に解明していく過程は、複雑化した現在のネット社会に生きる我々に、或る種のカタルシスを与えると思われる。
特に、生物学者ダンチェッカーや言語学者ドン・マドスンとの話し合いの後、急転直下していく展開は白眉である。
そして、何と言ってもSFの醍醐味であるセンスオブワンダーも遺憾無く発揮されている。
最初、月で発見された正体不明の死体が、その後の調査による厖大な情報によって、壮大な規模のストーリーに展開していく。
そのロマン溢れる過程は、往年の50年代SFさながらである。
60年代のニューウェーブの到来によって、SFは終焉に差し掛かると思われたが、70年代はSF復活の季節であり、その70年代SFの代表作がこの作品である。
感情的なストーリー重視よりも、ロジックを重視した結果、この作品はハードSFとして成功する事になったのだろう。
また、SFにありがちなアイディアやロジックばかりを重視する作風ではなく、随所に詩的な表現を見出す事が出来る。
つまり、50~60年代SFの進化の過程を辿って来た作品と言えるだろう。
ここまで感想を書いてきたが、この作品に関してはミステリー要素が至極高い為、ネタバレは避けた方が良い類ではあると思う。
しかし、そうすると、ディティールに欠ける無味乾燥なレビューになるのが気に掛ったが、要は何処までネタバレするかという匙加減の問題である。
基本的にネタバレに関しては余り気にしないで書いてる事が多いが、結局は個人的な主観に委ねられる処だろう。
読了した感想として、最後のダンチェッカーの演説が腑に落ちなかったりと不満点もあるが、それも続編を読むモチベーションとなるのかもしれない。
全四部作の大作であるが、何とか「巨人たちの星」までは辿り着きたい処である。
|