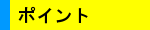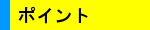概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>
日経ビジネスの特集記事(112)
2015 株主騒会
ROEで社長失格になる日
2015.06.22
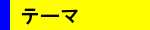
今週の特集記事のテーマは
緊張の面持ちで居並ぶ経営陣に、対峙する株主。
年に1度の株主総会シーズンがやってきた。
今年、その光景がガラリと変わる。
株主はROE(自己資本利益率)や配当などの還元策に
厳しく目を光らせ、満足しなければ容赦なく「社長失格」
の票を投じる。
アベノミクスが演出するこの株主“騒”会を何とか乗り越えようと、
新たな経営計画やROEの目標を打ち出す企業が続出している。
押し寄せる大波にのみ込まれるか、株主との対話を成長に
つなげるか。多くの日本企業がその岐路に立つ。
(『日経ビジネス』 2015.06.22 号 P.027)
ということです。

ROEで社長失格になる日
「日経ビジネスDigital」 2015.06.22

「日経ビジネスDigital」 2015.06.22
第1回は、
「PART.1 ROE目標、中期経営計画、株主還元・・・
企業を揺さぶる 『普通の株主』」
を取り上げます。
第2回は、
「PART.2 アベノミクスが舞台回し
踊り出す投資家 沸き立つ市場」
「PART.3 本誌独自ROE“分解”ランキング
持続力を見極めよ」
を取り上げます。
最終回は、
「PART4 圧力を活力に変える
脱・後ろ向きROE 解は1つじゃない」
をご紹介します。
今特集のキーワードは次の5つです。

ROE
持続力
株主還元
脱・ROE
自律
6月は、2015年3月期決算企業の株主総会が集中する月です。
今年の株主総会は、例年と異なり、「騒動」のある株主総会
ということで、『日経ビジネス』特集班は、株主「騒」会と名付け
ました。
この件について、飯田展久編集長は、「編集長の視点」に
次のように書いています。
(P.003)
今年は多くの企業で想定問答集の中身に
変化が見られるのではないでしょうか。
一般株主の間にも株主還元策に異常な関心が
集まっているためです。
ROE(自己資本利益率)の向上に目を光らせ、
ROEの低い企業には取締役の選任案に「ノー」を
突き付ける動きも出始めています。
現実に否決されることはまれですが、否決されない
案にあらかじめ作り直す例もあるようです。
こうした状況を本誌は「株主騒会」と名付けてみました。
総会をめぐる劇的な変化は一種の騒動のようだと見た
からです。
株主総会と言えば、昔は総会屋対策が重要な課題でした。
決算内容うんぬんよりも、総会屋をどう黙らせるかの方が、
大事だったのです。お金を握らせるという違法行為が公然
と行われてきました。
その後、総会屋の数が減少し、代わって増えてきたのが、
外国人投資家や外資系ファンドです。彼らは株式を買い
増し、株主の要求を経営者に突きつけます。
内部留保が多い企業には、設備投資や株主還元を強く
要求します。株主還元とは、配当金の割増です。
企業価値を高め、株価を上昇させる施策を採ることも、
当然要求します。
最近では、外資の「モノ言う株主」だけでなく、一般投資家
(今まではモノ言わぬ投資家と呼ばれてきました)が、
議決権を行使し、代表取締役の再任に“No!”を突き付ける
ケースが出てきたそうです。
ステークホルダー(利害関係者)には、社員、取引先、得意先、
株主、社会などがありますが、この中で株主の発言力がさらに
強くなってきていることが、今特集で再確認できます。
では、本題に入りましょう!
PART.1 ROE目標、中期経営計画、株主還元・・・
企業を揺さぶる「普通の株主」
新株価指数「JPX日経インデックス400」の選出に関して、
「異変」が起こったそうです。2013年11月のことです。
(P.028)
「どうしてうちが漏れたんだ!」
2013年11月、新たな株価指数「JPX日経インデックス400」
の構成銘柄に、同業で業界2位のAOKIホールディングスが
選ばれた。JPXはROEなど複数の基準で銘柄を選出する。
AOKIのROEは青山商事を上回っていた。
明確な理由があるはずです。
その理由とは?
(P.029)
明暗を分けたのは本業以外だった。
青山商事は紳士服事業が営業利益の9割を占める。
一方、AOKIは結婚式場やカラオケ店の運営などの
新規事業が営業利益の4割以上。
「紳士服事業が生むキャッシュを新規事業に回す循環
が定着した」とAOKIの田村春生副社長は語る。
手持ち資金を有効に使えていない青山商事と、
資本効率を上げたAOKI。
JPX採用銘柄の発表後、1カ月間の株価上昇率では
差が付いた。
将来への投資をしたAOKIと、しなかった青山商事に
明暗が分かれました。
ちなみに、ROEを比較しますと、青山商事は5.4%で、
AOKIは7.5%です。
この話には伏線があります。
青山商事のROEが5%を超えるかどうかが、ポイント
でした。
(P.029)
青山商事は2015年3月期決算を締める前まで、
ROEが5%を超えるという確証がなかった。
5%を切れば、総会で青山社長再任案への反対率が
高まる恐れがある。
そこで、約100億円の自社株買いを断行。
ROEの計算式の分母である自己資本を圧縮し、
帳尻を合わせた。
宮武副社長は怒涛の1年半をこう振り返る。
「過去の苦労から、キャッシュを手厚く持っておくべき
との考えが裏目に出た。
総会を乗り越えるメドがついたが、これがスタート
地点だ」。
ROEについては、次表をご覧ください。

「日経ビジネスDigital」 2015.06.22
ROEは、最終利益を自己資本で割った数値です。
ROEの数値を向上させるためには、分子の最終利益
を増やすか、分母の自己資本を小さくさせるしかあり
ません。分母の自己資本を圧縮するほうが容易です。
理論的には、分子を大きくし、分母を小さくすればよい
のですが、現実には最終利益を調整することは困難
ですし、ヘタをすると粉飾決算になりかねません。
ですから、自社株買いにより、自己資本を縮小させる
手段が使われるようです。
自社株買いのメリットは、次のことです。
「自社株買いが行われると発行済株式の総数が減ります。
総数が減るので1株あたりの資産価値やROEが向上
します」
(自社株買いのメリット 「初心者の株式投資道場」から)
株主総会が様変わりしているそうです。
株主総会の変遷を『日経ビジネス』は次のように
伝えています。
(PP.029-030)
かつて企業が恐れたのは「特殊株主」。
総務部門は、大物総会屋の一挙手一投足を気に
した。逆に、その他の株主は、さして気に留める
必要がなかった。
しかし今は違う。怖い相手は「普通の株主」だ。
ROEが低く、ガバナンスに不備があれば即「社長
失格」の票を投じる。そんな株主“騒”会を乗り
切るには、株主やその助言役であるISSなどと
対話し、理解を求めるしかない。
ここにあるISSというのは、
「米インスティテューショナル・シェアホルダー・
サービシーズ(ISS)。議決権行使を投資家に
助言する最大手だ。
ISSはROEが過去5年平均と直近決算期で
いずれも5%を下回る企業に対し、総会での
経営トップ選任案に反対する指針を表明して
いる」 (P.028)という組織で、企業にとって
怖い存在です。
『日経ビジネス』は、「今年は『ROE総会』の
元年だ」と述べています。
経営トップ選任案への賛成率とROEの数値との
関係を示すグラフがあります。

・3月の総会におけるROE別経営トップ選任案への賛成率
「日経ビジネスDigital」 2015.06.22
ROEが5%以上であることは、経営トップにとって
自分の地位を守る条件と言えます。
ROEを逆手に取った企業があるということで、
じっくり読んでみました。
(P.031)
ROEの神通力を逆手に取った企業もある。
「ようやく承認された」。
6月12日、ゲーム大手、カプコンの小田民雄副社長は、
深い安堵感に包まれた。
この日開かれた総会で、昨年否決された買収防衛策議案
が可決されたからだ。
復活劇の裏にはROEがあった。
同社は今年の総会で初めてROEの数値目標を議案に
入れた。
2017年3月期までの3年移動平均のROEを、前期の6.7%から、
8~10%に引き上げるというものだ。ROE目標を総会の議案に
入れるのは異例。株主に中期的な成長の青写真を見せ、
買収防衛策への理解を求める狙いが功を奏した。
買収防衛策のため、ROEの数値目標を掲げた、
ということです。必達しないとなりませんね。

ROEの向上は企業価値の向上
ROEが向上することは、1株あたりの利益が増えること
ですから、株主にとってもメリットがあります。
株価上昇や、配当金の増額も期待できます。
企業価値も向上します。自己資本を活用して利益を
上げていることになるからです。
ROEが5%というボーダーラインが果たして高いの
だろうか、という疑問が残ります。
そこで、日米欧のROEの推移を調べてみました。
日本企業のROEが欧米の企業より低いことは、
理解しています。
欧米企業のROEは二桁台はザラにあるということです。
10%以上でなければ、株主から経営者失格の烙印を
押され、CEO(最高経営責任者)を解任される、
という話を読んだことがあります。
次のグラフを見ますと、欧米と日本は乖離していること
が一目瞭然ですね。
2013年までのデータですが、日本は欧米との差を縮める
ことは容易ではないことが、分かります。
長年続いた円高から円安に転換し、少しは改善したの
でしょうか?
現時点では、データが見つからないため確定的なことは
言えませんが、少なくとも、劇的な改善はないでしょう。

三井住友アセットマネジメントのサイトから)
今特集のキーワードを確認しておきましょう。

ROE
持続力
株主還元
脱・ROE
自律
次回は、
「PART.2 アベノミクスが舞台回し
踊り出す投資家
沸き立つ市場」
「PART.3 本誌独自ROE“分解”ランキング
持続力を見極めよ」
をお伝えします。
ご期待下さい!
藤巻隆(ふじまき・たかし)オフィシャルブログ-
人気のブログランキング
こちらのブログやサイトもご覧ください!
こんなランキング知りたくないですか?
中高年のためのパソコン入門講座(1)
藤巻隆のアーカイブ
本当に役に立つビジネス書