昭和時代に、大演歌歌手の三波春夫さんは、
「お客様は神様です」というセリフを
よく口にし、その言葉が一世を風靡した
ことがありました。
お客様を大切に扱いましょう、という強い
メッセージでした。
それから数十年が経ち、世の中は大きく
変わりました。
もう、「お客様は神様」とは言えない時代
になりました。
多くのクレーマーの出現です。
本来のクレーマーの意味は、正当な理由が
あって、主張する人のことです。
ところが、自分の都合を優先させたり、
事実を歪曲したり、でっち上げて、
金品を要求する輩が増えてきたのです。
インターネットの普及が、クレーマーの
増加に拍車をかけているのは間違いあり
ません。
クレーマーへの対応を誤ると、企業価値を
毀損させるばかりか、社員が心身ともに
大きな痛手を被ることになります。
私の愛読誌「日経ビジネス」(2015.01.19 号)に
興味深い記事が掲載されていました。
タイトルは 「お客様は神様」じゃない 。
サブタイトルは、社員を守れぬ会社に先はない。
「日経ビジネス」は冒頭で次のように書いて
います。
(「日経ビジネス」2015.01.19 号 P.044 )
昭和の時代から商売の基本とされてきた
「お客様は神様」。その言葉に象徴される
徹底的な顧客第一主義は、日本企業が
躍進を遂げる上で重要な武器となってきた。
だが、今は時代が変遷。顧客を絶対的存在
と位置付け、“言いなり”になっていると、
社員が心身ともに傷つくばかりか、対応
コストが膨れ上がる事態になりつつある。
すべてのユーザーを満足させようとする
“最大公約数狙い”の商品開発も、むしろ
競争力を落とす要因になってきた。
欲求不満のはけ口を企業に求める反社会的
消費者の出現、ネットの普及で下がる苦情
のハードル、高齢化に伴い増え続ける
“孤独で元気過ぎる”老人たち、製品・
サービスに対する要望の多様化――。
顧客が「神」でなくなった背景は様々だ。
つい最近、異物混入事件が発覚しました。
実際には、容疑者が偽装し、スマホを使い、
ネット上に画像を投稿していました。
悪質な事件です。英雄気取りでした。
罪の意識が希薄です。
「日経ビジネス」は、大阪府茨木市にあるコンビニ、
ファミリーマートの店舗の内部について伝えています。
( P.045 )
大阪府茨木市にあるファミリーマート茨木横江店。
一見して普通のコンビニにしか見えないこの店には、
他の店舗ではまず見ることができない特徴がある。
午後10時に警備員が出勤してくることだ。
警備員は朝5時頃まで店内の事務所に待機し、顧客
と顔を合わせることはない。だが、“有事”の際には
待機所を飛び出し、敢然と店員を守る手はずとなって
いる。
実はこの店は、記憶に新しい「コンビニ土下座事件」
の舞台となった場所だ。
どんな事件だったのか振り返ってみましょう。
( P.045 )
報道によると、2014年9月8日深夜、駐車場で
たむろしていた数人の男女が入店。空のペットボトル
に水を入れろと要求し、店内で飲食を開始した。
抗議した店長に男女は商品を投げつけるなどした上で
土下座を要求。「店に車を突っ込ませる」などと
威嚇し、たばこ6カートンを脅し取ったという。
その後、男女は逮捕。既に執行猶予付きの有罪判決が
下っている。
やったことは、反社会勢力がやることと同じです。
全く勘違いをしています。
彼らは「お客様」ではありません。「犯罪者」です。
一時、どこかしこで「土下座」を強要する、事件が
頻発しました。今は、沈静化していますが。
このような行為は、りっぱな犯罪です。
「日経ビジネス」は次のように「よくある店頭
トラブルと問われる可能性のある罪状」として、
5つに分類しています。
土下座させる ――→ 強要罪(刑法223条)
居座り続ける ――→ 不退去罪(刑法130条)
カネを要求 ――→ 恐喝未遂罪(刑法249条、
250条)
大声を出す ――→ 威力業務妨害(刑法234条)
「異物混入」とウソ ――→ 偽計業務妨害罪(刑法233条)
「土下座」の話は、クレームではありません。
彼らは、「お客様」ではなく、単なる「犯罪者」です。
問題は、これからご紹介する「クレーマー」です。
最近では、言いがかりを吹きかけてくるの従来型
のクレーマーだけでなく、 新種のクレーマー
が出現しました。
後者は、前者以上に厄介な存在です。
まず、従来型でもエスカレートしてきたクレーマー
の例をご覧ください。激情型クレーマーです。
( P.046 )
「数年前に比べ苦情電話の長時間化が進んでいる。
激情型のクレーマーに当たるとベテランでも1時間
は覚悟せざるを得ない」。ある電機メーカーの
コールセンター社員はこう話す。
もちろん、上記のような激情型クレーマーの対応は
厄介です。
ですが、それ以上に厄介な 新種のクレーマー
が出てきました。こちらは対応する社員にとって
深刻さの度合いが全く違います。
( P.046 )
読者の中には「顧客とのやり取りを録音すれば
悪質な電話は減るのではないか」と思う人もいる
だろう。だが、それでも問題は解決しない。
最近は、一切の暴言も怒鳴り声も出さず、淡々と
担当者を追い詰める新種のクレーマーが出てきて
いるからだ。
実際には、どのようなクレーマーなのでしょうか?
担当者にしてみれば、「真綿で首を絞められる」
ような気がするかもしれません。精神的に追い詰め
られてしまう可能性が高い、と感じました。
( P.046 )
ある健康機器メーカーの顧客相談窓口にその
電話がかかってきたのは2014年夏のこと。
声の主は60代後半の男性で、「1カ月前に
購入した血圧計が故障した」というよくある
苦情だった。応対した担当者は謝罪した上で、
マニュアル通り「着払いで血圧計を送ってもら
えば新品に交換する」と申し出て、男性は了承
した。これが、この男性との長い“闘い”の
始まりだった。
一体どうしたことでしょう?
担当者の対応がマニュアル通りだったのが気に入ら
なかったのでしょうか?
実は、そうではなかったのです。
驚くといいますか、呆れるといいますか、
この 新種のクレーマー には、
簡単には太刀打ちできないな、と思いました。
( P.046 )
再び電話が来たのは1週間後。交換した商品にも
不良箇所があったのではと気をもんだ担当者だった
が、男性の口からは思いもよらぬ言葉が飛び出した。
「商品は受け取りました。では次に、なぜ不良品が
発生したのか原因を特定し、報告書を提出してくだ
さい」。
一体どうしてこのような要求を突きつけたのでしょうか?
このクレーマーはどういう人物だったのかを知ると、
対応の難しさがいっそう増幅されることに気づきます。
従来通りのマニュアルでは、対応できない事例です。
( P.046 )
話を聞くと、この男性は大手メーカーで品質保証
部門の責任者を務めた経験があった。そのため
モノ作りの現場に詳しく、原因を一通り説明して
も「そんな品質管理はあり得ない」「検査工程に
こうした課題があるのではないか」と一歩も引か
ない。何度もやり取りを重ね、やっと納得したと
思ったら、「次は、今後の対策をまとめていき
ましょう」と言い出した。
この男性が勘違いしているのは、自分が勤務していた
当時のやり方で、上下関係がないにもかかわらず、
専門知識と経験をひけらかし、メーカーに無茶な要求
をしていることです。
そうは言いましても、こうした 新種のクレーマー が
増えてくると、担当者が強いストレスを感じるように
なり、心の病(うつ病など)を引き起こす場合があり、
企業にとって憂慮すべき問題です。
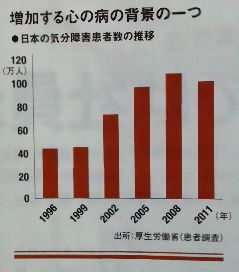
うつ病患者は増加しています。
( P.047 )
会社員の鬱病は年々増加し、厚生労働省によると
躁鬱病を含む気分(感情)障害の国内総患者数は
2011年には95万8000人と12年前の2倍以上に
達した。その一因は、店頭から顧客窓口まで、
企業における顧客対応が困難になっていることに
あるとも言われている。
「コンビニ土下座事件」が発生したり、 新種のクレーマー
が増加している理由は何なのでしょうか?
「日経ビジネス」は3つあると指摘しています。
① 苦情のハードルが下がった
② 反社会的消費者が増加した
③ “元気過ぎる”高齢者が増加した
( P.047 )
まず、多くの専門家が指摘しているのが、ネットの
普及だ。「電話をしてまで言うことじゃない」と
思っていた苦情も気軽に送りつけられるようになった。
格差社会の進展で、欲求不満のはけ口を企業に求める
反社会的消費者が増えたため、という声も根強い。
そしてもう一つ、今回取材した店員やコールセンター
社員のほぼ全員が、言葉を濁しながら、口をそろえて
指摘した理由がある。「孤独で元気過ぎる老人」が
増えていることだ。
企業に問い合わせをしてくる年代別データがあります。
下のグラフを見ると、全体で3分の1以上、「携帯通信」
部門を除き、他の全てで1位を占めているのは、60代
以上です。
定年退職で暇になり、時間を持てあまして、企業相手に
クレームしようとする人たちが増えた、と考えられます。
私は今年で、60代に仲間入りしますが、クレーマーには
なりたくないですよ!!

( P.047 )
「会社中心主義の人生を送ってきたため、女性に
比べ地域に居場所がなく孤独でもある。
彼ら(60代の男性)が持て余したエネルギーを
最もぶつけやすいのは企業。特に逃げ場のない
顧客相談窓口は格好の“標的”になる。実際、
厄介なクレームは団塊が大量退職を始めた時期から
一気に増えた」
大手メーカーのサポート担当者は、あくまで個人的
意見と前置きしながら、こう力説する。
団塊と言うのは、作家の堺屋太一さんが「団塊の世代」
と命名したものを指しています。
一般的に使われています。
団塊の世代とは、「昭和22年から26年頃までに
生まれた人々」を指します。
私が考えたのはこういうことです。
60代以上の男性は、クレームの相談窓口担当者は、
自分よりはるかに年下であると知っていますから、
文句を言いやすい状況にあるということです。
自分を上司に据え、担当者を部下と見立て、教育して
あげているのだ、と考えているかもしれません。
新種のクレーマー にはどう対応したらよいのでしょうか?
クレーム対応のコンサルタント、谷厚志氏は次のように
語っています。
( P.048 )
「プロクレーマーは1000人に1人。こじれる
ケースの大半は、企業側の対応が悪く、モンスター
化していくパターン」。
その対策にはマニュアル整備が欠かせないものの、
「過剰なマニュアル主義」は逆に問題だと言う。
型にはまった融通が利かない対応は、かえって
顧客をいら立たせることことが多いからだ。
本当に厄介な問題ですね。
相手が相手だけに対応が非常に難しいです。
「日経ビジネス」取材班は、次のように結論を
述べています。
( P.049 )
結論から言えば、「お客様はすべて神様だ」という
考えを変え、大胆な割り切りを図るしかない、
となる。
大胆な割り切りによって、「本当に大切なお客様」と
「大切な社員」を守ることができるのです。
今回のテーマはいかがだったでしょうか?
新種のクレーマー が出現していたとは驚きました。
あなたがもし、サポート担当者だったとしたら、
新種のクレーマー にうまく対応する自信はありますか?
私は恐らく、相手に言いたいだけ言わせた上で、
「ここまではできますが、これ以上はできません」
とはっきり言い渡します。
それでも相手が納得しないのなら、「消費者庁にでも
訴えてください」と言ってしまうかもしれません。
雇われている人間は辛い立場で、もし私のような対応
をしたら、異動させられるか、会社に損害を与えた
という理由で解雇されるかもしれません。
そうしたら、今度は私がクレーマーになってしまう?
いえ、なりません!
藤巻隆(ふじまき・たかし)オフィシャルブログ-
人気のブログランキング
こちらのブログもご覧ください!
こんなランキング知りたくないですか?
中高年のためのパソコン入門講座(1)
藤巻隆のアーカイブ