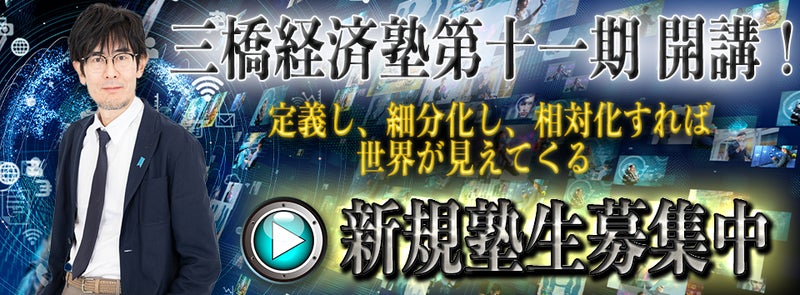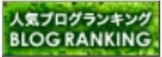株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから
三橋貴明のツイッターはこちら
人気ブログランキングに参加しています。
チャンネルAJER更新しました。
「食団連発足とコストプッシュ型インフレの正体」(前半)三橋貴明 AJER2022.5.3

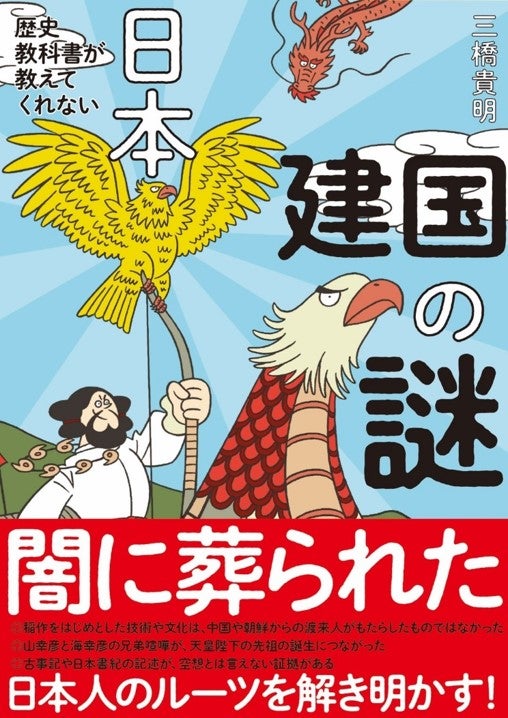
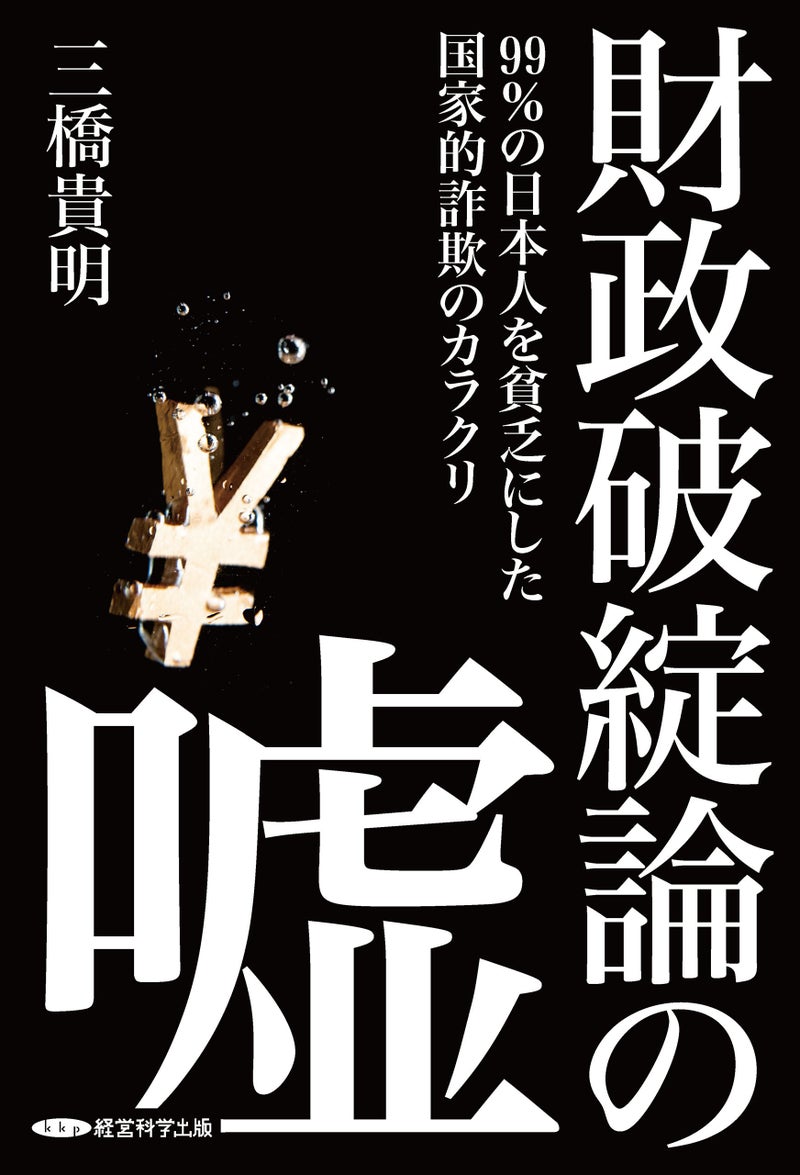
令和の政策ピボット呼びかけ人に「HAL YAMASHITA東京 エグゼクティブシェフ 社団法人日本飲食団体連合会 副会長 山下春幸」様が加わって下さいました。
また、メルマガ「令和ピボットニュース」が始まりました。皆様、是非とも、メルマガ登録を!
「元本割れしない」ことを魅力に国債を売る財務省の意味不明!?[三橋TV第550回]三橋貴明・高家望愛
【山下春幸さんのハル・ヤマシタ(東京ミッドタウン)にお伺いいたしました】
※高家さんと二人きりで行ったわけではありません。念のため。
日本国民は、デフレ(需要不足)が継続する中、コストプッシュ型インフレで国民の可処分所得が減るという二重苦状態になっています。
総需要不足は、「生産数量」を減らすため、実質賃金を低下させます。その状況で、「国民の所得は増えない」輸入物価上昇に起因するコストプッシュ型インフレ。
日本国民は二つのルートで「可処分所得減少」に見舞われているわけで、政府の対策は必至です。
ちなみに、輸入物価上昇に起因するコストプッシュ型インフレは、民間最終消費支出を増やしますが、輸入増でオフセットされます。つまりは、名目の需要すら増えません。
一つだけ、安心材料があり、それは「日本銀行」がまともであることです。正直、日本政府にこれほどまともな機関があるとは、と、ビックリするレベルです。
4月11日の参院決算委員会における、日本銀行の西田昌司参議院に対する答弁、
『現在の状況についてお答え申し上げます。ウクライナ情勢を受けました供給不安に起因する資源・穀物価格の上昇は、短期的にはエネルギー・食料品を中心に、物価の押し上げ要因となる一方、家計の実質所得の減少や、企業収益の悪化を通じまして、国内需要の下押し要因となります。このことは感染症からの回復がなお道半ばにある我が国経済に悪影響を与え、長い目で見れば、基調的な物価上昇率の低下要因ともなり得ます。』
これは、相当に「安心感」を覚えました。
コストプッシュ型インフレが、国内需要下押し要因になることを理解している(当たり前なのですが)。
そして、日本銀行は、現在のコストプッシュ型インフレに対しては、「財政政策」で対応するべきと結論付けています。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【経世史論】三橋貴明と「歴史に魅せられて my」がお送りする、経世史論。
http://keiseiron-kenkyujo.jp/keiseishiron/
第四十回「皇統論 平将門の乱-坂東燃ゆー」「歴史時事 ウクライナ国民共和国」がリリースになりました。
ぜひ、ご入会下さい。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
『コストプッシュ型インフレ、財政政策で対処を=日銀研究会
日銀は23日、3月に開催した日本の物価を議論するワークショップの詳細を公表し、外部の識者から、商品市況の上昇が主導するコストプッシュ型インフレには金融政策ではなく財政政策で対処するのが適切だとの指摘が出ていたことが分かった。黒田東彦総裁ら幹部は、改めて金融緩和の継続が重要だと語った。
日銀は23日、3月に開催した日本の物価を議論するワークショップの詳細を公表し、外部の識者から、商品市況の上昇が主導するコストプッシュ型インフレには金融政策ではなく財政政策で対処するのが適切だとの指摘が出ていたことが分かった。
日銀はコロナ禍での欧米と日本の物価動向の違いなどを分析し、学識経験者と議論を深める目的でワークショップを開催した。
渡辺努・東京大学教授は、日本は感染症拡大前から続く「慢性デフレ」と、商品市況の上昇などを受けた「急性インフレ」の2つの問題にそれぞれ適切に対応する必要があり、金融政策運営上も難しい局面にあると指摘した。
これに対し、小林慶一郎・慶應義塾大学教授は「急性インフレのリスクは財政政策で対応し、慢性デフレのリスクには金融緩和の継続で対応していくことが適切だ」と述べた。日銀の内田真一理事(企画局担当)は、小林教授の見解に賛同した上で「低成長で金利のゼロ制約にヒットする可能性が大きい日本では、慢性デフレのリスクの方が大きい」との見方を示した。(後略)』
小林慶一郎教授の「財政政策」が、具体的に何を指すのか分かりませんが、とりあえず「日本銀行の利上げ」が必要な局面があるとすれば、
「国民がカネを借りまくり、インフレ率が適正な水準を超えて上昇していく」
場合のみです。
円安は、確かにコストプッシュ型インフレの背中を押していますが、問題になっているのは「円安」そのものではなく「輸入物価上昇」であることを勘違いしてはなりません。
現在の日本国民は、輸入物価上昇に起因するコストプッシュ型インフレに苦しんでいる。ならば、政府の対策は、
「減税や給付により、国民の可処分所得を引き上げる」
が正解になります。(小林教授の言う「財政政策」が、上記であれば、感動するのですが)
日銀の研究会の言う通り、コストプッシュ型インフレへの対処は財政政策以外には有り得ません。
この状況で、PB黒字化目標を続けるとなると、政府は「国民の苦境を救う気はない」と宣言したのも同然なのです。
「コストプッシュ型インフレへの対処は財政政策で!」に、ご賛同下さる方は、
↓このリンクをクリックを!
本ブログへのリンクは以下のバナーをお使いください。
◆関連ブログ
日本経済復活の会のホームページはこちらです。
㈱日本富民安全研究所のブログ絶望の先にはこちらです。
◆三橋貴明関連情報
新世紀のビッグブラザーへ ホームページはこちらです。
メルマガ「週刊三橋貴明~新世紀のビッグブラザーへ~」はこちらです。