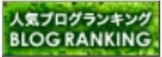株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから
三橋貴明のツイッターはこちら
人気ブログランキングに参加しています。
チャンネルAJER更新しました。
「構造改革路線を改革せよ」(前半)三橋貴明 AJER2020.9.7


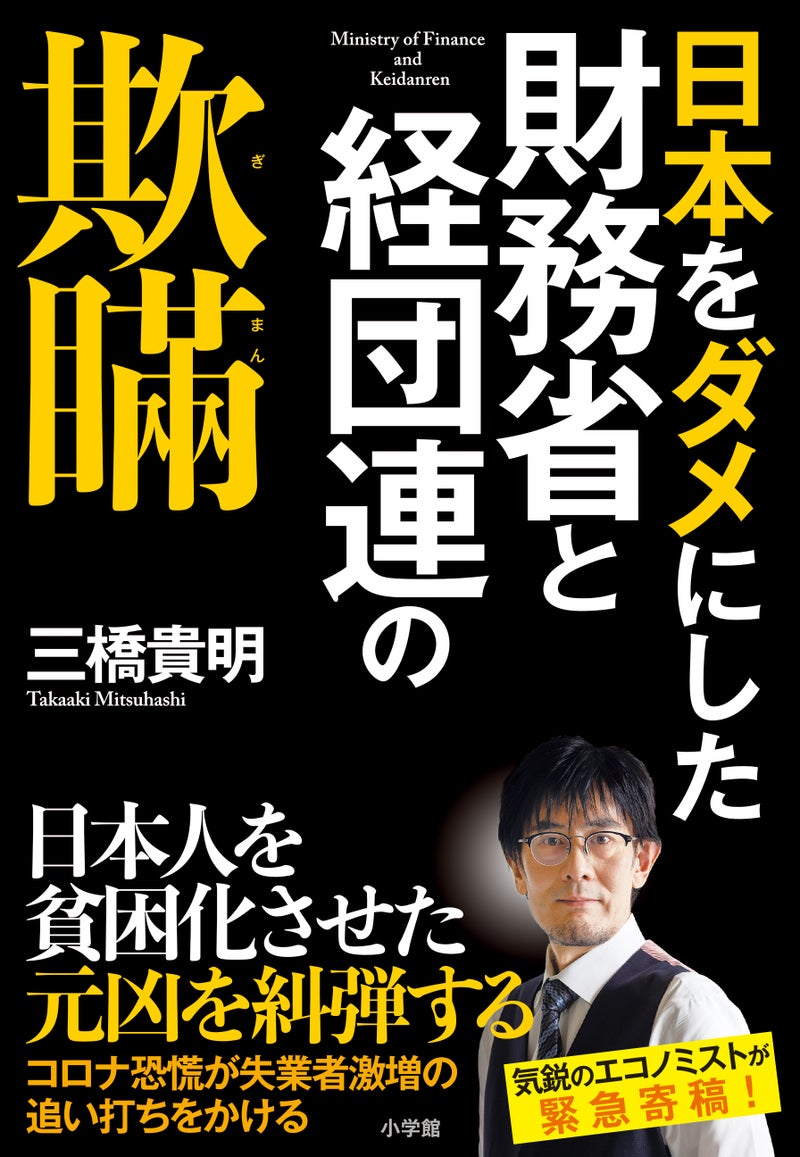
令和の政策ピボット呼びかけ人に「株式会社マネネCEO・経済アナリスト 森永康平様」が加わって下さいました。
また、メルマガ「令和ピボットニュース」が始まりました。皆様、是非とも、メルマガ登録を!
成長を知らない子供たちへ また「キラキラした日本」に戻せるよ [三橋TV第441回] 三橋貴明・高家望愛
自民党総裁選挙に出馬表明した河野太郎が、
「派閥をまとめることは全く必要がない」
「国のリーダーを選ぶわけだから、議員一人一人が誰がいいかを決めて投票するのが筋だ。グループでまとまって誰を選べというのは民主主義ではない」
と、発言しています。
なるほど。古臭い平成の政治家らしい、派閥観だと思います。
2021年8月時点、自民党の国会議員は385人。自民党議員の力は絶大に見えて、実は一人一人は385分の1の権力しか持っていないのです。
だからこそ、「政策集団」としての派閥が必要になる。理由は、派閥であろうがグループであろうが、「385分の1の権力」の国会議員が自分の政策を実現したいならば、連携するしかないためです。
無論、「全ての政策」が同じである必要はありません。政策により、所属グループを変えても構わないわけですが、いずれにせよ「国会議員一人では何もできない」というのが民主制(民主「主義」ではない)の真実です。
国のリーダーを選ぶという、「究極的な政策」の選択である以上、国会議員たちはじっくりと「議論」する必要があります。その上で、「連携」して投票しない限り、「自分にとってマシ」な結果は望めないのです。
つまりは、派閥(別に呼称は何でも構いませんが)という「中間組織」が適切に機能しない限り、日本の民主制もまた、適切に機能しない。(日本だけじゃないですが)
90年代後半の政治改革以降、小選挙区制、政党助成金により、派閥の力は弱体化しました。同時に「政策集団」としての議論も消滅した。
何しろ、小選挙区制では党中央の権力が肥大化します。党総裁(首相)の政策に反対すると、公認してもらえない。それどころか「刺客」を送られる。(実際に、これをやったのが小泉純一郎)
さらに、政党以外への企業・団体献金が禁止されます。となると、国会議員はますます党中央に逆らえない。
結果的に、竹中平蔵やデービッド・アトキンソンといったレント・シーカー(政商)が政府の諮問会議に入り込み、「自分の利益」のための政策を「首相指示」として推進する現在の構造に至りました。(というか、そうしたかったんでしょうね。今にして思えば)
しかも、内閣人事局設置以降は、官僚までもが官邸に逆らえない。
もはや「嘲笑」したくなるのですが、未だに90年代の政治改革の「間違った思想」を頑なに信じ、中間組織としての派閥を否定し、「議員一人一人が決めればいい」などと、ナイーブ(幼稚)なことを口にする連中が、政権の中核に多いわけです(国民もそうでしょうけど)。
いや、本当に「議員一人一人が決める」などとやったら、政策議論をすっ飛ばした、単なる人気投票になってしまうでしょうが。そうなると、マスコミを巧く活用した者が勝つ。
大阪の維新の連中が得意とする手法ですね。中間組織を破壊し、有権者を「個人化」した上で、マスコミを利用して情報を一方的に送り込み、議論(あるいは議会)をパススルーして「自分の利益」のための政策を実現する。分かりやすく表現すると「ナチス手法」です。
【三橋貴明の音声歴史コンテンツ 経世史論】
https://keiseiron-kenkyujo.jp/keiseishiron/
※要望多数につき、評論家・中野剛志先生 【通貨論争史:イギリス編】【通貨論争史:日本編】が再掲となりました。
『総裁選が揺らす派閥政治 問われる政策の求心力 恩恵薄れて縛りきかず
自民党総裁選で派閥の動きがまとまらない。支援する候補を一本化できたのは会長の岸田文雄氏を推す岸田派くらいで、ほかの派閥は所属する国会議員を縛れていない。資金やポストの面倒をみるのが派閥から党執行部に代わり、議員にとって派閥に尽くす恩恵が薄れた。今回の総裁選は本来なら求心力であるべき政策不在の派閥のありさまを浮き彫りにしている。(後略)』
日経新聞が、珍しく真っ当な「派閥」の記事を書いています。
『(引用)政策面でも各派閥の特徴ははっきりしていた。
例えば池田勇人元首相の「所得倍増計画」や、田中角栄元首相の「日本列島改造論」や中国との国交正常化など、派閥の領袖が主に経済や外交で政策を掲げた。派閥はその実現を旗印に結束し、派閥トップを総裁に押し上げる原動力に変えた。
今の派閥に政策の色は薄い。』
そう。かつての派閥は「政策」が異なっていた。つまりは、派閥内、派閥間の「議論」があった。
首相の虚偽答弁等の「政治家の問題」が派生したら、対立する派閥の力で引きずり降ろされた。故に、ある程度の「自浄能力」があった。
ところが、政治改革以降は派閥の「政策議論」「自浄作用」が消滅し、単なる政局の数合わせになってしまった。
そして、未だに河野太郎のように、民主制における中間組織の重要性、必要性を理解できず、「有権者が一人一人で決めればいい」などと、甘っちょろいことを口にする政治家が跋扈している。
現実を認めましょう。我々や国会議員一人一人の「主権の力」はあまりにも小さい。だからこそ、中間組織(グループ)で議論し、連携して動く必要があるのですよ。
「今こそ財政出動への競争を!」に、ご賛同下さる方は、↓このリンクをクリックを!
本ブログへのリンクは以下のバナーをお使いください。
◆関連ブログ
日本経済復活の会のホームページはこちらです。
㈱日本富民安全研究所のブログ絶望の先にはこちらです。
◆三橋貴明関連情報
新世紀のビッグブラザーへ ホームページはこちらです。
メルマガ「週刊三橋貴明~新世紀のビッグブラザーへ~」はこちらです。