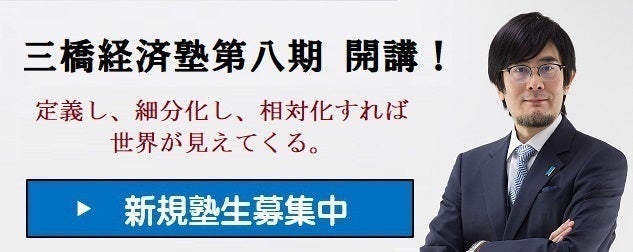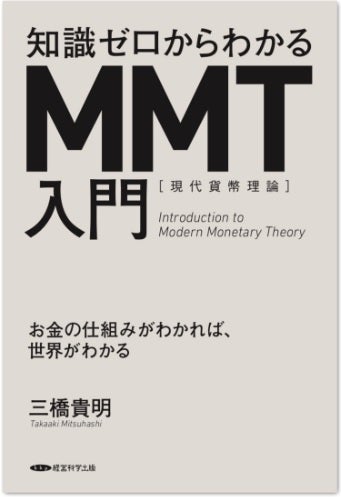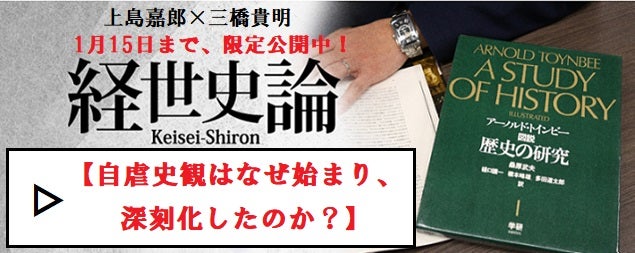株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから
三橋貴明のツイッターはこちら
人気ブログランキングに参加しています。
チャンネルAJER
『日本の少子化をくい止めるにはーその2ー(前半)』三橋貴明 AJER2019.10.22
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
12月21日(土)シンポジウム「令和の政策ピボットは実現可能なのか?」が開催されます。
また、メルマガ「令和ピボットニュース」が始まりました。皆様、是非とも、メルマガ登録を!
三橋TV第164回【国産のステルス戦闘機作ろうぜ!】
三橋経済塾の講義で青木泰樹先生が解説して下さいましたが、MMT(現代貨幣理論)は「特殊理論」です。
特殊理論とは、特定の条件を満たせば必ず成り立つという意味になります。MMTは、いかなる国も、どんな時にも成り立つ一般理論、あるいは普遍理論ではないのです。
三橋TVの、
三橋TV第157回【外為市場・国債市場から政府をコントロールする「奴ら」】
三橋TV第158回【ロシアのデフォルトから学ぶ国際金融資本のやり口】
で解説した通り、MMTがフルに有効となるのは、日本やアメリカのような主権通貨国、つまりは独自通貨国でかつ変動相場制の国になります。
三橋TV第157回【外為市場・国債市場から政府をコントロールする「奴ら」】
三橋TV第158回【ロシアのデフォルトから学ぶ国際金融資本のやり口】
で解説した通り、MMTがフルに有効となるのは、日本やアメリカのような主権通貨国、つまりは独自通貨国でかつ変動相場制の国になります。
厳密には、わたくしは上記二「供給能力がそれなりに有る」という条件を付け加えるべきだと思いますが、いずれにせよユーロ加盟国は全滅です。
イギリスはどうでしょう? イギリスは、主権通貨国ではありますが、「EU」という国際協定に加入したままで、財政ルールに違反をすると、「過剰財政赤字是正」の措置を取られます。
つまりは、完全なる主権問題である「財政」に、EUの官僚たちが嘴を突っ込んでくるのです。EUのルールでは、過剰財政赤字を是正するために、各国の財政をEUの監視下に置けることになっています。
というわけで、EU離脱前のイギリスは、とりあえずはMMTはフルに成り立たないように思えます。離脱後は、別ですが。
『監訳者に聞く 「MMT(現代貨幣理論)」とは何か?(1)
◆貨幣や財政の「現実」を説明するMMT
――MMTとはどういう理論でしょうか。
島倉氏(以下、島倉) MMTには2つの側面があります。まず1つは、貨幣や財政が現実にはどのようなものであるかを説明する理論としての側面です。もう1つは、そうした現実に基づいて、「経済政策はこうすべきである」と提言する理論としての側面です。
『MMT入門』の帯にもあるように、MMTの主張として、以下の3点があげられます。1つ目は、日本や米国のように「通貨主権」を有する政府は、「自国通貨建て」で支出する能力に制約はないというものです。
「通貨主権」とは、自国通貨を固定レートで金(きん)や外貨と交換する約束をしていない、すなわち変動為替相場制を採用していることを意味します。こうした政府は自国通貨をいくらでも発行できるので、デフォルト(債務不履行)を強いられるリスクはありません。従って、「財政赤字や国債残高を気にするのは無意味」という結論になるのです。(後略)』
◆貨幣や財政の「現実」を説明するMMT
――MMTとはどういう理論でしょうか。
島倉氏(以下、島倉) MMTには2つの側面があります。まず1つは、貨幣や財政が現実にはどのようなものであるかを説明する理論としての側面です。もう1つは、そうした現実に基づいて、「経済政策はこうすべきである」と提言する理論としての側面です。
『MMT入門』の帯にもあるように、MMTの主張として、以下の3点があげられます。1つ目は、日本や米国のように「通貨主権」を有する政府は、「自国通貨建て」で支出する能力に制約はないというものです。
「通貨主権」とは、自国通貨を固定レートで金(きん)や外貨と交換する約束をしていない、すなわち変動為替相場制を採用していることを意味します。こうした政府は自国通貨をいくらでも発行できるので、デフォルト(債務不履行)を強いられるリスクはありません。従って、「財政赤字や国債残高を気にするのは無意味」という結論になるのです。(後略)』
【歴史音声コンテンツ 経世史論】
※11月5日から上島嘉郎先生と三橋貴明の対談「自虐史観はなぜ始まり、深刻化したのか」がご視聴頂けます。
ランダル・レイ教授の「MMT 現代貨幣理論入門 https://amzn.to/35eHjyL 」の監訳を務めた島倉原氏が、インタビューでMMTについて解説しています。(連載されるようですね)
上記の「自国通貨を固定レートで金(きん)や外貨と交換する約束をしていない」という部分は結構重要で、逆に言えば固定為替相場制の国は、MMTは成立しません。三橋TV158回で、ロシアの事例を挙げていますが、例えばロシアが1ドル=6ルーブルの固定為替相場制を採用していた場合、ルーブル建て国債であっても外貨建て(ドル建て)国債とイコールになってしまうのです。
外貨建て国債、共通通貨建て国債、固定為替相場制下の自国通貨建て国債は、そりゃあ、財政破綻(デフォルト)する可能性はありますよ。
また、後略部で島倉氏が解説していますが、スペンディングファースト(徴税よりも支出が先)は単なる事実であり、誰にも否定できません。財源としての税金は、論理的には不要です。
となると、すぐに、
「じゃあ、無税国家誕生だな、ケラケラ」
といった感じで、MMTを揶揄し、バカにし、貶め、MMT全体を否定しようとする連中が出てきますが、税金には少なくとも、
1.ビルトインスタビライザー(埋め込まれた安定化装置)
2.所得再分配
3.租税貨幣論
4.政策的税制
と、四つの役割があり、税金を無くすことなどできるはずがありません。(無政府状態を望むなら別ですが)
4番目の政策的税制といえば、消費税は「国民の消費を抑制する」という政策目標を持った税金です。というか、他に政策的な役割はありません。
安定財源(事実ですが)という消費税の特徴は、1の安定化装置、2の所得再分配が「無い」という話であり、消費税が「欠陥税制」である根拠にしかならないのです。
いずれにせよ、特殊理論であるMMTの適用性は、
1.主権通貨国(独自通貨国)
2.変動為替相場制
3.通貨暴落やインフレ率急騰のリスクが小さい
2.変動為替相場制
3.通貨暴落やインフレ率急騰のリスクが小さい
の、三つの条件を満たせば満たすほど、強くなります。
上記を理解したとき、世界最大の対外純資産国で、インフレ率急騰どころかデフレで苦しめられている我が国が、
「世界で最も潜在力が大きい国」
であることが理解できるはずなのです(基軸通貨国のアメリカは除きますが)。
MMTが説明した「貨幣の真実」は、我が国が「正しい財政政策」により繁栄することが(まだ)可能であることを証明しました。
デフレが継続すると、次第に供給能力が衰え、財政拡大とインフレの相関性が強くなってしまいます。供給能力が残されている今、
「政府の財政政策による需要拡大⇒デフレ脱却⇒生産性向上の投資による供給能力拡大⇒実質所得上昇による需要拡大」
という経済成長の黄金循環を取り戻すのです。急がなければなりません。
「経済成長の黄金循環を取り戻せ!」にご賛同下さる方は↓このリンクをクリックを!
本ブログへのリンクは以下のバナーをお使いください。

◆関連ブログ
日本経済復活の会のホームページはこちらです。
◆三橋貴明関連情報
新世紀のビッグブラザーへ ホームページはこちらです。
メルマガ「週刊三橋貴明~新世紀のビッグブラザーへ~」はこちらです。