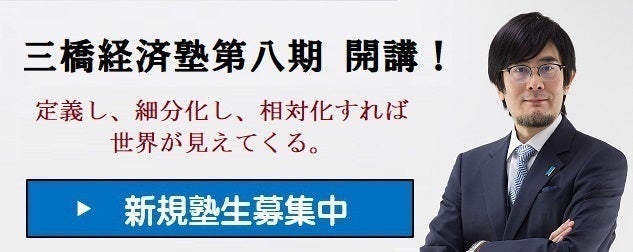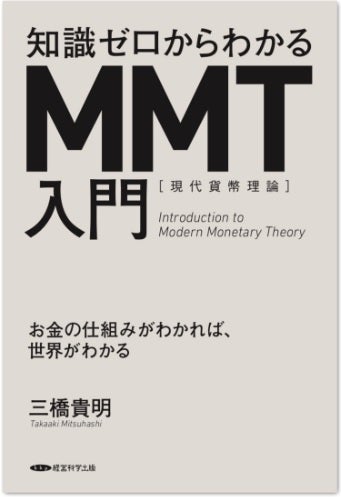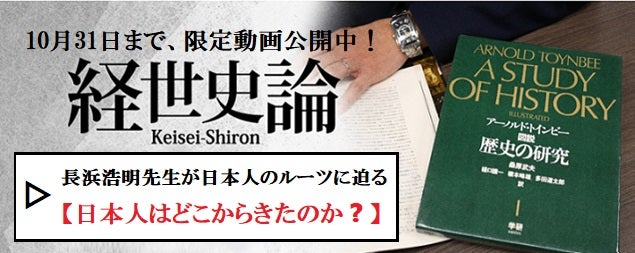株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから
三橋貴明のツイッターはこちら
人気ブログランキングに参加しています。
チャンネルAJER
『日本の少子化をくい止めるにはーその2ー(前半)』三橋貴明 AJER2019.10.22
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
令和の政策ピボットの呼びかけ人に、経済評論家・株式会社クレディセゾン主任研究員の島倉原氏が加わって下さいました。
また、メルマガ「令和ピボットニュース」が始まりました。皆様、是非とも、メルマガ登録を!
三橋TV第155回【質問回答編② MMTはハイパーインフレでヘッジファンドで国債暴落で日銀破綻!?】
昨日は、「あんどう裕と語る会 in 東京」でございましが、講演の後に出てきた質問がハイレベル過ぎてビビりました。
潜在GDPの計算方法の問題とか、TFP(全要素生産性)とか、普通はそんな用語出てきませんて。昨日集まられた皆様は、恐らく、日本で(下手したら「世界で」)最もハイレベルな質問者たちだと思います。
(別に、プレッシャーかけているわけではないですよ。今後も、基本の基本から質問されて構いませんからね。質問に答えることで、講演者側も学び、レベルもアップしていくものです)
長引くデフレにより「経済」に関心を持つ方々増え、インターネットで情報が共有され、我が国の「経済議論」は世界最高峰に達しているのだと思います。(良い話でもあり、悪い話でもある)
昨日、解説しましたが、経済成長は、
● 労働投入量
● 資本投入量
● 全要素生産性(TFP)
の三つで決まります。
うち、事前に予測がつくのは「労働投入量」のみです。資本投入量やTFPは、
「経営者がノリで投資を決めたら、資本投入量が増えた」
「なんだかわかんないけど、なぜか生産性が上がった」
ということが起き得るというか「普通」であるため、経済学者には、いや「人間」には事前の予想が全くつきません。
だからこそ、経済学者は、
「経済成長のためには、労働者を増やせばいい」
と、つまらないことを言うのです。この手の経済学者の言論が「人口減少衰退論」に繋がりました。
あの、まともそうなポール・クルーグマンですら、
「日本の経済成長のためには移民受入が必要だ」
と発言したので、吃驚したことがあります。
要するに、経済学者はよく分からん「資本投入(=投資)」「生産性」といった概念を扱うのが、面倒くさくて嫌なのだと思います。何しろ、あやふやで、よう分からんので、数式モデルにできない。
というわけで、「語る会」でも語りましたが、結局のところ「インフレ率」を唯一の手掛かりに、臨機応変、機動的に財政政策を決めていくしかないのだと思います。
さて、供給能力(潜在GDP)から総需要(名目GDP)を差し引いた値を「デフレギャップ(総需要の不足)」と呼びます。このデフレギャップの「存在」こそがデフレの真因です。
なぜ「存在」と書いたかと言えば、逆,総需要から供給能力を差し引いたインフレギャップは、「存在」し得ないためです。
※特別コンテンツ「MMTポリティクス 第三回」が視聴可能となりました。
※12月12-13日、邪馬台国視察ツアー「歴史に魅せられて、マイと辿る邪馬台国への道」開催決定!(三橋貴明、長浜浩明先生、高家望愛さんも同行します)取材の光景は、映像で記録し、特別コンテンツとして配信したいと思います。
「あなたは、一日に100個、生産できます。本気になれば」
という状況があったとしましょう。その状況で、需要(買い手)が90しか買ってくれなければ、10のデフレギャップになります。これは、誰にでも分かりますよね。
それに対し、インフレギャップは、
「あなたは、一日に100個生産できるが、需要は110だった」
という話になってしまいます。↑この場合、インフレギャップ10ですが、そもそも「生産不可能なものが、需要される(買われる)って、どういうことだ、こらあっ!!!」と思わなければなりません。
つまりは、供給能力が需要に追い付かなかったとして、「計算」されるインフレギャップは常にゼロなのです。
図で、インフレギャップが計算されるように見えますが、あくまで「概念」的なものなので、ご注意下さい。
さて、上記を理解した上で、以下の記事。
日銀は3日、4─6月期の需給ギャップが1.04%になったとの試算を発表した。1─3月期の1.64%(改定値)から需要超過幅が縮小した。プラスは11四半期連続。プラスの連続記録は2005年10─12月期から08年7─9月期までの12四半期連続以来。
内訳をみると、資本投入ギャップがプラス0.58%、労働投入ギャップが同0.47%となり、それぞれ前四半期の同0.96%、同0.68%からプラス幅が縮小した。需給ギャップは2四半期連続でプラス幅を縮小したが、これは2%台に上昇した18年10―12月期の反動や振れの大きい非製造業の資本投入ギャップによるもので、需給ギャップの基調に変化はないとみられる。 』
「我が社は本気になれば、一日に100個、生産できる」
という、正しい潜在GDP、供給能力に基づく「最大概念の潜在GDP」ではなく、
「過去の生産の平均は、一日に95個だった」
という、「平均概念の潜在GDP」で計算しています。結果、潜在GDPが低く見え、インフレギャップが「計算」されてしまう。
つまりは、生産不可能なものが、買われているという意味不明な状況になっているわけです。
しかも、平均概念の潜在GDPは、デフレで総需要(名目GDP)が低迷すれば、減少していく。何しろ、過去の生産の平均でございますので。
ご存知の通り、最大概念の潜在GDPを平均概念に変えたのは、竹中平蔵氏です。(彼が大臣だったとき。2004年)
潜在GDPが平均概念に変えられた結果、我が国はデフレギャップが小さく見える、あるいはデフレでも「インフレギャップが計算される」という奇妙奇天烈な状況に陥ってしまったのです。
それにも関わらず、この種の知識を政治家が持ちません。
その上で、
「いや、もうデフレではありませんよ。何しろ、デフレギャップは消えている」
といった官僚の答弁を、そのまま信じています(総理までもがそうでした。本人から聞いた)。
もっとも、一般の国民の方が「正しい知識」を身に着け、統計のおかしさを追求する状況になっています。
政治家が「国民のレベルの鏡」であるならば、我が国には政治力をレベルアップさせる「潜在能力」が蓄積されつつあるのです。
学び、発言して下さい。国民のレベルを引き上げ、政治に声を出すことこそが、我が国の「衰退途上国」化を食い止める唯一の道なのです

◆関連ブログ
日本経済復活の会のホームページはこちらです。
◆三橋貴明関連情報
新世紀のビッグブラザーへ ホームページはこちらです。
メルマガ「週刊三橋貴明~新世紀のビッグブラザーへ~」はこちらです。