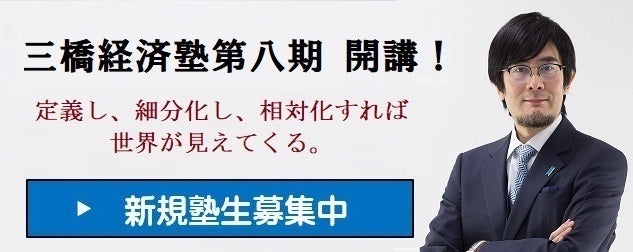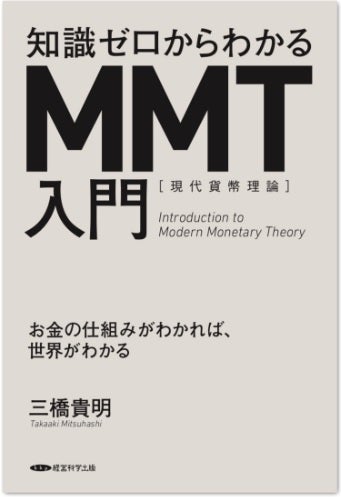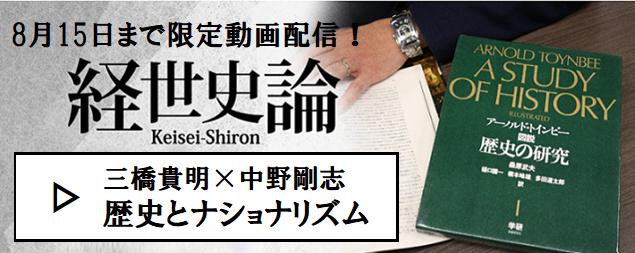株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから
三橋貴明のツイッターはこちら
人気ブログランキングに参加しています。
チャンネルAJER
『MMTとハイパーインフレ論者(その2)(前半)』三橋貴明 AJER2019.7.9
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
三橋TV第124回【新・貧困ビジネス「シェアリング・エコノミー」】
マッチポンプとは、
「マッチで火をつけ、ポンプで水を掛けて火を消す」
という、偽善的な自作自演の手法・行為を意味する和製外来語になります。
「マッチで火をつけ、ポンプで水を掛けて火を消す」
という、偽善的な自作自演の手法・行為を意味する和製外来語になります。
日本に巣くうグローバリストたち(※代表はもちろん竹中平蔵氏)は、
「自らのビジネスのために社会構造を叩き壊し、壊された結果、問題が生じると、新たなビジネスを売り込む」
という、悪魔も怯えるほど邪(よこしま)な手法を平気で推進します。
97年の橋本政権以降、我が国は公共投資を削りに削り、2018年度の公的固定資本形成はピークと比較し、56%の水準でしかありません。
半分近くも、公的固定資本形成(公共投資から用地費等GDPにならない支出を省いたもの)を減らしたのです。
【日本の公的資本形成(左軸)と対GDP比率(右軸)】
結果的に、日本の土木・建設産業は衰退。すでに13万社以上(!)が姿を消しました。
何しろ、日本政府は公共投資を容赦なく削減すると同時に、公共入札の一般競争入札化、談合廃止と、競争を激化する規制緩和を推進しました。
結果、
「地域を守る土木・建設業を、政府が予算と規制で保護する」
という、自然災害大国である以上「当然」の政策が不可能となり、削られるパイを、地域ではなく「全国」の業者で奪い合い、価格を叩き合うという恐るべき事態になってしまったのです。
当然ながら、土木・建設会社は弱いところから消えていきました。仕事柄、廃業に際して自殺した経営者を幾人も知っています。日本政府の緊縮財政、規制緩和は、人殺しというか「国民殺し」の政策なのです。
最近は、ようやく、
「自然災害大国の日本は、公共投資を増やし、供給能力を拡大しなければならない」
「ある程度の競争と存続を両立させるため、一般競争入札や談合は必然だ」
と、わたくしや藤井先生などが10年以上前から叫び続けてきた「当たり前のこと」に対し、理解が広がりつつあります。
2008年(リーマンショック前)頃は、
「日本は公共投資を増やさなければならない」
「どこの世界に公共サービスを全て一般競争入札にしているバカな国があるんだ! NASAにしても、随契と指名競争入札、一般競争入札を組み合わせているぞ。だいたい、指名競争入札や談合を目の敵にしているマスコミの連中は、自分の家を建てる時に一般競争入札にするのかよ!」
と主張したとしても、ひたすらサンドバックのように殴られる状況でございました。
「日本は公共投資を増やさなければならない」
「どこの世界に公共サービスを全て一般競争入札にしているバカな国があるんだ! NASAにしても、随契と指名競争入札、一般競争入札を組み合わせているぞ。だいたい、指名競争入札や談合を目の敵にしているマスコミの連中は、自分の家を建てる時に一般競争入札にするのかよ!」
と主張したとしても、ひたすらサンドバックのように殴られる状況でございました。
【歴史音声コンテンツ 経世史論 始動!】
公共投資を地域別に見ると、南関東(東京圏)に「選択と集中」がなされており、日本政府は明らかに「地方」を見捨てています。東北地方は、震災の影響で公共投資が増えていましたが、2016年に早くも減少に転じ、今後は減らされる一方になるでしょう。
『東経連、国交省に予算措置要望/公共投資で復興、成長へ
東北の経済5団体で組織する「東北の社会資本整備を考える会」(代表・東北経済連合会、会長=海輪誠・東北電力会長)は6日、国土交通省を訪ねて山田邦博技監と面会し、復興事業や東北全体の社会資本整備への予算措置などを求めた。今回の要望は、7月3日に仙台市内で開催した「フォーラム『がんばろう!東北』」で採択したもの。継続的な公共投資を通じた、震災復興とインフラ整備による持続的な成長を訴えた。』
東北の経済5団体で組織する「東北の社会資本整備を考える会」(代表・東北経済連合会、会長=海輪誠・東北電力会長)は6日、国土交通省を訪ねて山田邦博技監と面会し、復興事業や東北全体の社会資本整備への予算措置などを求めた。今回の要望は、7月3日に仙台市内で開催した「フォーラム『がんばろう!東北』」で採択したもの。継続的な公共投資を通じた、震災復興とインフラ整備による持続的な成長を訴えた。』
2014年には、地域の「担い手」としての土木・建設業発展のための「改正品確法(公共工事の品質確保に関する法律の一部を改正する法律)」が制定されました。
一応、地域の土木・建設業衰退を「問題」として捉える政治的な動きはあるのです。とはいえ、間に合わないかも知れません。
理由は、公共投資の削減や、土木・建設業衰退を「ビジネスチャンス」として捉える勢力が勃興しているためです。すなわち、シェアリング・エコノミーです。
三橋TV第124回で室伏先生が紹介して下さった「総務省における シェアリングエコノミーに関する取組について」の最新版がこちらです。
うわっ! 本当に、「雪かき」に関する青森市弘前市の事例がトップに掲載されています。
弘前市がシェアエコを採用する理由は、
・高齢者等の自宅玄関口における寄せ雪の除雪作業のマンパワー不足
・雪の処理場所の不足
とのことですが、本来は行政が予算を支出し、場所や人材の確保をすれば済む話です。
ところが、緊縮財政。しかも、すでに豪雪地帯においても土木・建設業が衰退し、冬に雪かきを受けてくれる業者すら消滅しつつあります。
となると、「民間活用」ということで、今後は雪かきのみならず、インフラ系においても、予算不足に苦しむ自治体がシェアエコに丸投げ、誰も責任を取らない形で「民-民」の取引が進み、間に入ったプラットフォーマーがぼろ儲けしていくのでしょう。
当然ながら、プラットフォーマー(あるいは低賃金労働者)として「外国」が入ってくることになります。というか、すでにAirbnbやウーバーなどの外資系巨大会社が入ってきていますが。
緊縮財政、規制緩和、自由貿易。見事なまでの、グローバリズムのトリニティ。
しかも、緊縮財政や規制緩和を叫び、日本の土木・建設産業を衰退させた連中が、今度は「シェアエコで」などと言い出すわけですから、まさに悪魔も怯える邪さでございますよ。
というわけで、とにもかくにも緊縮財政路線を終わらせない限り、我が国は「邪なビジネス」の「発展」は続きます。
問題を鳥瞰的に理解し、大本の緊縮財政だけでも、早期に終わらせる。そのためには、変な話ですが、現在の日本でもてはやされているシェアリング・エコノミーは、絶好の事例なのでございます。
「緊縮財政の早期終結を!」に、ご賛同下さる方は、↓このリンクをクリックを!
本ブログへのリンクは以下のバナーをお使いください。
◆関連ブログ
日本経済復活の会のホームページはこちらです。
日本経済復活の会のホームページはこちらです。