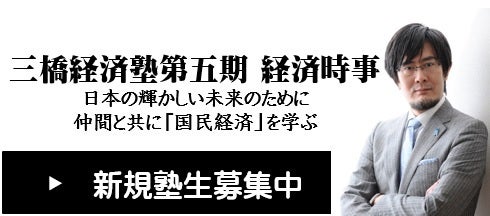
株式会社経世論研究所 講演・執筆依頼等、お仕事のご依頼はこちらから
三橋貴明のツイッター
はこちら
人気ブログランキング
に参加しています。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
『日銀総括検証を検証する①』三橋貴明 AJER2016.10.18
https://youtu.be/hZui036Rvxg
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
一般参加可能な講演会のお知らせ。
11月18日(月) 平成28年度 東ト協ロジ研第2回オープンセミナー
限定二十五名様のみ、弊社からお申し込み可能です。
https://ws.formzu.net/fgen/S55219779/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「月刊WiLL (ウィル) 2016年 12月号 」に連載「反撃の経済学 世界の歴史はイギリスから動く」が掲載されました。
内閣官房参与として、財政拡大について、
「マンデル・フレミング・モデルにより、変動相場制の国では財政策は無効」
「クラウディングアウトで、民間投資が抑制される」
などと、机上の黴が生えた経済学を盾に反対し続けた浜田宏一教授が、「正しい方向」に転身なさったようです。
『インタビュー:財政拡張で金融緩和強化を=浜田参与
http://jp.reuters.com/article/koichi-hamada-interview-idJPKCN12Q1I5?sp=true
安倍晋三首相の経済ブレーンで内閣官房参与を務める浜田宏一・米イエール大名誉教授は26日、ロイターとのインタビューで、雇用情勢の改善を持続させるには、金融緩和の効果を増大させる財政拡張が重要と語った。
2016年度第3次補正予算の編成にも前向きな見解を示した。
一方、金融政策について、現状でのマイナス金利深掘りは必要ないとした。
安倍政権の経済政策であるアベノミクスに関し、第1の矢である大規模な量的金融緩和の推進で労働市場や企業収益の改善など効果を発揮したが、「金利がゼロ%に近づき、量的緩和の影響は当初に比べると薄れてきている」との認識を示した。
こうした中、日銀は9月に政策の軸足をそれまでの「量」から「金利」に転換。短期のマイナス金利政策と長期金利をゼロ%程度に誘導する「長短金利操作付き量的・質的金融緩和(QQE)」を導入した。
浜田氏は金融緩和の効果が拡大しなければ「雇用情勢の改善も止まってしまう可能性がある」とし、すでに金融政策が「全開」の中で「効果を一層強化するには、財政政策も活用していかなければならない」と強調。
財政拡大で市場金利が上昇し、民間投資が抑制される「クラウディングアウト」懸念などから、これまでは財政の効果に懐疑的な見方を示していたが、日銀の長期金利コントロールによって「クラウディングアウトが避けられるとともに、財政の助けによって金融緩和が一段と効果を発揮する」と語った。(後略)』
「日銀の長期金利コントロールによってクラウディングアウトが避けられる」
要するに、デフレの国、つまりは国民がお金を借りようとせず、資金需要が不足している国で金融緩和をどれだけ拡大しても、そもそもこちら(民間)に借りる気がない以上、銀行の貸し出しは十分に増えず、モノやサービスの購入も増えず、インフレ率が上がることもない。という現実を、ようやくお認めになられたわけですな。
浜田教授は、後略部で、
「マイナス金利のさらなる深堀りは、ビジネスに脅威となる可能性がある」
とも語っているわけですが、その通りです。と言いますか、現状、すでに脅威になっています。今の日本銀行のマイナス金利政策は、銀行から政府への所得移転に過ぎません。一種の、緊縮財政としての働きをしてしまっています。
そもそも、マンデル・フレミング・モデルなど、閉鎖的な小国経済でしか成立しない「モデル」なのです。この特殊なモデルを、日本のような大国に当てはめ、財政拡大を否定しようとする連中が本当に多く、ウンザリしておりました。この連中は、結局は財政拡大を拒否する財務省の手先として動いたことになります。
また、クラウディングアウトなど、1998年以降の日本の「実績」が全否定します。
クラウディングアウトとは、政府が国債発行を増やすと金利が上がり、民間がお金を借りにくくなり、経済成長率が抑制されるという仮説です。現実の日本では、政府が国債を発行しても、発行しても、金利は上昇するどころか、むしろ下がっていきました。
日本がデフレで、民間が「お金を借りる気がない」以上、当たり前です。
クラウディングアウトは、「民間が常にお金を借りたがっている」環境、すなわちモノやサービスは生産すれば、基本的には売れる。生産を増やす投資をすればするほど、確実に儲かるという、「セイの法則」が支配する世界においてしか、成立しない仮説なのです。
それにしても、浜田教授は「財政拡張」や「第3次補正予算」を提言し、更にはマイナス金利政策の深堀を否定された点は評価できるのですが、相変わらず「消費税」については、
「それ(インフレ目標)が達成されれば、消費税率を毎年1%ずつ上げていくことも進言したい」
と、財務省の手先ぶりを発揮されています。
何度も書いていますが、消費税とは現在の日本において、非常に不都合な結果をもたらす税金です。何しろ、所得が多ければ多いほど、消費税率(消費税対所得比率)は下がっていくのです。高所得者層にとって、消費税など「どうでもいい」税金です。どうせ、人間はお腹がいっぱいになれば、それ以上は食べれません。
とはいえ、消費性向が高い低所得者層にとってはそうはいきません。消費税率の引き上げは、低所得者層を直撃します。所得が小さければ小さいほど、消費税率は上がるのです。
すなわち、消費税は明確に「格差拡大効果」がある税金なのです。
日本の格差を拡大するために、消費税を上げよう!
と、浜田教授が主張なさるのであれば、それは一つの価値観でございますが、本当にそうなのでしょうか。
いずれにせよ、財政拡大に猛烈に反対されていた浜田宏一教授が改心されたのは、まことに結構な話だと思います。現実を認め、過去の主張と真逆の提言をされた浜田教授の改心を、日本国民として喜びたいと思います。
「浜田教授の改心を評価する!」に、ご賛同下さる方は、↓このリンクをクリックを!
人気ブログランキングへ
◆本ブログへのリンクは以下のバナーをお使いください。

◆関連ブログ
◆三橋貴明関連情報
Klugにて「三橋貴明の『経済記事にはもうだまされない』」
連載中
新世紀のビッグブラザーへ ホームページ
はこちらです。
メルマガ「週刊三橋貴明~新世紀のビッグブラザーへ~」
は↓こちらです。




